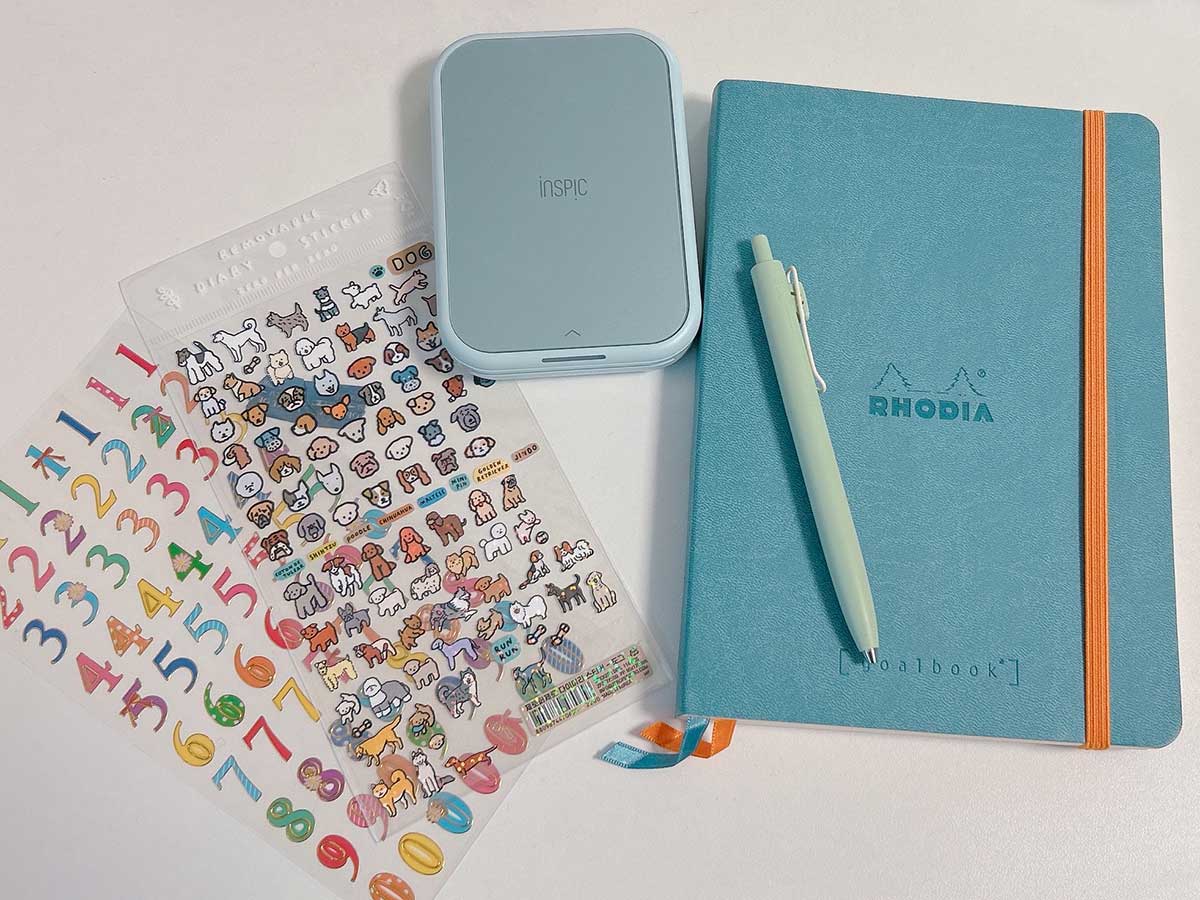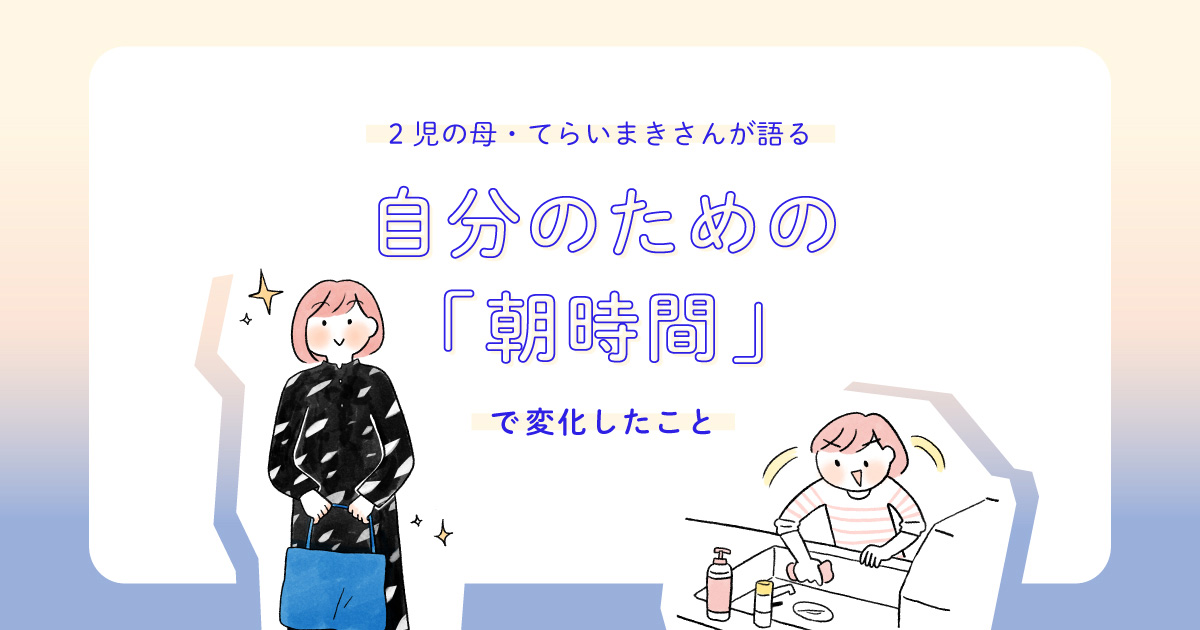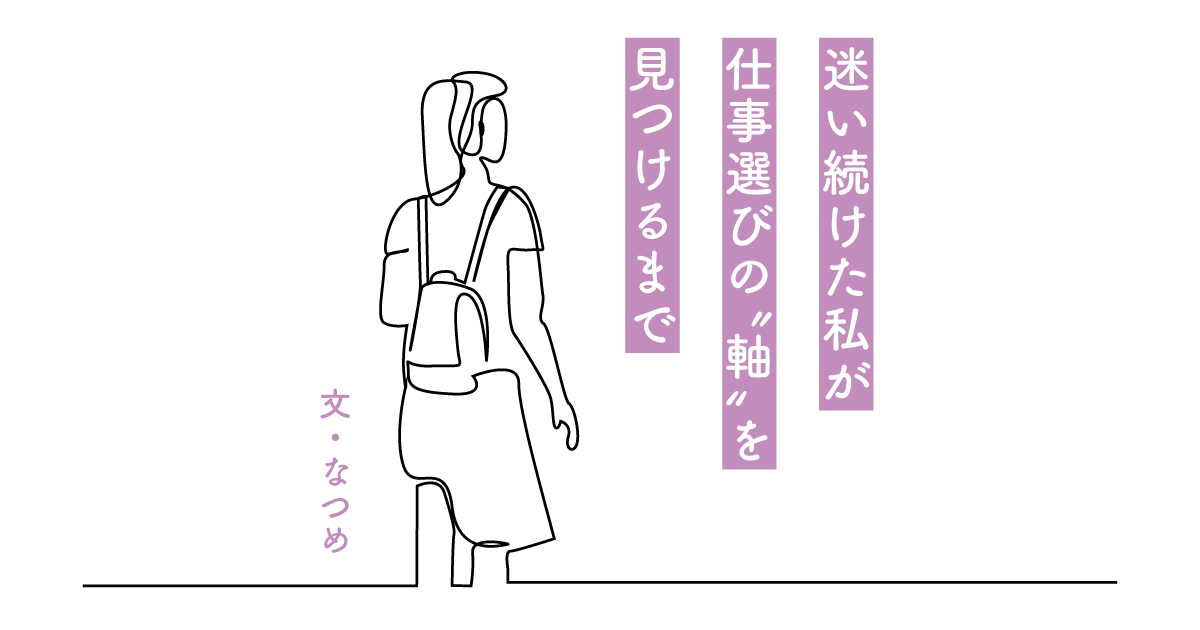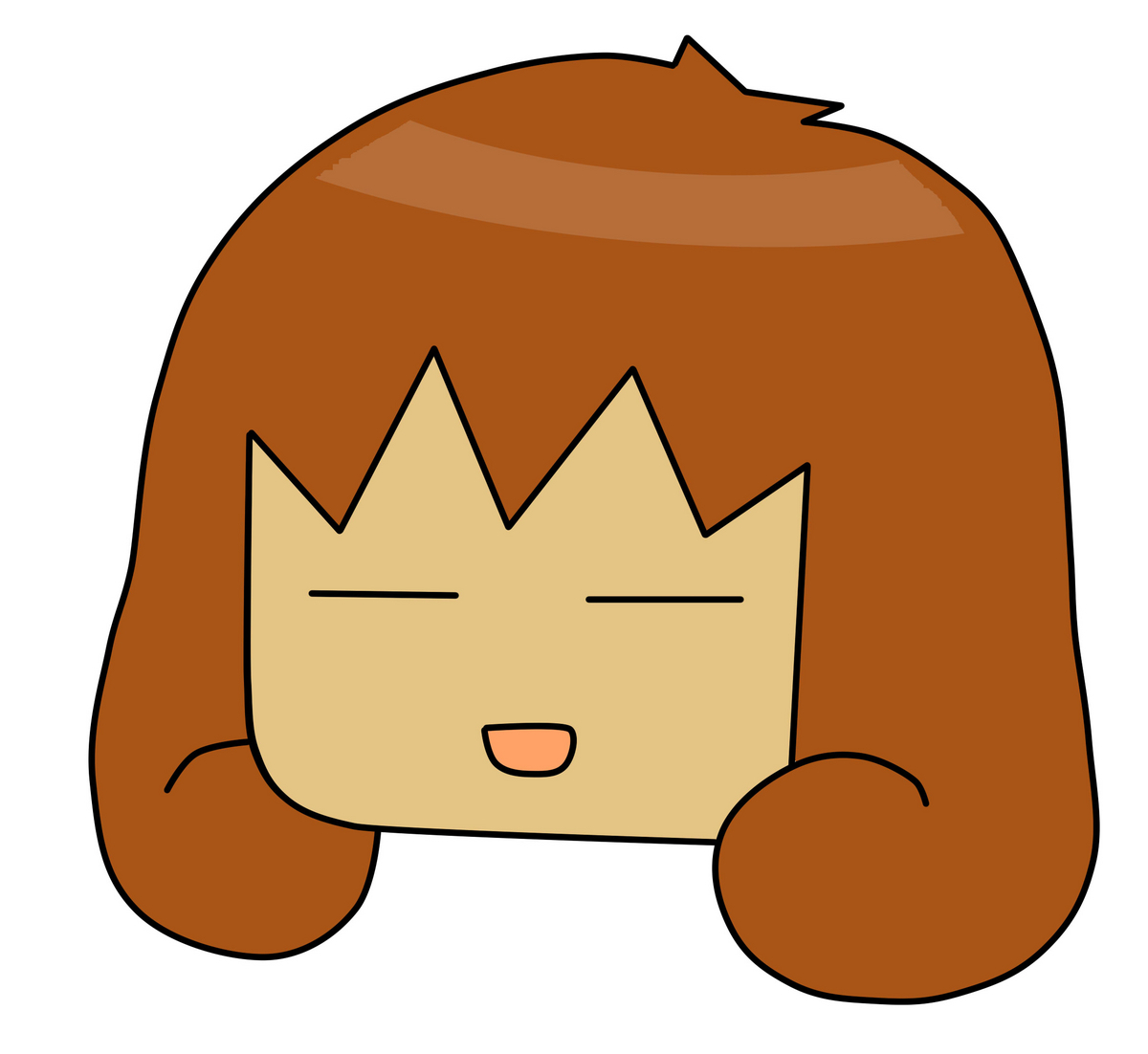トミヤマさんがやめたのは「敬語を完璧に使わなければ」と気負うこと。とあるきっかけで敬語がうまく使えない自分に気づき、克服すべく努力しても、今度は会話が弾まなくなり落ち込むという悪循環に。「敬語をうまく使えない自分」とどう向き合ってきたのかをつづります。
ことばのプロなのに、敬語がうまく使えない
わたしにとって、ここ数年の大きな変化といえば、「敬語をうまく使いこなせない自分」を受け入れたことだ。自分は敬語が下手なのだと認めてしまおう。抗っても仕方がない。そんな気持ちだ。
とは言っても、敬語を否定したり、おろそかにしたりしたいわけじゃない。使えるときは使うが、うっかり忘れたり、間違えたりしても、あまり気に病まないことにしたのだ。
フリーランスのライターで、研究者としての顔も持っているわたしを、世間は「ことばのプロ」だと思うだろう。自分でも、まあそうなんだろうと思う。でも、どういうわけか、敬語がうまく話せない。話に夢中になると、敬語がどんどん消えていって、最後はタメ口になってしまうのだ。
原稿を書くときは、どんなにラフな書き方をしても、あとから見直せばよいが、話すときはそうもいかない。口から出てしまったことばは、引っ込められない。その場にふさわしくないことばを使うたび、毎回フレッシュに「ああ、またやってしまった!」と落ち込んでいる。
「宇多丸さんにタメ口!」指摘されて気付いた自分のクセ
わたしの敬語がパーフェクトでないと気づいたのは、30歳を過ぎてからだった。『パンケーキ・ノート おいしいパンケーキ案内100』(リトル・モア)という本の出版をきっかけに、メディアへの出演が一気に増えたことで、遅まきながら自分の変なクセに気づいたのだ。
2013年、ヒップホップグループ「RHYMESTER」の宇多丸さんがMCを務めていたラジオ番組「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」に初めて出たときのことは、いまでもよく覚えている。乗せ上手&引き出し上手の宇多丸さんのお陰で、すっかり緊張の解けたわたしは、パンケーキについて思う存分しゃべりまくり、多幸感に包まれながら帰宅した。

一息ついたら、次にやるのはエゴサーチ。みんなパンケーキに興味を持ってくれただろうか。すごくおもしろい食べ物なんだと分かってくれたらうれしいな。そんなことを思いながらSNSを見ると、うれしい感想がたくさんあった……のだが、「このひと、宇多丸さんにタメ口きいてる!」といったこともまた書かれていたのだった。
これは完全に予想外だった。「え、マジで?」と思った。が、次の瞬間、ちょっとくらいのタメ口なら、わざわざ投稿などしないだろうということにも気づいてしまった。指摘せずにはいられないくらい、わたしのしゃべり方がラフだったに違いない。
そう思い、放送を聴き直すと、ボルテージが上がるにつれ、どんどん敬語が消えていくではないか。あいづちも「はい」じゃなくて「うん!」とか「そう!」になってるし……。あんた、宇多丸さんの友達じゃないんだから。リスナーさんが思っただろうことを、わたしも思った。自分のあまりに無防備なしゃべりに、頭を抱えずにはいられなかった。
しかし、一度頭を抱えたぐらいで直るようなクセではないのだった。実は、別のラジオ番組でも同じ失敗をしている。話が盛り上がっていくにつれ、どんどん敬語が消えていくわたし。それを見るに見かねたMCの方から「タメ口ですね!」と指摘されて、ハッとなった。
夢中になるとすぐこれだ。その場で「ごめんなさい」と謝り、どうにか語尾だけは「ですます」にして乗り切った。収録中に指摘せずにはいられないほど、わたしの語りがラフなのがいけない。「トミヤマさんはゲストだから」と我慢される方が100倍心苦しいので、その場で教えてくれて本当によかった。

敬語に気を付けたら、今度は会話が弾まなくなった
いい年した大人がこれでいいのか。メディアに出る人間がこれでいいのか。ことばのプロがこれでいいのか。いくつかの失敗を経験したことで、完全なる反省モードに入ったわたしは、ものすごく敬語に気をつけて話すようになった。
敬語を知らないわけではないので、正しく話そうと思えば話せなくはないのだ。が、そうすると今度はトークが全然弾まない。完璧な敬語を使おうとすることに意識を奪われてしまい、うまく話せないのだ。表面上は、会話が成立している。丁寧なことばづかいを通して、相手へのリスペクトも示せている。だが、会話にいまいち熱がこもっていない。いつもと比べるとどこか盛り上がりに欠ける。
なんだろう、この、関節のない棒人間にでもなったような気持ちは。歩けなくはない。一応、前に進んではいる。でも関節がないから、歩き方がぎこちない。ともすれば転んでしまいそう。
これは、とくにラジオというメディアにおいては、致命的な状況である。上っ面の情報をやりとりしているだけのラジオなんて、ラジオ好きからすれば論外である。わたしもラジオが好きだから分かるのだ、そんなトークじゃダメだってことが。
人と話すときに頭の中でいろいろ考えてしまってうまく話せない人がいるが、私の場合は敬語が絡むとそうなる。おしゃべりが得意なつもりで生きてきたが、そんなことないのかも……。
そしてわたしは「敬語以外」を頑張ることにした
そもそもの話に立ち返るが、わたしはなんでこんなに敬語が苦手なのか。その理由の一つに、大学→大学院→研究者と一般企業を知らぬまま過ごしてきたことが関係しているように感じている。
人生のほとんどを大学のキャンパスで過ごしているため、ある種の世間知らずというか、温室育ちな部分があるように思うのだ。(誤解のないように補足すると、同じ人生を送ってきた人でも敬語が上手に使える人はたくさんいる、わたしが環境に甘えていただけという説が濃厚)
若いうちは部活動やアルバイト経験を通じて上下関係や社会常識を身に付けたりするものだが、わたしが所属していた軽音部では「○○先輩」と名前を呼ぶことさえできればあとはタメ口でもOK。さらに一番長くやっていたバイトは家庭教師で、20代のうちから「先生」なんて呼ばれており、敬語を使うのはむしろ教え子たちの方だった。
編集プロダクションで編集補助のアルバイトをしたこともあったが、めちゃくちゃアットホームで小さな会社だったので、社会常識をゴリゴリに仕込まれる、みたいなことはなかった。そんなわけで、敬語をきちんとインストールしなくても、なんとかなってきてしまったのだ。
今いる研究者の世界には、尊敬する先生方がたくさんいて、敬語を使う必要に迫られることもあるが、個人的には、すごい先生ほどコミュニケーションの形式にはこだわらないという印象がある。ある程度親しくなれば、「先生が教えてくれた文献めちゃおもしろかったよ!」なんて言っても怒られたりはしないし、むしろ「そうでしょうそうでしょう!」と友達みたいに盛り上がってくれたりするのだ。

というわけで、わたしがどうしてこういう人間に仕上がったかは理解していただけたと思うが、ひとりの人間としてこれからどう生きていくべきかを考えたとき、ことばづかいは大事だと思いつつも、敬語に気を取られておしゃべりが弾まなくなるのはどうしても避けたいと思った。
じゃあ、どうするのか。「お話が楽し過ぎて敬語があやしくなるかもしれません、すみません!」とあらかじめ謝る方向にシフトした。ちょっとずるいかもしれないが、早めの自己開示で、「そういう体質」であることを相手に伝えつつ、コミュニケーションをはかることにしたのだ。
ただ、相手に対して「ありのままを受け入れろ」と求めるのは、一方的で乱暴な気もするので、おしゃべり以外のところをこれまで以上にがんばるようにしている。
例えば、依頼された仕事は一生懸命やって結果を出すことを重視する。社会性が「ない」ようで「ある」、と思ってもらうには、もう仕事をがんばるしかない。とくに、自分にはまだ早いとか、荷が重いとか思うような仕事こそ、逃げずにやるようにしている。
そういう仕事の仕方を、プレッシャーやストレスに感じる人もいるだろう。しかし、わたし個人は「痛きもちいい筋トレ」ぐらいの負荷だと思っているから、耐えようと思えるし、自分を成長させる意味でも、悪いことじゃないと感じている。できないことを無理してやらない代わりに、他のことをがんばる。それがいま、自分の中で、ちょうどいいバランスを保っている。
不完全な自分でいさせてくれる人たちに感謝
このような生活をしていると、周囲のひとに対して、いままで以上に感謝するようになる。わたしのような人間と一緒にいてくれてありがとうございます。心からそう思う。
いきなりタメ口をきいたわたしに怒ることなく、その後も繰り返し自身の番組に呼んでくださる宇多丸さんと番組スタッフさんには、心から感謝している。出演回数を重ねる中で、リスナーさんもわたしの喋り方に慣れてくださったのか、お叱りを受けることはなくなった。これも大変にありがたいことだ。
繰り返すが、パーフェクトな敬語を操れない自分を、許したわけでも諦めたわけでもない。いまでも、ちょっとアウェイな集まりに参加するときなどは、「わたし、ひょっとして、またやってしまうのか……」と思いつつも、果敢に敬語チャレンジをしている。
それで失敗しても、もう自分を責めたりはしない。早め早めの自己開示と、敬語以外のことを頑張って「結果」をしっかり出すことが大事! と言い聞かせながら、わたしは生きていく。それでこの世界に自分の居場所を作り続けられたら、とてもうれしい。
編集:はてな編集部
「できない自分」とどう向き合う?
りっすん by イーアイデム
Xも更新中!
Follow @shinkokyulisten
<Facebookページも更新中> @shinkokyulisten