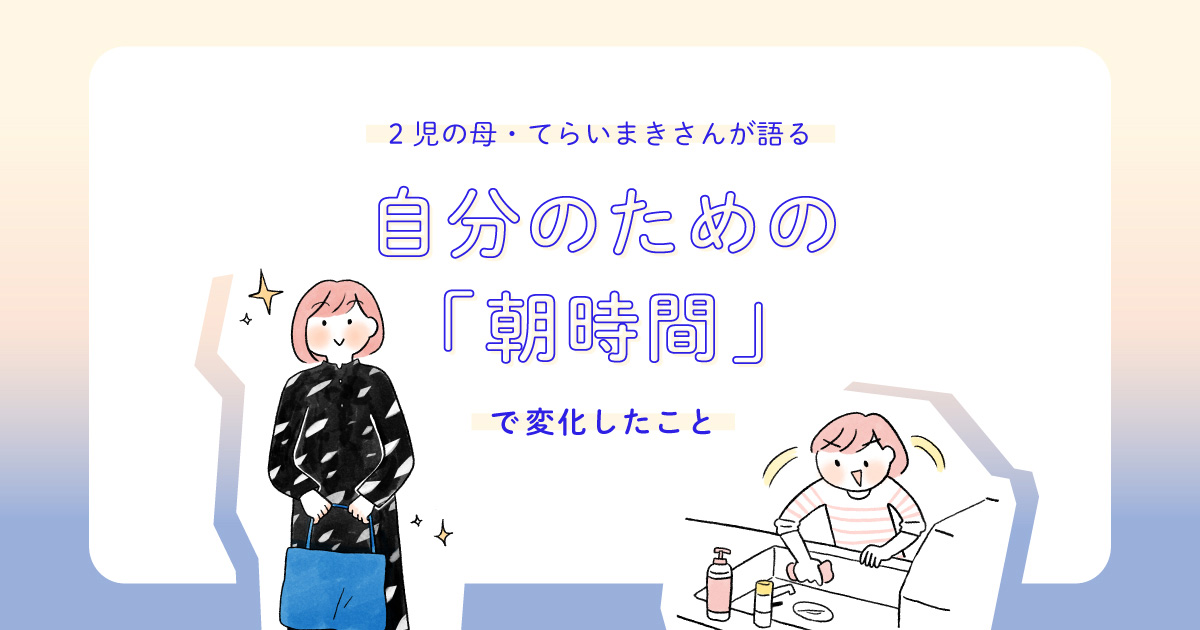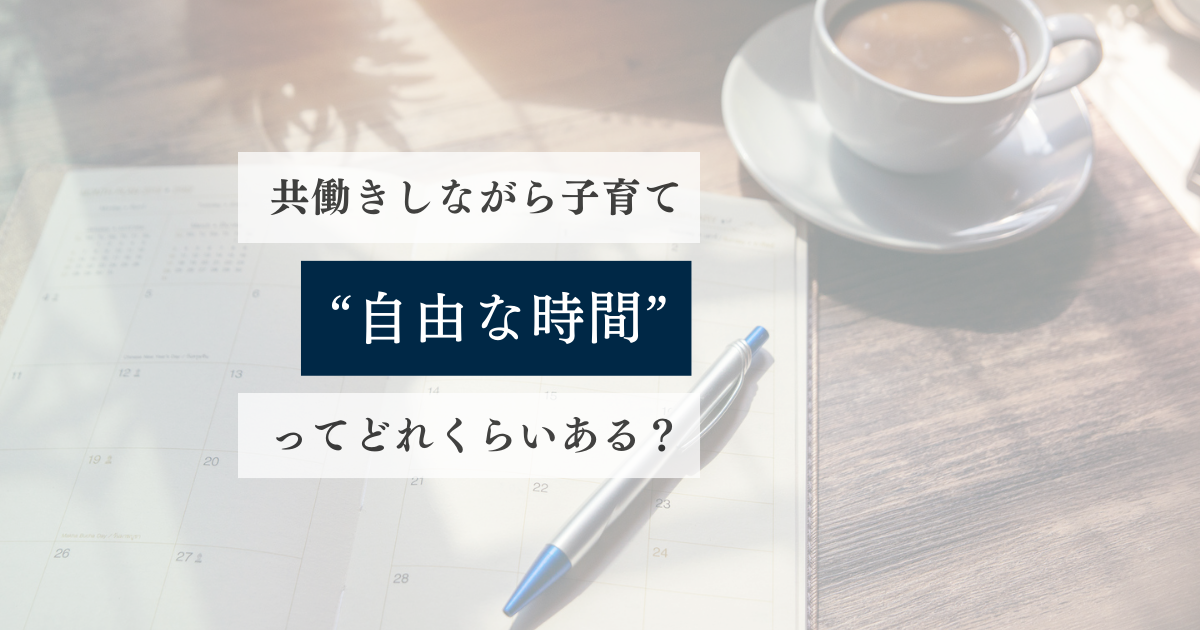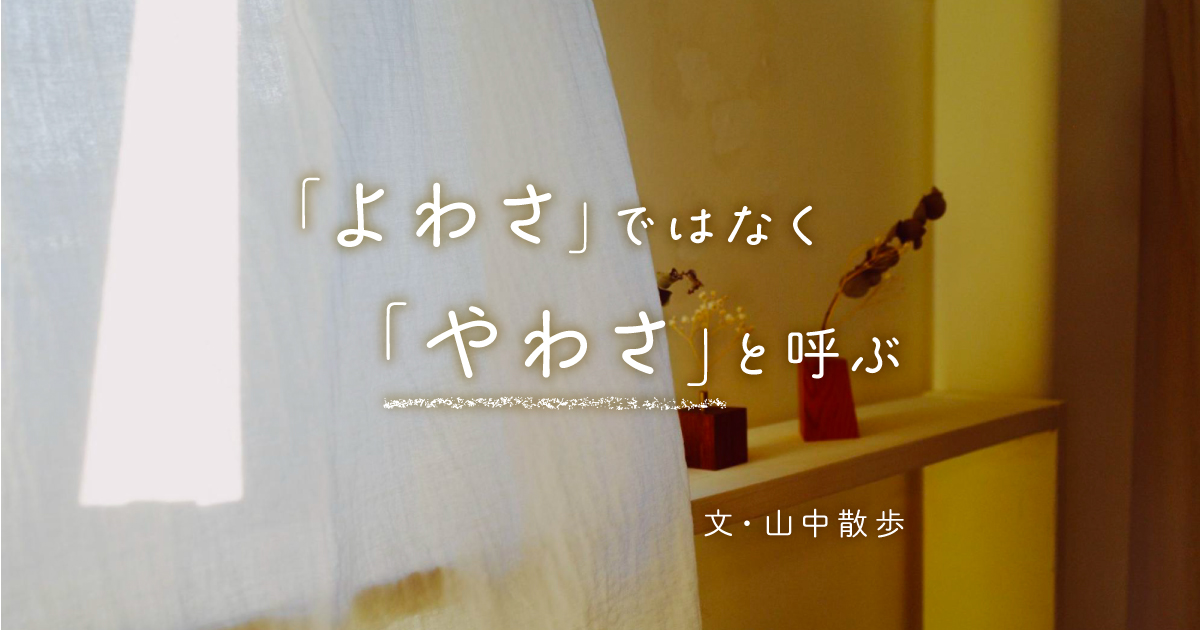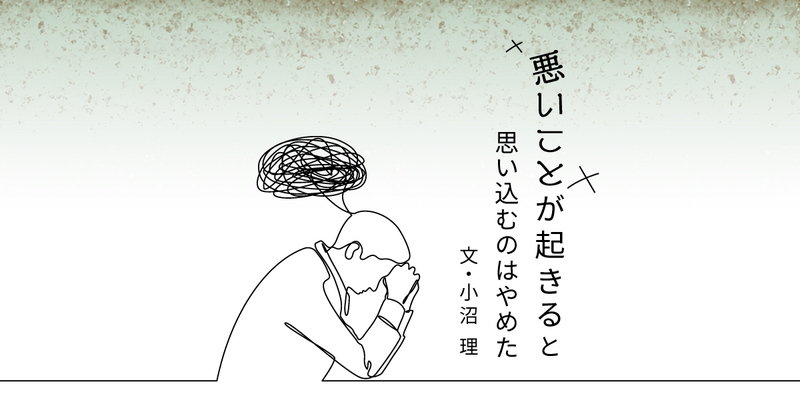「経理事務」は、ルーティンワークが多く業務時間を調整しやすいことから、子育て中の人でも働きやすい職種だといわれています。
子育てしながら働く中では、保育園の送迎や子どもの急な体調不良への対応など、自分の仕事を調整せざるを得ない場面が多々あるはず。お子さんを抱えながら「今よりもっと、タスクの量やスケジュールを柔軟に調整できる仕事を探したい……」と考えている人は少なくないでしょう。
2児を育てながら経理事務の仕事を続けているsakanaさんに、子育てと両立しやすいと感じている理由について語っていただきました。
こんにちは、sakanaといいます。3歳と5歳の子どもを育てている、共働きのワーママです。
私は今の会社に未経験で「経理事務」として就職し、16年勤めています。以前はフルタイムで働いていましたが、長男の出産をきっかけに時短勤務に切り替えました。
在宅勤務ができない職場のため週5フルで出社していますが、仕事の性質上、イレギュラーなことがない限り定時で帰れるので、子育て中でも1日のタイムスケジュールが立てやすく助かっています。
今回は、実際に私が経理事務の仕事をしながらどのように子育てと両立しているのかを紹介したいと思います。
経理事務とはどんな仕事? 資格は必要?

まずは、経理事務の仕事内容や、どんな人に向いているのかについて紹介します。
- 会社の「お金の流れを管理する仕事」で、さまざまな業種で働くチャンスあり
- PCやExcelの基礎知識があれば、資格不要・未経験OKな職場も
- ルーティンワーク中心で忙しい時期があらかじめ分かっているため、子育てとの調整がしやすい
経理事務は、企業のお金の流れを管理し、正しく記録する仕事です。具体的には、日々の会計処理、給与計算、請求書の作成、税金の支払いなどを担います。
どの会社にも欠かせない部署のため、さまざまな業種で働けるチャンスがあるのが特徴。私が勤めているのはデザイン制作や卸売業の会社で、発注や売上仕入れの伝票作成、Excelでのデータ作成、月末の締め処理をメインで任されています。
経理事務と聞くと「資格を持っていないと採用されないのでは?」と思われるかもしれませんが、私が勤めているような中小企業の場合は特に、一般的なPCの知識やExcelの経験があれば、経理事務の仕事自体は未経験でも応募可能なケースがあります。
私自身、商業高校で情報処理を専攻していたのでExcel、Word、PowerPointの知識はありましたが、特別な資格は持っていません。
業務内容はルーティンワークで、あらかじめ「この時期は忙しくなる」「この時期までにこの業務を終わらせておかなければならない」といったスケジュールの見通しが立っていることが多いです。そのため、以下のような人に向いているといえます。
<経理事務の仕事に向いている人>
- ルーティンワークにコツコツと取り組むのが好きな人
- スケジュール管理が得意で、自分の都合に合わせてうまく調整できる人
- (数字を扱うため)細かいチェックなども責任を持って取り組める人
経理事務の柔軟性を生かし、子育てとの両立のために私が工夫していること

経理事務の「仕事のスケジュールが立てやすい」というメリットは、子育てと両立する上でとても助かっています。この特徴も生かしながら、2人の子どもを育てる身として、以下のような工夫をしています。
- 忙しいのは「月末月初」なので、それを見越してスケジュール調整ができる
- ルーティンワークなので、勤務時間も柔軟。就業時間を30分前倒し、帰宅後に時間の余裕を作った
月末月初の忙しさを見越したスケジュール管理。夫婦での連携も
業務の性質上、月末月初が忙しいためその時期は休まないようにし、さらには前倒しで終わらせられるようなものは急ぎで片づけておくなどして、スケジュール管理をしています。やるべきタスクが決まっており、忙しくなるタイミングも分かっているので、調整がしやすいです。
万が一、忙しいタイミングで子どもが風邪を引いてしまった場合は、在宅勤務が可能な夫にお願いするなどして、何とか乗り切っています。
2人目を機に勤務時間を前倒して、帰宅後の時間に余裕を
1人目を産んで以降はずっと時短勤務をしていますが、2人目の育休から復帰するタイミングで会社に相談し、就業時間を10時〜17時から9時30分〜16時30分に繰り上げてもらいました。
子どもが2人になったことでこれまで以上にバタバタするようになり、退勤後の子どものお迎えから寝かしつけまでの時間になるべく余裕を持たせた方が、全体のスケジュールがスムーズになると考えたからです。
実際、朝の準備はややバタバタするものの、帰宅を30分早め、帰宅後のルーティンをしっかり決めるようにしたことで、子どもの寝かしつけを21時までに終わらせられるようになりました。
<1日のスケジュール>
- 6時:起床。朝の出勤前に夕飯の下準備(野菜を切っておく、冬場なら汁物を作っておくなど)
- 8時45分:保育園への登園
- 9時30分:出社、勤務開始
- 16時30分:退勤し、保育園へお迎えに
- 18時ごろ:帰宅後、子どもたちのお風呂
- 19時ごろ:夕飯
- 20時30分ごろ:布団に入り、21時には就寝
子どもたちを早く寝かせることで、自分の時間も確保できています。
時短勤務をしていたり、勤務時間をずらしたりしても、正直、平日は子供たちとゆっくり遊べる時間はないです。そこは休日に補うようにして、平日はなるべく規則正しい生活を心がけ、自身の体力も維持しています。
「子育てに理解のある職場」かどうかをできる限り見ておく

経理事務は子育てと両立しやすい職種とはいえ、子育てしながら働くことを周囲の人にどれだけ理解してもらえるかも重要だと感じています。
今の職場は、同じ経理事務の同僚や上司も含め、ほとんどが子育て経験者、もしくは子育ての真っ最中という方たちばかり。子どもの体調不良で急な休みを取得したり、子どもの行事や家族旅行などのために計画的に休んだり、といったことが当たり前になっています。
経理事務の仕事に限った話ではありませんが、転職を考えるならできるだけその会社の雰囲気を知れるようにしたり、面接の際に子育て世代の方がいるか聞いてみたりするのも、理解のある職場を見つけるための一つの策だと思います。
私は子どもと過ごす休日でも、大まかなタイムスケジュールを組むことで、できるだけスムーズかつ充実した時間を過ごせるように工夫しています。
スケジュール管理が得意な方は、仕事はもちろん、就業後までを含めた1日のスケジュールを組み立てるのが上手なはず。自分でスケジュール調整がしやすい経理事務の仕事なら、きっと子育てとも両立しやすいと思います。
それにプラスして、コツコツと取り組むルーティンワークも好きだという方はぜひ、経理事務の仕事を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
編集:はてな編集部
「子育てと両立できる働き方」を考える
りっすん by イーアイデム
Xも更新中!
Follow @shinkokyulisten
<Facebookページも更新中> @shinkokyulisten