
誰かの「やめた」ことに焦点を当てるシリーズ企画「わたしがやめたこと」。今回は、ブロガー・ライターのむらたえりかさんに寄稿いただきました。
むらたさんがやめたのは「『しっかりしている自分』であろうとする」こと。
幼い頃から「何でも自分ひとりでできる」人でありたいと思い、社会人になってからもその意識が大きかったというむらたさん。しかし、それ故に仕事を抱え込み過ぎたことで心身の不調をきたし、休職をすることとなります。
そんな休職期間中に気付いたことは「しっかりしている」状態の捉え方の曖昧さ。また、何でもひとりでできるようにすることが必ずしも「しっかりしている」=「責任感がある」ということではないこと、そして、ときには周囲に「頼る」ことの大切さでもありました。
電車内やスーパーで大泣きしている幼い子を見かけると、ときどき「ああ、いいなあ」と呟きそうになる。30代半ばにもなって。何かを訴えて大声をあげるこどもに憧れる自分に、その度に驚く。
幼い頃のわたしは泣かないこどもだったらしい。ひとりで本を読んでいることが好きで、下の妹弟たちの面倒を見ることも嫌がらず、ずいぶんと扱いやすい子だったそうだ。わたし自身も大人たちに「いい子だね」「もうお姉さんだね」と言われることを望み、うれしく思っていたようなおぼろげな記憶がある。「ひとりで何でもできるように」と父に繰り返し教育され、そうありたいと思っていた。
けれど、そうやってずっと心の支柱となっていた「ひとりで何でもできるように」が崩れてしまった。それは、病院でうつ病・抑うつ状態と診断されたときだった。
「しっかりしているわたし」を手放せなかった
2020年のはじめにうつ病・抑うつ状態と診断され、その夏から休職をしている。会社のせいではない。「ひとりで何でもできるように」が行き過ぎた結果、自分で抱えきれる仕事量を大きく見誤り、また仕事についても私生活についても誰にも相談ができず、いよいよ限界を迎えてしまった。
思えば、地元の宮城県から東京に出てきたときから無理をしていたのかもしれない。知り合いも頼れるひとも少ない土地で、わたしの「ひとりで何でもできるように」の意識は次第に大きくなっていった。
そして、「できません」と言わずに仕事を引き受ける扱いやすいわたしを、過去に所属していた会社の上司たちもいくらか重宝してくれていたように思う。それがたとえ、家に持ち帰って朝の5時までかけてできた仕事でも、寝ていないとか朝までがんばったなどとは職場の誰にも言わなかった。仕事量に文句を言うこともなかったし、ありがたいとさえ思っていた。だから、これくらいは当たり前にできるひとなのだと思われていたのではないだろうか。
抱え込みがちな点を気にしてくれる上司や同僚もなかにはいたけれど、本人が平気そうにしていて仕事もあがってくるものだから、深くは踏み込んで来なかった。
以前勤めていた広告制作会社では、自分の仕事はもちろん、後輩の仕事のフォローや修正まで自分でしてしまっていた。転職して書籍の編集の仕事をするようになってからは、ライター職や校正職の経験から、自分で文章の修正や校正までおこなうようになっていた。他にも自分でも気づいていない部分で「自分でできることは自分でしてしまおう」と抱え込んでいたものがあったはずだ。
いまでは、そんな仕事の仕方は良くないと分かる。仕事はひとりでおこなうものではない。ひとを頼ったり相談したりした方が、周囲も安心するし、気にかけてももらえる。でも、渦中にいるときには気づけなかった。「ひとりで何でもできるように」と思い込んでいたし、そんなわたしを上司や親が「しっかりしている」と見てくれている評価を手放したくなかったからだ。
「いいなあ」と思ったあの涙を初めて流した日
病院で休職を勧められたときに感じたのは、安堵の気持ちとそれを上回る挫折感だった。「ひとりで何でもできるように」という支柱が崩れ、また「しっかりしている」という評価も諦めなければいけない。職場のひとたちにも親にもそんな自分を見せるのがつらくて恥ずかしくて堪らなかった。
ただ、尊敬している上司に病気の報告と休職の申し出をしたとき、そのひとの前でボロボロに泣いてしまい、何か憑き物が落ちたような感覚があったのを覚えている。
最初は涙を堪えていた。目が潤んできたのを感じて、でも大人だから、わたしはお姉ちゃんだから、それを溢してはいけないと思った。けれど、上司が「あなたはひとりでもできるひとだと思って何でも任せてしまっていた。もっと気にかけてあげれば良かった」と言ってくれたのを聞いたら、溜めていた涙があふれて止まらなくなった。出会って数年の上司には申し訳なかったけれど、その言葉はきっと、わたしが幼少期からずっとずっと大人に言ってもらいたかった言葉だったのだと思う。
さまざまな感情と記憶が立ちのぼり熱くなった頬に大粒の涙が絶え間なく落ち続けるのを感じながら、これがわたしがこどもの頃に流したかった、「いいなあ」と思っていたあの涙だと思った。
休職中に振り返った自分の働き方
わたしの職歴を振り返ると、フリーランスと会社員を行ったり来たりしている。絶対にフリーランスで成功したいとも、絶対に会社員でいなければいけないとも思ってはいなかった。とにかく忙しくて、どちらが自分に合っているのか、どちらが自分の生きたい道なのか、自分で判断する時間も経験も足りていなかったのだ。
フリーランスライターとしてお世話になっていた編集者の方は、ずっとフリーランスとして活動していくことを勧めてくださっていた。わたしの性質にも合っていそうだし、もっともっと書くべきひとだと言ってくださった。それをうれしく思いながらも、上司の前で大泣きするまで会社員でいようとしたのには理由がある。またしても、「しっかりしている」という評価を手放せなかったからだ。
フリーランスでいるときよりも会社員でいるときの方が、親は安心していた。転職して会社に勤めると報告すると、うれしそうなメッセージを返してくる親への配慮の思い。そして、「やっぱりお姉ちゃんはしっかりしているね」という言葉。それを思うと、フリーランスとして働いていく選択から距離を取りたくなってしまった。
また、東京でフリーランスとして活動していくにあたって「何者かにならなければいけない」というプレッシャーを感じてもいた。広告業界や出版業界で働いているなかで、大きな目標や高い志を持った同世代にたくさん出会ってきた。彼らにとって東京は夢を叶える場所、あるいはその礎になる場所である。本当は葛藤もあったのかもしれないが、わたしにはその明確さが眩しく感じられた。
彼らに影響を受けて、わたしも「こんな大きな仕事がしてみたい」とか「自分の本を出版したい」などと目標らしきものを掲げてみた時期もあった。大きな目標があるように見せれば「しっかりしている」ように見えるのでは、と感じていたのかもしれない。それが本当に心からやりたいことだったのか。そう自問することができたのは、休職期間に入ってからだった。
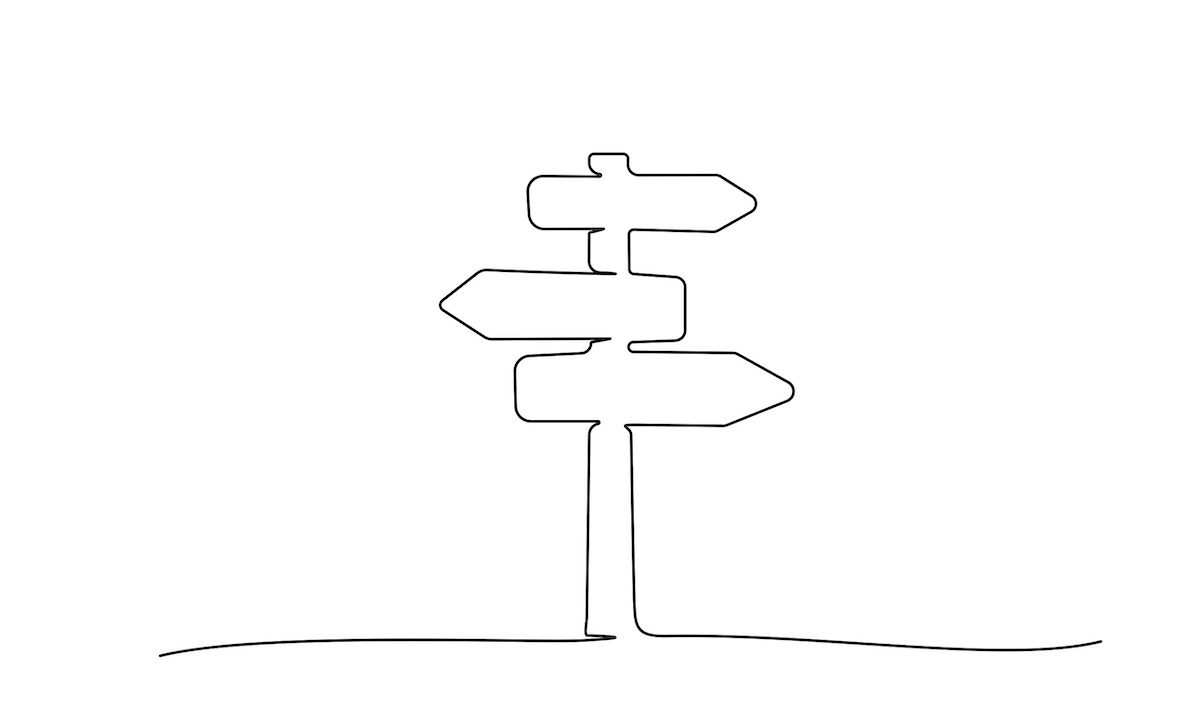
「しっかりしている」の曖昧さに気づく
休職期間に入るとき、自分がうつ病・抑うつ状態であることや休職していることを、あまり隠さずにいようということだけ決めていた。上司の前でこどものように大泣きしたときの、あのさらけ出した感覚に何かがあると感じていたからだ。
しっかりしていないと思われることは、責任感がないとか頼りにならないと思われることに似ている気がして怖かった。それでも、自分の状態・状況を隠さずに伝えたことでわかったのは「しっかりしている」と「責任感」は違うということだった。
休職期間中、体調やメンタルが少し回復してきた頃に、知人の飲食店の手伝いをさせてもらえることになった。そこでは、わたしと同じようにメンタルの不調に悩むひとも働いていた。不調があるからといって、わたしはその子を「しっかりしていない」とは思わなかった。むしろ、仕事をキッチリとこなして柔軟な対応もでき、仕事のできる責任感のある素敵なひとだと思った。
また、休職期間中に出会ったひとのなかには、わたしが自分の悩みや状況を話すことで「実は自分にもこういう悩みがあって」と相談したり頼ったりしやすくなったと言ってくれるひともいた。以前からの知り合いで、わたしが休職したことによって離れていってしまったひともいる。けれど、わたしの状態を知った上で、それでもわたしを頼ってくれたり支え合おうとしてくれたりするひとが周囲にいる、いまの環境の方がずっと気持ちが楽だ。
「しっかりしていない」と「責任感がない」「頼りにならない」は、同じ括りだと思っていた。休職やうつ病というわたしにとっての挫折は、そうした烙印であるとも。
しかし実際は、休職やうつ病は自分の状況であり、性質とは違う。状況が変わって、自分の理想どおりにしっかりできなくなってしまったとしても、わたしのなかにある「ちゃんと仕事をしたい」とか「話を聞いて、サポートできることがあればしたい」という思いを見つけてくれるひとはいる。そして、そういう思いのことを、他者は「責任感がある」「頼りになる」と感じてくれるのかもしれない。
しっかりしていない「何者でもない自分」だから見えてくるもの
1年以上の休職を経た現在、ようやく自分のやりたいことや、向いている仕事について落ち着いて考えはじめられるようになった。まだはっきりと答えが出ているわけではないけれど、周囲に相談しながら、どんな形なら長く生き生きと働いていけそうかを模索しているところだ。
「しっかりしなきゃ」という幼少期からの思いは、もっと詳細に言葉にするならば「大人から見て『しっかりしている』ように見えなければいけない」というプレッシャーだったのだと、いまは思う。「しっかりしているね」と思われたい気持ちへの名残惜しさがないわけではないが、わたしはもう大人だ。誰かにこう思われたいという生き方から、自分はこう生きたいという主体的な感覚へのシフトにチャレンジしてみたい。
そのためには「何でも自分でできるように」というやり方ではうまくはいかないことも分かった。知人の飲食店の手伝いも、いまいただいている執筆の仕事も、その仕事とわたしの性質との接点を見出してくれた他者のおかげでできている。わたしに何か良いところがあると思ってくれた誰かを、わたし自身も信じ、頼りにして、それに報いたいという気持ちで向き合っていく。漠然とした誰かからの評価ではなく、仕事をする相手のためにと最小の関係を大切にしようとすると、おのずと意欲的に仕事ができるようになってきた。
「自分ひとりで」ではなく「頼る」のも一つの強さ
何でも自分でやろうとか、ひとりでもしっかりしなければいけないと思ってがんばっていた自分を否定はしたくない。それだけ気を張って生きていたのだ。でも、それはひとりで抱え込んで自分を守り、他者を信用しないことにつながってしまっていた。
いまは、意識的に知人、友人や編集者の方の意見を聞くようにしている。また、悩んでいることやどうしたらいいか迷っていることも、些細なことでもひとに聞いてみるように心がけている。そんなわたしをダメなひとだと言うひとはいまのところいない。逆に、もっと頼っていいんだよ、と快く言ってもらえるようになった。
最近でも、電車やスーパーで大泣きしているこどもを見かけると「ああ、いいなあ」と思うことはまだある。でも、そのあとに、上司の前で大泣きしたあの日の自分と、上司の言葉を思い出す。「しっかりしている自分」という支柱は折れてしまったかもしれないけれど、しっかりしていない自分でも「支えてあげたい」と思ってくれるひとがいる。自分でこだわっていた部分とはまったく違う、他の良いところを見出してくれるひともいる。失ってしまったからこそ、そうした他者のありがたみをより感じられるようになった。
失うこと、やめることで、新しく変わっていける。新たに得られたその考え方は、これからもわたしの背中を押し続けてくれると思う。
著者:むらたえりか (id:ericca_u)
編集:はてな編集部






