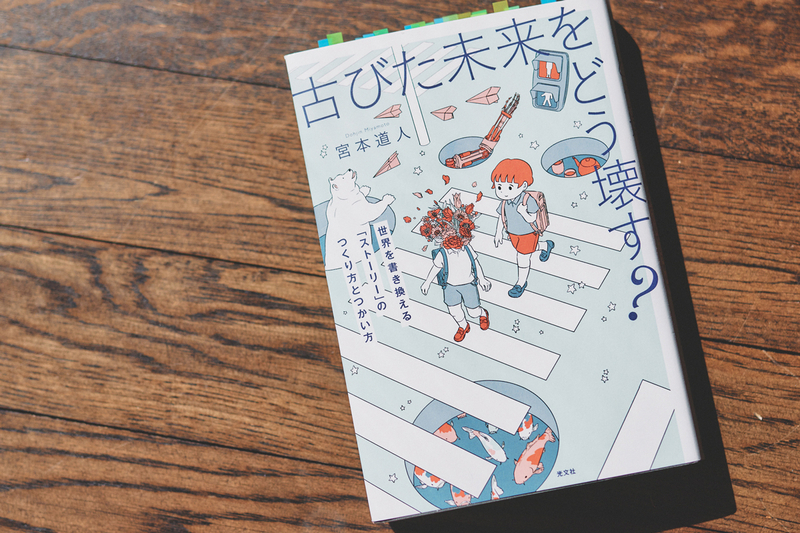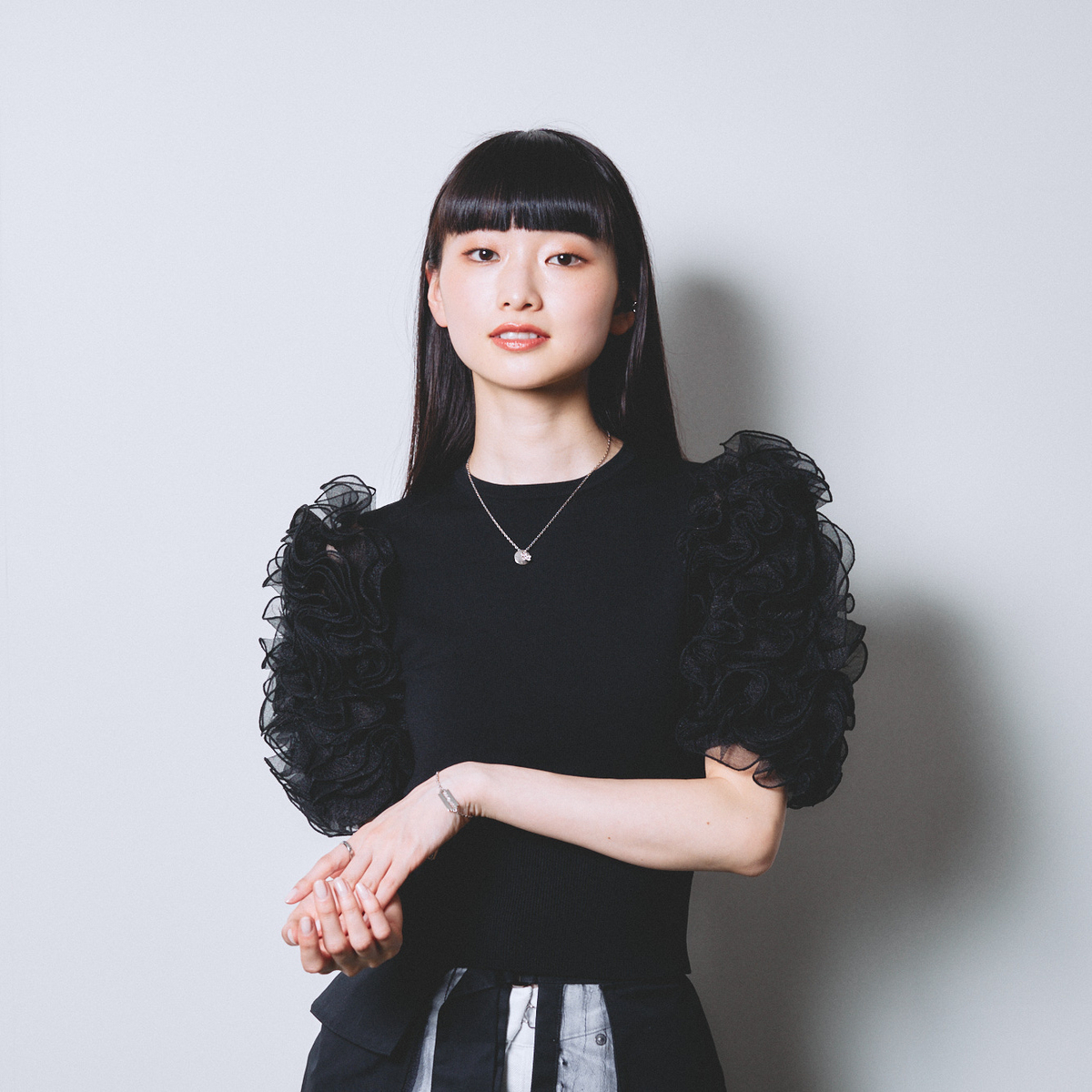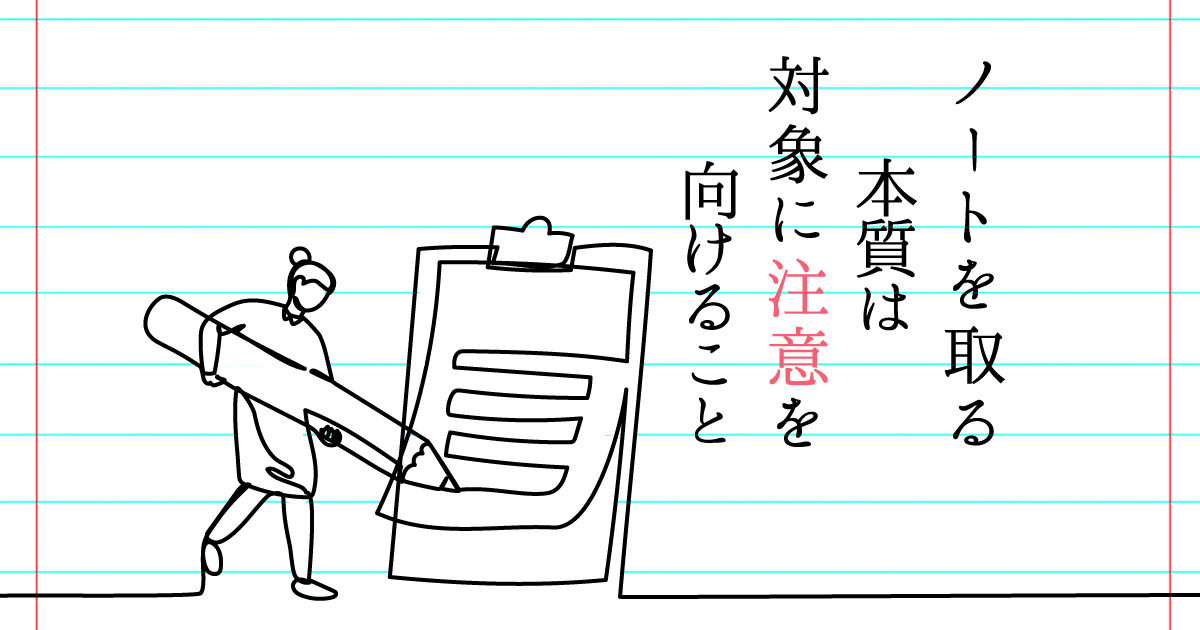SNS疲れに悩んでいる人に向け、その対策の一つにもなる場として「イドコロ」の必要性を提唱している伊藤洋志さんに、疲れた心身を回復するためのヒントを伺いました。
TwitterやInstagram、Facebook、LinkedInなどのSNSは、仕事においても趣味においても、現代を生きる私たちにとって必須のツールです。しかし、つい習慣的にSNSを開いては、過激な言葉にモヤモヤしたり、周囲の人々の活躍に焦りを感じたりと、疲れや悩みを感じている人も多いのではないでしょうか。
仕事をひとつに絞らず、複数の「ナリワイ」で生計を立てる暮らし方をしている伊藤さんは、現代の複雑な情報環境に対応するためには、SNS以外に複数の「イドコロ」を持つことがキーになると説きます。伊藤さん自身のSNSとの付き合い方から、現代人にとっての「イドコロ」の意義と、そのつくり方や見つけ方について伺いました。
競争原理の働くSNSで疲弊するのは当たり前
伊藤洋志さん(以下、伊藤) 僕も例外ではないですが、みんな軽い依存状態になっていますよね。運営企業からすればたくさんSNSを使ってもらった方が良いわけで、そのために優秀なエンジニアの人たちがさまざまなアルゴリズムを日々考えている。脆弱な私たちが吸い寄せられるのは避けられないんだろうなと思います。
しかもフォロワー数やLike数のほか、近年はページビューが可視化されているものもあり、とにかく競争原理が働く設計になってしまっている。競争環境が好きな人のカルチャーに、競争が苦手な人もフィットさせられてしまっているわけだから、不調が生じるのは必然ではないでしょうか。基本的にアテンション(注目)が集まるトピックって過激なものが多いので、そういった話題ばかりを目にしているとさすがに疲れますよね。

伊藤 もともとは僕も物書きの仕事柄、SNSにひたる時間は長かったと思うのですが、最近はTwitterをブラウザからしか開かなくなったんです。そうしたら使用頻度も自然と減ってきました。イベントの告知など、自分が発信したいときや、その反応を見たいときだけ開くようにして、それ以外はたまに見るだけというスタンスになりつつありますね。
段取りを面倒くさくして、本当に必要なときだけ触れるようにしてしまうのは意外と重要なのかなと……。
伊藤 もちろん、使い方によっては当初のmixiのように、趣味に関する交流を楽しむ人たちにとってプラスに機能することもあると思います。ただ、個人的にはSNSに向いている趣味と向いていない趣味があるように感じます。
例えば、僕は廃村を巡るのが好きな人たちをフォローしているんですが、そういう特殊な趣味の場合は、まだ比較的うまく機能していることが多いんじゃないかと思います。マウンティングもなく、「その村、僕が行ったときよりも寂れてしまいましたね……」みたいな好きなものに対する純度の高い牧歌的なリプライが飛び交っているだけで(笑)。なので僕もそういうアカウントを中心にフォローしています。
伊藤 多くのファンを獲得したいコンテンツの場合は、特にSNSでの発言が過激化していく傾向はありますよね。その状況に疲れているということであれば、自分がどうSNSと距離をとっていくかは各自考える必要があると思います。現状、私たちができることとしていちばん簡単なのは、他に熱中できるものや心安らげる場所を増やして、SNSの存在感を相対的に弱めていくことではないでしょうか。
複数の「イドコロ」を持つことで心身のバランスを取る
伊藤 はい。疲弊した精神を回復し、自分が居心地よくいられる空間や場を「イドコロ」と呼んでいます。よくおしゃべりする友人やお気に入りのお店など、誰にとってもイドコロのような場所はあると思いますが、それらを複数持っておくことにより、一つの言葉や考え方に極端に依存せずに済むと考えています。
これからはコミュニティが大事だみたいな話もありますが、コミュニティは依存度が高くなると内部で序列ができたり相互監視が発生したりする危険性をはらんでいる。だから、コミュニティよりも流動的で、人が行き交う「淀み」のようなものとしてイドコロが必要です。
かつては「サードプレイス」*1、つまり自宅や会社以外の第三の場所の重要性が説かれることも多かったですが、サードプレイスの代表格だったカフェなどは近年、回転率を上げて長居させない経営方針にシフトしつつあります。家賃や材料費が高騰しているのでやむを得ないのでしょうけど。
伊藤 それに加えて、現代の情報環境は、たとえるなら体にさまざまな種類の病原菌が絶えずアタックしてきているような状況です。それこそ陰謀論から脅しのような広告、個人への高金利金融へのいざない、怪しい不労所得ビジネスへの誘いまで無数にあります。
私たちもサードプレイスひとつでこの環境に対応しようとするのではなく、免疫の仕組みのように複数の“免疫細胞”を連携させて対応していくべきではないかと思うんです。自然界での病原体は寄生虫、細菌、ウイルス、毒素など無数にあるのに、私たちが概ね健康でいられるのはそれぞれに対応した複数の免疫細胞が連携して対応しているからです。一つの対策では対処できません。
伊藤 自然系のイドコロは、家族などの生活を共にする集まりや、友人・仕事仲間といった接する時間も持続時間も長いものです。これらは意図的につくろうとしなくても生活の中で自ずと生じるものなので、「自然系」と名づけました。
対する獲得系のイドコロは、必要に応じて自分でつくったり見つけたりするものです。例えば「日頃通える小さいお店」もそうですし、個人が立ち上げる非営利のイベントスペースやシェアスペース、集会所といった「有志でつくるオープンな空間」なども挙げられると思います。

伊藤さんも運営者に名を連ねるシェアスペース「スタジオ4」。空いた時間などにユニークなイベントを開催している
伊藤 僕も社会人になりたての頃がそうでした。当時、京都から東京に引っ越してきたばかりで気軽に会える友達もおらず、会社に行って帰ってくるだけの生活で、充実感どころか生活感までもが乏しかったんです。周囲にお店は多いエリアだったんですが、薄給だったので金銭的な余裕も時間的な余裕もなくて、ひたすら零細チェーン店の立ち食い蕎麦ばっかり食べていたのを覚えています。
伊藤 不確実なものに時間と労力を使うくらいであれば確実なものを選びたい、という気持ちはすごく分かります。忙しく働いていると特に「そんな暇があったらもっと稼げ」という空気も感じるでしょうし。
ただ、チェーン店の場合、お店の人やお客さんとのイレギュラーなやりとりが発生しづらいんですよね。もちろんやり過ぎると迷惑なので限度はあると思いますが、ときどき行くお店で知らない人や顔なじみの人とひと言ふた言喋るのって、すごく健康的なことだと思います。
そういう意味では、自分がそこにいて居心地よく思えることがポイントなので、知り合い同士が集まる場所ではなくてもイドコロになりえます。僕は銭湯によく行くんですが、名前も知らないおじいちゃんたちが軽い会話をしているところに居合わせる時間が好きなんですよね。一方が「長生きしなよ!」と言うと、もう一方が「もういいよ!」とか言いあっている(笑)。
コロナ禍では数年にわたって移動の自由が制限され、人と喋る機会も減ってしまったわけですが、好きな場所に移動して軽い世間話ができるというのは本来、メンタルヘルスにとっても非常に重要なことだろうなと思います。

伊藤 あるいは「文明から離れて一人になれる場所」も重要なイドコロのひとつです。都市生活の中ではなかなか想像しづらいかもしれませんが、現代だと神社にある森の中などが当てはまるでしょうか。ソロキャンプも一人になるためのいい機会でしょうね。これがなんで大事かというと、今の社会環境だと人間関係の占有率が高過ぎるからです。長い人生で考えたら些細な上司や職場の人間関係が世界の全てになってしまうと、精神的に追い詰められてしまう。
伊藤 屋上はいいですね。都会暮らしの人にとっては手軽に一人になれる場所だと思います。僕自身もいっとき屋上付きの物件を探して住んでいたことがあります。屋上はどうやっても有効活用しきれない余白空間になっていて、太陽とか風を感じやすい場所です。商業的にフル活用できない空間はいいと思います。
それとも少し重なりますが、公園や図書館など、公共空間の中に気に入ったイドコロを見つけるのもおすすめです。公園はよほど人が集まるところ以外はそこまで混んでいないと思うので、ボーっとベンチに座って人々の動きを眺めるだけでもいいんじゃないかなと。疲れているときは特に、自然のある場所に行くのが精神的にもいいと思います。
久しぶりに誰かと交流したいけれど急にイベントなどに行くのはちょっと尻込みしてしまう、というときも、公園のような公共空間で他者に対する信頼感をある程度得た上で、段階的にどこかに足を運んでみるのがいいかもしれないですね。周囲を見回してみて、のんびり過ごしている人達が多い場所、時間帯がおすすめです。その空間で過ごすだけでも「意外とみんな悪い人じゃないな」という実感が取り戻せると精神に良いと思います。
何十人も集まる必要はない。「強い趣味」を起点にしたイドコロ
伊藤 はい。ややマニアックな趣味や遊びを何人かで集まってするような「強い趣味の集まり」も獲得系イドコロになるんです。例えば、僕の場合は住居の床を張るだけの集まりや、ブロック塀をハンマーでぶち壊す集まりをやってるんですが、同好の士を少し見つけづらいぐらいの趣味の方が、集まったときの感動も大きいですし、変に人が増え過ぎないのでイドコロになりやすいと感じています。
伊藤 オープンなイベントの場合、シンプルですが、興味がありそうな人に個別でメールやメッセージを送りつつ、イベントページを作成して応募も受けつける形が多いですね。紙でチラシを配ったり関連するテーマのZINEをつくって頒布したりするのも最近の好みです。
伊藤 確かに、そういう心配をする方は多いですね。「イベントに人が集まらなかったらどうするんですか?」と聞かれることもあるんですが、たくさん集まらなくても楽しめる企画をやることがおすすめです。それに、仮にあまり集まらなかったとしても、単にアルゴリズムの問題でタイムラインに表示されなかったとか、忙しい人が多い時期だったとか理由はさまざまあるはずなんですが、なぜか「嫌われているのかな」など自分のせいにとらえがちなんですよね。
現代社会はどうしても、そういった抽象的な恐怖が強まっている社会だと思うんですが、その中身を具体的にすることによって対応可能なものに変えていくという工夫もありじゃないかなと。実際に個別に聞いてみたら、「外でブロック塀で壊すには、ちょっとその日、暑過ぎないですか?」と返ってくる可能性もあるわけじゃないですか(笑)。そうしたら壁壊しは涼しい季節にやるべきだ、という学びが得られる。あるいは「かき氷付き!熱闘ブロック塀壊し」と称して告知するのがいいのでは? とか。

伊藤さんが設立した「ブロック塀ハンマー解体協会」の活動の様子

伊藤 人ができるだけ集まった方がいい、という価値観に引っ張られてしまう引力が今はありますが、本来の集まりの目的や目標をできるだけぶらさないようにしたいですよね。思ったよりも人が集まらなかったとしても、数人でブロック塀を壊して楽しかったらそれは成功ですから。
むしろ、「100人に呼びかけてひとり来るか来ないかぐらいのラインを狙ってみよう」と思えたら、ちょっと気が楽になります。実際のところ、それなりに告知した結果で一人しか来なかったとしたら、その一人は稀有な方です。相当濃いイベントになるんじゃないでしょうか。
イドコロという観点から言えば、何十人も集まるよりも、長年の友達になりそうな人がひとり来てくれたり、細々と続く集まりになっていく方がよっぽど本人にとっては意味があるでしょうし。集客以外に、自分なりの狙いや目標を定めてみるのがいいかもしれません。もちろん会場費の関係で、たくさん人を集めないと赤字、とかそういうことはあると思いますので、条件によりけりですが。

同じく伊藤さんが設立した「全国床張り協会」の活動の様子
損得勘定の優先順位を下げてみる
伊藤 複数回開催のワークショップや講座はおすすめかもしれません。単発で終わってしまうのではなく、ある程度時間をかけて一つのことに取り組むことにより、参加者同士で自然と相互作用が生まれて、イドコロになり得る可能性が高いと思います。
僕も新社会人時代は疲弊しきっていたので、この際東京を出て、田舎で農業をしようかな……と具体的に研修先を探したり、かなり悩んでいたんです。ただその前に、せっかくならすこしでも都たる東京っぽいことをしてから帰ろうかなと思って、世田谷ものづくり学校という場所で開かれていた社会人向けの講座に3カ月間通いました。僕の場合は、そこでさまざまな専門や興味を持つ知り合いが増えたことがとても大きくて、今でも重要なイドコロの一つになっています。
伊藤 それはすごく重要な点ですね。ダイレクトな交流は難しい! 人がなんの媒介もなしにいきなり会話を弾ませるって難易度が高いんです。例えば茶道などは、茶器を媒介にして喋っているうちに自ずと交流が深まるしくみになっている。イドコロをつくったり見つけたりする場合、まずは人以外のものに注目し、二次的に他者との交流が生まれるという形が理想的だと思います。
個人的な話でいうと最近、何人かで穴掘りをしたんですよ。とある学生が「穴を掘りたい」と言い出して。同じ頃、知り合いが「竪穴式の小屋をつくりたい」と言っているのを聞いたので、これは奇跡だと思い「ちょうど穴掘りしたがってる学生さん知ってるよ!」と(笑)。そこであらためて穴を掘りたい人を募集してみたら意外と集まったので、人が入るくらいの巨大な穴を、みんなでただ掘って帰ったという。
伊藤 穴掘りのよかったところは、お金儲け要素が一切ないどころかたいした目的もないことと、上手・下手で争いようがないこと。もちろん穴掘りである必要はないんですが、もしも参加するなら、その作業自体に純粋に惹かれるような集まりは良いと思います。

伊藤 そうなんですよ。それと、ときにはどうなるか分からない要素を許容して飛び込んでみるのも大切なんじゃないかと思います。「絶対におもしろい、役にたつ」という確信があるものだけを選んでいくと、知らず知らずのうちに路線が規定されて、もうこの道を進んでいくしかない、と錯覚してしまいやすくなると思うので。
仕事で不確実な道を次々と選んでいくのは難しくても、趣味なら気軽にできますからね。せっかくの趣味なんだから、あえてノイズを取り込んでみるのもありじゃないかなと思います。もちろんその趣味が仕事に繋がるときもあるし、結果として多少の損得勘定はあってもいいけれど、損得を最優先の価値基準にはしない、というルールで僕自身はやっていますね。
取材・文:生湯葉シホ
撮影:小野奈那子
編集:はてな編集部
自分にとってよい「人間関係」を築くには?
お話を伺った方:伊藤洋志(いとう・ひろし)さん
*1:アメリカの都市社会学者レイ・オルデンバーグが提唱した概念。自宅や職場ではなく、居心地の良い第三の場所のことを指し、日本でも大きな注目を集めた