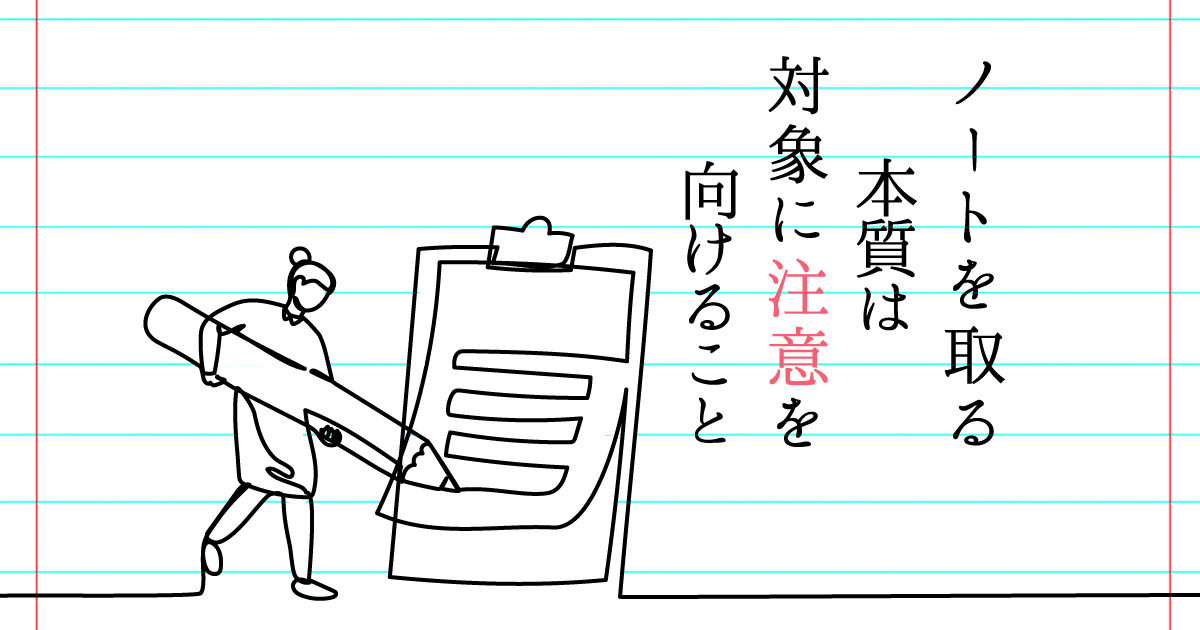
職場での仕事に慣れてくると、次第に“習慣”で仕事をこなすことができるようになってくるもの。それは一見すると快適なようにも思えますが、うまくいかないこともそのままにしてしまったり、いざ新しい業務を任されたときに、仕事の仕方を変えられず、行き詰まりを覚えてしまったりすることにもつながりかねません。
作家の倉下忠憲さんは、絶えず自分の仕事のやり方や作業環境を見直しながら日々の業務に取り組んでいます。そこで重要なのがノートを取り続けること。著書の『すべてはノートからはじまる あなたの人生をひらく記録術』でも、仕事に役立つさまざまなノート術を紹介されています。
働き始めた当初は仕事の振り返りとして日報を書いたり、ノートにメモをとったりしていても、徐々にそうした時間をとらなくなったという人は意外と多いはず。ただ、この記録を取り続けることは、仕事のやり方や習慣をアップデートしていくためにも有効なようです。
今回はそんな倉下さんに、そもそもノートをとることの効用や、仕事のやり方を見直すためのノートの使い方などを伺いました。
ノートをとることは、対象に「注意を向ける」こと
倉下忠憲さん(以下、倉下) 英語の「note」には「記録をとる」だけでなく「注意する」という意味もありますが、まさにこの「注意する」がノートをとることの本質だと考えています。ノートをとろうと思ったら、雑多な情報の流れのなかで、自分が興味・関心を持っているものに注意を向けなくてはいけません。それによって、ふだんは無意識のレベルでできていることでも意識せざるをえなくなり、時間の使い方が主体的・自主的に変化していく。これが僕の思う、ノートをとることの意味です。
習慣とは何かと言えば、私たちが無意識にやっていることですよね。ただ、たとえば仕事のやり方にまつわるノートをとろうと思ったら、「自分はいまこういうふうに仕事をしている」とまず言語化し、意識する必要が出てきます。だから、ノートをとることには、習慣を変えるための土壌を整えるような役割があるのではないかと思います。
倉下 それこそ無意識で書いているような状態だと、仕事のやり方を改善する、という観点からは効果が薄いでしょうね。もちろん、それでも日報という形で「自分がやった作業の総数が残っている」こと自体にも、一定の意味はあると思いますよ。人間の記憶って曖昧で、自分が積み重ねてきた実績を軽んじやすい。だから、作業の総数を記録しておくだけでも、自分が進んできた道のりがどんなものだったかを客観的に確認できる、という効果は得られると思います。
ただ、日報と違ってノートは自分だけの情報環境という点が重要です。日報だと、社内のシステム上に記録することになるでしょうが、それでは転職したときに自分の記録が失われてしまう。一方で、自分のノートに記録を取り続けていけば、これまでの仕事のやり方がいつでも参照できるようになります。仕事のやり方を俯瞰し、業務を改善するスキルは、どんな職場でも生かせると思うので、できるなら日報とは別にノートを取るのがおすすめです。
仕事の進捗や変化が実感できないのは、記録が不足しているから
倉下 人によるとは思うのですが、基本的には自分が担当している仕事の内容と作業手順を記録することが重要だと思います。これまでノートを取る習慣が全くなかったのであれば、最初はできるだけ細かく作業の内容や時間を記録することにより、どこでどれだけ時間を使っているのか、よく使用するツールは何なのかなど、自分の仕事のやり方の全体像が見えてきます。
僕自身は一日の仕事が全て終わってからまとめて書くのではなく、作業と記録を一つのパッケージとして考えています。具体的には、毎日仕事を始める際に、作業記録用のテキストファイルに「いまからこういう作業をする」と宣言を書き、作業しながら同時並行的に記録を追加していく。
そのときに、できれば作業中に感じた課題や気付きも同じテキストファイルに記録していき、余裕があれば次回以降の作業で意識したいポイントを書き残しておくんです。このやり方であれば書き忘れも減ると思いますし、記録することを念頭に置きながら作業することで課題などにも気付きやすくなると思います。

倉下さんが記録している作業記録の一例
倉下 そうです。もちろん、いきなりたくさんノートを取ろうとし過ぎると続かなくなってしまう恐れがあるので、まずは作業記録を優先でいいと思います。ただ、余裕があるときに記録を眺めて感じる疑問を文章の形にして残していけば、課題とその原因が明確になってくるはずです。
最初は、「ここが詰まってる」とか「時間がかかり過ぎ」とか、ごく簡単なことで構いません。その上で、自分なりに改善のための仮説を立てて、仕事のやり方を少しずつ変えていくんです。例えば、ある特定の作業に時間がかかり過ぎなのであれば、使用しているツールを変えてみて、前後でどれだけ時間が短縮されているのかを記録から比較してみたりとか。
あるいは、自分で課題の原因がハッキリしない場合には、記録したノートを同僚や先輩に見てもらうのもいいと思います。作業の記録があれば人に相談しやすいですし、そうすることによって自分では気付かない仕事の進め方の癖を知ることができます。
倉下 「進捗がいまいち分からない」というのは、たいてい記憶に頼って、記録が不足しているからです。作業記録をつけることで、プロジェクトごとの進み具合が明確になりますし、変化を楽しむこともできるようになると思います。
たとえば、僕は仕事を進める上で「フォントを変えてみた」というくらい微々たる変化であっても、それが意識的に変えたことであれば記録しておきます。そこには「変えたったぞ」みたいな軽いドヤ心もあって、モチベーションにもなります(笑)。もちろん、その時点ではフォントを変えたことがどういう価値を持つかは分かりませんが、継続的に記録することで徐々に結果が見えてきます。
倉下 そうですよね。みなさん、仕事をはじめたばかりの頃といまとを比べたら、いまの方がはるかに精度の高い作業をされているはずですからね。でも、それを無意識にやっていると、成果がなかなか実感できずマンネリ感を覚えてしまうというのはあるのではないでしょうか。
走り書きのメモは生鮮食品のようなもの
倉下 そうですよね。僕自身は、作業記録はテキストファイル、作業とは別に何かアイディアを思いついたりしたときには、Scrapboxというツールにメモしています。当然、外出先などでiPhoneに思いついたことを走り書きするような場面もあるのですが、そのときはできるだけ一両日中にまとまった形に整理するようにしています。僕の中では、iPhoneに残すような短いメモっていわば生鮮食品なんですよ。早く処理しないとせっかくのメモがロストしてしまいます。
倉下 そうなんです。あと強いて言えば、急いでスマホにメモするようなときは、できるだけ文章の形にしておくことを意識しています。単語など断片的にしかメモしていないと思い出しづらいですが、一文程度でも文章にしておけば仮に何日かたってしまっても、読み返したときに思い出しやすいと思います。
ただ、同時に意識しているのは、それでも思い出せないものは、思い切ってロストしてしまってOKと割り切ることです。走り書き全てをきちんと整理した形にまとめようとすると義務感が芽生えて長続きしないので、このあたりの調整は必要になってくるかなと思います。
倉下 一つは、やっぱりノートを不真面目に扱うことですよね。作業記録にしてもアイディアのメモにしても、何か一つのフォーマットに則って続けようとすると、それに当てはまらない項目が出てきたら嫌になってしまう。そうではなく、せっかく自分だけの情報環境なわけですから、記録のとり方自体もどんどん変わっていくことを許容することが大切だと思います。僕自身も、1年前と今とでは記録のとり方や内容が変わっていますし、疲れているときはすごく簡素なメモだけの日もあります。
それと、僕の場合は先ほどの作業記録がメモであり、毎日の仕事を始める上での起点でもあるんですよね。まず昨日の作業記録を読み返すところから仕事を始め、それによって昨日の自分の感覚や気付きを引き継ぎながら、その日も記録を取りながら仕事をすると。何をするにせよ、基本的にまず作業記録を読み返すところから始まるので、続くのかもしれません。
倉下 そうですね。僕の場合は、そもそも自分の仕事のやり方を完成形と捉えずに、実験の積み重ねのように考えているところがあるんです。だから、積極的に新しいツールが出れば試してみますし、それを記録することで変化を楽しむことができる。だから、仕事自体の捉え方を少し変えてみると、ノートも続くかもしれませんし、相乗効果で仕事の改善も進むのではないでしょうか。
取材・文:生湯葉シホ
編集:はてな編集部
仕事のやり方に行き詰まったら
お話を伺った方:倉下忠憲(くらした・ただのり)さん







