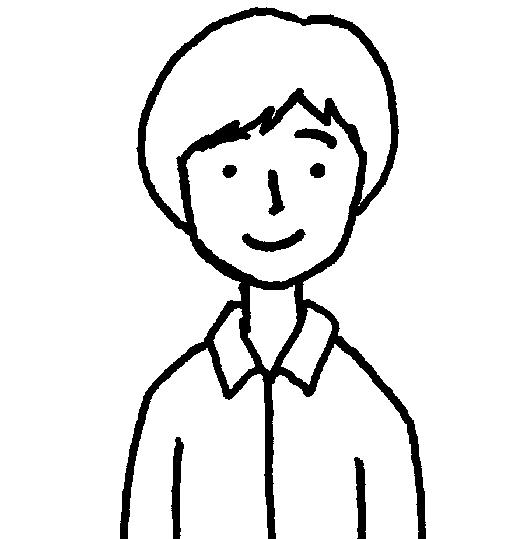自分には、今より合っている仕事や、もっと夢中になれる仕事があるんじゃないかーー?
働く上で、そんな悩みを抱いたことはありませんか。
好きなことを仕事にすることの素晴らしさや、一貫したキャリアを歩むことばかりが評価されがちな現代ですが、「自分はどんな仕事に向いているのか」を自己分析し、就職・転職するのは簡単なことではありませんし、それが“正しい”とも限りません。
今回お話を伺ったフリーランス校正者の牟田都子(むた・さとこ)さんも、30歳で「校正」という仕事に出会うまで、「好きだけど、向いていない」という理由で何度か転職を経験してきました。ときにはあてもなく仕事を辞めて「無職」になったことも。
しかし校正の職に就いて13年がたち、「指名」で仕事が来るようになった今でも、この仕事が自分に向いているとは思っていないそうです。そんな牟田さんに「仕事との出会い方」や「好きな仕事と適性のギャップ」などについて伺いました。
※取材は新型コロナウイルス感染対策を講じた上で実施しました
「たかが仕事」に追い詰められなくていい
牟田都子さん(以下、牟田) 大きく分けると言葉そのものの間違いをチェックする仕事が「校正」、事実関係に間違いがないかを確認する仕事が「校閲」なのですが、私はどちらも合わせて校正、と呼んでいます。
私の場合は本や雑誌の校正が専門で、著者や編集者がなにを伝えようとしているのかを考え、より伝わりやすくするためにサポートをする仕事、と捉えています。
牟田 いえいえ。最近になってやっと仕事がおもしろくなってきましたけど、今でも自信はないですし、校正が「自分に向いている仕事」だとは感じていません。たまたま続いているだけで、10年、20年先も同じ仕事をしているか、と聞かれたら正直、全然分からないです。
この仕事をはじめたのが30歳とひとつの節目の時期だったので、「辞めたらもうあとがない」と思ったこともありましたが、実際には仕事なんて何度変えてもいいと思うんですよ。急にもっとやりたい仕事が見つかるかもしれないし、私はフリーランスだから、ある日とつぜん仕事がこなくなるというのもありえない話ではなくて。
牟田 私も無職を経験したことがあるので、「次の仕事が見つからないかも」と怖くなる気持ちはとてもよく分かるのですが、「この仕事しかないはずだ」と必要以上に自分を追い詰めて苦しまなくても大丈夫だと思うんです。
仕事なんて「たかが仕事」ですからね。自分の人生を犠牲にしてまで苦しい仕事を続ける必要はまったくないかなって。

牟田 私も若いときはそうでした。特に20代、30代は「今の仕事を続けるかどうか」や「転職したいけれど新しい仕事をどう探そうか」など、迷うことも多いと思います。
でも、1つの仕事を続けられる人もいれば、職を転々とする方が性に合っている人もいる。最初はそれほど思い入れのなかった仕事が、続けていくうちに好きになったり、うまくできるようになったりすることもある。仕事の内容そのものでなく、職場の雰囲気や人間関係の心地よさを重視するという選び方もある。
たまに「どうしても校正の仕事がしたいんです」という相談を受けることがあるんですが、「そんなに思いつめない方がいいよ」と思うんですよね。想像していた「校正」の仕事と実態にギャップがあったら、つらいじゃないですか。「私にはこの仕事しかない!」とまでは、思わなくてもいいんじゃないかな。
好きで始めた仕事。でも私には「向いていなかった」
牟田 もともと本が好きで、図書館員になりたくて大学で司書の資格を取りました。「本を読む」を手伝える仕事っていいなあって思ったんです。
最初はアルバイトとして近所の図書館で働きはじめて、翌年に運よく嘱託職員になりました。途中で契約期間が終わり一度他の図書館に再任用されましたが、図書館員自体は7年ほど続けて、28歳のときに辞めました。
牟田 最初にいた図書館ではいろいろな業務を経験させてもらえたし、同時採用になった人たちと息が合っていたこともあって、すごく楽しかったんです。けれど再任用された図書館は最初のところとカラーが違い、職場の雰囲気になじめなくて。
それ以上に理由として大きかったのが接客に「向いていない」ことでした。7年かけて「話しかけられて業務を中断する」ことがすごく苦手だと気付いたんです。
牟田 けれど図書館員としては、本を探している方に話しかけられたら、自分の業務を放り出して対応すべきですよね。私は、それがどうしてもうまくできなくて。この仕事に向いてないんだなと思って、そう思う自分もすごく嫌で、どんどん追い詰められていって……。
職場の雰囲気にいつまでもなじめないというストレスも重なって、ある日プツンと糸が切れてしまい、次の日に辞表を出しました。
牟田 ちょうど私が図書館員を辞めるすこし前に、図書館を民間業者に委託できるようになる指定管理者制度が始まり、同僚の間でも「図書館員を一生の仕事にしたいけど、いつまで続けられるか分からない」と考える人が増えていました。
そういった流れもあり、じゃあ私が一生できる仕事ってなんだろう、私に向いている仕事ってなんだろうと考えるようになったんですが、そのときは見当もつかなかったです。
父から言われた「その仕事は向いていない」が転機に

牟田 まったくなかったので、とにかく不安でした。友人に誘われてゲームの攻略本やシナリオを書く仕事を手伝ったりしたんですが、それも長くはできなくて。周りの同世代の人たちは30歳を前に次々と結婚・出産していて、ただでさえ迷う時期でした。
そんなときに、近所の商業施設にある生活雑貨店がアルバイトを募集しているのを見つけて。接客が苦手で図書館を辞めたはずなのに、そのお店が好き過ぎて飛びつくように販売員になりました。
牟田 そうですそうです。周りは販売員歴が長い人ばかりで、私だけがまったくの素人だったので、もう、本当に使えないアルバイトだったと思います(笑)。
ギフト需要が高い店で「この商品を30個、夕方までに包んでほしい」「予算1万円でギフトボックスに詰めてほしい」など、毎回お客さまから違うオーダーを受けるんですね。その全てにいちいちテンパってしまって……。
ギフト用のリボンを結ぶ練習を家でどれだけしても、いざ職場に行くとうまくできない。土壇場に弱くて、お会計を間違える。
職場ではずっと緊張しているから家に帰ると倒れ込むように寝てしまって、気が付いたら朝がきている、という毎日でした。
牟田 つらかったです。あまりにもつらくて、実家に帰ったときにぽろっと父にこぼしたんですよ。そうしたら「販売は向いていない」ときっぱり言われました。
牟田 「わざわざ言う!?」と思いましたけどね(笑)。
と同時に「正社員としてではないけれど、自分のいた校閲部の仕事を紹介することはできるかもしれない」と言ってくれたんです。
じつは父は、30歳で大手出版社の校閲部に転職して、そのまま定年まで勤め上げた人で。それまで私自身が「校正」の仕事に就くことはまったく考えていなかったんですが、「校正は腕さえよければ一生できる仕事だ」と言われて、確かに父もそうだったしな、と。

今働いているお店のことがやっぱり好きだし、“コネ”のような形で入るのは……とすごく悩みました。
けれど、図書館員としての本の知識がすこしは役立つかもしれないと思って、悩み抜いた末に、父がかつて働いていた出版社の校閲部に業務委託で入ったんです。ちょうど30歳になった年のことでした。
「がむしゃら期」のおかげで、今の自分がある
牟田 毎日戸惑うことだらけでした。けれど、他にやりたい仕事があったわけでもないし、身内に紹介してもらったのに何もできないままやっぱり辞めます、なんて言えないじゃないですか。30歳という節目のプレッシャーもある。
なんとかして早く一人前にならなきゃと思っていたんですけど、最初の頃はまったく使いものにならなかったと思います。
2年目に、見かねた部長が、定年まであと1年の大ベテランの“師匠”と同じチームにしてくださったんです。
「この1年を逃したらあとがない、どうにかして仕事を覚えなければ」と必死になって、師匠が仕事をするのを隣で見ながら、できるだけ同じように仕事しよう、ぜんぶ真似して覚えようとがむしゃらな1年を送りました。
牟田 もちろんありました。けれど、師匠は「校閲部にこの人あり」と言われるほど仕事のできる人で、こんな人と組ませてもらえているのに辞めるなんて絶対にできない、という気持ちの方が強かったですね。
当時は、私が読んだゲラ(校正用に刷った原稿の試し刷り)を次に師匠が読んで、見落としや間違いを全てフィードバックしてもらっていたんですが、毎日すっごく胃が痛かったのを覚えています。
牟田 最初にお話ししたとおり「辞めたらもうあとがない」「私にはこの仕事しかない!」とまで思い詰める必要はないですが、人生にはどこかで「がむしゃらにならないといけない」時期があるとは思っていて。
私にとっては師匠と組んでいた1年とそのあとの数年ががむしゃら期でした。矛盾するかもしれませんが、そういう時期が自分を成長させてくれるという一面も、間違いなくあるだろうなと思います。

牟田 いえいえ、私は「校正」という仕事を覚えるのにすごく時間がかかった方です。
職場には師匠のほかにも、本当に仕事ができる人が嫌になるくらいいて、追いつくためにもっと仕事を覚えなきゃ、と必死になっていたら、5年、10年があっという間に過ぎていたというのが素直な実感です。
校正者になって13年たった今、ようやく、仕事が「楽しい」と感じるときもある、という感じで。
自分の適性を「信頼している人」に見つけてもらう
牟田 私はこのごろ、自分の適性は自分で探すのではなく、信頼している周囲の人たちに見つけてもらってもいいんじゃないかと思うようになりました。自分のことを一番よく知っているのは自分ではなく、逆に「自分は自分のことを一番知らないんじゃないか」とさえ感じています。
というのも、私が校閲部で文芸誌の校正をしていた頃、評論や批評のようなジャンルを任せていただくことが多かったんです。自分では評論や批評の校正が向いているなんて思ったことは一度もないんですけど、小説などのフィクションと違い、調べると「明確な答え」が分かるのが楽しくて。
でも、私のそういう適性を見抜いたのって、私自身ではなくて、仕事を振ってくれた上司だったわけです。
牟田 実は30代半ばくらいのとき、校正の仕事をしつつも「私にもっと合う仕事があるんじゃないか」とまだ悩んでいて、いろんなワークショップに行ったり、あこがれている人のトークイベントに行ったり、人に会いまくっていた時期があるんです。
そこで尊敬する方の言葉に直に触れたり、いろんな人の働き方を知ることができたのは自分にとってすごく大きな機会だったと思います。会社勤めを辞めてフリーランスになったのも、信頼している人に「あなたは自分のペースでやりたい人だよね」と言ってもらえたことが大きかったです。

イベントに通っていたことがきっかけで、「こっち(登壇する方)になってみない?」と言われてトークショーをやったり、今日みたいに取材を受けたり。
……考えてみたら、校正以外にいろんな仕事をするようになったのも、やっぱり周りの方が「あなたはこういうことが向いていると思う」と声をかけてくださったからなんですよね。自分ひとりでは、ここにたどり着けなかったと思います。
牟田 確かにそうかもしれません。いい意味で「受け身」になって、他者に委ねてみてほしいです。
どんなベテランでも「ミス」が起こり得る仕事
牟田 そうですね。まずはゲラを1文字1文字鉛筆でたどりながら読む「素読み」で、漢字の正誤や変換ミス、「てにをは」の抜けがないか、文章がねじれていないかなど、文字や単語の間違いを確認します。
最後まで読み終わったら、次は資料を確認して書かれていることが事実かどうか調べながらもう一度読んでいく。言葉の確認と調べものが終わったら、最後にもう一度、全体を通して読む。これで3回というのが私の基本のスタイルです。
牟田 近年はインターネットの出現で「調べられることの幅」が広がったので、文字を読む「校正」の時間よりも、調べものをする「校閲」の時間の方がずっと長い、というケースも珍しくないんですよ。

時事性の高い情報はまだ「紙」になっていないこともあるので、インターネット上の情報をいくつも見比べて、できるだけ信頼できる情報を見極めていく、ということもしなければいけない。 信頼できる情報にどれだけ短時間でたどり着けるかは校閲の「技術」ですね。
しかも、最近は誤植に気付いた読者の方が、レビューやSNSに書くことも少なくないので、本当に気の抜けない仕事です。間違いがひとつでも残っていると、読者の方がその本を信頼できなくなってしまうと思うので。
牟田 そうですね。私が出版社の校閲部にいた頃担当していた雑誌は、校正を2回通さないと世に出ないことになっていて。1回の校正につき2人で見るのが原則だったので、校正を2回通すあいだに、4人の目が入るわけです。それだけ「目」を替えているのに、本になったあとに誤植に気が付く、ということが完全には防げなくて……。
この仕事をしてる人は、みんな自分のことなんか信用してないと思います。私もすごく疑り深いですから(笑)。
牟田 赤字を入れるための引出し線がきれいに引けたとき、とか……(笑)。
ゲラに書き込む文字や線は、著者、編集者、デザイナーなどいろんな方が見るので、きれいで読みやすくないとだめだと思うんです。私は字が汚いのがずっとコンプレックスだったんですが、あるとき先輩に「でも、ゆっくり丁寧に字を書くことはできるでしょう?」と言われて、それを心がけていたら13年かけてやっと自分の思う字が書けるようになってきたんです。
いまでも自分の字は好きではないんですけど「あっ、この字はうまく書けたかも」という瞬間がたまにある。そういうときは楽しいです。

牟田 もちろん、1冊の本をここまで時間をかけて深く読み込むという経験はなかなかないので、本を通じて新しい世界が拓けていく、という楽しみもありますよ。
当然ですが校正する本は毎回内容が違うので、同じ著者の本でも、1冊目と2冊目で時間のかかり方がまったく違ったりするんです。だから、新しい1冊をお預かりするときは「これ本当に終わるのかな」っていまだに怖いです。
たぶんずっと慣れないんだろうな、と思っていますし、慣れちゃいけないんだろうな、とも思っています。
取材・文:生湯葉シホ
写真:関口佳代
編集:はてな編集部
お話を伺った方:牟田都子さん