
子どもが学校に行くのを嫌がる「行き渋り」。人間関係や勉強へのプレッシャー、環境変化によるストレスなど、さまざまな原因によって起こると考えられています。
特に働いている親にとっては、朝の登校と自身の勤務開始が迫るなかで対応・判断に迫られる難題。さらには、その後も行き渋りが続くのではという不安も残るでしょう。
子どもが登校を嫌がったとき、親はどのように対応すればいいのでしょうか? 元小学校教諭で現在はフリースクール「コンコン」代表などを務める福田遼さんにヒントを伺いました。
時代の変化に伴って「学校に行くこと」の意味が揺らぎ始めている

- 学校に行きたくない理由は「分からない」がほとんど
- 昨今、教育を取り巻く環境の変化が複雑に絡み合い「学校に行くこと」自体の意味が揺らいでいる
- 子どもと一緒に登校のメリット・デメリットを整理して、家庭としての方針を決めるのが理想
福田遼さん(以下、福田):実は、子ども自身に行きたくない理由を聞いても「分からない」と言われることが多いです。ただ昨今の行き渋りや不登校の背景には、教育を取り巻く環境の変化に伴うさまざまな要因があると考えられています。
例えば、以下のような事象です。
- 学習指導要領の改訂によって、主体的な思考や発言を促す「アクティブラーニング」が増え、授業を受ける子どもたちのプレッシャーが高まっている
- 感染症への捉え方や対策が変化するなかで生活習慣や衛生観念も変化し、たくさんの人や物に触れる学校生活に対して、子どもたちの抵抗が生まれやすくなった
- デジタルデバイスの普及やフリースクールの登場などによって、学校に行かなくても学べる選択肢が増えた
こうした複数の要因が絡み合い、子どもたちのなかで「学校に行くこと」に対する“揺らぎ”が生じているのかもしれません。
登校しなくても、デジタルデバイスを使えば効率的に学べる。フリースクールに行けば人間関係が築ける。そもそも、学校に行かなくても幸せな人生を送っているロールモデルはたくさんいる。
従来の「学校に行かなくなったら勉強ができないし、人生の可能性が狭まる」といった固定観念が揺らぎつつある今「何のために学校に行かなくてはならないのか」という疑問が出てくるのは、ある意味で当たり前だと考えています。
福田:そうですね。毎朝早く起きて登校し、決められた時間割どおりに集団で行動しなければならない学校生活は、そもそも子どもにとって負荷が高い行動なんです。
学校に行くことに対する疑問を抱えたままなんとなく続けるのは、難しくて当然。社会の急速な変化に対して学校や家庭がついていけていないのも、致し方ありません。
「学校とどう付き合っていくのか」という答えのない問いに向き合い始めたのが、現在の状況だと感じています。
福田:現時点では、例えば中学生が家庭学習を選ぶと出席日数が確保できず、公立高校の受験が難しくなるといったデメリットがあります。でも、自分で計画的に勉強を進めていけるなら、必ずしも出席しなくたって、何らかの進学先を見つけられる可能性はある。
だからこそ、子どもと一緒に登校のメリット・デメリットを整理して家庭としてどうするのか方針を定めることが、本質的にはとても重要だと考えています。
福田:はい。その上で「やはり学校に行こう」となる場合もあれば、別の道を模索する場合もあると思います。
「休みたい」と言われたら、子どもの自己決定を促しつつ擦り合わせを

- 進級や長期休暇明けなど、環境の変化があるタイミングで行き渋りが起こりやすい
- 「休みたい」「保健室登校にしたい」など、まずはどうしたいかを子どもに自己決定させる
- 子どもに自己決定させた上で、親の意向も含めて擦り合わせを
- 双方の意向をうまく擦り合わせるために、段階的な選択肢をいくつか用意しておく
福田:進級や長期休暇明けのタイミングなどは、環境や生活習慣が変わるため負荷が高まり、行き渋りが起きやすい時期です。今後の生活に見通しがつきにくい不安感も関係していると思います。
そして先ほどもお話ししたとおり、行きたくない理由を聞いても「分からない」「理由なんてない」が圧倒的に多い。「先生が怖い」「昨日友達とケンカしたから」などともっともらしい理由を教えてくれても、実際には建前でしかなかったりします。
福田:私は、一番大切なのは「子どもに自己決定させる」ことだと考えています。
親が「休んでいいよ」と許可する形だと、子どもは他人軸で判断することになって、その後も他責思考を引きずってしまいがちです。
そんな時に私が参考にしているのが、子どもの自律力を磨く取り組みを続ける、教育者の工藤勇一先生の言葉です。工藤先生は子どもの自己決定を促す声かけとして、次の3つの言葉を挙げています。
- どうしたの?
- どうしたいの?
- 私は何を支援したらいい?
参考:教育図書NEWS「工藤勇一×鈴木寛「これからの学校の話をしよう」part2」(詳細)
ここで重要なのは、困りごとをキャッチすること。「どうしたの?」という質問には、子どもが何に困っているのか、課題を整理して客観視するという意図があります。困りごとを吐き出し、保護者に一緒に解決策を考えてもらえるだけで、前向きな気持ちになれることも少なくありません。
しかし、ここで「(行きたくない理由が)ない」「分からない」と答えた場合は次の質問「どうしたいの?」に移ります。そうすると「休みたい」「保健室登校にしたい」などと本人の意向が見えてくるはず。
最後に「何を助けたらいい?」と聞くことで「学校に連絡してほしい」などと頼んでくるかもしれません。このように、親が勝手に動くのではなく、子ども発信の願いを親がサポートする状況を作ることが大切だと考えています。
福田:子どもが自己決定したあと実際にどうするかは、親の意向も含めて擦り合わせてほしいと思います。
私としては、従来の不登校サポートは「子どもの気持ちが何より大切だから、休みたいならすべてを受け止めて休ませてあげよう」というトーンが強過ぎたのではないかと思っています。親御さんからすれば、子どもが休んで自分が仕事に行けないのはとても困りますよね。
学校を休むか休まないかといった「子どもが主語の行動」は子どもの権利なので、これを親が強制することはできません。ただ、仕事を休んでほしいなどといった「親が主語の要求」は、断ることがあっていいと思っています。
その代わり、どうすればお互いに妥協できるかを、ちゃんとコミュニケーションして探っていきましょう。
その際、子どもの意思とは別に、親御さんが「私は〜と思う」という自分主語で対話することも大切だと思っています。「午前中は会社に行かなきゃいけないから、休むなら一人でお留守番できる? 午後には戻るよ」とか「朝、校門まで送っていけば登校できそうかな?」とか。
寄り添いたい気持ちのあまり、全ての要求を「子どものために」で受け入れていると、変な上下関係が生まれてしまいます。だから、時間のない朝に大変だとは思いますが、親の方からも自分の事情や意思を伝えてみてください。
福田:段階的な選択肢をいくつか用意しておくといいと思います。
「学校に行く/行かない」ではネガティブとポジティブの極端な二択になってしまうので「保健室登校にする」「給食を食べ終わったら帰ってくる」「フリースクールに行く」「家で自習する」などのメニューから、自分で選ばせるようにしたいですね。
保育園・幼稚園に通う幼児、小学校低学年生に対しても基本的には同じで、子どもの意向を聞くこと、親の意向を伝えること、段階的で選びやすい選択肢をいくつか用意しておくことが大切です。まだ「言語化」や「選択」が難しい年齢かとは思いますが、少しずつコミュニケーションを重ねてみてください。
ただ、暴言や暴力を振るうなど、社会的に不適切な方法での要求には絶対に応えないようにします。つい、目の前の朝を平穏に乗り切りたくて言うとおりにしてしまいたくなるのですが「泣けば聞いてもらえる」と思われるのは、長期的な視点だとやっぱりマイナスだと考えています。落ち着いて対話できるまで時間を置くことも大切です。
学校を休ませた日、家庭での過ごし方はどうする?
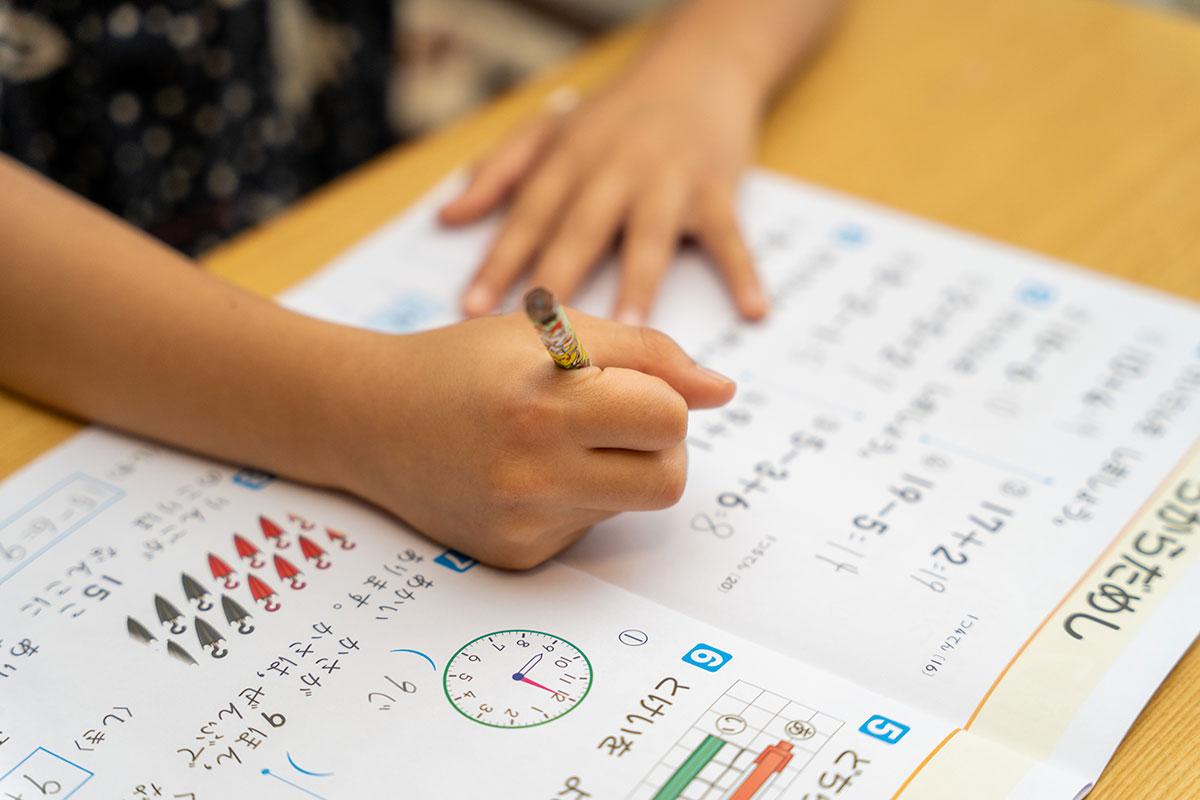
- いじめなどの明確な原因がある場合は、まず休養を最優先
- 明確な理由がなく再登校を目指すなら「学校でできないことを家でさせない」
- 家でやったことの成果が目にみえるような仕組みがあると、自己効力感につながる
福田:まず、いじめや人間関係のストレスといった明確な原因がある場合は、文字どおり休養することが大切。精神的な安心感につながるなら、子どものやることに対してとやかく言わずに、子どもが好きなことをする時間を多く取り、メンタルの回復を最優先します。
でも、明確な理由がない行き渋りで、かつ今後はできるだけ学校に行ってほしいと考えている場合は、学校でできる活動に絞って行うようにします。「学校を休んだらゲームができる」という状態になってしまうと、そりゃあ休んだ方が楽しいに決まっていますから。
その代わり、子どもが楽しめて、かつ依存性がないことに時間を使ってもらいます。好きなことの調べ学習や工作、お絵かき、読書など、没頭できる活動に取り組めるよう促しましょう。
ドリルなどの自習計画を立てたり、家庭のお手伝いで役割を作ったりして、やったことの成果が目に見えて分かるようにするのもいいです。小さな達成感を積み重ねることで、自己効力感(「自分にはこれができる」「うまくやれるはずだ」という自信や信念)が育まれます。
ただ、低学年のうちはこういったルールを決めれば納得してくれることが多いですが、学年が上がるにつれ「なぜルールが必要なのか」に疑問を持つようになります。なので子どもが理解できるように説明し、納得感を高めることが大切です。
福田:学校に行くことの負荷の高さを認めてあげた上で「今はしんどいかもしれないけれど、少しずつ慣れて力がつけば、負荷は小さく感じられるようになるよ」など、成長した先をイメージさせてあげるといいでしょう。
行き渋りが続きそうな場合、学校とどう連携していくか

- 慢性化しそうな場合、行き渋りの原因となっている原因を特定し、解消できる方法を考える
- 学校と相談して「子どもの得意なこと」を学校活動に組み入れてもらい、登校したくなる動機づけを
- 学校に相談する際は「目標と方針を共有」し、保護者主導で対応しようとする姿勢を示す
福田:行き渋りが長期化する子どもは、学校生活に対して何らかの困りごとがあると考えられます。原因を特定して解消できれば、登校のハードルが下がっていくかもしれません。
例えば、課題に応じて以下のような手法が考えられます。
- 学習面で自信を失っている場合
- 自身のレベルに合った予習復習で学力を高めていくなど、周りではなく「過去の自分と比較するマインド」を身に付ける
- 友人関係で困っている場合
- 良好な友人関係を築くための、コミュニケーションスキルを高めるトレーニングに取り組む
ただ、主だった原因を解消してもやっぱり休みがちになる……といったケースも珍しくはありません。その場合は学校との相談が必要ですが、子どもの得意なことを学校活動に組み入れてもらえるとベストです。
作文や読書が得意な子にクラス新聞の係を任せてみたり、電車が好きな子を電車クラブに入れたり。内発的動機が高まる活動があれば、登校したくなる可能性もあります。
福田:学校には、目標と方針を共有しながら相談するのがいいでしょう。
例えば「今はいきなり教室に行くのは難しいので、給食の時間は別室で食べ、少しずつ友達と接する時間を持つことで登校のきっかけを作りたい。子ども自身も頑張っているので、給食を食べられるスペースを貸してもらえませんか?」など、状況や先の見通しを共有するイメージです。
いきなり「別室を貸してください」だけ言っても、多忙な学校側がすぐ動いてくれるとは限りません。もし教師を責めているように受け取られてしまったら、以降の連携も難しくなってしまいます。
でも「子どもが頑張っているからこうしたい」と、子どもの頑張りをふまえて保護者主導で対応しようとする姿勢を示せば、力になってくれる可能性は上がるのではないでしょうか。
まずは他者に話すことで、自分の考えと状況を整理しよう

福田:子どもの自己決定を尊重したり、納得するまで話し合ったり、大変ですよね……。
そうしたコミュニケーションは、行き渋りの解決のためだけでなく、一生ものの親子関係を築くためにやっていると考えてみるのはどうでしょうか。
ただ実際のところ、行き渋りや不登校の問題は本当に複雑で、親御さんだけで抱え込むには難しい問題だと思います。だから、ぜひ人に頼ってください。
専門家のアドバイスを聞きに行く手もありますが、心に余裕がない状態で正論だけを説かれても、お説教をされた気分になって余計苦しくなってしまうこともあります。
なので、私がファーストステップとしておすすめしたいのは、自分の周囲にいる、問題と直接的に関係のない人にまず話を聞いてもらうことです。例えば、信頼できる友達や地域の保護者会、スクールカウンセラーなどです。ひたすら話を聞いてもらって、自分の感情や考え、事実の整理をしてから、専門家や関連コミュニティーにアクセスするのがいいと思います。
取材・文:菅原さくら
編集:はてな編集部
働きながら、子どもをサポートするには?
りっすん by イーアイデム
Xも更新中!
Follow @shinkokyulisten
<Facebookページも更新中> @shinkokyulisten












































































武石惠美子さん法政大学教授
1991年の制定(1992年施行)時から「働く人であれば男女ともに対象」としたこと「育児休業の取得に関しては、本人が請求すると事業者(雇用主)は拒めない」強い権利を労働者に与えたことが非常に重要なポイントです