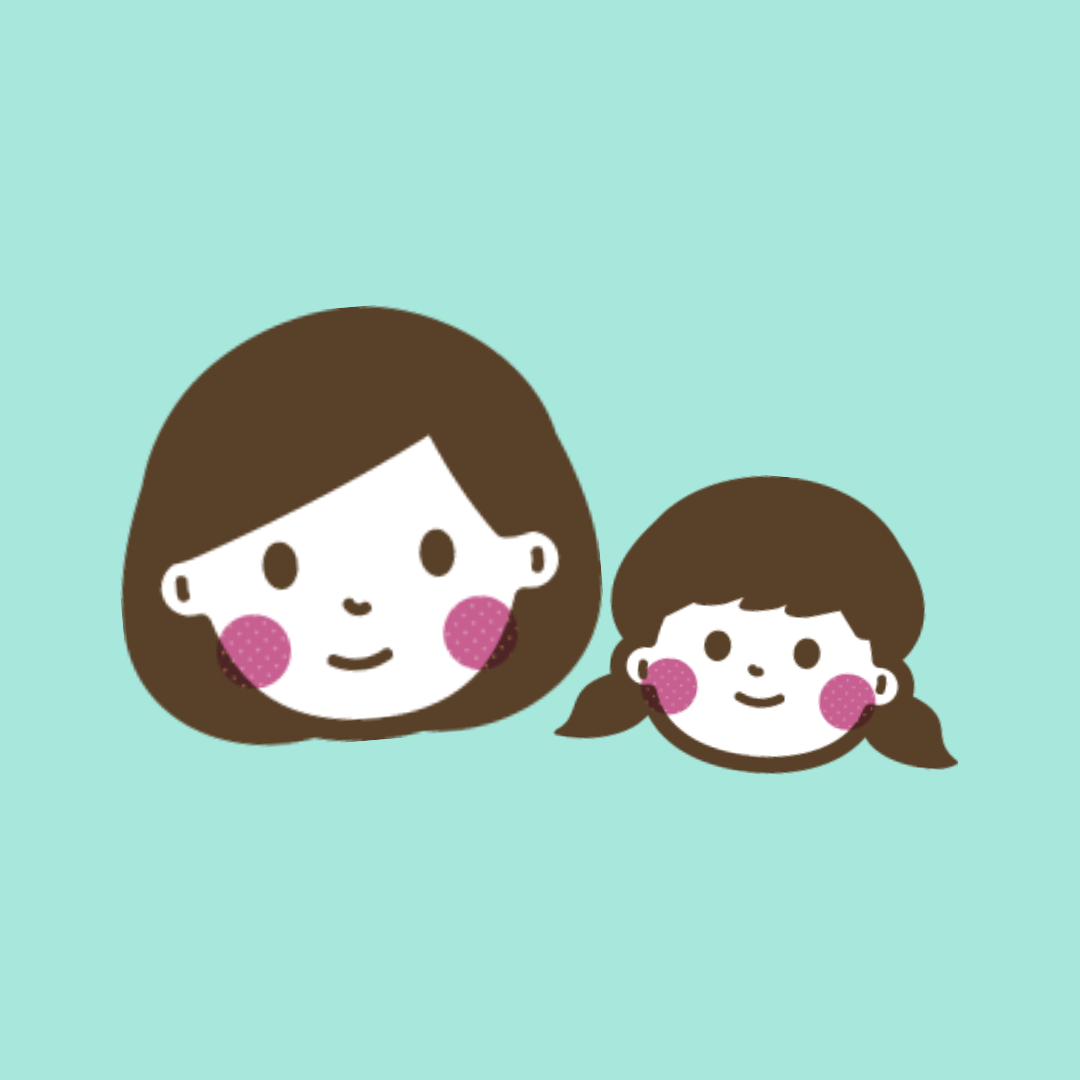自分に合った働き方が分からず、モヤモヤを抱いている方に向けて、「ちょうどいい働き方」を模索してきた碇雪恵さんの寄稿をお届けします。
現在、フリーランスのライターとして活動しつつ、バーでアルバイトもしているという碇さん。これまで正社員・契約社員・派遣社員など、さまざまな働き方を取り入れてきましたが、以前は「正社員以外ありえない」と思い込んでいたそうです。
そんな碇さんが柔軟な働き方を選ぶに至った経緯や、そこで得た気付きや変化をつづっていただきました。
昼の12時ごろ、自宅から歩いて5分ほどのコワーキングスペースで仕事を始める。コンビニやドラッグストアに行ったり、食事休憩をとったりしながら、夜の22〜24時近くまで仕事をする。そのままジムに立ち寄りフィットネスバイクを20分ほど漕いで帰宅。寝るのはだいたい深夜2時半くらい。起きるのはだいたい10時半くらい。
これがわたしの生活の基本形である。こうして書いてみるとまあまあな夜型だが、この生活リズムが今は体に合っている。
なぜこのようにややズレた時間帯での生活が可能かと言えば、現在のわたしの職業がフリーランスのライターだからである。ある会社と業務委託契約を結んでいて、取り決めた月間稼動時間を目安に取材や執筆、原稿の編集などを行いWeb記事を制作している。取材時以外オフィスに出社することはない。
その会社以外からもWebや雑誌に掲載する記事制作などを請け負っているほか、自分で本(いわゆるZINE)を作って売り、さらには週に一回バーでバイトをしている。少し前までは、派遣社員とフリーランスの仕事を並行していた。

碇さんが35歳の時に始めたブログをもとに制作したZINE。独立系書店を中心に話題となり、刷り部数は1,900部に到達したという
都内に一人で暮らし、演劇やお笑いを観に行ったり、月額3,000円のジムに通い始めたり、たまに友だちと外食したり、たまーに高速バスで遠出をしたりするくらいの生活は今のところできている。人によってはまったく物足りないだろうし、今の状況がずっと続くかどうかも分からない。それに、一人暮らしで身軽だからこそ選べた生き方だと思う。こうした前置きはあるものの、複数の仕事を組み合わせて生計を立てる方法は、今の自分にはしっくりきている。
しかし、ずっとそのような働き方をしてきたわけではない。社会人として働き始めて10年ぐらいは「正社員以外ありえない」という思いを漠然と抱いていた。収入だとか福利厚生の問題ではなく、ただなんとなくその方が安全そうだから、という世間知らずな思い込みがあったにすぎない。
本稿では、働き方を変えるに至った経緯を振り返ってみたい。
ちなみに、この文章は正社員を貶めるものでも称揚するものでもない。同じく、フリーランスを称揚するものでも貶めるものでもない。言うまでもなく、どちらも一長一短である。時代によっても捉えられ方は変化するだろう。
さらには、正社員としてどこかの会社に属していても、無理なく心地よくいられるならその方がいいのでは、と今も思う。正社員だからこそ得られる福利厚生や制度というのは実際にある。わたしの場合、そのことに気がついたのは、正社員ではなくなってからのことだったけれど。
9年勤めた会社を退職。当時は「次も正社員」と思っていた
先に述べた通り、現在に至るまでにはいくつかの働き方を経験してきた。
新卒カードを無駄にする気はなく、当然のように「正社員以外あり得ない」と思っていた大学卒業後のわたしが入ったのは、就活で初めて存在を知った出版取次(書店などに書籍や雑誌等の流通を行う)の会社だった。今から15年前の2008年のことだ。
初任給はあまり高くなかったが、その代わり無茶苦茶に働かされることもなさそうだった。さらに、会社の規模が大きくさまざまな部署があったので、「一つの仕事に飽きても、他の部署に異動すればいいや」などと考えて入社を決めた。その頃は一つの会社に長く勤めたいと思っていた。今にして思えば、いわゆる安定志向だったのだろう。当初の思惑は当たり、結局わたしはその会社に9年勤めることになる。7年は書店営業の部署を、2年は新規事業開発の部署を経験した。
9年間の勤務の後、さまざまなことが積み重なり、次が決まっていない状態で、とりあえず会社をやめることにした。9年も同じ会社に勤めると「(会社名)の碇です」と名乗ることが板につき過ぎていて、それがなくなった時にはアイデンティティを失ったような気分になり、不安だったことを覚えている。
しばらくはバイトでつなぐのもいいかと思ってはいたけれど、ちゃんと就職するなら正社員としてまたどこかの会社に入るつもりだった。この頃もまだぜんぜん「正社員以外はあり得ない」と思っていた。わたしを心配した友人・知人が契約社員やバイトの仕事を紹介してくれたのはとてもありがたかったが、いずれも気持ちだけ受け取ってお断りしていた。
正社員としてまた会社に入るなら、と転職サイトや転職エージェントに登録し、経歴を入力して出てくるのは大体メーカーや卸の営業職だった。これまでの経験を生かして年収をキープするのであれば、そういう求人に応募すればよかったのだが、なぜだか気が進まなかった。面談した転職エージェントの人は、年収キープこそが最優先であることに疑いのない様子だったが、自分にはそう思えなかった。
知人の問いかけをきっかけに「やってみたいこと」に気付く
しかし、だとしたら自分が優先したいことって何だろう。
そんなことをうっすらと考えながら無職期間を過ごしていたある日、出版社の知人に声をかけてもらい、発送作業を手伝う単発のバイトをした。
作業後、オフィス近くの居酒屋で今後のことを聞かれた。何も決めていないと答えると、「じゃあ、今の時点でできるかどうかは一旦置いておいて、やってみたいことは?」と、さらに質問が返ってきた。口に出すのが恥ずかしいなと思いながらも、少し酔いが回り始めていたことも手伝って、思っていたことをぽつぽつと話してみた。
気になる人に話を聞きに行ってみたい。それを文章にまとめる自信はないが、つまりインタビューみたいなことをしてみたい。これまでも本にまつわる仕事をしてきたが、流通がメインだった。今は本の中身を作ることに興味がある。
そんなことを話した。どんな返答をもらったかは覚えていないのだが、ひそかに考えていたことを口に出してみると、思いがけないインパクトがあった。そう思っているのなら、ライターや編集の道に進むべきではないか。年収キープを優先する気になれなかったのは、そういう理由なのではないか。
できないと決めつけていたが、そんなこともないかもしれない。メディア専門の転職サイトに登録をし、未経験でも応募できるライター・記者職を探してもらった。結果、あるにはあったが、ほとんどが契約社員としての募集だった。しかも、変わるのは雇用形態だけではない。どの求人も一社目に比べると年収が大幅に下がる。
しかし、この頃から少しずつ「何年もかかるかもしれないけれど、スキルを身に付けることを目指すなら、正社員にこだわらなくてもいいのかもしれない」と考えが変わり始めていた。年収にしても、働きながら仕事を教わると考えたら飲み込める。いわゆるやりがい搾取と隣り合わせの考え方かもしれないが、今はよしとすることにした。

自分自身の方向性が明らかになるにつれ、「正社員以外あり得ない」という考えはもう捨ててもいいかも、と思い始めていた。というか、やってみたいことに向き合わないでいたからこそ、正社員という安定した立場でいることが大事だと信じ込もうとしていたのかもしれない。社会的な安定を求めていたのは、軸を自分の外に持っていたからであり、軸を自らの中に見出そうとするようになって、無邪気な正社員信仰は氷解し始めた。
会社とは別の「居場所」としての副業バーテンダー
結局、4カ月半の無職期間を経て、ある出版社に契約社員として入社することになった。記者職に就き、インタビューや構成の仕事が担当業務の一部になったので、まずはスタートラインに立つことができた。
その後、別の出版社に同じく契約社員として転職し、インタビューだけではなく、編集補佐や本の発送作業、営業や事務作業など、幅広い業務を経験した。とにかく目の前のことをやらなければ、と日々粛々と働いていたが、一方でこことは別の居場所を持ちたいと考えるようにもなっていた。インタビューは楽しいが、もっと雑多な場所でいろんな人の話に触れたい。また、友人や知人がふらっと会いに来てくれるような場があったら、という思いもあった。
そんなある日、なんとなく流していた夕方のニュース番組で「副業バーテンダーが人気」といった内容の特集が組まれていた。昼は違う職業に就いているが、週に一回だけ夜にバーで働く人が登場して、「飲みながら楽しくおしゃべりできる上に、お金までもらえて最高」と話している。
「これだ!」と思った。ただ、思ったはいいが、働く場所のアテがあるわけではない。
一応、求人サイトで探してはみたものの、自分の理想よりもずっとオーセンティックなバーか、スタッフが女性性を全面に出す形態のお店しか出てこなかった。普段の服装で、普段の気分のまま働けるバーが自分の理想だった。そう簡単には行かないなぁと、副業バーテンダー構想をあきらめかけていた頃、「人手不足……」とつぶやくアカウントがTwitterで目に入った。
それは、以前一度だけ友人に連れていってもらったことのある、新宿ゴールデン街のバーのアカウントだった。ここでなら、普段の服装で、普段の気分で働けるかもしれない。「これはもしや」と勢いのままに「人手不足と拝見したのですが、働かせていただけませんか?」とDMを送ってみた。それがきっかけで、ゴールデン街のバーで週に一度働くことになった。雇用形態はバイトだが、この頃には「正社員以外あり得ない」という思いは姿を消していた。

碇さんの働くプチ文壇バー「月に吠える」
社会も自分も変化するから「調整」していけばいい
その後、契約社員で働いていた出版社の勤務を週4にし、残りの平日1日で他の出版社の営業代行を始めるなど、働き方はどんどん複合的なものになっていった。2019年秋には、契約社員として働いていた出版社を辞めてフリーランスになった。
しかし、その半年後、コロナ禍に突入。ライターとして決まりかけていた仕事が飛び、バーも営業できない時期が続いた。営業代行の仕事もそのタイミングで契約が終了した。
いよいよ東京での生活継続が難しいかも、と地元に帰ることも考え始めていたが、地元の友人から「まだやりようがあるはず。今、帰って来たら絶対もったいない」とアドバイスをもらって思い直した。その「やりよう」を考え、2020年12月、人材派遣会社に登録し、ITベンチャーの会社で週に3日働くことにした。仕事内容はWebの記事制作なので、今までの仕事の延長線上にある。
東京に残るにしても、以前の自分であれば「世の中がこんなふうに思いがけず変化するなら、やっぱり正社員でいた方が安心」と考えたかもしれない。ライターや編集職としての数年の経験を生かして、出版社や編集プロダクションに転職することも選択肢としてはあったはずだ。
しかしこの頃には、「世の中がこんなふうに思いがけず変化するからこそ、自分で働き方を調整できた方がいい」と考えるようになっていた。それに、一社だけで働くよりも、さまざまな人たちと少しずつ関わり合いながら働く方が自分にとって心地よい、という気づきもあった。
一つの会社に勤めるということは、自分の生活を支えるのがその一社のみということになる。となると、その一社に「捨てられたら」生活が成り立たなくなる。それは困るので、忠誠心を持たなければ、という意識が勝手に働く。その結果、自分の声を無視してでも、会社の意向に沿う言動を心がけるようになる。
冷静に考えれば、誰もそんなことは求めていない。会社なのだから、仕事さえしていればいいはずだ。頭では分かっている。しかし、わたしはどうやらそこを切り分けられない。
どこか一つの会社に勤める以上、例えばSNS一つとっても自由に発言できなくなる。実際、以前勤めていた会社でSNSへの書き込みを咎められたことがある。今のわたしは、もうそのことに我慢できない。自分の名前で、自分の責任の範疇(はんちゅう)で、自分の思ったことを発信したい。であれば、自分の生活を支える会社や個人を複数に分散し、無闇な忠誠心を発揮しない仕組みを作った方がいい。
そういうわけで、派遣で週3日働くことで一定の収入を確保しながら、別の会社からもフリーランスとして仕事を請け負うようになった。さらには、自分で本を作って売るという楽しい仕事の仕方も習得して、約1年前からは派遣ではなく業務委託として仕事をするようになり、冒頭に説明したような複合的な働き方をすることになった。2019年に始めたバーのバイトは今も継続していて、4年目となった。基本的には一人で黙々とパソコンやらタブレットに向かう毎日を送る自分にとって、週に一度雑談補給の場があるのはありがたい。

「月に吠える」でお客さんと雑談中の碇さん
また、前から薄々感じていたのだが、わたしがいちばん仕事に集中できるのは18時以降なのである。これは会社員で言うとほとんど定時を過ぎた時間にあたる。「朝型か夜型かは自分の努力ではどうにもならない部分があり、ほとんどが遺伝子によって決められている」。そう医師が語っている記事を読み、きっとこれにも諸説があるとは思いつつも、都合よく解釈した。
それで今は冒頭のような時間帯で生活している。朝型に憧れる気持ちもいまだになくはないが、自分が効率よく働けるのはこのやり方だと今は思っている。
自分の性質を知ることで雇用形態へのこだわりが薄れていった
かつて「正社員以外あり得ない」と思っていた頃に比べると、今のわたしはどう変わったのだろうか。さまざまな変化があるが、その中でも大きいのは、自分の性質を理解するようになったことかもしれない。自分は何がしたくて、何をしたくないのか。何が得意で、何が苦手か。軸を自分の中に置き直した結果、さまざまな人たちとゆるやかに関わりながら仕事をすることが、自分にとって息がしやすい働き方なのだと知った。
要するに、雇用形態よりも大事なのは、自分自身がどうしたいか、である。もちろん、フリーランスの保証のなさには不安がある。しかし、自分が息をしやすい環境を選ぶ方が、結果的に健康なまま働き続けられるはず、と今は考えている。
今後も自分は変化するであろう。わがままな自分に付き合い続け、その都度働き方を調整していけたらいい。
この考えに至るまでには、ずいぶん時間がかかった。かと言って「早く軸を自分の中に取り戻せ」と昔の自分に伝えたいかといえば、そんなことはない。その時々、一生懸命やってきたはずの過去の自分に説教などしたくない。ただ一つ言えることがあるとしたら、無職期間中に誘われた出版社の単発バイトには絶対に行ってほしい、ということくらいだろうか。蓋をしていた思いを口に出し、働き方を変えるきっかけをくれた人には感謝している。
編集:はてな編集部