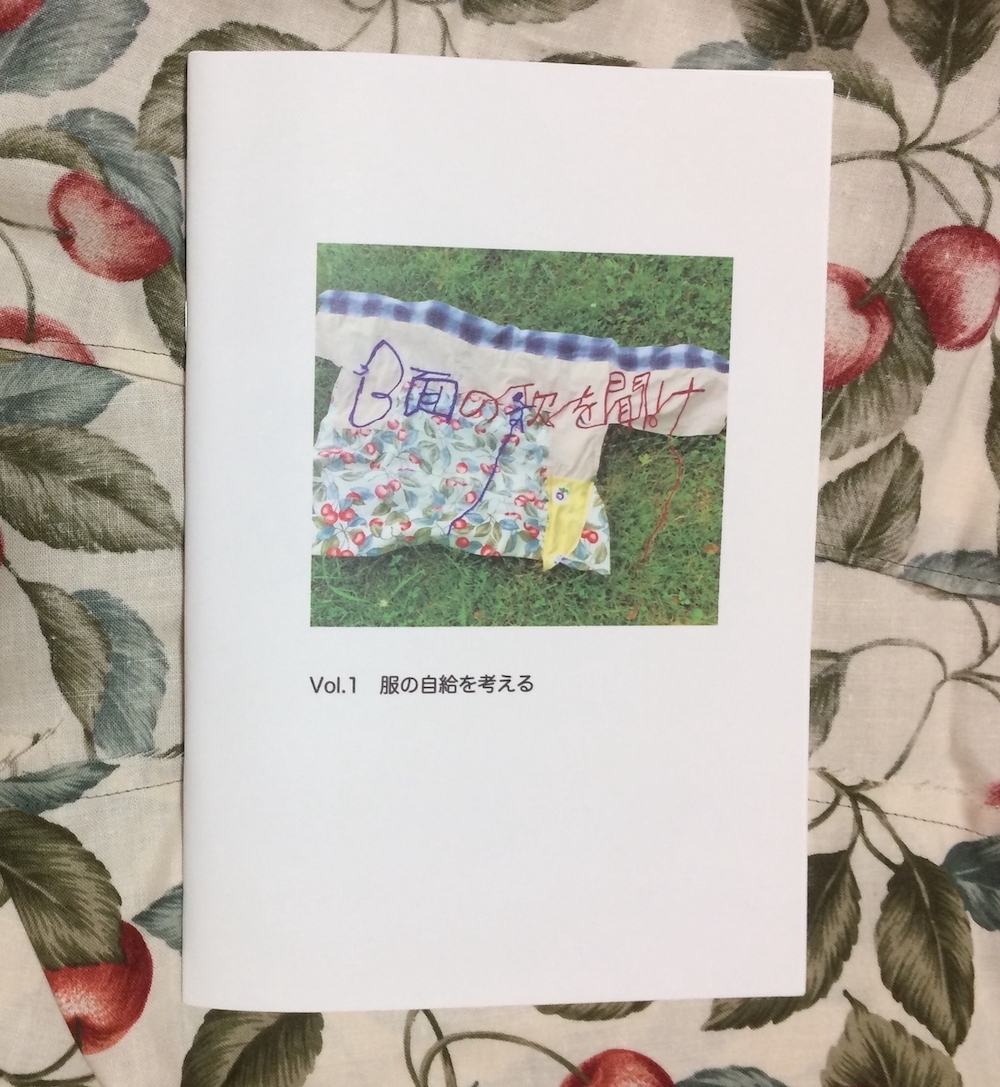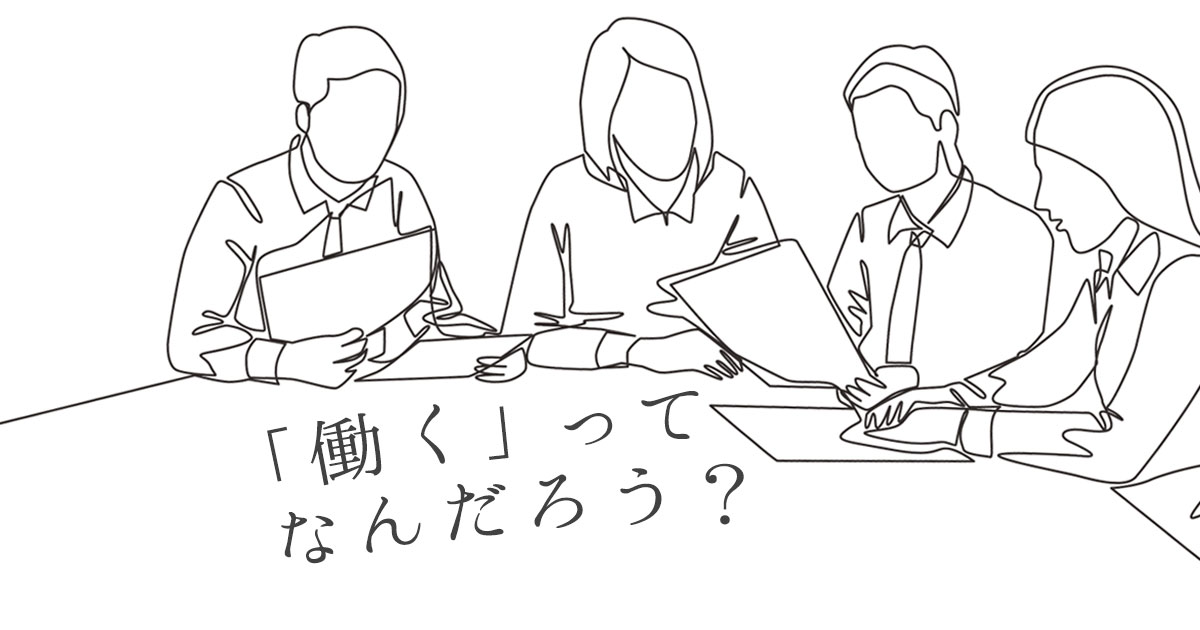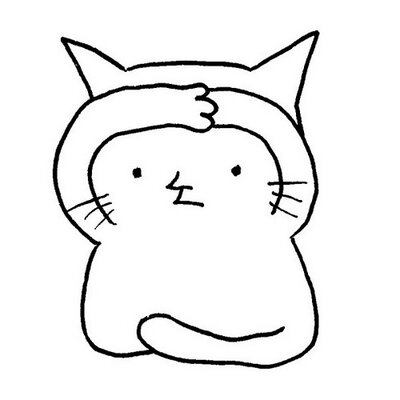デスク周りの収納や整理、テレワーク(リモートワーク)下で悩んでいませんか? 自宅ではオフィスのように十分な仕事用のスペースが確保しづらく、書類やPC周りのガジェットなど、さまざまなアイテムがデスクの上に出しっぱなしになりがち。「すっきり、おしゃれなデスク周りにしたい!」と一度片付けや掃除をしたとしても、気付けばすっかり元に戻っている、なんてことはよくありますよね。
今回は家事代行マッチングサービス「タスカジ」の仕事を通じて、多くの家庭の「片付かない」悩みを解決してきた“予約の取れない家政婦”sea(しー)さんに、在宅勤務をする人に向けて、デスク周りの収納や整理のコツ、片付いた状態をキープする方法を伺いました。片付けが苦手な人でも無理なく取り組めるポイントや、100均などで手に入る便利グッズも紹介します。
片付けをサポートするときに私が重視しているのは、使うためにいったん出したモノを「戻す・しまう」めんどくささを、徹底的になくすこと。
見た目をいくら整えても、使い始めたところから早々に散らかり始めてしまっては、気持ちもがっかりしてしまいますし、使い勝手もよくなりません。なので、きれいにしまいきった一瞬の仕上がりではなく、片付けた後で無理なくその状態が続けられる仕組み作り を大切にしています。
さて、この数年で、私のもとにも「テレワークのため、自宅のワークスペースを改善したい」というご相談が増えてきました。その中には、自分のデスクや書斎を持つのが難しく、ダイニングやリビングのテーブルを一時的にワークスペースにしながら、テレワークをしている方も多くいらっしゃいます。
そこで今回は、これまでの片付け経験をもとに「限られたワークスペースでも、テレワークを快適にするための片付け・収納術の考え方」を紹介します。
***
片付かないワークスペースにありがちな、4つの特徴
散らかったダイニングテーブル(写真提供:タスカジ) 突然ですが、みなさんが在宅勤務で作業しているデスクは今、どんな状態でしょうか?
ごちゃつきの状況にもいくつかのパターンがあり、大きく分けて下記の4つの特徴と改善方法があると私は考えています。
これらの特徴は、重なって存在している場合も多々あります。
1. デスク・テーブルの「多目的(マルチスペース)化」
2. いろんなモノが出しっぱなしで「今」仕様になっていない
3. 書類が分類されないままデスクの上に置かれていて作業スペース自体が狭い
4.すぐに仕事が再開できそうなほど、デスクが「途中」の状態になっている
1. 仕事も食事も子どもの勉強も同じ場所。テレワーク下でのデスクの多目的化
コロナ禍でテレワークの習慣が始まった方の中には、専用の仕事部屋がなく、ダイニングテーブルをワークデスクとして利用している人も多いのではないでしょうか。
ダイニングテーブルはもともと食事をする場所でもあったり、子どもが勉強をする場所でもあったりして、目的の異なるモノが混在しがち。さらにワークスペースとしての役割が加わったことでより多目的化しています。
ダイニングテーブルが多目的化している様子(写真提供:タスカジ) 片付けの作業に入る前に、まずは今のデスクが自分や家族にとって「何をするための場所なのか」を把握しておきましょう。
改善策:デスクにあるモノを目的別に大まかに分ける ダイニングテーブルが多目的化している場合、まずはテーブル上にごちゃっと置かれているモノを下記のような大まかなカテゴリで分けていきます。
仕事
家族・家(契約関連/お金関連/健康管理関連など)
子どもの学習(家庭学習アイテム/進学資料など)
チラシ
文具
食品や生活雑貨(体温計や薬など)
(子どもがいる方の場合)おもちゃ
片付けが苦手な人ほど、分けながら「こんなにあったら棚に収まらないかもしれない」「これは、やっぱり捨てるべきだろうか?」などと考えて作業が進まなくなる傾向があります。これが失敗の元。
「分ける」と「残すかどうか検討する」「しまい方を考える」はそれぞれ別のタスクです。片付けのコツは、カテゴリごとの仕分けのような大まかなシングルタスクを高速でつなぎ、片付いてきている手応えや達成感を得ながら進めること。
他のタスクのことはいったんおいておき、まずは「分ける」に集中です。目についたところから、機械的にどんどん仕分けていきましょう。
2. 過去・現在・未来のモノが混在し、デスクスペースが「今」仕様になっていない
続いては、デスクの上に「今使うモノ」「使うけど今じゃないモノ」「使わないモノ」があり、「今」仕様になっていない状況です。
デスクスペースが「今」仕様になっていない様子(写真提供:タスカジ) リビング・ダイニングは特に、家族の歴史が積み重なりがちな場所。古いモノの上に新しいモノがどんどんやってくるので、例えば仕事で毎日使うイヤホンと、何カ月も前に見終わった子どものプリントがごっちゃになっていたりするんです。
仕事用のデスクがある人でも、過去の参照資料がずっと手元に残ったままになっていることはあるかもしれません。
改善策:「今使うモノ」を優先して、取り出しやすい場所にしまう デスクスペースが「今」仕様になっていない場合にありがちなのが「今、ないと困るモノが埋もれてしまう」状況です。
ダイニングテーブルを仕事兼用にしている場合は、1で紹介したようにカテゴリごとに分けたあと「今、ないと困るモノ」を厳選し、優先的にしまっていきます。
デスクにあったアイテムを眺め、「この場所で今、ないと困るモノはどれ?」と考えてみてください。絶対に必要なモノは、案外多くないはずです。例えば文具なら、ワークスペースに置いておきたいのはボールペンとはさみ、メモパッドなど、トレー1つに収まるぐらいの量ではないでしょうか。
そこまで検討したら、収納の仕方を考えます。
まずは日常的に確実に使うモノ=「今使うモノ」の定位置を決めていきます。「使い終わった後、ラクに戻せる場所」がベストポジションです。「使うけど今じゃないモノ」については、「控え」として、今使うモノより奥に収納します。
今使う文具がトレー1つ程度の分量なら、そのトレーをデスクの隅に常設して「定位置」とします。残りの使わないペンやはさみ、クリップなどは引き出しにしまっておく、というようなイメージです。
3. さまざまな書類が整理されておらず、作業スペース自体が狭い 仕事用のデスクがある場合でも、書類の整理が追いつかずに、作業用スペースを圧迫しているようなケースです。
狭い作業スペース(写真提供:タスカジ) 会議の資料や進行中の案件の資料、新しく導入したツールのマニュアルなど、日々増えて場所を取ってしまう書類は、整理の仕方を見直してたまらない仕組みを作りましょう。
改善策:たまりがちな書類は、ステータス別に3つに分類する デスクの上でスペースを取りがちな書類は、
1.要対応 2.対応済み(要保管) 3.対応済み(保管不要) という3種類に大きく分けて整理し、片付けてみましょう。
「要対応」は、埋もれないための工夫が重要。マグネットクリップとマグネットシートで目の前に掲示させておいたり、赤色の透明クリアファイルに入れて、書類トレーのいちばん上に置いておいたり、「見える状態」を作っておく必要があります。
「対応済み(要保管)」書類は、デスクに「参照資料」のボックスを作って入れておくか、長期保管書類用の棚をデスクと別に作って移動させるかするとよいでしょう。
書類管理に使う収納グッズとしては、トレータイプとボックスタイプがありますね。トレーは、朝入ってきて当日中に処理を終わらせて出ていくような、動きのあるタイプの書類管理に向いており、テレワーク環境にはどちらかというと不向き。トレーを使うなら「当日使うモノと要対応書類のファイル置き場」として、一つで十分です。
それよりもダイニングテーブルまわりでの書類整理には、ある程度の量が入り、ワンアクションでしまえるボックスタイプの収納がぴったりです。
書類整理にはボックスタイプの収納が便利(写真提供:タスカジ) そして「対応済み(保管不要)」は、できるだけ手元で止めずに処分しましょう。ペーパーレスの時代、紙で保管しなければならない情報はそれほどないはずです。
「参照資料」としてキープしておいたモノも、月に1回は内容を確認する習慣をつけましょう。「結局見なかったな」というモノが結構あるはずです。それらを処分していくことで「参照資料」のファイルボックスが無限に膨らんでいくのを防ぐことができます。
4. 仕事が終わっても、ワークスペースが常に『途中』の状態になっている デスクまわりをすっきりさせ、作業上のロスを防止するためにも、
日々ワークスペースをリセットする習慣をつける ことが大切です。
1日を通してさまざまな家事などが発生する、家庭という場所。
ワークスペースをリセットし「終わった!」と思える体験の積み重ねは、業務をスムーズにしてくれるだけでなく、自己効力感を育むための重要なアクションです。
改善策:「しごとNOWボックス」で毎日デスクの上をリセット 毎日の習慣にしたいのが、デスクの上を“何もない状態”にすること。
今仕事で使っているモノを出しっぱなしにせず、まとめて入れる「しごとNOWボックス」 を作り、やりかけの書類や現在使っている参考資料、ノートパソコンやタブレット、ペンケースなどをそのまま入れてしまってください。道具をそれぞれを元の位置に戻すのではなく、「今のカタマリ」としてまとめるイメージです。
「しごとNOWボックス」には、取っ手付きのA4書類ケースやA4サイズの入る帆布バッグなどが向いています。イヤホンやレコーダーなど細かい物がある場合は、「しごとNOWボックス」にポーチやジッパー付き袋などを入れておき、その中にまとめてしまいましょう。
「しごとNOWボックス」のイメージ(写真提供:タスカジ) このような片付けは、明日やることの整理にもなるので、仕事が終わり次第、家事に戻る前にやっつけてしまうのがおすすめです。
一方、ほこりを取ったりデスクを拭いたりする掃除は、業務開始前に行うのがおすすめです。ルーティン化にもコツがあり、それは「○○の後」ではなく「○○の前」に設定すること。
「ごはんの後」「お風呂の後」など、「○○の後」は定義があいまい。「ちょっと休んでからやろう」などと考えているうちにやらなくなりがちなので、習慣化したいのなら断然、タイミングは「○○の前」がおすすめです。
目次に戻る
片付けたデスク周りがすぐ散らかる原因は、5つの「めんどくさい」があるから
デスク周りがごちゃつく原因を知って一度はすっきり片付けたとしても、気が付けば散らかっている、ということはよくあります。その原因として、私は5つの「めんどくさい」があると考えています。
1.使ったアイテムを戻す場所がデスクから遠い
→「またすぐ使うからこのままでいいや」と、そのままデスクに置きっぱなしにしてしまう
2(戻すまでにいくつも何かを開ける動作があるなど)障害物がある
→障害物を越えて戻すのが億劫になり、途中に意図しない一次置き場ができてしまう
3.使ったアイテムを戻す場所がバラバラ
→どれをどこにしまうか思い出すのが面倒で、適当な場所に戻してしまう。定位置を家族と共有するのも大変で、違う場所に戻されてしまう
4.(収納場所と入れるモノの形が合っていないなど)動作が窮屈
→しまう作業がストレスになり、収納をあきらめてしまう
5.収納がぎゅうぎゅうでアイテムが入らない
→物理的に収納が不可のため、デスクの上に置かれたままになる
よく使っている資料の束やUSBハブを、デスクまわりに収納がないために、リビング収納が定位置とされているケースはよくあります。
収納場所までたった数歩の距離であっても、扉をひとつ開けるだけであっても、ラベルのついた引き出しに従って戻すだけであっても、それが毎回のこととなると片付けるのが面倒になってしまうもの。特にダイニングやリビングで仕事をしている場合は、キャビネットなどが近くにないことから、上記の1〜3がよく当てはまる印象です。
また、せっかく収納を増やしても、中で電子機器やイヤホンのコードなどが絡み合ったり、付箋やクリップなど細かいモノがごっちゃになったりして、ぎゅうぎゅうになってしまっては意味がありません。しまう場所がないからといって、ただ収納グッズを増やすだけではダメなんですね。
5つの「めんどくさい」に気づくだけで、これまでどうして片付かなかったのかが分かるようになります。片付かない理由が分かれば、あとはそれをやっつければいいだけです。
何度片付けてもデスク周りがすぐにごちゃついてしまう……という人は、一度デスクまわりの「片付けのめんどくささ」をじっくり分析してみるのがおすすめです。
「めんどくさい」を減らす収納グッズで、片付いた状態をキープ
デスクの上のごちゃつきを減らすためには、収納グッズの選び方も重要なポイント。使い勝手がよくないアイテムを選んでしまうとまた「めんどくさい」が発生して、片付いた状態をキープできないこともあります。
デスク周りの整理に使いやすいグッズとしては、取っ手付きのA4書類ケースやファイルボックス、ジッパー付きの袋があります。
おすすめ収納グッズ(1)取っ手付きA4書類ケース
取っ手付きのA4ケースは、すぐに使う仕事道具を持ち運ぶのに使います。 仕事を始める際にデスクにケースごと運び、終わったらケースに入れて収納場所に戻すことで、デスクがごちゃつくのを防ぎます。
取っ手付きA4書類ケースで仕事道具をまとめる(写真提供:タスカジ) デスクの近くにカウンターなどの空きスペースがあるのなら、そこをケースの収納場所にするのもいいでしょう。
近くに収納できる場所がない場合は、カラーボックスを1つ置き、そこに在宅勤務グッズを入れる用のファイルボックスを置くという方法もあります。
おすすめ収納グッズ(2)ジッパー付きの袋
100円ショップなどで購入できるジッパー付きの袋は、コード類など細かい物の整理に役立ちます。 小さい袋に1つずつ入れるのではなく、「文具」「コード」など、ざっくりと分類して大きめの袋に入れるのがおすすめ。立てて収納できるようになり、出し入れも簡単になります。管理しやすいように中が見える透明タイプがマストです。
「ジッパー付きの袋」には小物をジャンルごとに分けて入れる 引き出しが使えるなら、間仕切りとしてお菓子の空き缶、スマートフォン購入時の箱、名刺ケースなどが役立ちます。案外、すでに家にある物の組み合わせで整えることができるんですよ。
片付けが苦手な人こそ、細かく収納場所を分けるのではなく、カタマリにまとめてしまい「デスク周りのどこに何があるか、ざっくり把握している」状態を目指しましょう。
「片付けられない自分」ではなく「片付けの仕組み」を変えてみる もし同居人もテレワークをしている場合、相手の荷物が片付いてなくて気になる(相手は気にしていない)、ということもあるかもしれません。そんなときは相手を責めても状況は好転しません。
双方のメリットになる方法を考える のがおすすめです。
「ワークスペースの収納にカラーボックスがあると便利かなと思うんだけどどう思う? 置くとしたら、場所はカウンター下と壁沿い、どちらがいい?」など、具体的な選択肢を用意して尋ねると相手も答えやすいもの。意思決定にさりげなく巻き込むことで「自分が決めた」と感じられ、ルールを守ってもらいやすくなるでしょう。
私はこれまでいろんなご家庭にうかがってきましたが、片付けが苦手な方ほど「『片付けられない自分』を変えなければいけない」と思っているのを感じます。私はそんな方に、自分を責めるのではなく「今の自分には、この片付け方の仕組みが合っていないんだ」と考えてみてほしいんです。
変えるべきなのは「自分」ではなく、「片付け方」。今の自分のままでも、「これならできるな」と思える片付け方がきっとあります。それを見つけ、自分専用に家をカスタマイズするために不可欠なのが、「私の生活の“今”」に向き合い、棚おろしをすることです。
今の部屋の環境に隠れている「片づけのめんどくささ」に気づくことを入り口に、快適なワークスペース作りにチャレンジしてみてくださいね。
目次に戻る
テレワークを快適に進めるヒント
ベテランリモートワーカーに聞く、作業効率を上げる「気分転換法」
子育てしながらの夫婦での在宅ワーク、ストレスや不満をためないコツは?
リモートワーカーにこそ、オンオフ切り替えに“朝の散歩”がおすすめ
著者:sea
家事代行マッチングサービス「タスカジ」ハウスキーパー、家族の片付けコンサルタント。