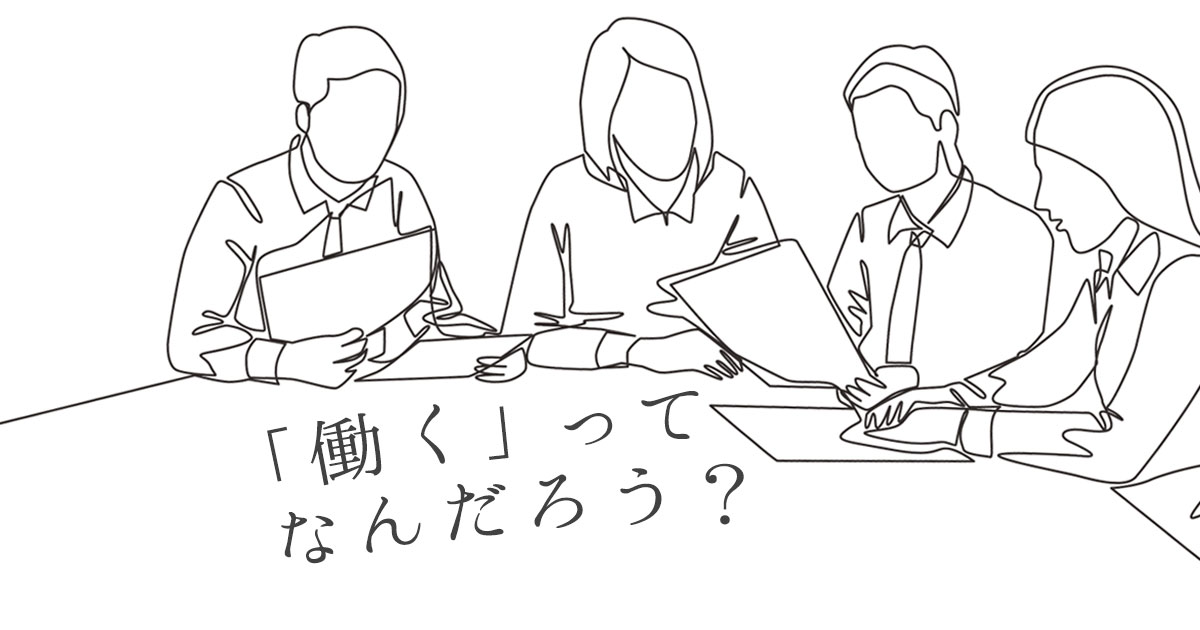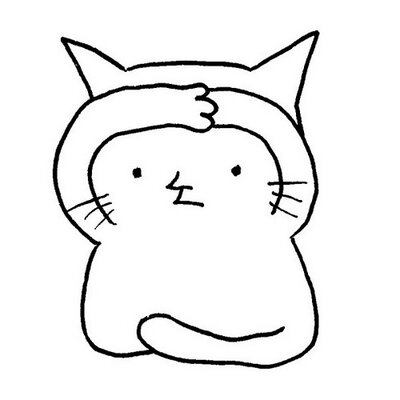近年よく見かける「“好き”を仕事に」といった言葉。しかし、好きな仕事を選べる人も、目の前の仕事を自分の天職だと思える人も実際のところはごく一部で、「自信が持てない」「向いていないんじゃ」といった気持ちを抱きながら、日々働いている人も多いのではないでしょうか。
中高一貫校で非常勤講師として働きながら、エッセイや短歌などを発表している堀静香さんも、そんな気持ちを抱える一人。
就職活動での挫折や、会社員として働くことへの不安から選んだ「教員」という仕事に自信を持てずにいる葛藤や、それでも自身の働き方を肯定できるようになった気持ちの変化などについてつづっていただきました。
就活に失敗し、選んだのは「でもしか先生」だった
「情熱大陸」や「プロフェッショナル 仕事の流儀」「セブンルール」など、その道を極めて邁進する人に迫ったドキュメンタリーが好きだ。ストイックで、かっこいい。自分にはできないなぁ、などと思いながらぼんやり眺めているが、画面の中の人は、たまにこんなことを言う。
「自信をもってこの仕事を選んだわけではないですね」
「気づいたら、この仕事をやっていました」
こちらから見れば異次元の世界にいるような人たちも自信があるわけではないのか、とちょっと拍子抜けしつつ、でも多くの人がそうなのではないかとも思う。かくいう私もそんな一人だ。
私が教員になろうと思ったのは、就職活動にあざやかに失敗したからだった。本が好きだから本に携わりたいと思い、大学三年の夏に集中講座で司書免許を取得した。でも、正規の図書館司書は採用倍率がものすごく高く、新卒で司書になるのはどうやら難しそうだった。なので編集者になろうと決めた。今思えば単純過ぎるが、やっぱり本が好きだったから。

しかし愚かな私が就活として取り組んだのは、ろくに調べもせずいくつかの大手出版社にエントリーシートを提出することだけだった。運よく面接まで進んだところもあったが、緊張し過ぎてほとんど何も話せずに、あっさり全ての持ち駒がなくなった(当たり前だ)。
気づけばもう大学四年の春、今から他の職種をリサーチする気力はなかった。そもそも事務能力が皆無で(今もExcelの使い方が分からず、よく泣きそうになっている)、周りの大学同期やサークルの友人たちのように会社勤めをできる自信がない。できそうもないことのために、また振り出しに戻って就活を始める気力など湧くはずがない。
今の自分にできることは、ずっとつづけている塾講師のバイトくらいか……と思って、それで私は「教員に“でも”なるか。いや、教員“しか”できない」と進路を決めた。ははあ、これがいわゆる「でもしか先生」か、と自分のことながら妙に納得してしまった。
教員免許を一から取得するために留年はしたが、モラトリアムが延びたと思えたので苦ではなかった。無事免許は取れたものの、激務に耐えられる自信がなくて、結局選んだのは非常勤講師。ほんとうに、自分は「でもしか先生」だなあと当時は思っていた。
「教員である自分」に自信がないまま、それでもまだ働き続けている
元々、自分が生徒だった頃から学校が好きではなかった。
だって学校はこんなにも息苦しい。勝手に決められた校則やクラス、みんな「同じである」ことを強いられる人間関係の中で長く過ごさなければならない。学校は監獄である、と以前ある記事に書いたことがあるが、今もそれはあながち大げさではないと思っている。
もちろん、学校が好きで、学校が楽しい人を否定したいわけではまったくない。例えば、家にいる方が苦しくて、学校が自分にとって安心できる居場所だった、という話を知人から聞いたこともある。
しかし私にとって学校はずっと「息苦しい場所」だった。雑談の折、生徒にそう話すとたいていびっくりされるが、そんなふうに自分の置かれた状況を客観視することは難しいからかもしれない。私も中学から高校、高校から大学へと進んでやっと、ふり返ればこれまで過ごしていた場所は苦しいヘンテコなところだったと気付いた。水面に顔を出してはじめて呼吸がこんなに楽だったんだ、と身体が解放されるみたいに、そこにいる時にはなかなかその息苦しさに気付けない。

好きじゃないところに身を置くなんていったいどういう了見で、と思われるかもしれない。教員というのは、学校が好きで、恩師がいて、なりたいと思って志す人と、そうでない人がきっといる。私のような後者は少数派だろう。
矜持がないわけでも、この仕事が嫌いなわけでもない。ただ、自分で選んだ「教員である自分」に自信がないのだ。中途半端な気持ちで、ここにいていいのだろうか。もっと情熱がなければ。もっと生徒に尽くさなければ。
自分が学校のなかにいて、学校が嫌いだと放言できるのは、他の多くのまっとうな先生たちのふるまいのおかげであるということに後ろめたさもずっと感じている。職員室のなかで、自分だけ浮いているのではないかと、ふと思う。
そんな込み入ったもやもやを抱えつつも、五年前、東京から山口に転居した際に新たな土地で選んだ仕事はやはり「教員」だった。当時、たまたま近所の学校で募集が出ていたからというのもあるが、自分が他にどんな仕事ができるのか、見当がつかなかったのだ。
子どもが生まれた現在は、家事、育児、執筆活動とのバランスを取るため、働く時間を一時期の半分以下のコマ数に減らした。辞めるタイミングは何度もあったのに、それでもなお「教員」を続けている。
先生が持つ「権威」を、生徒を肯定するために使いたい
ただ、「教員である自分」に自信がなく、学校という場所に苦手意識を感じるからこそ、決めていることがある。それはできるだけ「教師然」とするのは止めること。そしてかつての私のような学校が苦手な生徒に寄り添える教員でいようと思うことだ。
普段はめったなことでは怒らないし、授業中にはよく雑談もする。学校が嫌だという生徒には「そうだよね、学校って嫌だよね、変だよね」と寄り添う。そういう「先生らしくない」ふるまいが功を奏し、「話しやすい先生」と言ってくれる生徒もいる。
しかしいくら「親しまれる先生」になったとしても、自分が「教員」であることに変わりはなく、先生であることそれ自体が、生徒達にとっては権威である。その肩書はつねに権力をもつ。
たとえばテスト返却の際に、どうしても採点に納得がいかない生徒をやさしく説き伏せる私は紛れもなく「教員」という権力をもった一人の大人だ。そもそも、生徒も私を「話しやすい『先生』」として接してくれているのだから、お互いが権力関係のなかでしか「関係しつづけられない」ことに、うっすらと、けれど確実に、絶望を感じもする。
だから私は、できるだけ多く、生徒を褒めるようにしている。テスト返却の時には一人ずつ名前を呼んで「漢字、前回よりがんばったね」「○○さんは、今回のテストもう全然言うことないよ」「安定して点数取れてるね」となるべく褒める。
もちろん、もっと些細なことも褒める。「髪切った? すごい似合ってるね」「そのキーホルダー何!? めっちゃかわいいね」など、とにかく目に止まったら口に出してみる。どうしても振りかざしてしまう権威ならば、せめて生徒を肯定するものとして使いたい。それがものすごく乱暴なやり方であることは承知の上で、それでもせめて、肯定してくれる身近な大人の一人になるためにだけ、教師としての権威を保持していたいのだ。
自信がない毎日の中で気付いた「それでもいいのかも」という気持ち
なんとなく選んだ「教員」という仕事に不安や自信のなさを感じながら、矜持とまではいえない「こういう先生でいよう」という考えを携えて、私は今日も毎日(といっても今は週に三日)職場までの道を自転車で行く。今もいい先生でいられる自信がないまま、「ここにいてもいいのかな」と思いながら。
職場に行けば、廊下で生徒とすれ違う。おはよう、と声をかわす。「今日漢字テストありますか?」と聞かれ、「あるよ、先週言ったじゃん!」と返すと「えー聞いてないー」とぱたぱたと駆けていく。教室に行けば、うつむきがちな生徒がいる。そういえばここ最近、元気な声を聞いていない。そんなことを考えながら、授業をする。
授業だって、全員が前のめりに聞いてくれるわけではない。でも、まあそれでもいいや、と思う。そのとき、この教室で呼吸がしづらいかもしれない生徒に向けて、話をする。少しでも息継ぎができるように、と思って話している。
そのようにして長年、生徒たちと関わり合いをもつうち、近頃はでもしかで選んだこの場所に「いてもいいのかもな」と少しは思えるようになってきた。
前向きな気持ちで「教員」という仕事を選んだ人たちの中に、私のような人がいてもいいのではないか。そんなことを思う。

ドキュメンタリーに出てくる「すごい仕事をしている人」たちも、そこへ行き着いたのは偶然なのかもしれない。流される、というのとはまた違って、多くの人がいろいろあって、結果「なんとなく」始めた仕事に、今日も向き合っているだけなのではないか。翻って、そう思う。
今の仕事が嫌いなわけではない。人間関係にはすこし、不満もある。古い体制には頷けない。けれど目の前の業務と自分をつなぐ相手がいて、今日もここにいる。多くの人がそうして、働いているのではないか。
「迷いながらもここにいる」という選択肢があってもよい
そういえば、高校生の頃から志していた職種に就いたという友人とて、毎日「あークソクソクソ!!!」と思いながら働いていると言っていた(ちなみに彼女はふだん、とてもおだやかである)。
当たり前かもしれないが、たとえ念願叶ってなりたいものになれたとしても、そこには目下利害の絡んだ人間関係、折り合いのつくことそうでないこと、大小さまざまな苦労があるのだろうと改めて思う。
もしもあなたがしんどさを抱えきれずにこころのなかで右往左往しているのだとしたら。非正規、正規、キャリア、ライフワークバランス、職場の人間関係や業務内容、そのどれか、あるいは全てにおいて今の条件や状況がつら過ぎて今にもパンクしそうなら、無理する必要はまったくない。
けれどうーん……自分はそこまでではないかもしれない、と考えるなら。たとえ大きな情熱はなくとも、この仕事を選んだことに自信は持てなくとも、そこにいる人との関係に無理がないのなら、つづけることに後ろめたさを感じることはないのだと思う。「迷いながらもここにいる」という選択肢があってもよい。そういう働き方であっても、まったくかまわない。
「迷いながらもここにいる」。それは、だれかをエンパワーするために出てきた言葉でありながら、それ以上に自分を納得させるために口にする言葉でもある。いろんなスタンスの人がいる方が、きっとその場は豊かであるはずだから、と都合のいいことを考えて、今日も職場へ向かう。
「働くこと」に自信が持てなくなったら
著者:堀 静香