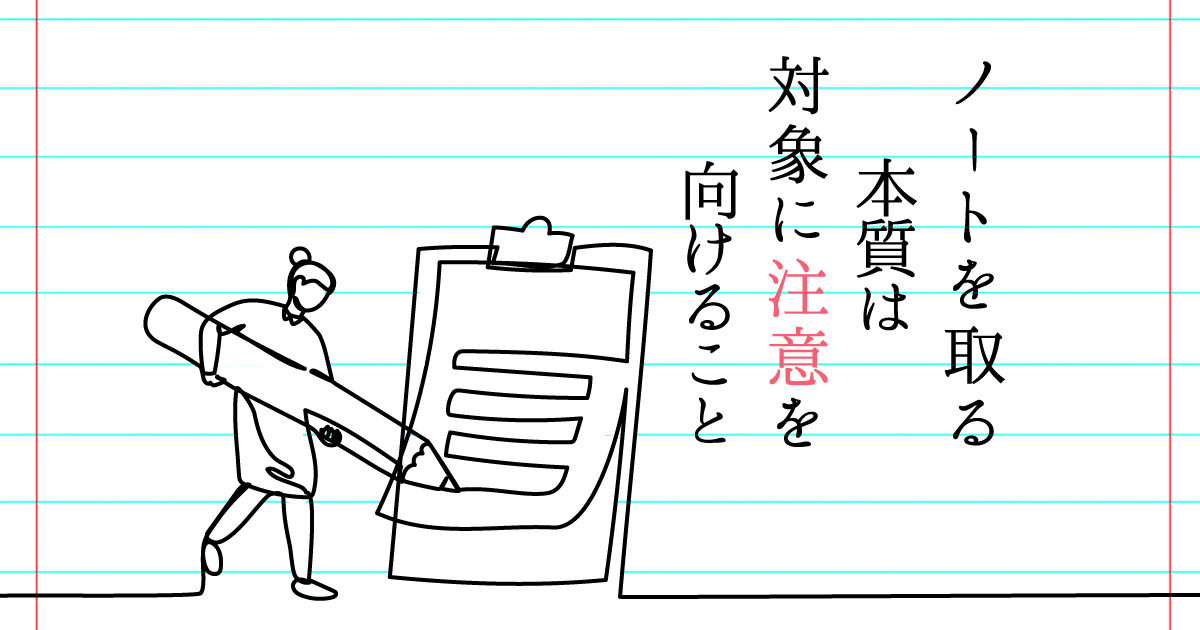なんだか毎日、うっすら体調が悪いーー。ハードな仕事や不規則な生活、テレワークによる運動不足などから「体調が万全!」と感じることが減ったという人は少なくないのではないでしょうか。ただ、病院に行くほどつらいわけでもないし……と、そのまま日々を過ごしてしまったり、心身を整えるための行動を始めてみても継続しなかったり、なんてこともありそうです。
そこで注目したのが、書籍『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』(翔泳社)で紹介されている「アジャイル式」健康カイゼンというプロセス。
ここで言う「アジャイル」とは、システムやソフトウェア開発における進め方のひとつである「アジャイルソフトウェア開発(以下、アジャイル)」に由来します。
著者の懸田剛さんは20年に渡りアジャイルを研究・実践・指導。現在はスポーツプログラマーの資格も取得し、自身で実践しながら他者への助言も行っています。共著者で保健師の資格を持つ福島梓さんも、過去エンジニアとしてアジャイルを実践・支援した経験を、働く人がいきいきと過ごすための支援に生かしています。
そんなおふたりが、健康に向き合うためのプロセスとアジャイルは共通していると考え、日々の生活で取り入れやすく継続しやすい健康改善方法として提唱したのが「アジャイル式」健康カイゼンです。健康のためにアジャイルがどのように役立ち、また継続につながるのか。おふたりに聞きました。
「うっすら体調が悪い」状態を見過ごさない
テレワークが浸透したことで運動不足になったり、忙しくてついつい食事をおろそかにしてしまったりと生活が乱れ、常に「うっすら体調が悪い」と感じている人が増えているように感じます。『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』でも書かれていましたが、この「うっすら体調が悪い」とは、どのような状態なのでしょうか?
懸田剛さん(以下:懸田) 例えば、朝起きたときにスッキリ目覚められるときと、なんだかつらいなと感じるときがありますよね。その「なんだかつらいな」という違和感が何日も続いていて、でもそれに手を打てずに常態化しているのが「うっすら体調が悪い」という状態です。
福島梓さん(以下:福島) 朝スッキリ起きられなくて会社に行くのが毎日すごく億劫だとか、日常的に頭痛があるのが当たり前になっているとか、そういうちょっとした不調が常態化してしまうと、だんだん「調子がいい」状態を実感できなくなっていくんですよね。
懸田 ただ、うっすら体調が悪いからといって「健康じゃない=不健康」と言いたいわけではありません。健康・不健康をジャッジするための言葉ではなく、なんだかスッキリしないとか、集中しにくいとか、そういった小さな違和感を「うっすら体調が悪い」と表現しています。
心当たりがあります……。どうしても日々の忙しさにかまけて自分の「うっすら体調が悪い」に見ないふりをしてしまいがちなのですが、忙しい中でも始めやすいことはありますか?
懸田 まずは日々、自分の状況を把握(モニタリング)しておくことでしょうか。僕は朝起きたときの感覚に違いが出やすいので、睡眠記録アプリなども活用して睡眠時間や睡眠の質をモニタリングしています。
シャキっと起きられる日とそうでない日があって、後者が続いたら黄信号。自分の生活を見直し、可能ならば、仕事量やストレスをコントロールするようにしています。ランニングが趣味なので、調子が悪くなってきたら仕事を早めに切り上げて走りに行ったりもしていますよ。
福島 私も、モニタリングと振り返りが大事かなと思っています。ときには仕事などでどうしても無理をしなければならないときもありますよね。
日ごろからモニタリングと振り返りをしていると、“体調変化の兆し”みたいなものが、自分の場合はどこにどのようにアラートとして出てくるのかが分かってくると思います。
日々の状態を把握して振り返りの時間が取れていると、今は無理をしても大丈夫か、休養を優先した方が良いか、など頑張り方の調整がしやすくなります。私自身も、20代の頃に比べて無理をし過ぎて大きく体調を崩すことがなくなったと感じています。
いざ、健康状態を改善しようと思っても続かない……という経験がある人も多そうですが、その原因は何なのでしょうか。解決策はありますか?
福島 一番の原因は「やる・やらない」のゼロイチ思考になってしまっていることだと思います。例えば「ストレッチを毎日10種類やる」と決めても、疲れているから「できない」と考えてしまい、続けるのがつらくなってしまいがちですが、「5種類やる」「1種類だけやる」というようなゼロとイチの間の選択肢も実はあるんですよね。
それに、人はどうしてもできなかったことの原因を自分の内面に求めてしまいがちです。基本的帰属錯誤という心理バイアスなのですが、「自分がダメな人間だからできない」と考えてしまうんです。でも本当にそうでしょうか。もしかしたら外部の環境に影響されていることもあるかもしれませんし、自分に合わないやり方だったのかもしれません。
できないことを自分のせいにし過ぎず、どんなことならできそうかを考えてみるのも継続のカギだと思いますよ。
懸田 本にもいくつか書いていますが、僕も挫折経験がたくさんあります(笑)。ジムに通っていたけど、コツコツ筋トレするのが合わなくて挫折したり、自転車通勤をしていたけど、引越しで職場が遠くなって挫折したり。
ただ、一貫してこだわってきたのは、自分が楽しんで取り組めること。どんなことなら楽しめるか、続けられるかを考えていろいろ試してきました。登山にもいろいろなルートがあるように、目標へ向かう道もたくさんあるんです。一つダメでも、他の道があるはず。そう考えていろいろ試してみるのもいいと思いますよ。
自分で選び、小さなステップを積み重ねていくから「無理なく」続けられる
『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』で取り上げられている「アジャイル」について教えてください。

『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』(翔泳社)
「アジャイル実践家&スポーツプログラマ」「元SEでスクラムマスターをしていた保健師」という著者陣が、
ITエンジニアをはじめとするデスクワーカーに向けて、アジャイルに基づいてポジティブな気持ちで健康カイゼンを行うための知識(食・運動・休息)やテクニック(カイゼンパターン)を網羅的に解説した一冊。▶「アジャイル式」健康カイゼンガイド
懸田 ここで言う「アジャイル」とは「アジャイルソフトウェア開発」のことで、顧客に価値あるプロダクトを提供することを目的に、少しずつ作り、フィードバックを受けなから顧客や市場の環境に合わせて柔軟に改修・改善していくソフトウェア開発プロセスのことです。
 ソフトウェアを一連の流れで開発・構築されてきた従来の模式図(上)と、
ソフトウェアを一連の流れで開発・構築されてきた従来の模式図(上)と、
アジャイルソフトウェア開発の模式図(下)
『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』第4章よりこれが、健康改善にも生かせる考え方だと思っていて。「これをやるだけでやせる」「これをやるだけで筋力がつく」といったようなやり方は、合う人にはそれでよいのですが、取り組む中で継続するのが難しく感じたり、自身の生活にフィットしないと感じるようになることもあると思います。
そこで健康改善における「継続」に重きを置き、目標の捉え方や取り組み方を柔軟に調整していくのが「アジャイル式」健康カイゼンです。
「カイゼン」とカタカナ表記にしているのには意味があります。元々は自動車メーカーのトヨタさんの業務改善において改善ではなくカイゼンとカタカナで呼ぶ文化があり、そこには「継続的な改善(英語だとContinuous Improvement)」という意味が込められています。
そもそもアジャイルは、トヨタさんの生産方式や仕事の進め方に大きな影響を受けています。その流れで、本書での「カイゼン」というカタカナ表記にも、あるやり方を一度やって満足するのでなく、「常に現状の変化に応じて、あるいは、現状でよりよいやり方に改善し続けていく」という意味を込めています。
「アジャイル式」健康カイゼンが「続けやすい」とされる理由を教えてください。
懸田 健康改善に向けた行動を継続するために必要なポイントとして、「自己効力感」「自律的動機づけ」「フィット感の調整」の3つを挙げています。
アジャイル式では、どの健康カイゼン行動=カイゼンパターンも小さくスタートするもので、一足飛びに負荷の高い行動はとりません。
小さく始めて「うまくいった」「次はこうしよう」と成功体験を積むことを重視しているので、「できなかった」という挫折感よりも「できた」「これもできそう」と自己効力感を高めることができます。
自律的動機づけは、自分自身が選んで決めるということです。お医者さんに「健康のために食事に気をつけるように」と言われて取り組むのと、自分が数ある方法の中から「食事管理ならできそうだ」という方法を選ぶのとでは、その後のモチベーションが大きく変わります。
「アジャイル式」では数々のカイゼンパターンから自分で選んで取り組むので、自然と自律的動機づけができるんです。
3つめのフィット感の調整は、まさにアジャイル式の基本的な構造です。体の変化というフィードバックを受けてPDCAを回し、よりよい状態を作っていくことができます。「アジャイル式」ではこの3つの継続ポイントを押さえているので、無理なく続けやすいといえるでしょう。
福島 フィードバックのサイクルを回していくことで、目標が変わっていくこともあると思います。例えば「何キロやせたい」という目標を立てていたけれど、自分が心身ともに健康でいられるベスト体重は? という視点から考えると「やせる」ではなく「キープ」や「体重を増やす」という方向に変わっていくケースも考えられます。
なるほど……! 具体的に、「アジャイル式」にはどんな方法があるのでしょうか。
懸田 本の中では、運動や食事、休養などの基礎知識とともに、健康カイゼン行動=カイゼンパターンを紹介しています。
例えば位置情報ゲームアプリで楽しみながら歩く習慣をつける、食べ過ぎ防止のために小さめの食器を使う……など、手軽さや目的に応じて様々なパターンがあります。これらの中から好きなものを選んで試し、自分に合うかどうか、継続が負担にならないかどうかを含めてモニタリングしながら、自分にフィットする健康習慣をつくりあげていきます。
中には合わない方法もあると思います。でもそれは失敗ではなく、合わない方法がわかったということ。自分に合う方法を見つけるためのプロセスだと考えましょう。
自分に合った方法を見つけるコツはありますか。
懸田 自分の今の生活のなかで、取り入れやすそうなものからチャレンジしてみるのが基本ですが、それを知るためにもまずは現状を知ることからですね。睡眠アプリなどもそうですが、運動や食事のログをとれるアプリなどはたくさんあります。
歩数や消費カロリー、摂取カロリーなどもアプリでチェックできるので、現時点で自分がどのくらい運動できているか、食事のバランスはどうかなどを把握するのが第一歩です。
歩数が少ない、食事バランスが偏っている、などの課題を見つけたら、それに対応したカイゼンパターンに取り組んでいきます。1週間ほど続けてみて、負担になっていないかをチェック。成果が出ているかは短期間で分かりにくいこともあるので、2週間から1カ月単位でチェックしてみるのがおすすめです。
 「アジャイル式」健康カイゼンにおけるプロセスの全体像を示した図
「アジャイル式」健康カイゼンにおけるプロセスの全体像を示した図
『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』第7章より福島さんが言っていたように、「やる・やらない」のゼロイチ思考をやめて、疲れているときでもできる行動パターンにアレンジしておくのも大切です。
これを「度合い思考」といいますが、「元気なとき・普通のとき・疲れているとき」などの状態別に取り組みの強度を変えておけば「今日もできなかった……」という落ち込みをなくせます。
それと、「自分にしっくりくる」というフィーリングを大事にしてほしいです。人はそれぞれ好みや大切にすることが違いますので、自分に向いていることを行うのが一番です。正解を一発で見つけようとするのでなく、実験しながら「しっくりくるやり方」を見つけていくプロセス自体も楽しんでほしいですね。
脱・挫折。成果が出ないときは行動を見直す・専門家を頼ってみる
ちなみに、成果が出なくて挫折しそうになってしまったときには、どうすればいいのでしょうか。
懸田 あまり結果をあせらないことは大前提ですが、成果が出なくてモヤモヤしている場合は行動指標を見てみるのがおすすめです。
今取り組んでいるカイゼンパターンをきちんと遂行できているかをチェックし直し、できているなら「もう少し様子を見てみよう」と思えるかもしれないし、「負荷を上げようかな?」「他の方法も試してみようかな?」と検討することもできます。
同じような取り組みをしている仲間をSNSなどで見つけて、情報交換をしてみるのもおすすめです。知らなかったことや違う視点からの情報が解決のヒントになることもあります。
福島 加えて、専門家を頼るというのも手段のひとつです。例えば、効果が出るまでに想定よりも時間がかかるケースもあります。自分は「1カ月で効果を出したい」と思っていても、専門家から見ると「3カ月はかかりますよ」というカイゼンパターンだったりすることもあります。そうした時間的な目安を知るのに専門家の知識が役立ちます。
また、正しい方法で行えているかどうかも重要なポイントですね。スクワットをしているのに成果が出ないという人は、姿勢など身体の使い方が正しくないことが多いのだそうです。他にも、歩き方や走り方など、人によってクセがあったり、関節などを痛めやすいフォームだったりすることがあるため、運動を新たに始めようとしている方や思うように成果が出ない方は専門家に相談してみるのがおすすめです。
専門家……。今まで健康に無頓着だったので、なかなかハードルが高いです。
福島 運動についてなら、パーソナルトレーナーを探してみるのもいいですよ。短期の結果重視のところよりも自分に合ったやり方を提案してくれて、長く続けられるところが健康改善という点ではマッチすると思います。
健康全般について相談したいなら私のようなフリーの保健師を探してみたり、地域の保健センターや暮らしの保健室*1などで行われている健康相談やイベントに足を運んでみるのもいいと思います。会社員の方なら、社内に相談できる医師や保健師がいることもあります。
懸田 運動のきっかけを作りたいならば、行政や地域の総合型地域スポーツクラブが主催するスポーツイベントなどに参加するのもいいですね。
PDCAを回し、無理なく続けられるカイゼンパターンに出合う
『「アジャイル式」健康カイゼンガイド』では、いろいろなカイゼンパターンとともに、ゼロイチ思考から抜け出す「度合い思考」や、普段の生活で負荷をかける「ニート
*2を増やす」という考え方が面白く、また無理なく取り組めるポイントでもあるように感じました。
懸田 この本では、「水泳」や「ジム通い」といった一般的な健康改善方法は記載していません。それができる人は、きっとこの本がなくても自分で取り組めるはずですから(笑)。どちらかといえば、本当にゼロの状態からスタートして、金銭的・時間的・精神的に負担にならないレベルでできるというところを意識していますね。
それが「やる・やらない」の間をとって「これだけできればOKにする」という選択を行う「度合い思考」であったり、日々の何気ない動作に負荷をかけたりスキマ時間を活用して体を動かしたりする「ニートを増やす」などの形をとって表れています。
「頑張ろう」という気持ちはとても大切ですが、それが無理につながってしまうと継続できません。無理に頑張らなくても自然に生活のなかに組み込めて、続けられるのが理想的なカイゼンだと思います。
無理に頑張らなくてもいいんだ、と思えるだけでも気持ちがかなり楽になりそうです。
懸田 人間の体調や環境には波があります。どうしてもできないときは負荷を下げてもいいし、繁忙期で時間がとれない・疲れてつらいときは思い切って休んでもいいんですよ。休むことも含め、状況に合わせて取り組むカイゼンパターンも見直しながら、自分のリズムを作っていければバッチリではないでしょうか。
福島 無理なく、という点では「ゆとり」も大切にしてほしいですね。忙しいけど、なんとかしなきゃ!と無理に始めてしまうのは挫折につながりかねないので、「今、改善に取り組めるゆとりはあるのか」を忘れずにチェックしてほしいです。
それから、やる気が出る要素を見つけるのも無理なく続けられる秘けつだと思います。自分がどんなことでモチベーションを高められるのかを知っておけば、取り組みの合間に楽しみを用意しておくこともできますよね。「ごほうび」というとらえ方もあります。
また、取り組みそのものに楽しい要素を組み込む、という考え方もあると思います。例えば、達成度合いを可視化することで喜びを感じるなら、達成できた項目を記録するチェックリストを用意するとか。競い合うのが好きなら、一緒に競い合えるライバルを見つける、などです。
私はパーソナルトレーニングに通っていますが、お話していて楽しいと思うトレーナーさんと厳しく指導してくれるトレーナーさんを日によって使い分けているんです(笑)。トレーニングの合間の会話を楽しみに通っている感じです。
最後に、仕事や家事育児など、忙しい日々の中で健康改善に取り組みたいと思っている人に向けて励ましのメッセージをお願いします。
福島 「思うようにできない自分」を許してあげましょう。どうしても無意識に「自分がダメだから続かないんだ」と思ってしまいがちなのですが、自分に合ったやり方や環境に出合えていないだけかもしれません。アジャイル式によってPDCAを回し、自分にフィットしたカイゼンパターンを見つける手がかりにしてほしいです。
そしてなにより、私は健康は目的ではなく、皆さんが自分らしくハッピーに生きるための手段のひとつだと思っています。皆さんが自分らしくハッピーな日々を送れるための手がかりとなれたらうれしいです。
懸田 優先順位はまず「自分」です。仕事の都合や周囲の人のことを考えるとどうしても自分のことは後回しになってしまうものですが、身体は自分自身に「調子が悪いよ!」とどんどん訴えかけてきます。それに気づけるのは自分だけ。だからこそ、定期的に体からのフィードバックを受け取って、「アジャイル式」で改善サイクルを回していただけたらと思います。
「アジャイル式」健康カイゼンに興味があるけれど、本を読んだだけではなかなか思うようにできない、本が読みきれないという方向けに、参加型ワークショップ「『アジャイル式』健康カイゼンに取り組んでみよう」が2023年1月から全3回にわたってオンラインで開催されます。
イベントでは、本書で扱っているワークを参加者皆で行い、振り返りと軌道修正をしていきます。健康カイゼンを考え・アクションプランを考えるきっかけとして、ぜひ参加ください。詳細は下記のイベント告知ページからどうぞ。
「アジャイル式」健康カイゼンに取り組んでみよう(全3回):第1回健康カイゼン導入編 - connpass
「ずっと疲れている」と感じたら、こちらも
"疲れている自分"を当たり前にしない「正しい休み方」
テレワークによる肩・腰・お尻の疲れに「座りながらストレッチ」
お話を伺った方:懸田 剛さん、福島 梓さん
懸田 剛(かけだ・たけし)
日本にアジャイルが紹介された2000年からアジャイル開発の研究・実践を始め、現場への導入支援を行うようになる。40歳から始めたランニングをきっかけに身体へ目を向け、心身の統合・ウェルビーイングを探求しはじめる。いきいきとした個人、組織、環境づくりに携わる。認定スクラムマスター、日本スポーツ協会公認スポーツプログラマー。
福島 梓(ふくしま・あずさ)
保健師、看護師、産業カウンセラー。 臨床心理学を学んだ後、SEとして働き始める。アジャイル開発やUXデザインの実践・支援に携わる中で、働く人の健康について問題意識を強くし、2014年千葉大学看護学部に入学。 卒後、産業保健師として組織・個人の健康支援、組織開発支援に従事。 現在は個人の健康相談や企業の組織開発や新価値創造支援に携わりながら「皆が自分らしくイキイキと働き続けられる社会」の実現に向け、日々模索している。