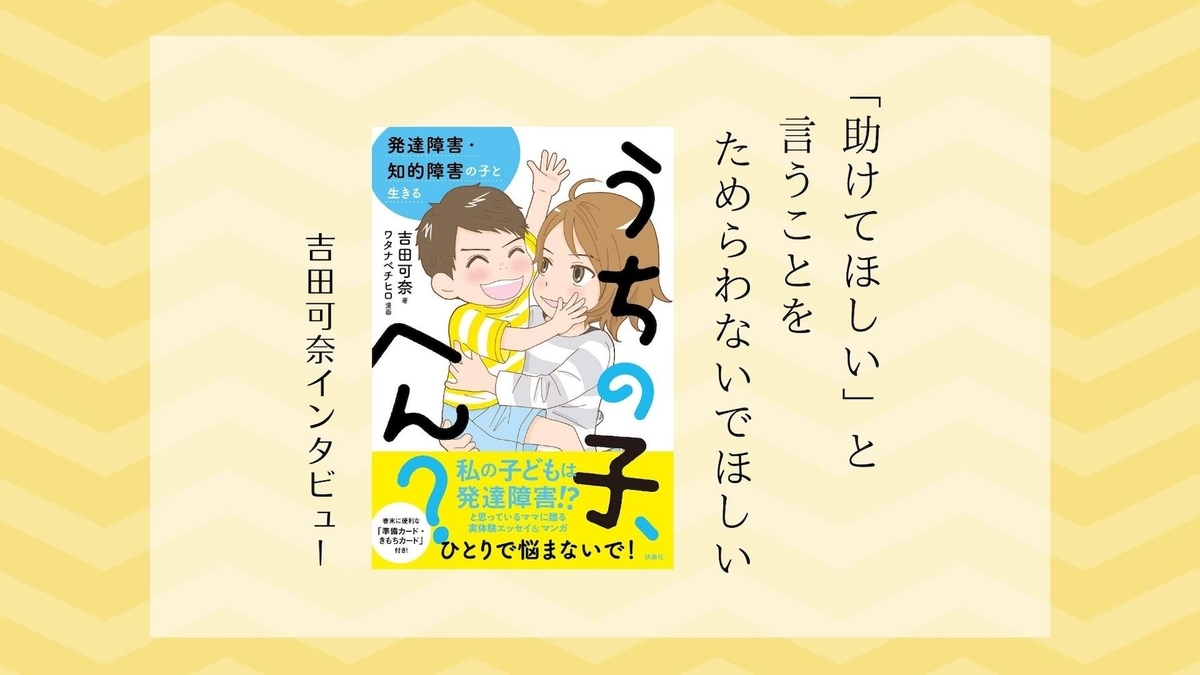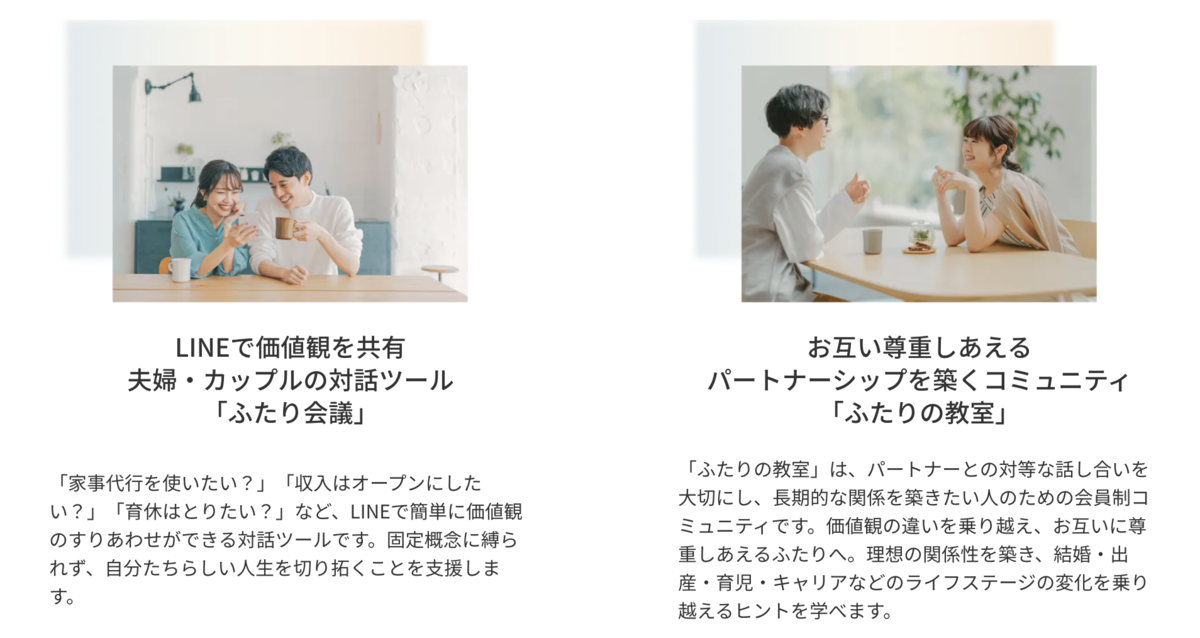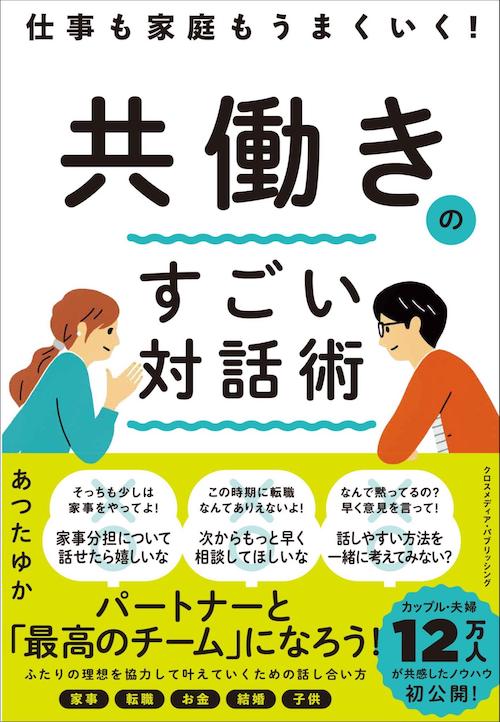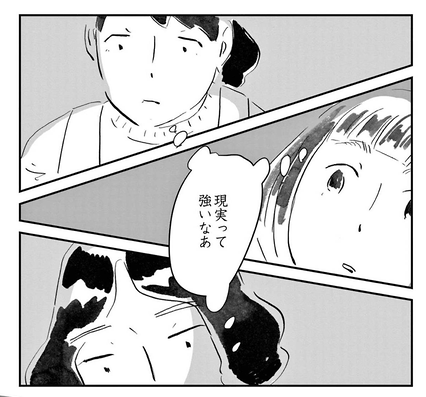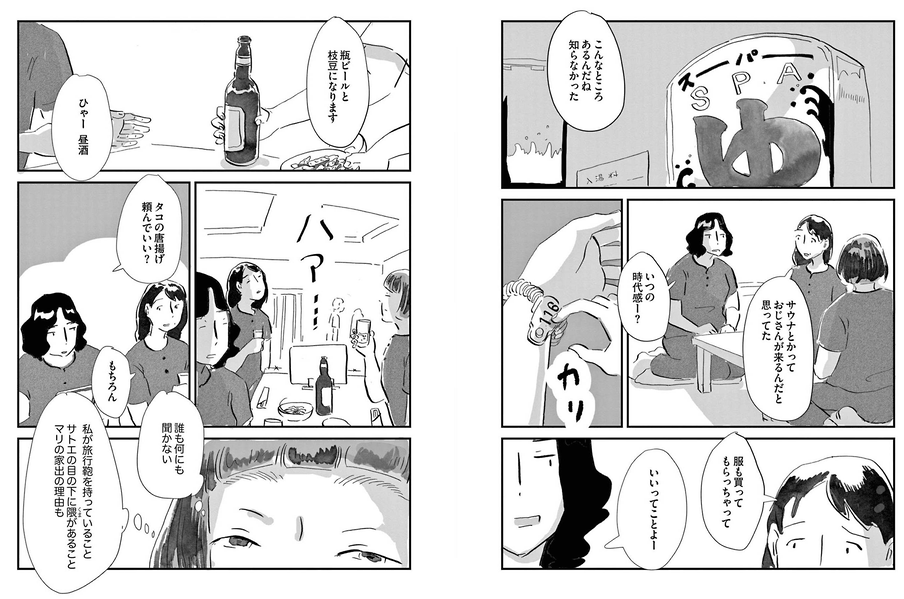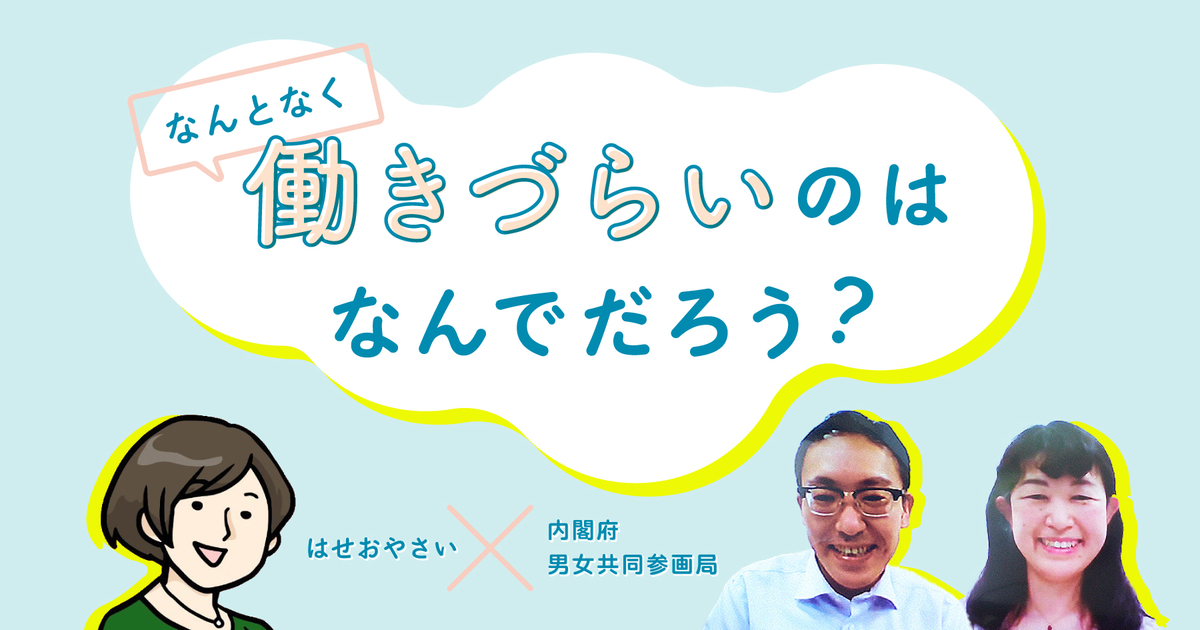
「仕事が忙しくて自分に使える時間が少ない」「頑張って働いているのになかなか収入が増えない」「子どもが生まれたら今までと同じようには働けないのかな」
働く上で、こういった悩みを抱えている方は少なくありません。誰もが不満や不安のない状態で働くには、まだまだ国や企業の制度が整っていなかったり、慣習や自分の思い込みが足かせになったりしています。
そこで今回は、会社員兼ブロガーのはせおやさいさんと一緒に「働く人が抱えている課題」について考える対談を実施。対談相手は内閣府男女共同参画局の方々です。男女共同参画局は毎年、ジェンダー・ギャップにまつわるさまざまなデータやエビデンスを調査し取りまとめた「男女共同参画白書」を発行しています。
私たちが「働きづらいな」と感じる背景にはなにがあるのか、なかなか見えづらいけれど「国」や「企業」は変わろうとしているのか、どうしたらみんなが「自分が納得する働き方」を選べるようになるのか――。いち会社員であるはせさんが日々感じている不満や課題を投げかけてみました。
<<プロフィール>>
そもそも「男女共同参画局」って何をしているの?
はせおやさい(以下、はせ) こんにちは! 今日はおふたりに、私が普段働く上で感じているさまざまな悩みをお話しできればと思うのですが……そもそも「男女共同参画局」ってどんな組織なんでしょう? 名前はニュースなどでよく見かけますよね。
由井啓太郎(以下、由井) 「男女共同参画局」はその名のとおり、男女共同参画を推進する部署です。内閣府に置かれていて、ジェンダー・ギャップを解消していくために5年ごとの基本計画を制定したり、政府内の会議を運営したりするのが主な業務です。そのなかに「男女共同参画白書」の作成や国会報告が含まれています。

左・内閣府男女共同参画局の由井啓太郎さん。右・同 丹下留美子さん
はせ 「男女共同参画白書」は毎年ニュースやネットで話題になりますよね。今年は「20代男性の約4割がデート経験なし」「もはや昭和ではない」といったトピックに注目が集まっていました。
由井 「男女共同参画白書」には、社会の現状と対策をオールインワンで提示するという役割があります。盛り込まれているのは、大きく分けて「男女共同参画社会形成の状況」と「そのために政府が講じた政策」「これから講じようとする政策」の3つです。
また、価値観が多様化する社会の中で、国民の誰もが納得できる政策をつくっていくには、客観的なデータの裏付けが欠かせません。そのためにも、白書では印象や雰囲気ではなくエビデンスをもって「実態」を示すことを目的としています。
はせ 日ごろ「なんで分かってもらえないんだ!」とモヤモヤしていることが、実態やエビデンスに基づきデータで示されている、と。それは心強いです! ところで白書って毎年、個別のテーマが設けられているんですよね。どんなふうに決めているんですか?
丹下留美子(以下、丹下) その年の「ホットトピック」を取り上げるようにしています。例えば令和3年は、その前年から続くコロナ禍や生活の変化を踏まえ、「コロナ下で顕在化した男女共同参画の課題と未来」となりました。
そして、よくよく分析してみると、緊急事態宣言などによって生活や雇用が脅かされた方には女性が多く、男女共同参画が推進しきれていなかったことが分かりました。そこで令和4年はその背景を探るため、「人生100年時代における結婚と家族~家族の姿の変化と課題にどう向き合うか~」というテーマを設定したんです。
はせ 「白書」といわれると堅い印象を受けるのですが、どちらもすごく身近なテーマですね! ただ、社会で働く一会社員としては白書でまとめた内容がどうやって政策に反映されていくのかが気になります……。
由井 具体的な政策に落とし込んでいくのは、制度等を直接担う各省庁の役割ですが、私たちは白書の中で、さまざまな政策を検討する際の前提となるデータをまとめて示しているというわけですね。今日は白書をもとに、どんな政策が取られているかもお伝えできればと思います!
はせ なるほど! では早速、私が日ごろ働いて生活する上で感じている悩みごとについてお話しさせてください。
由井 リアルなお話、こちらもぜひお伺いしたいです!
キャリアが一時中断すると“元”に戻りづらい……
はせ 私は昨年、40代で転職活動をしたのですが、これがもうとても難しくて。未就学児を育てていることもあり、転職エージェントに相談するとまず「子どもがいるなら時短勤務ですね」と提案されるんです。
わが家は私の収入が家計の多くを占めているのですが、時短勤務になると収入が6~7割まで減ってしまいます。「子どもがいる既婚女性」という属性だけで、当たり前のように「時短」を提案されたことに不安を感じました。
丹下 IT産業でも難しいのですね。IT産業はもっと柔軟に対応してもらえるものだと思っていました。
はせ IT産業は確かにかなり柔軟でフラットな企業もありますが、その手前で転職エージェントの固定観念に阻まれた感じもありましたね。私の場合は「40代子持ち女性の転職」の悩みでしたが、「30代フリーランス男性」である夫も、育児をきっかけにキャリアについて悩んだことがあって。
私は子どもが生後半年のときにフリーランスを辞めて会社勤めをはじめたんです。なので子どもが保育園に入れるまでは、フリーランスの夫が仕事をセーブして、専業主夫をしてくれていました。でも夫は、社会復帰のときに「以前と同じ仕事や収入で働けるのか?」と不安がっていたんですね。
私たちのように、今の日本の「育児や介護などでキャリアが一時停止すると、収入の水準や役割を戻しづらい」という状況に不安を感じている人は多いと思います。

由井 出産や育児だけでなく、介護など家庭の事情で一度現場を離れても、同じ条件で戻れるといいですよね……。
はせ そうなんです!
由井 日本ではまだまだ「稼ぎの主体は男性で、女性はそれを補助する」という昭和的な家族モデルが根底にあるため、「家庭の事情」が考慮されづらいと思います。
これらに紐付く問題は、「勤続年数」を賃金を定める際の考慮要素として重視する組織が多いことや、男女間の賃金格差もあります。同じ組織の中でも、正規・非正規や勤務時間といった雇用形態の違いによって、男女間で賃金格差があるケースは少なくありません。
はせ 私は「フルタイムから時短になって収入が減るかもしれない」という点に悩みましたが、そもそも非正規雇用しか選択肢がないという方も多いですよね。既婚で子どもがいる女性は特に……。
由井 そうなんです。社会全体で見てみても、女性が多いサービス業やエッセンシャルワーカーは、業務と賃金が見合っていないことがあります。こうした現象はいずれも、「女性の稼ぎは補助的である」という古い考え方に基づいているのでは? と推察しているところです。
はせ そういう構造的な格差って、どうすれば解消するんでしょうか。
由井 まずは民間企業に対して、男女間の賃金格差に関するデータを開示してもらうよう、仕組みをつくっています*1。それから、同一労働同一賃金を徹底するための政策も進めていて*2、さまざまな角度から格差を解消していきたいと考えています。
はせ ぜひ解消してほしい……! 社会全体に「働いている母親は時短勤務」「主たる稼ぎ主は男性」という決めつけが根強く残っていて、別の選択肢を検討しづらいと感じるので……。
由井 社会保障制度が昭和の「夫が外で働いて、専業主婦が家を守る」という前提をベースにつくられたままになっているのも大きいんですよね。そこで白書では、これまでの家族の姿はもうスタンダードではないことや多様な生き方についてとらえ、実態をレポートしています。
 平成初期に共働き世帯と専業主婦世帯の割合が逆転し、その差は開き続けている(令和4年版「男女共同参画白書」より)
平成初期に共働き世帯と専業主婦世帯の割合が逆転し、その差は開き続けている(令和4年版「男女共同参画白書」より)
丹下 実際に「社会保障は世帯単位ではなく個人単位にすべきではないか」といった議論も生まれています。ただ、省庁横断でまるごと変えていかなければいけない問題なので、なかなかスピードが出せずに歯がゆいのですが……関係者それぞれ、頑張っていきたい思いは確かです!
「1日8時間×週5勤務」がデフォルトなのは大変!
はせ 先ほどの時短勤務の話ともつながっているのですが、「働き方」についても考えたいなと思っていて。
会社員は「1日8時間×週5日」勤務がデフォルトのケースが多くて、それだけ働いていないと受けられない社会保障も少なくありません。でも、暮らしを営んで子どもや親の面倒を見ていると、フルタイム勤務は本当に時間が足りなくて!
家族と過ごす時間や睡眠時間など、何かを切り捨てないとやっていけないんです。「稼ぐ人」と「母」を両立しようと思うと、身も心も引き裂かれそうになることがあります……。
丹下 私も子育て中なので、お気持ちはよく分かります。ある程度柔軟に働けていたって、大変ですよね。
ワークシェアリング(労働者を増やすなどして、労働者同士で雇用を分け合い、社会全体の雇用者数を増加させること)はひとつの解決策ですが、どうしても収入が減ってしまうため、根本解決にはなりません。
キャリアを落とさず、かつ負担を減らして働き続けられるような方法だと……例えば海外では、女性の幹部職員と意欲の高い男性ミドル層にペアで働いてもらい、限られた時間で仕事をうまく回す取り組みがあると聞いています。そうした例を紹介しつつ、国内でも前例を積み重ねていきたいですね。

はせ そのアイディアは面白いですね。もしくは、働き方自体がもっとフレキシブルになったらいいなと感じます。
私はフルリモート勤務ですが、それでもやっぱり体調不良や休園などで子どもが家にいたら仕事はできません。協力し合えるパートナーがいればまだしも、ワンオペやシングルの方は本当に大変だと思います……。
由井 今後のためにぜひ伺いたいのですが、はせさんは社会にどんな働き方を許容してほしいと思いますか?
はせ 時間単位で取れる休暇があったらいいなと思います。企業によってはすでに時間単位の有給休暇を導入しているところもありますが、子どもがいる・いないにかかわらず時間ごとに休暇が取れたら、どうしても仕事を抜けなければいけない時間帯だけ休めるのでありがたいですね。
それから私自身はフレックスタイム制で雇用されていて、月の総労働時間で勤怠管理されていることに、とても助けられています。子どもが体調を崩して3日間労働時間が短くなったとしても、そのあとの稼働時間を調整すれば、なんとかなったりする。
もちろんそういった働き方が難しい職種もあるでしょうから、いろんな方法で「働き方の裁量」を自由にしてもらえると、みんなが少し楽になるんじゃないかなと思います。
丹下 そうした働き方の問題は、女性だけでなく、男性も含めて考えていきたいですね。時代の変化に伴って「仕事より家庭を大切にしたい」「育児にしっかり参加したい」という男性も増えてきているので。
そのためには、誰もが柔軟に働ける仕組みづくりが必要ですが……じつは、女性に比べるとまだ男性の分析は進んでいなくて。そこも今後の課題です。
はせ 性別や子どもがいる/いない、家庭の状況にかかわらず、みんなの働き方が柔軟になって、仕事に忙殺されず自分の時間も大切にできるようになるといいですよね。
働くことと結婚・出産はトレードオフなのか
はせ 最近、年下の女性から「結婚や出産をしたら、キャリアを維持するためにはいろんなことを犠牲にしないとダメでしょうか?」とよく聞かれるんです。若い世代にまで「働く」と「出産」はトレードオフになるという価値観が浸透していると感じるんですが、実際のところ、どうなんでしょうか?
由井 働いている女性の8割以上が、結婚しても就業を継続しています。なので、結婚はさほど大きなターニングポイントにはなっていません。が、第一子を出産したタイミングでは、約3割の女性が仕事を辞めてしまいます。第二子、第三子となると就業継続率は8〜9割をキープする*3ため、「第一子出産」と「働く」は、少なからずトレードオフになっている可能性があるといえるでしょう。
 子どもの出生年別にみた、出産前後の妻の就業変化(「第16回出生動向基本調査 」より)
子どもの出生年別にみた、出産前後の妻の就業変化(「第16回出生動向基本調査 」より)
はせ 第一子が転機だったんですね! そして、ただ一口に「働く」といっても、「本人が納得する形で働けること」が大事なのかなと。
もちろんそれぞれの家庭の事情や方針によっては「時短や非正規雇用を希望する」こともあると思うのですが、「フルタイム」や「正社員」を希望しているのに、「時短」や「パート」になってしまう人もいて……。働き続けたい方が、働きたい方法で働き続けるには、どうすればいいのでしょうか。
由井 まずはやはり「働き続けたい方をサポートする仕組みづくり」が大事だと思いますし、私たちとしても今後いっそう大切にしていきたい部分です。支援が不十分なことで働き続けられなくなっている方は、一定数いらっしゃいますから。
ただ、とくに団塊ジュニア周辺の世代には「子どもが小さいうちは家で育てたい」という声も、案外少なくないようで……。

女性が職業を持つことに対する意識の変化(令和4年版「男女共同参画白書」より)
はせ 確かに……! 私の親は昭和10年代生まれで、まさに「3歳児神話(3歳までは母親が家で育てるべきという考え方)」の世代です。そんな母にしっかりと手をかけて育ててもらってきたぶん、私自身も幼い我が子を保育園に預けることに抵抗があって……。
こういう葛藤によって、自主的に仕事を離れてしまったり、雇用形態を変える方がいるのは想像できます。企業も変わろうとしているし、私たち自身の価値観も変わっていく途中なのかも。
丹下 社会の機運も高まっており、出産しても働き続けられる環境は、以前に比べてずいぶん整ってきていると感じます。
とはいえ、先ほどのお話のように「時短を余儀なくされる」といったケースもありますし、働きたくてもそれぞれが希望する方法で働けない方を阻害している要因が何なのかを引き続き探り、対策を講じていきたいです。
多様化する人生。 性別・属性を問わずみんなが生きやすくなるには?
はせ 少しずつ変わってきてはいるものの、これまでのお話にもあった通り、男は外で稼いで女が家の中のことをやるという意識は、若い世代にも根強く残っているのかなと感じています。
30代の夫は現代的な男性なんですが、駆け出しのフリーランスをしていたとき、周りの人に「奥さんが会社員だから大丈夫でしょ」と言われて、すごく悔しかったそうなんです。そのとき、自分のなかに「男が稼いで食わせたい」という価値観が残っていることに気づいてびっくりしたと。
丹下 まさにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)ですよね。実際「男性は稼がなければいけない」という男性の考え方は、調査結果にも表れています。
また、コロナ下で男性の仕事時間は減り、その分、育児時間が増えたのですが、家事参画の時間はほとんど増えていません。育児をしても、家事をする男性は少ないんです。そうした価値観は、世代間で継承されている部分も大きいんですよね……。

令和3年度「性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査研究」より
由井 ただ、変化の芽は見えてきていて、やはりコロナ下で働き方が変わったことは大きく影響しています。
まず一部の業種・職種に限定した話ではありますが、働く場所と住む場所が一致したことで余剰時間が生まれました。働きながら家事育児をしたいと考える男性も、若い世代には増えている。これからの調査でその実態を把握していけば、男性の家事育児参画を促す制度の誕生にもつながっていくはずです。
もちろん、男性の人生も多様化しているいま、結婚や出産が前提ではありません。結婚や家事育児をしたい男性をフォローしながら、そうではない人生を歩む男性も支援することが必要です。
例えば、女性に比べると数が少ない男性の地域における相談窓口の整備拡充などは、今後大切な施策のひとつだと考えています。
はせ 男性と女性の生きやすさは両輪だから、併せて変わっていかないといけませんよね。
由井 おっしゃるとおりです。国民の意識と制度は、補強し合って最適化していくもの。今は時代に合っていないと思われがちな社会保障制度も、少し前の時代には最適でしたし、ひとつの均衡を達成していました。
いまは、そのバランスが少し崩れている過渡期。次の均衡を目指して、制度と意識の両面にアプローチをしていきたいと思います。

撮影:小野奈那子
編集:はてな編集部
みんなの“仕事”の悩み
*1:2022年7月8日、女性活躍推進法に基づく省令改正により、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に男女間の賃金差の開示が義務付けられた。
*2:同一企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の待遇差の解消を目指し、パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法の改訂が行われた。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
*3:第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)より