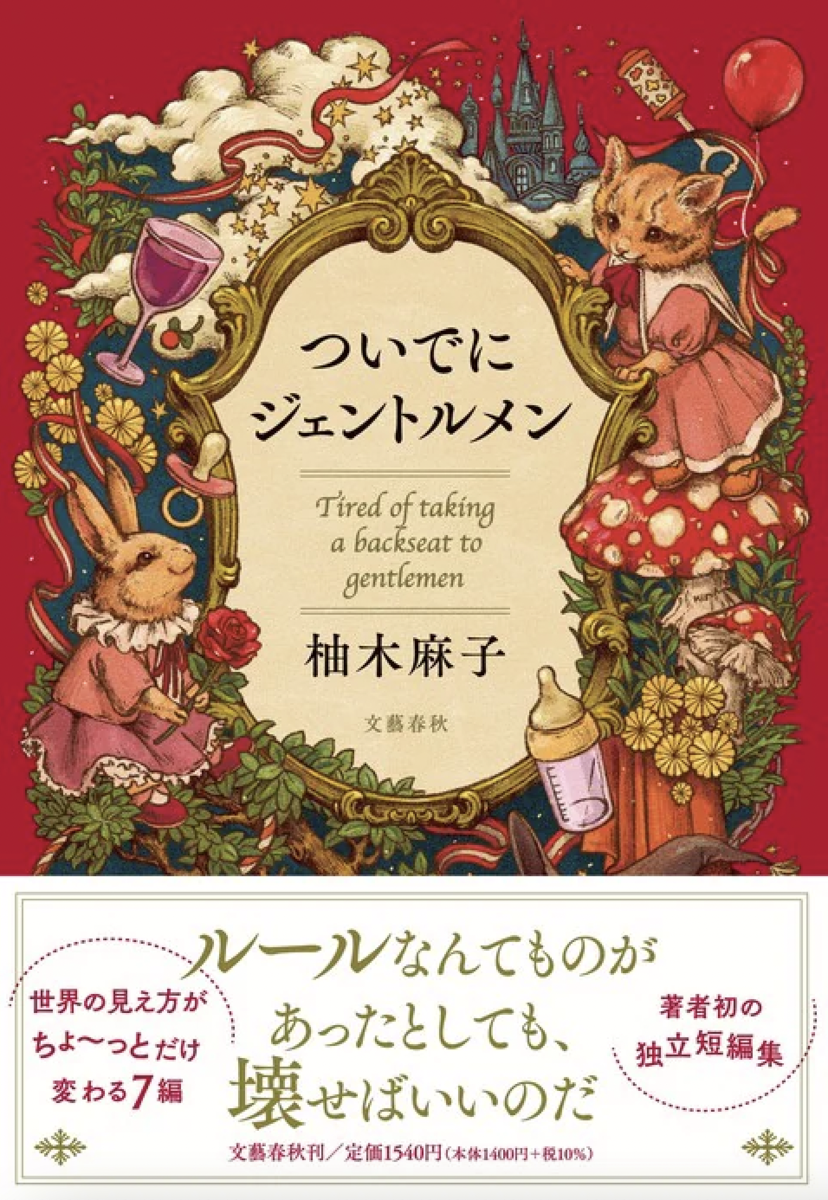友人や同僚の“らしくない”一面を見てしまい、ハッとしたことはありませんか。相手に対してよいイメージや悪いイメージをあらかじめ抱いていたときほど、「こんな面もあったのか」というギャップを強く感じるように思います。
しかし、他人の“自分には見えていない”面は、プライベートをあまり知らない人はもちろん、家族やパートナーのように、自分にとってごく身近な人にも多かれ少なかれあるものです。
会社員として働きながら作家活動を続ける一穂ミチさんは、人の“多面性”や“ブレ”を、作品の中で非常に繊細につづります。どんな人物を書くときにも必ず「ほころび」が一箇所は出てしまう──という一穂さんに、その創作論を起点に、“人をジャッジしない”まなざし方についてお話を伺いました。
現実でもフィクションでも、人は「秘密」を抱えている

『スモールワールズ』(講談社)
夫婦円満を装う主婦と、家庭に恵まれない少年。「秘密」を抱えて出戻ってきた姉とふたたび暮らす高校生の弟。初孫の誕生に喜ぶ祖母と娘家族。人知れず手紙を交わしつづける男と女。向き合うことができなかった父と子。大切なことを言えないまま別れてしまった先輩と後輩。誰かの悲しみに寄り添いながら、愛おしい喜怒哀楽を描き尽くす連作集。
▶一穂ミチ『スモールワールズ』特設サイト
一穂ミチさん(以下、一穂) 「家族」というテーマは、実際にはそこまで強く意識しなかったんです。強いて言えば、連作短編という枠組みのなかで、それぞれの作品の構成が似過ぎないようにしようと考えたくらいでした。家族がいることで生まれる何かはもちろん、家族がいないこともお話になりうると思ったので、実質ノーテーマみたいな感じでしたね。
一穂 そうですね。家族がいる/いないということそれ自体が、なんらかの強烈な因果を生むことってあるよなと思ったんです。
最近「親ガチャ」や「毒親」という言葉もよく聞くようになりましたが、そういう言葉が表す感情がひとつの典型なのかなと思います。どんな親のもとに生まれるかで人生の最初のパラメータが決定してしまって、なかなかそれを埋めることができないと感じる若い人が増えている、ということなんじゃないかと。
私自身、毒親とは思わないまでも、親に対して抱いた「あれはないよな」という気持ちってけっこう覚えていますし。相手は忘れているだろうけど、こっちはずっと覚えてるだろうなと感じる言動ってありますよね。
一穂 ですよね。私の場合は歳を重ねたこともあって、「今の私くらいの年齢のときに親は小学生の私の面倒を見てたのか、えらいねえ……」みたいな気持ちにもなるんですけどね(笑)。どんな形にせよ、家族というものに対して好き嫌いでは割り切れない気持ちを抱いている人は多いんだろうなと感じます。
一穂 どんな作品でもそうなのですが、最初のプロットの時点では、なんの秘密も事情もなくスルッとお話が終わってしまうこともあるんです。でも書き進めるうちに、私が想定していなかったような嘘をキャラクターがついていたり、隠しごとがあったりするのが見えてくるという感覚があって。そういうときは、「あれ、この人はこういうことするはずではなかったんだけどな」と思いつつ、まあいいかって感じで書いていくんですね。
一穂 そうなんですよ。感覚的には、現実の人物と出会って対話を重ねていくときとあまり変わらないというか……。もちろん、年齢や性別、属性といった大まかな設定は最初に決めるんですが、その人らしさみたいなものは、他の登場人物とのやりとりや日常生活の中での振る舞いを通じて徐々に知っていく感覚なんですね。だから登場人物の性格や印象に対してひとつの正解があるわけではなく、あくまで「私の中ではこの人ってこういう人だな」という感じでいつも書いているんです。
一穂 BLのお約束である攻め・受けを最低限決めるというのと、挿絵を描かれるイラストレーターさんにビジュアル面のイメージは頼らせていただく、という点では違うのですが、それ以外はあんまり変わらないですね。
……身長がどのくらいとか、オフィシャルの情報が細ければ細かいほどBLの読者はうれしいというのはわかってはいるんですよ、自分もそうなので(笑)。でも私が書く場合は、読者の方のご想像にお任せしますという部分がどうしても多くなりますね。
一穂 お話を作るときは、設定や展開を細かく決め過ぎない代わりに、そういったディテールから着想を膨らませることも多いですね。例えば目の中にほくろがある子を出そうと決めたら、その特徴を生かす方向に頭が働いていくというか。
ディテールに関しては、日頃からツヤツヤのどんぐりを拾うみたいな感覚で少しずつため込んでいるんです。一見値打ちがないように思えても、自分には奇麗に思えたり、何となく気になったりするものってあるじゃないですか。そういうものに日常生活で出会うたびに、「これツヤツヤだな、ためとくか」みたいな感じでとっておく。仮にそれを何にも使わなかったとしても、どんぐりがいっぱいあるとうれしいんですよね(笑)。
誰に対してもフラットな人って、実はあまりいない
一穂 ゲームのキャラクターのように、いつ話しかけても同じことを言う、という感じにはしないように心がけています。例えば私自身、AさんとBさんという二人の人物がいたら、そのどちらにも全く同じ態度で接するということは恐らくしないですし。そんなにメンタルが安定しているタイプでもないから、天気や体調によっても、考えること自体が大きく変わってくるんですよね。
それに、職場の上司や同僚、学校の先生、それこそ親に対しても「あれ、前と言ってること違うな」と感じることってあるじゃないですか。この人がする分にはOKなのに私はNGなのか、とモヤっとすることもありますし。常に同じように人に接することができるほどフラットな人って、実はあまりいないんじゃないかと思います。
一穂 たくさんあります。一番感じるのは、会社の人の家庭での顔を見てしまったときかもしれないです。前に、会社の同僚とそのご家族と一緒に舞台を見に行ったことがあるんです。その方はけっこうはっきりした物言いをするタイプで、会社ではちょっと話しかけづらく感じていたんですが、お子さんと一緒にいるときは全く違って、すごくやさしくて。
終演後、CDを買うと出演者の方と写真が撮れるというイベントがあったんですが、「娘が写真撮りたいって言ってるから、俺ちょっと並んでくるわ」と率先してその列に並びに行ったんですよ。「マジで!?」と思って(笑)。全然そんなタイプに見えていなかったんです。でも、お子さんにとってはお父さんのそういう姿の方がナチュラルなんだろうなとも思って。
……例えば友人と食事したりしていても、相手が恋人からの電話に出るときって、なんとなく分かったりしませんか? 態度というか、空気が変わる感じがして。
一穂 そういうとき、当人は全然気付いていなかったりしますよね。他人のそういう面って面白いなと感じますし、たぶん自分も同じなんだろうなと思いますね。人ってそういうものだろうと思っているから、そういう人たちを書くのかもしれないです。
一穂 ぶれない人の方が読んでいて安心はしますよね。例えば、スカッと事件を解決してくれることが現れた瞬間から約束されている、一貫したスタンスの名探偵のようなキャラって私も格好いいなと思うんですよ。そういうキャラクターが出てくる作品ももちろん楽しく読むのですが、私の場合は、ブレブレの人の方が書きやすいかもしれない。
人の揺らぎみたいな部分を書くのが楽しいというか、どこか一箇所でもいいからその人のほころびが見たいと思ってしまうんですよね。……というより、意識せずとも、書いているうちにそういうほころびがどこかで勝手に出てきてしまう気がします。
好きと嫌いの間の「グレーの部分」が大切な気がする
一穂 何かを絶対的にいいと言う人も悪いと言う人も、どこか信用ならないという気持ちがあるのかもしれないです。さっきの同僚の話じゃないですけど、私の目から見た「いい人」が、他の人から見ていい人かどうかも分からないですし。それに、曖昧さが許されるのが創作のいいところだと私は思っているので。
一穂 いや、そうは言いつつも、私も全然できてないですよ。人のきらびやかなインスタとか見たときに、「この人ま~たアフタヌーンティーしてるよ」とか思ってしまう(笑)。
……でもやっぱり、SNSやYouTubeのようなプラットフォームを使って誰しもが自分のことを発信する時代になっているからこそ、ときに「これは見せたい自分を見せているだけなんだよな」ということを忘れないようにしないと、と思うようになりました。
それと、昔は家族のことにしても「家のことはあまりよそで言うもんじゃない」という価値観を多くの人が持っていたと思うのですが、今はそれをごく当たり前に発信する人も増えましたよね。
一穂 そう。人の発信を見ることによって「うちだけじゃないんだ」と安心できることもあれば、反対に「うらやましい」とか「おかしい」と感じてしまうこともあるから、いいことだけではないよなと思います。
一穂 「人に見せるための自分」をみんなが当たり前に持っている時代って、考えてみたらたぶん、今が初めてなんじゃないかと思います。私自身、自分のSNSに関しては情報をろ過した上で投稿している自覚がありますし、それは誰しも一緒だろうなと思いますね。
それに今って、誰かが炎上したり失言で注目されたりしたとき、これまでのその人の人生や人格までも否定するような勢いで叩かれることもありますよね。そういう過激さは少し怖いなと思ってしまいます。自分自身、迂闊な言動ひとつで叩かれる立場になる可能性もありますし、いつ自分にも火の粉が降りかかってくるか分からないことを考えると、人を一方的に断罪したり善悪を決めつけたりするのはやめておきたいなと思います。
一穂 自分が好きだったその人のイメージが崩れて「裏切られた」とか「騙されていた」と感じてしまったり、今まで好きだったことすら全否定してしまう、というのはちょっと違うように思いますね。
一穂 けれどその一方で、自分の価値観とはどうしても相容れないことを人が言ったときに、そのひと言や行動をきっかけに相手のことを嫌いになる、というのもありだと私は思うんです。誰しも、絶対に受け入れられないことや許せないことはありますから。
重要なのは、人を見るときに、相手によって自分の中の物差しの目盛りを粗くしないことじゃないかと思います。例えば1メートル尺ではなく、もっと細かく目盛りを刻むことで、初めて計れる部分があるんじゃないかなと。人に対する感情って、好きと嫌いの間のグレーの部分がすごく大事な気がします。
一穂 私はやっぱり、なかなか割り切れないものとか言葉にうまくできないものを、なんとか言葉に落とし込みたいと思って小説を書いているところがあります。小説というもの自体が今、ほかのメディアと比べて、非常にスローなメディアになっていると思うんです。例えば物語のあらすじを3行でまとめようとしても、いいところは伝わらないと思いますし。その点は、早く簡潔に結論だけをくれ、早くすっきりさせてくれ、という今の社会のムードとは真逆だと感じます。
でもそれが小説のいいところだと個人的には思いますし、たぶん、それがいいと思ってくださる方って減ることはあるにせよ、この世から消えることはないとも思うんです。だから、まあこれからもこの感じでやっていこうかな、と思いますね(笑)。
編集:はてな編集部
職場や知人友人の人間関係に悩んだら
お話を伺った方:一穂ミチさん