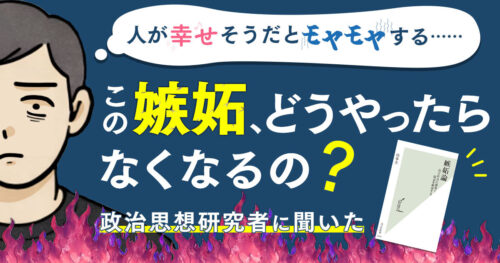東京・神楽坂にある中華の名店、「龍朋(りゅうほう)」にて。

こちらは、いつもパワフルで元気をくれる柳下恭平さん。神楽坂の書店「かもめブックス」の店主で、ご近所さんです。
 「やっぱり龍朋はおいしいね」
「やっぱり龍朋はおいしいね」
 「ですね。昼からビールが飲みたくなってきました」
「ですね。昼からビールが飲みたくなってきました」

 「ところで柳下さんの後ろの壁に貼ってあるメニューって手書きですよね」
「ところで柳下さんの後ろの壁に貼ってあるメニューって手書きですよね」
 「これ?そうだね」
「これ?そうだね」

 「風の噂によると、『書楽家(しょがくか)』と名乗る方が書いているらしいよ」
「風の噂によると、『書楽家(しょがくか)』と名乗る方が書いているらしいよ」
 「書道家じゃなくて、書楽家ですか。初めて聞きました。このメニューの文字がおいしそうで、いつも注文しすぎちゃうんですよね」
「書道家じゃなくて、書楽家ですか。初めて聞きました。このメニューの文字がおいしそうで、いつも注文しすぎちゃうんですよね」

 「たしかに独特で味わいある文字だよね。誰が書いているのかは僕も知らないんだけど、気になってきたな……」
「たしかに独特で味わいある文字だよね。誰が書いているのかは僕も知らないんだけど、気になってきたな……」
 「(回鍋肉もおいしいなあ)」
「(回鍋肉もおいしいなあ)」
 「冨田さん、調べてきてよ」
「冨田さん、調べてきてよ」
 「私も気になりますけど、柳下さんもどこにいる誰なのか知らないんですよね。どうしたものか……」
「私も気になりますけど、柳下さんもどこにいる誰なのか知らないんですよね。どうしたものか……」
 「あ、私すぐに連絡できますよ」
「あ、私すぐに連絡できますよ」
 「おや、この声は……」
「おや、この声は……」
 「いつもお世話になってる、龍朋の結子さん!」
「いつもお世話になってる、龍朋の結子さん!」
 「このメニューを書いてくれているのはうちの昔からの常連さんで。きっと話を聞かせてくれるはずだから、連絡してみますね」
「このメニューを書いてくれているのはうちの昔からの常連さんで。きっと話を聞かせてくれるはずだから、連絡してみますね」
 「いつもいつも、ありがとうございます!」
「いつもいつも、ありがとうございます!」

創業1978年の中華の名店・龍朋。昼から夜までひっきりなしにお客さんが訪れる人気店で、一日中活気に溢れる
ということで、神楽坂にある龍朋のメニューの文字を手がける、「書楽家」さんのアトリエに伺うことになりました。
書を扱う方と聞くと、なんだか寡黙なイメージ。
きっと静かな方なんだろうな……。うるさくしたら怒られるかもな……。
話が止まらない! マシンガントークで取材スタート。

 「やあやあ、ようこそ!僕が書楽家の、安田有吾(やすだ・ゆうご)です! 龍朋さんには通い始めてもう30年以上経ちますから、身体の70%が龍朋でできていると言っても過言ではありません。僕が好きなメニューはね……」
「やあやあ、ようこそ!僕が書楽家の、安田有吾(やすだ・ゆうご)です! 龍朋さんには通い始めてもう30年以上経ちますから、身体の70%が龍朋でできていると言っても過言ではありません。僕が好きなメニューはね……」
 「(想像を覆えす、マシンガントーク……)今日はよろしくお願いします!あ!あの壁にかかっているのは、まさに龍朋のメニューですね」
「(想像を覆えす、マシンガントーク……)今日はよろしくお願いします!あ!あの壁にかかっているのは、まさに龍朋のメニューですね」

 「硬やきそばだ!これはもしかして、龍朋の」
「硬やきそばだ!これはもしかして、龍朋の」
 「そうそう! 消費税の引き上げや物価高騰で全メニューを2回書き換えたんだけど、一番最初のやつ」
「そうそう! 消費税の引き上げや物価高騰で全メニューを2回書き換えたんだけど、一番最初のやつ」
 「そうなんですね。わあ、筆がこんなにたくさん」
「そうなんですね。わあ、筆がこんなにたくさん」

 「種類も太さもバラバラですね」
「種類も太さもバラバラですね」
 「書く道具によって文字の印象は変わるんだよね。3mもの大きな紙に、細いペンで大きな文字を書けって言われても無理があるし。どこに何を書くのかに合わせて筆記用具を選ぶことが、書く作業のはじまりです!」
「書く道具によって文字の印象は変わるんだよね。3mもの大きな紙に、細いペンで大きな文字を書けって言われても無理があるし。どこに何を書くのかに合わせて筆記用具を選ぶことが、書く作業のはじまりです!」
 「なるほど。あ、こっちには板がたくさん!」
「なるほど。あ、こっちには板がたくさん!」

 「浅草にある神輿や太鼓を作る老舗の宮本卯之助商店さんというところで、どうしても再利用できない端材をいただいてるんだ」
「浅草にある神輿や太鼓を作る老舗の宮本卯之助商店さんというところで、どうしても再利用できない端材をいただいてるんだ」
 「何のためにですか……?」
「何のためにですか……?」
 「ちょっと、こちらをご覧くださいませ」
「ちょっと、こちらをご覧くださいませ」

 「洋食ガッツ。どこかにあるお店の名前ですか? 大盛りのメニューが豊富に揃ってそうですね!」
「洋食ガッツ。どこかにあるお店の名前ですか? 大盛りのメニューが豊富に揃ってそうですね!」
 「架空のお店なんだけどね」
「架空のお店なんだけどね」
 「え、有吾さんが考えたんですか」
「え、有吾さんが考えたんですか」
 「そうそう。他にもあるよ」
「そうそう。他にもあるよ」

 「おお。架空のお店が次々と。何のためにこのようなことを……?」
「おお。架空のお店が次々と。何のためにこのようなことを……?」
 「飲食店を妄想するのが楽しくて。棄てられてしまう端材を活用しているから、一石二鳥でしょ」
「飲食店を妄想するのが楽しくて。棄てられてしまう端材を活用しているから、一石二鳥でしょ」
 「たしかに。『小料理山椒』なんて、すぐにでも通いたいほど魅力的なネーミングです」
「たしかに。『小料理山椒』なんて、すぐにでも通いたいほど魅力的なネーミングです」
 「山椒に反応するとは、冨田さんスパイス好きなの? そしたらこんなグッズもあるよ」
「山椒に反応するとは、冨田さんスパイス好きなの? そしたらこんなグッズもあるよ」

 「スパイスカレー『メニクル』。これも妄想ですか?」
「スパイスカレー『メニクル』。これも妄想ですか?」
 「そう。架空のお店のグッズを作っちゃった。ほら、スパイスって目にくるでしょ。目にくる、で、『メニクル』」
「そう。架空のお店のグッズを作っちゃった。ほら、スパイスって目にくるでしょ。目にくる、で、『メニクル』」
 「有吾さん、ダジャレも好きなんですね」
「有吾さん、ダジャレも好きなんですね」
 「よくわかったね」
「よくわかったね」

 「これはちゃんとしたお仕事。味の素冷凍食品さんが両国駅のホームで餃子を食べる『ギョーザステーション』っていうイベントをやったときに、僕が書いたんだ」
「これはちゃんとしたお仕事。味の素冷凍食品さんが両国駅のホームで餃子を食べる『ギョーザステーション』っていうイベントをやったときに、僕が書いたんだ」
 「やっぱりおいしそうな文字! 餃子が食べたくなってきた!」
「やっぱりおいしそうな文字! 餃子が食べたくなってきた!」
 「イベントの担当者が龍朋で僕の文字を見て、仕事を依頼してくれてね」
「イベントの担当者が龍朋で僕の文字を見て、仕事を依頼してくれてね」
みなさまーっ?
8月30日から始まる #ギョーザステーション 両国駅3番ホーム店
WEB予約開始日程のご案内ですっ?前期 (8/30~9/3) 分
WEB予約開始 8/23 お昼12時←今週金曜?後期 (9/4~9/9) 分
WEB予約開始 9/2 お昼12時https://t.co/HxhFsg1R1H#ギョーザステーション2019 pic.twitter.com/U4Oh5vJicf— ギョーザ【味の素冷凍食品】 (@iza_gyoza) August 21, 2019
会場である両国駅のホームに吊るされた、たくさんの提灯の字もすべて有吾さんが担当
 「わかります。本当にお腹がすいちゃう文字ですもの。有吾さん、私も上手においしく文字を書けるようになりたいです」
「わかります。本当にお腹がすいちゃう文字ですもの。有吾さん、私も上手においしく文字を書けるようになりたいです」
 「うーん、そうだねえ。あんまり上手に書こうと意識しすぎずに、楽しむのが上達への近道。むしろ『上手く書こう』とする意識を取り除くことが大事。冨田さんって野球はやる?」
「うーん、そうだねえ。あんまり上手に書こうと意識しすぎずに、楽しむのが上達への近道。むしろ『上手く書こう』とする意識を取り除くことが大事。冨田さんって野球はやる?」
 「やったことないです」
「やったことないです」
 「野球選手はボールを投げるとき、疲れてくると逆に力が抜けていい投球ができるって聞いたことがあってね。その感覚はよくわからないんだけど」
「野球選手はボールを投げるとき、疲れてくると逆に力が抜けていい投球ができるって聞いたことがあってね。その感覚はよくわからないんだけど」
 「(わからないのに、なぜたとえに……?)」
「(わからないのに、なぜたとえに……?)」
 「書も楽しんでたくさん書いて、力を入れずに文字が書けるようになると、上手く『自分の字』が書けるようになる。そういうものだと思うんだよね」
「書も楽しんでたくさん書いて、力を入れずに文字が書けるようになると、上手く『自分の字』が書けるようになる。そういうものだと思うんだよね」
 「上手に書くために、まずは上手く書こうとしないだなんて。難しい……」
「上手に書くために、まずは上手く書こうとしないだなんて。難しい……」
 「ちょっとミニワークショップをやってみようか」
「ちょっとミニワークショップをやってみようか」
書から生まれるコミュニケーションは、合コンにも使える

 「よろしくお願いします!」
「よろしくお願いします!」
 「筆を持つのはいつ以来?」
「筆を持つのはいつ以来?」
 「ちゃんと墨で書くのは小学生のとき以来かもしれません」
「ちゃんと墨で書くのは小学生のとき以来かもしれません」

 「はい、そしたら文鎮をいつもと逆側、自分のほうに置いてください」
「はい、そしたら文鎮をいつもと逆側、自分のほうに置いてください」
 「自分のほうに?」
「自分のほうに?」

 「で、自分じゃなくて相手に向けて、書く」
「で、自分じゃなくて相手に向けて、書く」

 「今日僕が朝食べた……」
「今日僕が朝食べた……」

 「おかゆだ! 健康的な朝!」
「おかゆだ! 健康的な朝!」
 「はい、次は冨田さんの番」
「はい、次は冨田さんの番」
 「ええ、そもそも朝ごはん何を食べたか思い出せません」
「ええ、そもそも朝ごはん何を食べたか思い出せません」
 「記憶力!」
「記憶力!」

 「ああ、思い出した。思い出したけど、逆向きに書くのって難しい……」
「ああ、思い出した。思い出したけど、逆向きに書くのって難しい……」

 「合ってますか? これで合ってる?」
「合ってますか? これで合ってる?」
 「僕は冨田さんが何を食べたか知らないけど、まあ怖がらないで、思い切って書いてみて!」
「僕は冨田さんが何を食べたか知らないけど、まあ怖がらないで、思い切って書いてみて!」

 「できた! おにぎり!」
「できた! おにぎり!」
 「おお! 文字の配置は不思議だけど!」
「おお! 文字の配置は不思議だけど!」

 「ぎおにり」
「ぎおにり」
 「楽しい! もっと書きたいです!」
「楽しい! もっと書きたいです!」

 「今一緒にやったようなワークショップを神楽坂だけじゃなくて、全国各地で開催しているんだ
「今一緒にやったようなワークショップを神楽坂だけじゃなくて、全国各地で開催しているんだ


有吾さんが実施するワークショップの様子
 「『上手く書こう』じゃなくて『みんなで楽しく書こう!』というのが僕のワークショップのスタイル。年齢や障がいがあるかなどで区別せず、みんな平等に楽しんでほしいと思っているんだ。書く姿勢からは人となりが見えるから、それもまた面白くて」
「『上手く書こう』じゃなくて『みんなで楽しく書こう!』というのが僕のワークショップのスタイル。年齢や障がいがあるかなどで区別せず、みんな平等に楽しんでほしいと思っているんだ。書く姿勢からは人となりが見えるから、それもまた面白くて」
 「人となり、ですか」
「人となり、ですか」
 「たとえば、冨田さんはさっき声がものすごく大きかったから、真剣になると声が大きくなる人なんだな、とか」
「たとえば、冨田さんはさっき声がものすごく大きかったから、真剣になると声が大きくなる人なんだな、とか」
 「(そんなこと思ってたんだ)」
「(そんなこと思ってたんだ)」
 「書く時間から垣間見える、その人の生き方や人生観があるんだよね。ワークショップの内容にはペアで行うものもあって、お互いに自然なコミュニケーションが生まれる。だから合コンでも使えるんじゃないかなと思っていて」
「書く時間から垣間見える、その人の生き方や人生観があるんだよね。ワークショップの内容にはペアで行うものもあって、お互いに自然なコミュニケーションが生まれる。だから合コンでも使えるんじゃないかなと思っていて」
 「書を楽しむ合コン! 斬新!」
「書を楽しむ合コン! 斬新!」
 「そうそう。『あの人が字に取り組んでる姿、とっても素敵』みたいな」
「そうそう。『あの人が字に取り組んでる姿、とっても素敵』みたいな」
 「たしかにいいかもしれませんね。ぜひ開催を検討しましょう」
「たしかにいいかもしれませんね。ぜひ開催を検討しましょう」
ラブレターの延長線上で生まれた、「書楽家」という仕事
 「それはそうと、有吾さんは昔から書が好きだったんですか?」
「それはそうと、有吾さんは昔から書が好きだったんですか?」
 「思い返すと、そうかもしれないね。黒板の字をどれだけ綺麗にノートに書き写すかにこだわったり、女子の丸文字を特訓したり。あとは、昔からラブレターを書くのが大好き。歴代の彼女全員に、ラブレターをしたためてきたなあ」
「思い返すと、そうかもしれないね。黒板の字をどれだけ綺麗にノートに書き写すかにこだわったり、女子の丸文字を特訓したり。あとは、昔からラブレターを書くのが大好き。歴代の彼女全員に、ラブレターをしたためてきたなあ」

 「ああ……なんであんなこと書いたんだろう……まだ残っちゃってるのかな……」
「ああ……なんであんなこと書いたんだろう……まだ残っちゃってるのかな……」
 「(どんな情熱的な文章を書いたんだろう)」
「(どんな情熱的な文章を書いたんだろう)」
 「おかげで、文字を気持ちに乗せるという行為を数えきれないほどやってきた。今の仕事は、ラブレターの延長線上にある気がします」
「おかげで、文字を気持ちに乗せるという行為を数えきれないほどやってきた。今の仕事は、ラブレターの延長線上にある気がします」
 「たしかに有吾さんの文字からはパッションを感じます。書を仕事にしたきっかけは、なんだったんですか?」
「たしかに有吾さんの文字からはパッションを感じます。書を仕事にしたきっかけは、なんだったんですか?」
 「僕が大学生のとき、母が道に迷っているジェニーを助けてね」
「僕が大学生のとき、母が道に迷っているジェニーを助けてね」
 「ジェニーさん」
「ジェニーさん」
 「それがきっかけでジェニーと仲良くなって、彼女がオーストラリアに住んでいたから遊びにおいでよ、という話になったんだ。あれは大学卒業間際の頃だった」
「それがきっかけでジェニーと仲良くなって、彼女がオーストラリアに住んでいたから遊びにおいでよ、という話になったんだ。あれは大学卒業間際の頃だった」
 「ほう」
「ほう」
 「行ってみたら、公園でカンガルーに首根っこを掴まれて。空は原色で気持ちがよくて、オーストラリアが気に入ってね」
「行ってみたら、公園でカンガルーに首根っこを掴まれて。空は原色で気持ちがよくて、オーストラリアが気に入ってね」
 「カンガルーのくだりは謎ですが、景観が綺麗で素敵な国のイメージはあります」
「カンガルーのくだりは謎ですが、景観が綺麗で素敵な国のイメージはあります」
 「大学を卒業して、しばらくアルバイト生活をしていたんだけど、当時のことはずっと覚えていて。25歳のとき、ワーキングホリデーでメルボルンに住むことにしたんだ」
「大学を卒業して、しばらくアルバイト生活をしていたんだけど、当時のことはずっと覚えていて。25歳のとき、ワーキングホリデーでメルボルンに住むことにしたんだ」
 「メルボルンですか」
「メルボルンですか」
 「当時お付き合いしていた人がメルボルンに留学していたのが大きな理由なんだけど」
「当時お付き合いしていた人がメルボルンに留学していたのが大きな理由なんだけど」

 「そこで仲良くなった日本人のタカシが、日本の力を試すイベントをやりたいって言い出して」
「そこで仲良くなった日本人のタカシが、日本の力を試すイベントをやりたいって言い出して」
 「どんなイベントだったんですか?」
「どんなイベントだったんですか?」
 「現地にいた日本人のDJを集めた音楽イベント。で、ポスターなどのデザインを僕が担当することになって、『これ、筆で書くのがいいんじゃない?』って思ったの」
「現地にいた日本人のDJを集めた音楽イベント。で、ポスターなどのデザインを僕が担当することになって、『これ、筆で書くのがいいんじゃない?』って思ったの」
 「既に有吾さんは筆で文字をよく書かれていて?」
「既に有吾さんは筆で文字をよく書かれていて?」
 「ううん、全然。筆も持って行ってなかったから、両親に書道セットを送ってもらった。実際に筆で書いてみたら、突然覚醒して!そのまま勢いでメルボルンで作品展を開いて、作品が売れて、調子に乗って、今に至る」
「ううん、全然。筆も持って行ってなかったから、両親に書道セットを送ってもらった。実際に筆で書いてみたら、突然覚醒して!そのまま勢いでメルボルンで作品展を開いて、作品が売れて、調子に乗って、今に至る」
 「ジェニーと出会って、タカシさんと出会って、すさまじい勢いで今があるんですね」
「ジェニーと出会って、タカシさんと出会って、すさまじい勢いで今があるんですね」
 「そうなの。僕は誰かに師事して書の道を歩いているわけではないんだ。だから、『書道家』ではなくて『書楽家』と名乗っています。音を楽しむ『音楽』みたいに、ただ書を楽しむ『書楽』として活動していけたらなって」
「そうなの。僕は誰かに師事して書の道を歩いているわけではないんだ。だから、『書道家』ではなくて『書楽家』と名乗っています。音を楽しむ『音楽』みたいに、ただ書を楽しむ『書楽』として活動していけたらなって」
 「素敵な考え方ですね」
「素敵な考え方ですね」

 「これは先日開催した個展で作った『楽ちゃん』。針金に粘土を貼り付けて制作したんだ」
「これは先日開催した個展で作った『楽ちゃん』。針金に粘土を貼り付けて制作したんだ」
 「文字を立体にしたんですね。丸っこくてかわいい!」
「文字を立体にしたんですね。丸っこくてかわいい!」
 「自分が生まれ育った神楽坂の街に、いつかパブリックアートとして大きな『楽ちゃん』を作りたいと思っているんだ。子どもたちがぶら下がって遊ぶことができるし、立体だから目が見えなくても触って文字を楽しむこともできる。そんな光景を見てみたくて」
「自分が生まれ育った神楽坂の街に、いつかパブリックアートとして大きな『楽ちゃん』を作りたいと思っているんだ。子どもたちがぶら下がって遊ぶことができるし、立体だから目が見えなくても触って文字を楽しむこともできる。そんな光景を見てみたくて」
 「まるで公園の遊具みたい。私も触って、遊んでみたいです!」
「まるで公園の遊具みたい。私も触って、遊んでみたいです!」

 「ところで有吾さん。私、お腹がすきすぎて、お腹痛くなってきちゃいました。朝からおにぎり一個しか食べてなくて……」
「ところで有吾さん。私、お腹がすきすぎて、お腹痛くなってきちゃいました。朝からおにぎり一個しか食べてなくて……」
 「せっかくだから、“あの場所”へ行きましょうか」
「せっかくだから、“あの場所”へ行きましょうか」
有吾さんと龍朋、今は亡きマスターへの思い

 「さて、今日は何を食べましょうかね。ラーメンに、チャーハン、回鍋肉も食べたいし……」
「さて、今日は何を食べましょうかね。ラーメンに、チャーハン、回鍋肉も食べたいし……」
 「よく食べるね」
「よく食べるね」

 「わあ、もう15時だけど、今日も賑わってますね」
「わあ、もう15時だけど、今日も賑わってますね」
 「神楽坂で昼から夜まで通し営業している店は少ないしね」
「神楽坂で昼から夜まで通し営業している店は少ないしね」
 「あ、ちょうど席が空きましたね。さあさあ入りましょう」
「あ、ちょうど席が空きましたね。さあさあ入りましょう」

 「有吾さんが書いたメニューがずらっと並んでいるから、龍朋で作品展を年中開催しているともいえますよね」
「有吾さんが書いたメニューがずらっと並んでいるから、龍朋で作品展を年中開催しているともいえますよね」
 「そうだね。龍朋で僕の字を見た人が、仕事の依頼をくれることはよくあるよ」
「そうだね。龍朋で僕の字を見た人が、仕事の依頼をくれることはよくあるよ」

 「最初にここを訪れたのは僕が19歳で、まだ何者でもなかったとき。祖父母と一緒にやきそばを食べたことを覚えている。あの頃はメニューを書くのを任せてもらえるなんて、思いもしなかったなあ」
「最初にここを訪れたのは僕が19歳で、まだ何者でもなかったとき。祖父母と一緒にやきそばを食べたことを覚えている。あの頃はメニューを書くのを任せてもらえるなんて、思いもしなかったなあ」
 「そもそも、どうしてメニューを書くことに?」
「そもそも、どうしてメニューを書くことに?」
 「もう亡くなってしまったマスターが、依頼してくれたんだよ。長年通っていて大好きなお店のメニューを書けるなんて、本当に嬉しかった。今の僕があるのはマスターのおかげだから」
「もう亡くなってしまったマスターが、依頼してくれたんだよ。長年通っていて大好きなお店のメニューを書けるなんて、本当に嬉しかった。今の僕があるのはマスターのおかげだから」

2010年8月17日投稿の有吾さんのブログより。「夢がひとつ叶いました」と喜ぶ有吾さんとマスター
 「マスターはどんな方だったんですか?」
「マスターはどんな方だったんですか?」
 「情に厚くて、本当に素敵な人だった。僕は店の近所に住んでいたから、よく夜中に店をのぞきに行ってね。スープを仕込んでいる合間のマスターが席で新聞を読んでて、『おお有吾、飯食ったか?』って声をかけてくれて」
「情に厚くて、本当に素敵な人だった。僕は店の近所に住んでいたから、よく夜中に店をのぞきに行ってね。スープを仕込んでいる合間のマスターが席で新聞を読んでて、『おお有吾、飯食ったか?』って声をかけてくれて」
 「ふたりだけで過ごす、静かな時間があったんですね。何か作ってもらっていたんですか?」
「ふたりだけで過ごす、静かな時間があったんですね。何か作ってもらっていたんですか?」
 「春キャベツとコンビーフの炒め物をよく作ってくれたなあ。トマトたまごめんと生姜ラーメンは、二人で考案したメニューなんだよ」
「春キャベツとコンビーフの炒め物をよく作ってくれたなあ。トマトたまごめんと生姜ラーメンは、二人で考案したメニューなんだよ」
 「亡くなられたのは、寂しいですね」
「亡くなられたのは、寂しいですね」
 「もちろんそうだけど、亡くなった人は眠り続けているだけだと思っていてね。きっと、マスターは今もずっと楽しい夢を見ていて、それは悲しいことではない。だから僕は目が覚めている間は、この世界をとにかく楽しみたいんだ」
「もちろんそうだけど、亡くなった人は眠り続けているだけだと思っていてね。きっと、マスターは今もずっと楽しい夢を見ていて、それは悲しいことではない。だから僕は目が覚めている間は、この世界をとにかく楽しみたいんだ」

ダンスカンパニー「コンドルズ」でダンサーとしても活動している有吾さん。主宰する近藤良平さんと龍朋でたまたま会ったことが、所属するきっかけになったのだそう。
 「さあ、まずは楽しく食べよう!」
「さあ、まずは楽しく食べよう!」
 「はい!」
「はい!」

 「さっそくチャーハン! いただきます!」
「さっそくチャーハン! いただきます!」
 「僕はマスターと一緒に考案した、トマトたまごめんを食べるよ」
「僕はマスターと一緒に考案した、トマトたまごめんを食べるよ」
 「私も食べたいです!」
「私も食べたいです!」

 「それにしても、有吾さんの文字ってどうしておいしそうなんですかね」
「それにしても、有吾さんの文字ってどうしておいしそうなんですかね」
 「『おいしく書くぞ』とは思っていないんだよね。わざとらしくならないように、とにかく自然体で。たとえばラーメンを書くときには、一文字一文字の良さを引き出しつつ、ラーメンを思い浮かべてただ書くだけ」
「『おいしく書くぞ』とは思っていないんだよね。わざとらしくならないように、とにかく自然体で。たとえばラーメンを書くときには、一文字一文字の良さを引き出しつつ、ラーメンを思い浮かべてただ書くだけ」

有吾さんのHPより書の作品。龍朋だけでなく、国内外問わず様々な店舗ロゴや題字をデザインする
 「もしかしたら、何百回と龍朋のラーメンを食べてるから、僕の身体から筆先へとスープが出ているのかも。だからおいしそうに見えるのかもね」
「もしかしたら、何百回と龍朋のラーメンを食べてるから、僕の身体から筆先へとスープが出ているのかも。だからおいしそうに見えるのかもね」
 「もしかしたら、もしかするかもしれませんね。私もおいしいものをたくさん食べて、おいしい文字が書けるように頑張ります!」
「もしかしたら、もしかするかもしれませんね。私もおいしいものをたくさん食べて、おいしい文字が書けるように頑張ります!」
おわりに

書にはその人が生きてきた道のりや思いが現れる。有吾さんと龍朋、そしてマスターとの思い出が、龍朋のメニューのおいしい文字を作り出していました。
おいしく楽しく、文字を書き続ける有吾さん。これからもどんな作品が、どんな思い出が、龍朋でできあがっていくのでしょう。私もおいしく楽しく、見守っていきたいと思います。