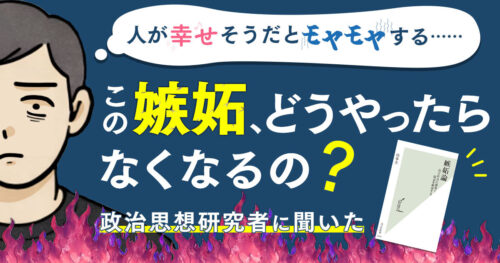『山梨なら、豊鮨行きなよ!』
食通の友人と話をすれば必ずあがる「豊鮨(とよずし)」の名。とにかくすごいと噂を聞いて、はじめて暖簾をくぐったのは2023年の秋でした。

パッと見の店構えは、古き良き「町の鮨屋」。カウンターには鮮魚が並び、奥には職人らしい大将の姿。


けれど運ばれてくる料理は、ビストロさながらの自家製ソーセージにパテ。そして餃子にエジプト塩冷奴。さらに、カウンターにずらりと並ぶのは日本酒ではなくワインのボトル。
寿司を頼みたいんだけど、寿司までなかなか辿りつかない。なんでもあって、ちゃんと全部おいしいから胃袋が足りない。その計り知れないコンテンツ量に圧倒されて店を後にしました。

一度行ったら忘れられない。そんな店を営むのは、若月武司さんと美紀さん夫婦、そして息子の大地さん。
「豊鮨」という名のこの店が、寿司以外にもこんなに力をいれるのはなぜなのか? そしてそれらがちゃんと美味しく、全国から人を集める名店たる背景には、どんな秘密があるのか。
今回は3代目の若月大地さんに、豊鮨に加わる前の料理人時代の話から、豊鮨を営む今の話まで、じっくり聞きました。

豊鮨3代目・若月大地さん
客の8割が、ボトルワインを頼む鮨屋

瀬谷「前回お邪魔したとき、メニューの多さに目移りして……餃子にソーセージにと色々頼んでいたら、結局お寿司まで辿り着かずにお腹いっぱいになりました(笑)」
大地「よく言われます(笑)。うちはワインも充実しているから、寿司以外をつまみに飲んでいく方も多いです。大体のお客さんがボトルでワインを頼みますね」
瀬谷「鮨屋でワインって珍しいですよね。これはどんな意図ですか?」
大地「意図っていうほどのものではなくて、父(武司さん)の頃からずっとなんです。山梨の地酒を扱いたいと思っていたそうなんですが、日本酒の酒蔵は少なくて、山梨では地酒といえばワインだったという。シンプルな理由です」

セレクトされた地元のワインがずらり
大地「ナチュラルワイン」っていう言葉がブームになったのも最近のことで、父はそれより前から山梨のワインを仕入れていたので、どれがナチュラルワインで……みたいなことにはこだわっていないんです。
好きな作り手さんから、良いワインを仕入れるだけ。だから今もワイナリーの名前より『○○さん(作り手の名前)のワイン』って呼んでます」
瀬谷「なるほど、地酒だからワイン。そう思うと鮨屋なのにソーセージや餃子があるのにも、何かシンプルな理由がありそうですね。そもそも大地さんはどんな経緯でここを継ぐことになったんですか?」
デザインへの興味から、食の世界に惹かれて

大地「そもそも僕は、豊鮨を継ぐつもりは全くなくて。学生時代は美大でデザインを学んでいて、インテリアが好きで、住まいや空間に関わる仕事がしたいと思っていました。
でも、卒研でたまたま友人が『おいしいってなんだろう?』というテーマで、”シズル感”についての研究をしていたんですね」
瀬谷「おもしろそう!」
大地「そのプレゼンを聞いているうちに、食っておもしろいなと思い始めて。食も家具や照明と同じ、空間をデザインする一部だと気づいたら興味が深まっていきました。
ちょうどその頃に知り合ったのが、オカズデザイン(※料理とグラフィックデザインのチーム)さん。イベントの手伝いをするようになったんですが、僕が考えていた『デザイン×食』という働き方をまさに体現していて、こんな風になりたい! と思ったんです」

大地「ちょうどオカズデザインさんがスタッフ募集をしていたので応募したんですが、残念ながらだめでした。
それでも諦めきれなくて、デザイン×食で何か働ける場所ってないだろうかと探して、見つけたのがD&DEPARTMENTの求人。飲食の経験はなかったので、まずはなんとかここに入ろうとホールスタッフとして働きはじめました」
瀬谷「こっちだ!と決めてからの推進力がすごいですね」
大地「自分の中に、ずっとデザインと食は繋がっているという漠然とした思いがあったんですが、じゃあどういうことがしたいのか、具体的にはわかっていなくて。それを見つけるために、とにかく動いていたいという気持ちでした。
その後は東京の豪徳寺にある『uneclef(ユヌクレ)』や、東京都現代美術館のレストランを経て、最終的には料理家・たかはしよしこさんのアトリエ『S/S/A/W』で長く働きました。ここで、今のベースになる色々なことを教わりましたね」

スタッフとして長く働いた「S/S/A/W」のエジプト塩やモロッコ胡椒は豊鮨でも取り扱っている
「あと1年で戻ってくるって、約束しちゃったんです」

瀬谷「豊鮨に戻ったきっかけは?」
大地「30歳くらいまではずっと東京で働くつもりでした。でも当時、30年以上豊鮨で働いていた、僕にとっても兄のような存在だったベテランの職人さんがいたんです。その人が、ある日東京へ遊びに来て。一緒に食事に行ったときに『大地はいつ山梨に帰ってくるんだ?』と聞かれたんです」
瀬谷「大地さんはなんと返事を?」
大地「もう少ししたら地元に戻ろうと思ってる、と。すると職人さんはこう言ったんです。『じゃあ、あと1年って約束しよう。俺もそれまで頑張るから』と。その時、咄嗟だったし、真剣な雰囲気にも気圧されて『わかった』って言っちゃったんです」
瀬谷「約束しちゃってますね!(笑)」

大地「はい、ほんとに。戻るって言っちゃったけどどうしよう? って妻に相談したのを覚えています(笑)。正直、最初は戻るつもりはありませんでした。東京で自分がやっていたことと、豊鮨が繋がるイメージがまるでなくて。
けれどその後、S/S/A/Wが豊鮨を会場に行ったイベントが、大きなきっかけになったんです」
瀬谷「どんなイベントだったんですか?」
大地「甲府出身のバンド『WATER WATER CAMEL』と、その親交があるお店の人たちが集まったイベントです。たかはしよしこさんをはじめ、地元の味噌屋さんや北海道のパン屋さんなど、いろんなお店が参加してくれました。
今まで酢飯しか炊いたことのなかったうちの釜で、たかはしさんがドライトマトのピラフを炊いて。さらに菓子研究家の方がオーブンで焼いたマフィンが、カウンターの上にずらりと並んで。見慣れていたはずの豊鮨が、全然違うものになっていくのを感じました」

たかはしよしこさんが豊鮨の厨房で腕を振るったイベント限定メニュー

2階の宴会場では、「WATER WATER CAMEL」のライブが開催された
瀬谷「すごい。その時、ご両親の反応はどうでしたか?」
大地「それが、楽しそうだったんですよ。最初はふたりが嫌がるんじゃないかと思っていたんですが、なんだかすごく喜んでくれて。そのことが自分の中では大きかったです。
それまでは、そもそも自分が実家に戻るなんて思ってもなかった。でも、良い形で両親とも一緒にやっていく方法もあるのかも、とそこで初めて思えたんです」
”鮨屋” という括りに縛られず、「皆のできること」を集めて

瀬谷「それが戻るきっかけに。豊鮨にお寿司だけじゃなく洋風のつまみや餃子があるのも、大地さんが加わったからですか?」
大地「いえ、それも前からです。豊鮨では昔から、お寿司以外も出していたんですよ。今は使われていませんが、厨房には元々、揚げ物用のフライヤーやうなぎを焼く焼き場もあって。
鮨屋というよりは、町の人が集う大衆酒場みたいなイメージですかね。家族で来たり、宴会をしたり、いろんなニーズに寄り添う料理を用意していました」

2代目の武司さんが握る鮨。ワインと合わせて締めに食べる客も多い
元々は僕の祖父が、魚をメインにいろんな料理が楽しめる、なんでも屋のような飲食店を始めたんです。その跡を継いだ父が浅草の寿司屋で修行を積んだことで寿司の技術も確立されて、今はその両方の要素がミックスされています」
瀬谷「豊鮨という昔ながらの屋号だけど、モダンな料理も出されているギャップがユニークだなと感じます」

母の美紀さんが作る餃子は、ファンの多いメニューのひとつ
大地「そもそも、僕も父も豊鮨を『鮨屋』だとは思っていないんですよ。父は鮨で、母は餃子で、僕は焼き物とシャルキュトリーと、シンプルにそれぞれが得意なものを作っているだけ。
料理も一見統一感がないように思えるかもしれないですが、味への自信と、ワインに合わせたいという想いは共通しているので、それが共存することに違和感はないんです。でもそれを客観的に見ると、面白いギャップに感じられるのかもしれないですね」
店を継ぐときに決めたのは「自分の個性を出さない」こと

瀬谷「豊鮨に大地さんが加わって、どんな変化が起きましたか?」
大地「戻ってきて7年になりますが、客層はガラッと変わりましたね。それまでは大衆酒場のような雰囲気で、主に地元のおじさんおばさんたちが飲みにくるような場所でした。でも、今は年齢層が一気に若返って、地元のワインやビールを楽しみに、県外から来る若いお客さんが多いです」
瀬谷「そうなんですね! 大地さんが何か仕掛けたりされたんでしょうか?」
大地「それが、特に何も。もちろん、戻ってきてから地元の同世代のお店と繋がったり、個人のSNSで豊鮨について投稿したりはしてます。でも、それくらいで。どちらかというと、『息子さんが帰ってきたんだ』と豊鮨の外側からの見え方が変化して、その連続の結果、少しずつ客層も変わったような感覚ですね。
うちの両親にしても、豊鮨としてのスタンスは何も変わってないです」
瀬谷「意外です。東京でいろんな経験を積んで、山梨に戻って、私なら『地元を変えてやるぜ!』みたいに意気込むと思うんですが(笑)。でも、大地さんはそうじゃないんですね」
大地「昔はそう思っていたこともあります。承認欲求みたいなものがあって、自分の個性をお店で発揮したいと。でも、ここにくるお客さんのためにものづくりをしようと考えたとき、自分らしさを前面に出す必要がないと気づいたんです」

友人のデザイナーさんとともに作った、豊鮨のショップカード。ポスターにして貼っている
大地「正直に言うなら、今の豊鮨で自分らしい表現ができているのは、ショップカードと瓶詰めの自家製粒マスタードだけです。どちらも、それ単体でプロダクトとして100%完結しているものですよね。
いっぽう、料理は一皿では完結しなくて、他の料理とともにテーブルに並べてはじめてひとつの表現になる。だから僕が作るものは、あくまで豊鮨の一部。そこに自我を出し切ることはできませんでした。でも、それでいいと思っています」
瀬谷「豊鮨らしさが尊重されているんですね。豊鮨自主企画のイベントなどは何かやられていないんですか?」
大地「コロナ前には、ワインの作り手さんを呼んで、色々なワインを試飲しながら話を聞く『いい流れ』というイベントを定期的に開催していました」
瀬谷「『いい流れ』! 由来が気になります」

大地「父とは休みの日によく一緒にワインを飲むんですが、最後に飲んだボトルを順に並べて『今日はいい流れだったね』って話すのがお決まりなんです」

大地「たとえば春の気持ちいい日なら、シュワっとした微発泡の白やロゼワインからはじまり、だんだんに白、赤と重厚感のあるものへ。その流れが心地いいと、満足感が高くて、いい時間を過ごせたなと思うんですね」
瀬谷「ワインの流れもあるし、その場の時間の流れもある」
大地「豊鮨に来てくれるお客さんたちにも、そんな『いい流れ』を感じてほしいと思っています。
満足感って、ただ目の前の料理がおいしかったということだけじゃなくて、そこで誰と過ごしたか、店員との距離感、店の雰囲気、いろいろなエッセンスが関わってくるものですよね。そしてワインもその大事な一部」

大地「僕はワインがそれ単体では完結しない存在だと思っていて、そこが好きなところなんです。人と分け合ったり、料理と合わせたりすることでワインの受け取り方がまるで変わるんですよね。
だからいい時間を過ごしてもらうためには、お客さんそれぞれに合ったワインや料理を提案していくことが大事。それがこの仕事の難しさですし、やりがいです」
瀬谷「大地さんの話を聞いていると、ワインや料理を選ぶことってひとつのデザインなんだと思いました。その空間や、人や、時間に寄り添うものという意味では、家具や音楽のように、空間の一部なんですね」
大地「行った事のないお店でも、ビジュアルを見れば佇まいからそのおいしさが伝わってきます。単なる『味がおいしい』だけでなく、『どんな風に時間を過ごしてもらいたいか』という店主の意図を、お皿の上やその周りから感じられるお店には足を運んでみたいと強く思います」
瀬谷「それも一種のデザインですね」
大地「たとえば料理のひと皿に関してもそうです。食材の切り方や、器やカトラリーのセレクト、店内の照明の明るさなど。
SNSの写真1枚で、その店がどんなイメージで客に時間を過ごしてもらおうと思っているのかが伝わってくる。良い店とは、そういうものだと思うんです」

大地「だから自分の店も、そうであってほしいと思います。今は豊鮨で、そのために自分がどうあればいいのかを考えていますね。
今後も豊鮨を続けるのか、自分の店を持つのかはまだわからないですが、食を通じて ”いい流れ” を作っていきたいと。それだけはこれからもずっと変わらないことですね」

ご家族での一枚。写真左が大地さんの母・美紀さん
おわりに
取材のあと、そのまま豊鮨で食事をさせてもらうことに。名物のエジプト塩をのせた冷奴からはじまり、お母さんの手作り餃子、お父さんの鮨、大地さんのシャルキュトリーと、ワインに合わせてそれぞれの料理をいただきました。

終盤、『これ、よかったら食べてみてください』と大地さんがそっと机に置いたのは、からりと揚がった手割りのじゃがいもに、にんにくとスパイスの効いたソースがかかった一皿。
満たされてきたお腹がもう一度空いてくるようなおいしさで、ますますワインが進みました。

これが「ポテトフライ」という何の変哲もなさそうな名で、鮨屋らしい品書きの隣にひっそりと書かれているところこそ、豊鮨らしさ。そして絶妙なタイミングで、想像を超えるクオリティのポテトフライを、そっと出してくれるその心遣いこそ、大地さんらしさ。
個性は出さないと話していたけれど、そこには確かに大地さんの個性が表れているように感じました。
はたからみると、一見バラバラな料理が集う店。けれどそれらがなぜかまとまっていて、店を出る頃には「いい流れ」だったなと思える店。
豊鮨が唯一無二のバランスで成り立っている理由は、それがひとつの思いの中でしっかりと”デザイン”されているからなのでしょう。
撮影:土屋誠
山梨の記事がもっと読みたいあなたへ
画像ギャラリー
この記事を書いたライター
編集者 / ライター。鎌倉でマフィンの店「doyoubi」を営み、旬の野菜や果物を使った食事のようなマフィンを焼く。マフィンにまつわるこぼれ話は、noteで更新中。