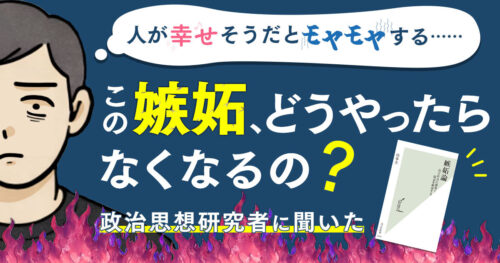東彼杵。この漢字を見て「ひがしそのぎ」とすっと読める人は、きっと近隣の方か、もしくは仲里依紗さんのファンの方くらいじゃないだろうか(東彼杵は仲里依紗さんの出身地)。
長崎県のほぼ中央、大村湾の東側に面する東彼杵町は、長崎街道の宿場町として、また鯨肉の集積・流通の中心地として栄えたという。いまでも鯨肉料理をいただける店がいくつかあるし、最近は、全国茶品評会で個人賞・産地賞の2部門で日本一に輝いた「そのぎ茶」の産地としても有名です。

ということで、こんにちは。昨夏、初めて訪れた際、案の定、東彼杵の読みがまったくわからなかったライターの藤本智士です。かれこれ20年くらい日本中を旅してもなお、読むことすらできない町があるから日本はおもしろいなあとつくづく思います。
さて、お洒落でいまっぽいお店が集積するイケてる町という印象を超えた、独特の空気を東彼杵に感じた僕は、ある人物に出会ったことでその謎がスルスルと解けていきます。その人物こそが、今回インタビューをお届けする、森 一峻さん。

地域交流拠点「Sorriso riso(ソリッソ リッソ) 千綿第三瀬戸米倉庫/くじらの髭/uminoわ」を中心に、周辺の古民家をリノベーションした店舗や拠点づくりをサポート。
日々研究所株式会社の代表として、また、一般社団法人 東彼杵ひとこともの公社の代表理事として、名実ともに東彼杵の現在をつくってきた立役者です。
 古い米倉庫をリノベーションした複合施設「Sorriso riso 千綿第三瀬戸米倉庫」。1号室には名産「そのぎ茶」のドリンクも楽しめる「Tsubame coffee」
古い米倉庫をリノベーションした複合施設「Sorriso riso 千綿第三瀬戸米倉庫」。1号室には名産「そのぎ茶」のドリンクも楽しめる「Tsubame coffee」
 2号室にあるのは、東彼杵町のお米でキンパや惣菜等を販売するOSOTOYA米饋室(コメディールーム)
2号室にあるのは、東彼杵町のお米でキンパや惣菜等を販売するOSOTOYA米饋室(コメディールーム)
 『東彼杵ひとこともの公社』と『九州電力』との協業で生まれた「uminoわ」。コインランドリーやレストランなどが入った複合施設
『東彼杵ひとこともの公社』と『九州電力』との協業で生まれた「uminoわ」。コインランドリーやレストランなどが入った複合施設
東彼杵の町がほかの地域とどう違うのか、その差異に、地域づくりのヒントがあふれているはず。まちづくりなんて言葉で簡単に片付けることができない、属人的でリアルな思いと汗をシェアします。
話を聞いた人:森 一峻(もり・かずたか)

長崎県東彼杵町出身在住。地元東彼杵町へUターンし、現在は東彼杵町を中心に長崎県の地域のコーディネーターとして地域住民と連携した地域・文化づくりに取り組んでいる。地域交流拠点「Sorrisoriso千綿第三瀬戸米倉庫・くじらの髭・uminoわ」を中心に、周辺の古民家をリノベーションした店舗や拠点づくりをサポート。日々研究所株式会社、代表取締役・一般社団法人 東彼杵ひとこともの公社 代表理事を務める。
父の「これからはコンビニだ!」からはじまった

藤本:森さんはこの町で生まれたんですよね。
森:そうです。東彼杵町の千綿(ちわた)地区で育って。家業が、ひいじいちゃんの代から続く酒屋だったんです。
藤本:造り酒屋ではなく、小売の酒屋さん?
森:はい。もともと東彼杵は漁師町、港町なので、創業時は行商に来た魚屋さんの魚を買いつつ、お酒と、ほかにもいろいろ売っていました。じいさんの代からは完全に酒屋に。
藤本:時代や町の変化とともに、お店も変化していったんですね。
森:親父の代に、あちこちで酒屋さんが潰れていくのを見て。親父がコンビニをやりたいって言い始めたんです。
藤本:「これからはコンビニだ!」って? それはいつぐらい?
森:自分が小学2年生のときにコンビニに変わりました。
藤本:その時代にコンビニって、早くないですか? 言ってみれば田舎じゃないですか。

森:そうなんです。いまから32年前なので、かなり早かったみたいですね。まだ長崎県内にコンビニがなかったので、「コンビニ行ってみよう」って、遠くからもひとが来て。だから当時は売り上げが良かったみたいです。
藤本:コンビニっていろいろあるけど、どのコンビニだったんですか?
森:ヤマザキデイリーストアーです。でも、親父はセブンイレブンにしたかったんですって。

藤本:なのに、なんでデイリーストアーに?
森:セブンイレブンは、ドミナント戦略をとっているんです。
※ドミナント戦略……特定の地域に集中して出店する経営戦略
藤本:ここにポツンと1店舗だけあるのは、当時のセブンにはありえなかったと。
森:あとは配送の問題もあって。セブンって、ほかのチェーンと比べると比較的、保存料や合成着色料、トランス脂肪酸なんかを極力入れないことを先行してやってたんです。そのためには、近くに商品をつくる場所をつくらないといけない。
藤本:なるほど。
森:たとえば大阪から商品を届けるとなると、けっこうな量の保存料を入れないといけなくなる。それをセブンはしたくない。そうやって商品自体のおいしさにこだわっているんです。
藤本:そういう話って、森さんが大人になってからお父さんに聞いたんですか?
森:自分が8歳のときには。当時、家から15分くらいで着く佐賀県嬉野市のセブンに連れていかれて、親父が弁当とかを買って「味が違うだろ」って。
藤本:コンビニ英才教育! お父さんはなんでそういうことを知ってたんだろう。
森:親父は町の消防団とか商工会に所属していて、その研修旅行に行くのが好きで。そこで知ったって言ってました。
藤本:35年前にデイリーになってからは、ずっとそのまま?
森:自分が高校に入るときぐらいにセブンに切り替わったんです。セブンの長崎県1号店なんですよ。

藤本:お父さんの意志の強さ。
森:ただ、借金をすることになるから、両親はけんかしてました。これからの時代、生き残るためなんだって親父は言って。
藤本:いま思えばそのとおりだったのかもしれないですね。
森:そうしてなかったら経営が厳しくて、僕も東彼杵に帰ってこれなかったかもしれないです。
22歳でセブンイレブンのスーパーバイザーに

藤本:ということは大学は県外?
森:いえ、僕は高卒でセブンの本社に入ったんです。
藤本:完全にお父さんの影響じゃないですか。
森:ですね(笑)。親父の店に、セブンイレブン本部から、おもしろいひとが担当者として来ていたんですよ。よく話し相手になってくれて、かわいがってくれました。そのひとがやっていたスーパーバイザーっていう仕事もおもしろいなと思って。
※スーパーバイザー……加盟店オーナーに、売上・利益改善のアドバイスや経営カウンセリングを行う職種。セブンイレブンでは、スーパーバイザーのことをOFC(オペレーションフィールドカウンセラーの略)と呼ぶ
森:いつかは継がなきゃいけなくなるかもしれないし、このまま町に残る選択肢もなかったので、まずはいろんなものを見てみたいってところから、セブンの本社の採用面接を受けてみて。入社することができたんです。
藤本:すごい。高卒で入るのって難しそう。

森:同期が400人いるうちの350人が大卒で、50人が高卒でした。だから肩身が狭かったです(笑)。
藤本:入ってからは、まずどこに行ったんですか?
森:最初は多摩の研修センターで研修をしながら、配属先が決まるのを待って。数か月してから福岡に配属になったので、九州に戻ってきたんです。ただ、1〜2週間に1回は本社がある東京に行っていたので、行き来している感じでした。
業務内容としては、クロージングの店や、オープニングの店のお手伝い。あとはひたすら棚卸し。オーナー見習いというか、仕組みを知るための仕事ばかりでした。
藤本:そうやって現場のことをいろいろとわかっていく。
森:そうです。棚卸しをすると会計のことがわかるので。セブンのPLBS(損益計算書と賃借対照表)の仕組みとかを肌感でわかるようになっていくためですね。
藤本:親父はこういうことをしてたのか、みたいなこともわかってくるんですね。
森:そうなんです。そのあと副店長、店長として太宰府、久留米や大分県の日田で店を任されて。22歳でスーパーバイザーになったんです。最年少でなりたいと思っていたんですけど、同期に少し先を越されました(笑)。
藤本:なにかテストみたいなものがあるんですか?
森:PLBSの問題集みたいな試験を10回ぐらい受けて、平均点数が70点を超えることが第1の関門。あとは適性審査と、現役のスーパーバイザーにくっついて現場をまわって、OJTとしても簿記みたいな試験を受けました。
藤本:スーパーバイザーになってからも福岡に?
森:広島です。当時は九州ゾーンとか中国ゾーンっていうようにゾーン分けがあって、親父の店がある九州からは離れないといけなかったんです。スーパーバイザーになると、近隣店舗の売り上げとかの数字が全部わかっちゃうので、親父に伝えてしまう可能性をなくすために。
藤本:なるほど。とはいえ、お父さんの店の数字を見ればいろんなことがわかるわけですよね。正直、ご実家の経営状況はどうだったんですか?
森:数字を見なくても並んでいる商品の量とかを見れば、だいたいの売り上げがわかるので、けっこう厳しいんだなって思ってました。
藤本:長崎1号店だからやれたけど、いまのように冷静に数字を出されていたら、当時セブンはOKを出さなかったかも?
森:そう思います。
まさかの「自分でドミナント戦略」

藤本:セブンには、どれぐらいいたんですか?
森:6年ぐらいです。24歳でやめてこっちに帰ってきました。
藤本:帰ってくることにしたのはどうして?
森:親父から「体調がわるいから帰ってこれないか」って言われていたのがひとつ。もうひとつは、便利を追求していくことを是とする企業で、個性を生かすというより、組織のひとりとして頑張らなきゃいけないことに違和感が出始めたんです。
当時スーパーバイザーが4000人いたんですけど、全員が東京の社内にある同じ部屋に入って、モニターを通して会長とコミュニケーションをとるんです。
藤本:数千人規模になると、そうなるんだ。ミュージシャンのホールライブみたい。
森:ほんとに(笑)。そのあとスーパーバイザーひとり一人が、会長の言っていたことを全国に伝える役目を担うんですけど、なんだか個性を発揮しにくいなって思ってしまって。
藤本:想像するほどにすごい景色かも。
森:それで、「個性が生きる」とか「個人の営み」みたいなことを考え始めて、こっちに帰ってきたんです。
帰ってきてから、親父の店とは別に自分で新しくセブンをつくってオーナーをしたんですけど、広告用のモニターをつけてみたり、お客さんが休みやすいように休憩所をつくってみたり。いろいろしてみた結果、気持ちはわかるけれど、フランチャイズとしては困るってセブンの担当者に言われました(笑)。たしかにそうだなと。
藤本:そういう個性を出す工夫もしてみたんですね。

森:オーナーだったらもう少し自分の色を出せるかもしれない、接客とかで差をつけられるかもしれないって思ってたんです。
でも、大きなチェーンの中にいる以上は一律のパッケージでやらないといけないし、売っているものは全国どこのセブンでも一緒。これを、わざわざ地方で自分がする意味はあるんだろうか? そういうことも積み重なり始めていきました。あとそのとき、自分は20代後半で、親父はもう引退しているような状態だったんですね。
藤本:お父さんはおいくつだったんですか?
森:57歳です。だから早く引き継ぐために、自分が融資を受けて建て替えないといけない状況だったんです。
藤本:建て替えないといけない?
森:2013年に、「いまの売り上げでは2年後の契約更新ができない」って言われていて。なるべくエリアを変えずに移転先を探したんですけど、交通量とかいろんな調査をしていくとどこも条件が揃わなくて。
藤本:なるほど。
森:銀行からは、実績のない二十代に、5000万ぐらいかかる建て直し費用を貸すのは難しいって言われて。どうやったら借りられるんだろうって考えたんです。そのときに、ここ(千綿第三瀬戸米倉庫)の解体の話が出ていたので、ここを使って、周辺のエリアごと、小商いをドミナントさせたエリアに変えたらおもしろいんじゃないかって思ったんです。
藤本:すごい発想! セブンのドミナント戦略のように、町のいろんなお店が集積したらいいんじゃないかって思ったんですね。
森:うちの家業が厳しいのは、うちだけの問題なのか。でも、周りの店もどんどん潰れていくから、エリア的にどうなんだろう。そう思って、人口とか生産人口がどうなっていくのかを見ていたら、うちの店だけの問題じゃないことがわかってきた。
藤本:なるほど。
森:ということは、コンビニも潰れかけているこの町で新しくお店を出してもらうのは、高いハードルがある。だったら、テストしてもらうような場所がつくれないか、っていうことで、最初は仮店舗を出してもらうひとたちを集めていくことにしたんです。
藤本:空き店舗のある商業施設を活用するために、若いひとに何かやってもらいましょう、みたいな考え方のチャレンジショップって、いろんな地方でよく見るんです。でも、いま森さんが言っているそれは、まったく違う。
最初の設定、展望みたいなものが仮に妄想だとしても、ビジョンがあって向かっているひとと、ただ空きをどう埋めるかって言ってるひととは、こんなに違うんだって、はっきりとわかった気がしました。

いまや世代も業種も超えた幅広い人たちが集まる場所となったSorriso riso
森:たしかに、チャレンジショップとは言いたくないですね。当時は「パッチワークプロジェクト」って言っていたんですよ。寄せ集めの布をパッチワークするみたいなイメージで、町がパッチワークみたいに、それぞれの個性が生きたものがつながって、ひとつの布になる感じです。
藤本:めっちゃわかりやすい。点ではなく面をつくりたいってことですね。
森:だれかひとりがずば抜けるっていうよりは、個性ちょっと強めのひとたちが集まっている。パッチワークの布ってそういう感じじゃないですか(笑)。
藤本:どういうひとが何をやるか、コントロールしようと思ってないんですね。コントロール不可であるところの良さを感じている。
森:そもそも、みんな一律であることが嫌になってるのがスタートだから、なおさら。
パワーや熱量だけを伝えても、ひとは動かない

藤本:とはいえ、動き始めるには仲間が必要じゃないですか。そこはどうしたんですか?
森:最初に、ここで自分も何かやりたいから手伝うよって言ってくれたのが、アンティークショップGonutsの沖永。高校の同級生なんですよ。あとはTsubame Coffeeの北川と革屋のtateto(当時SOLE)の中島。彼ら東彼杵の仲間数人で、片付けをするところから始めました。

写真左からGonutsの沖永さん、森さん、tatetoの中島さん、Tsubame Coffeeの北川さん
藤本:Sorriso risoは、もともと米倉庫だったんですよね。それが必要なくなったのはどうして?
森:旧千綿村と旧彼杵町にあったJAながさき県央の支店が合併して、東そのぎ支店になったことで、千綿の施設が空いたんです。
なので、解体されることが決まっていたんですけど、そこをなんとかって言って、理事会に1年ほど通って。そしたら大山さんっていうお茶屋さんが、めちゃくちゃ力を貸してくれて、決定が覆ったんです。
藤本:とはいえ改修するには、お金もひとも必要じゃないですか。それはどうしたんですか?
森:当時お店に入るって言ってくれた仲間と、どうやってお金を掴むかを話して。とにかく、ここにひとを集めてワークショップをしたり、説明したりする機会をつくりました。自分で語ってファンを掴んでいくというか。お金もですけど、一緒にやってくれるひとを集めることが、ここの活動では一番大事だと思って。
ラッキーなことに当時の町長や県北振興局の局長も動いてくれました。改修は、ベース工事以外のところはセルフリノベーション。Gonutsの沖永がリノベーション好きなので、いろいろしてくれて。

藤本:図面を引いたり、設計ができるひともいたんですか?
森:設計施工は、里山建築の里山賢太さんっていう大工さんが、ボランティアで図面を簡易的に描いてくださったり、いろいろアドバイスをしてくれたりしました。
藤本:なんとか仲間が見つかり、無事にオープンできたのはいつですか?
森:2015年です。オープン当初は、Tsubame CoffeeとGonuts、tatetoがここに入っていました。ギュウギュウで超狭かったと思います。
藤本:そこまでこぎつけるのがすごいこと。
森:とにかく話をする順序には気をつけました。あとは、自分は消防団に入っていて、前分団長が農協の農薬散布のヘリコプター組合員をされていたんです。お互いに顔を知っているので交渉できるかもというのもありました。
藤本:もともとの町のコミュニティがうまく機能したんだ。「なんで先に俺に言わないんだ」みたいな地雷はあるあるだけど、元々の関係性をわかっているのは、その土地のひとの強みですね。
森:そうですね。あいつが言うんだったら、みたいに言ってもらえるような動きはしておかないとって思っていました。
藤本:それにしてもそういう交渉術みたいなことは、セブン時代に覚えたことなのか、自分の中にあることなのか。
森:セブンのときは若過ぎて話が通じなかったので、経営学と心理学みたいなものが混ざったものを自主的に勉強していたんです。それで、パワーとか熱量だけで言っても、ひとは動かないっていうのを知ったかもしれないですね。
藤本:若いときって熱量だけで行きがちですもんね。すごいな。地方、田舎あるあるかもしれないですけど、何をやるにしても年配のひとを相手に交渉していかなきゃいけない。ビジョンを現実のものにするためにはなんとか口説かなきゃいけない。
森:そうなんです。どんどん店がなくなっていく町に、店がいっぱいできるとどうなるんだろう。個性を出せるひとたちがいっぱい集まって、町がエリアとしておもしろくなってくれたらって想像して、ワクワクしながら伝えていました。
個と集合体のバランス
藤本:この地図は、どういう地図なんですか? 飲食店とかいろいろあるけど。

森:いま商工会で創業企業の検証みたいなことをしていて。この10年で東彼杵町は66の小商いや企業が創業しているんです。
藤本:約10年の間に、66も創業?!
森:隣町の波佐見町と川棚町は、人口が1万3000人ずつぐらいで、東彼杵町は約半分の7000人。でも創業企業の数は東彼杵町が圧倒的に多いんです。移住者もこの10年で500人ぐらいいます。
藤本:森さんが関わったところは何店舗ぐらいあるんですか?
森:それぞれ関わり方が違うので一概には言えませんが、十数店舗です。移住の方たちも50人ぐらい直接お話ししました。
藤本:関わり方にグラデーションがある。
森:移住とか引っ越しから関わっているところもあれば、家の交渉だけをしたところも。Sorriso risoの裏にある「Little Leo(リトル・レオ)」さんのように、東彼杵に縁もゆかりもない方に関しては、地域でコミュニティをつくるところからお手伝いをしました。
藤本:そこからやってるんですね。
 古民家をリノベーションした「Little Leo」
古民家をリノベーションした「Little Leo」
 本場フランスで10年に渡り料理の研鑽を積んだシェフの宮副玲長奈さんが東彼杵へ移住し、2019年にオープンした。詳細は『くじらの髭』の記事をぜひ!
本場フランスで10年に渡り料理の研鑽を積んだシェフの宮副玲長奈さんが東彼杵へ移住し、2019年にオープンした。詳細は『くじらの髭』の記事をぜひ!
森:レオさんの場合は商材がフレンチなので、いきなり始めるのは難しいから、仲間集めを先にしようってなって、古民家を改修するワークショップをしたんです。その説明会を大工さんと一緒にやったときの写真がこれですね。

藤本:へえ。
森:レオさんがなぜこの町でフレンチをやろうと思っているのか、みたいなことを語りつつ、みんなでワインを飲みながら巻き込んでいって。
藤本:仲間づくりから始めようっていう発想になったのは、ここSorriso risoがあったから?

森:ここをつくるまでの過程で、ひとを巻き込んだり、余白を生み出したりする感覚がすごく気持ちよくて。所属の欲求みたいなものが人間の芯にはあると思っているので、この店をつくるときに関わったひとたちが、所属の価値みたいなものを感じている感覚があったんです。
だからレオさんの店をつくっていく過程でも「自分もここの土壁を塗ったんだよ」みたいなことを自慢げに言う、みたいなことが起きることによって、レオさんのお店の経営が安定していくんじゃないかと。

藤本:それがひとつのモデルケースになったんですね。それにしても、どうしてこんなにうまいこといったんですかね。
森:うまいこといっているところもあれば、いろんな人間関係も起こるので悩ましいところもあります。
藤本:でも、面として俯瞰で見たときに、感慨深いものはありますよね。
森:そうですね。バランスよくやれている感じが続いているかなと思います。

森:普段から一緒に何かをやらなきゃいけない雰囲気はまったくないけど、一緒にやろうと言ったらみんな一緒にやってくれる。その感覚がちょうどいいって思ってくれているひとが多いかもしれないです。あまりにもザ・チームみたいにしちゃってたら、たぶん続いていないだろうなって思います。
藤本:その辺の微妙なつながりと、さじ加減がポイントなんですね。
森:みなさん、それぞれに飲食店としてフィーチャーされるし、自分たちも活動がフィーチャーされるので、それぞれの役割を認識してるひとたちだけが残っているし、それがちょうどいいって言ってくださります。
「くじらの髭」の編集がもたらしたもの

東彼杵の「ひと」「こと」「もの」を発信し、まちを盛り上げるプロジェクトを企画、運営するサイト『くじらの髭』。東彼杵にまつわるさまざまな取材記事やニュース、イベントレポートなど、積極的に更新している
藤本:『くじらの髭』のサイトを立ち上げようと思ったのは?
森:SNSで発信するだけだとタイムラインとしては流れていっちゃうけど、記事になるとちゃんとアーカイブされる。この違いがあることに気づいてサイトが欲しくなったんです。それで2019年から準備をして、できたのが2020年1月25日。
藤本:たまたまコロナ禍だったんですね。
森:逆にチャンスだと思って。取材先は地元だし、遠方に行けないコロナ禍だからこそ取材に行けるんじゃないかって、なおさら加速した感じです。
藤本:どんどんいろんな店がアーカイブされて、より面として見えてきますもんね。
森:そうですね。最初はライティングや編集の経験があるひともいないし、まずはSNSでやっていたことを載せるだけでもいいんじゃないか、素人だけどやってみよう。みたいな感じで始めたんです。
藤本:まず走るって大事。メディアを持ってよかったなって思いましたか?
森:そうですね。いろんなひとたちのお手伝いをするなかで、地元でも知らないことが多いなって思ってはいたんです。
たとえばコロナ禍に、これまで関わりのなかった割烹料理屋さんの相談まで入り始めたんです。それで取材に行くと、じつは京都で修業してきたとか、お母さんが防空壕で鰻のタレをずっと守ってきたとか、いろんな話が出てきて。取材でそういうことまで掘り起こせるんだな、めっちゃおもしろいなと思ったんです。リブランディングにも役立つし、編集ってすごいなって。
藤本:いいことばっかり。

森:取材って、もちろん話を聞きに行くんですけど、自分たちの話も聞いてくれるので、こいつらこんなことしようとしてるんだっていうことが伝わったのか、対応も変わってきて。
藤本:取材対象の側がこっちを知ってくれる機会にもなったんですね。
森:地域における自分たちの役割をあらためて伝えられたり、一緒にやれることが増えたりして。いまも正直、くじらの髭の記事はどうあるべきか、みたいなこともあまりないんです。自分たちが聞いて自分たちで伝える言葉だから、あまりしばりを設けたくない。
藤本:ある程度の個性や属人性みたいなところを、コントロールしないことの大事さ。
森:よく、どうやって維持してるのかって聞かれるんですけど、みんながそれぞれ自分でやっちゃってるだけ(笑)。みんなが好きでやってることだから、コントロールできないし、してないですね。
藤本:そこがいいんだな。この先も、どんなひとが来てどうなるかわからない。
森:この町での自分の役割に色が出すぎると、今度はそれぞれの色が生かせなくなってくる。パッチワークって言ってるのに、パッチワークじゃなくなってしまう。1枚の同じ色の布になってしまうのは嫌なので。自分の色が出過ぎないように意識しています。
おわりに
ローカルの取材を続けていると、ついつい老舗企業の事業継承のお話などに視線が行きがちだなあと思うことがあります。そんな僕にとって「親父のコンビニを守りたい!と、小商いのドミナント戦略を思いついた」なんて話は、斜め後ろからの球すぎてもはや避けようがなく、ストレートに胸にぶっささりました。
イオンやセブンやマックなど、大規模チェーンストアの恩恵を受けながら生きる僕たちは、そんななかでなお、地方の小さな商店との幸福な共存について考えることが大切です。森さんの話を聞いていると、そんなローカルの未来がリアルに見えてくるようでとてもワクワクしました。
読んでくださったみなさんにも、そのワクワクが伝わっているといいなと思います。
インタビュー:藤本智士(Re:S)
構成:山口はるか(Re:S)
写真:山田聖也(Instagram)
あわせて読みたい
この記事を書いたライター
有限会社りす代表。1974年生まれ。兵庫県在住。編集者。雑誌『Re:S』、フリーマガジン『のんびり』編集長を経て、WEBマガジン『なんも大学』でようやくネットメディア編集長デビュー。けどネットリテラシーなさすぎて、新人の顔でジモコロ潜入中。