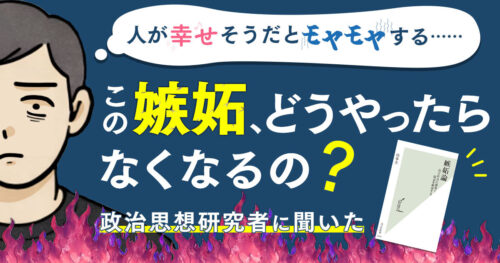こんにちは。日本を旅する編集者、藤本智士です。
ところでみなさん、本読んでますか?
なかなか読めないですよね、本。
読みたい気持ちはあるのに、仕事に追われて、せっかく買ったのにそのまま読めずにいる本が積み上がる日々。そんなときに出会ったのが青森県十和田市の『TSUNDOKU BOOKS(ツンドクブックス)』でした。

実はぼく、編集者でありながら、読書の8割は買うときに済んでるんじゃないかと本気で思っています。もちろん全文読んでもらえるのが一番うれしいんですけど、それでも本の役割の多くは、出合う瞬間にこそあるんじゃないかと。
ふらり立ち寄った書店で偶然出合った一冊。なぜかその本を読みたいと思って手に取ったときの心持ちとか、謎に高揚した自分に対して、その本が果たしてくれた役割はとても大きい。
つまりは積読上等! 全肯定の大歓迎! 積んでも積んでも罪にならない、人生詰まない。それどころか、薔薇色の人生を積み紡ぐ最高の蓄積こそが積読本の正体だ! と鼻息荒く思うわけです。

そんなぼくの目の前に、積読推奨店とも言うべき店名を掲げて現れたTSUNDOKU BOOKS。訪問してみると、その店名を超えて、「毎月1〜15日の半分だけ営業」をはじめ、目から鱗な提案と編集にあふれるお店づくりに大感動。
これはシェアしなければ! という使命にかられ、店主の長嶺李砂さんにインタビュー。ちなみに長嶺さんは、ぼくと同様、編集者でもあるのです。同業者だからこそわかる長嶺さんのクレバーさと凄みを、日本中の積読ラバーに送ります。
さあ今日も、本積んでこ!

話を聞いた人:長嶺李砂(ながみね・りさ)さん
1984年青森県十和田市生まれ。編集者。「TSUNDOKU BOOKS」店主。東京で食や暮らしを中心とした雑誌や書籍編集のキャリアを積んだのちにUターン。2024年5月、TSUNDOKU BOOKSを開業。編集者と書店主という二つの顔を持ち、さらには小さな出版社や宿の立ち上げもしながら、本と人と街をつなぐ活動を続けている。
月の半分、毎月1〜15日だけ営業する理由

藤本:ぼくが初めてTSUNDOKUさんにお邪魔したのは去年の7月だったと思うんですけど、最初に思ったのが失礼な言い方ながら「意外とちゃんとしてる」だったんです。
長嶺:わかります(笑)。わりと今、書店やりたい人いっぱいいらっしゃいますもんね。
藤本:あくまで本屋さんは副業というか、趣味的にやってると思ってて。だけど、「なんだかぼくの本めっちゃ売ってくれるぞ、なんでだ?」と。
長嶺:趣味なのかどうかって難しいですよね。実際今もよく言われるのが「本業があるしね」って言葉。わたしはそのつもりは一切なくて、いわば本業を二つやってるんですけど、見え方としては、おそらく編集業の仕事がベースにあるからいいよね、みたいな感じ。
藤本:ですよね。きっとそう言われる要因の一つが営業日だと思うんですけど。
長嶺:ですね。毎月1〜15日が営業日です。
藤本:月の半分くらいお休みっていうお店は珍しくないですけど、ふつうは曜日で分けるじゃないですか。日〜水は休みで、木〜土は開けてます。みたいな。
長嶺:そうですよね。
藤本:それが、月を半分に分けちゃった。そこが本当に発明だと思っています。
長嶺:ありがとうございます。いろんなところで書いたりしてくれてますもんね。
藤本:周りの友人に話すのはもちろん、ぼくがやっているVoicyとかnoteとか、いろんなところで「ヤバい本屋が十和田にあるぞ!」って。
長嶺:うれしいです。

藤本:年間同じだけ休むにしても、2週間のまとまった休みと、曜日ごとの細々とした休みとでは、どう考えてもまとまった休みのほうがしっかり休めますもんね。
いろんな地域の商店街とか、なんだったら役所とか企業も、前半営業と後半営業と半分づつに分けたら日本人の働き方もめちゃくちゃ変化するんじゃないか!? って本気で思ってます。どうしてこんなことを思いついたんですか?
長嶺:まずわたしの場合は、いつ開いてるかわからない店にはしたくなかったんです。そういうやり方を否定しているわけではないけれども、やっぱり商売として考えたときに、約束を守るのが一番大事なことだと思って。
藤本:それって、長嶺さんが編集者だからかもですね。不明瞭な情報の扱いづらさを知っていることと、やっぱり締め切りを守る人としか仕事できないから。いい意味で適当な人たちも多いけど、仕事をご一緒できる人って、みんな謎に締め切りはちゃんと守ってきますよね。
長嶺:そうですね。そういうのが個人的には大事だったから明確に決めたかったんです。もう一個はすっごいバカみたいなこと言いますけど、旅行に行きたかった。

藤本:いや、それバカなことじゃない! めちゃくちゃよくわかるし、なんで世間はこんな当たり前のことに気づいてないんだろうって目から鱗でした。
長嶺:あとやっぱりわたし、レシピ本を作る仕事がすごい好きなんですよ。東京から十和田に戻って来たけれど、レシピ本の仕事はやりたいので。レシピ本の仕事って、一冊の本の撮影にまとまって4、5日かかるんです。
藤本:そうでした。長嶺さんは編集者のなかでもレシピ本が専門というか、かなり特殊なジャンルの編集者さんですもんね。ちなみにぼくは編集者人生で一度しかレシピ本を作ったことがないんですけど、その段取りの大変さはわかります。
長嶺:もちろん著者さんに合わせるので、シェフの方とかだと、そのお店の定休日に合わせて何度かに分けて撮影するみたいになっちゃうんですけど、わたしを指名してくれる仕事だったり、わたしが提案した企画だったりしたら、意外とコントロールできるじゃないですか。
その文脈でいくと、お仕事を依頼いただくときに「月の後半だったらやれますよ」って言えることがすごく大事で。
藤本:なるほど! そこでちょっと計っているんだ。
長嶺:いや、なにかを試してるわけじゃないんですよ。だけど、本当にわたしにお願いしたいものだったら、後半にしてくれるはずって思ってて。もう自分はそういう仕事の選び方でいいのかなって。
藤本:なるほどなあ。TSUNDOKU BOOKSを本屋さんとして認識している街の人たちはこういう話を知らないだろうけど、「本業二つ」というのがいまの話聞いててもよくわかります。いわば笑い飯の漫才っていうか、西田さんと哲夫さんのダブルボケが均等にある感じ。
長嶺:そうそう、均等です。なので、想像つくと思うんですけど、半々なのはもちろんお店が開いてるか開いてないかだけであって。二つの仕事が同時に進んでいるってことですね。

長嶺:本屋が休みの時期にいろんな編集の仕事の打ち合わせとか取材とかを進めたりするものの、本の仕入れとか翌月の本屋の準備もやってるし、逆に本屋をやってるタイミングに、自分でまとめられるテキストを書き進めたりして。業務内容が入れ違いになりながら両方やってるのが実情です。
藤本:それでいて、自分の裁量で海外旅行にも行ける。
長嶺:そうなんです。あと、最近おもしろいのが「またTSUNDOKU始まるぞ」とか「TSUNDOKUが終わるってことは月の半分終わったか」みたいな感覚が地元の人たちに定着し始めてるらしくて。それをお客さんたちは「TSUNDOKUタイム」って呼んでる。
藤本:おもしろい! あ、そう言えばほら、以前教えてくれた売り上げの話あるじゃないですか。
長嶺:はいはい。これは意図していたものでは全くないんですけど、うちの店は1日と15日の売り上げがかなり高いんです。1日は「やっと開いた〜!」って本を求めに来てくれて、15日は「後半に読む本買っておかなきゃ〜」って来てくれる。
藤本:それ、ほんと心理としてありますよね。
長嶺:結果論なんですけどね。そういう話で言うと、2年目に入って変化したことがあって。TSUNDOKUは営業時間が15時〜21時なんですけど、最初、特に主婦の人たちから13時に開けてくれって何度も言われたんです。15時開店だと買い物行って夕飯の支度に入っていくからと。だけどここにきて、お母さんたちが20時以降に来てくれるようになってる実感がすごいあるんですよ。
藤本:夜に?

長嶺:たとえば、ちっちゃい子供を連れて15時ぐらいに来てくれてる人とかも、20時ぐらいに今度は一人で入ってきて、ビール飲んで本読んでたりとか。本当にゆっくり本を見て帰ったりとか。その流れがすごくうれしくて。
多分ですけど、ある程度やることやって「ちょっとTSUNDOKU行ってくる」って言って出てきてると思うんですよ。で、たまにパートナーに送ってきてもらってビール飲んで、電話したらまた迎えに来てくれて、みたいな人もいて。
藤本:すごくいい!
長嶺:初めのうちは全くそういう方はいなかったんです。でもお客さんはお客さんでTSUNDOKUの使い方を攻略してくれてるのが見えてきているので、やっぱりブレずに自分なりの最適解を提示し続けてきてよかったなあって。
藤本:そのことが、街の人たちにとっても新しい習慣というか、生活の一つの楽しみみたいになってるんですね。
長嶺:だとしたら、それは本当にめちゃくちゃうれしいことだなと思います。
「とにかく今は本屋だ」という感覚で、準備してきた

藤本:実は今回、ぼくはTSUNDOKUの2階に泊めてもらってるんですけど、いよいよ2階の宿の営業も始めるんですよね。
長嶺:そうなんです。「cozy」という名前で、開店当初から準備してたんですけど。っていうか、宿を先にやるつもりだったんです。最初、本屋にはこんなにお客さんが来ないだろうと思ってたので。だから割合的には、編集仕事が5だったら、本屋は1か2ぐらいで、宿を3とか4にしようみたいな。
藤本:そしたら本屋が意外に好調だった?
長嶺:そうですね。当初の事業計画的には、月に100冊売れればよくて、その分、2階の宿で収益を上げていくモデルにして、かつ、編集業でガッツリ背骨を支えるような感じだったんです。けど、今は本が400冊とか500冊とか出るようになって。
藤本:毎月? 15日間の営業で?
長嶺:そうなんです。
藤本:すごー! ちなみにオンラインはやってないですよね。
長嶺:まだやってないんですよ。準備中で。この記事が上がる頃には、最近自分たちで作った本は売ってるかもっていうぐらい。
藤本:この本ですよね。さらに始めようとしてるTSUNDOKU BOOKSの出版事業。
 ライターの朝井麻由美さんと長嶺さんによるポッドキャスト『物書きと本屋の「ほんとのこと」』から生まれた一冊。もっとも反響のあった「マウント」にまつわるポッドキャストの会話を書き起こして再編集し、書き下ろしエッセイも加えた内容
ライターの朝井麻由美さんと長嶺さんによるポッドキャスト『物書きと本屋の「ほんとのこと」』から生まれた一冊。もっとも反響のあった「マウント」にまつわるポッドキャストの会話を書き起こして再編集し、書き下ろしエッセイも加えた内容
長嶺:そうです。朝井麻由美さんとの共著で、通販してほしいっていう声がめちゃくちゃあるのに、わたしが追いついていないっていう。
藤本:ワンオペですもんね。
長嶺:そうなんです。売り時を完全に逃してる感じしかしないんですけど、つらくならないためにも、順番にやろうと思っていて。
 取材後、無事にオンライン販売も開始。購入はこちら
取材後、無事にオンライン販売も開始。購入はこちら
藤本:そこですよね。営業日も、営業時間も、一つひとつ明確にしてやっていかなきゃ、やれない。
長嶺:そんななかで、すんごいちょっとずつ、このスタイルならいけるっていうのを探ってる感じです。
時代の流れもあると思うし、ひょっとしたら、街の人が深層心理で本屋さんを望んでくれてたのかもしれないし、とにかく今は本屋だっていう感覚があって。なのでここまでは本屋にかなり比重をおいて育ててきて、ようやくわたしの中でその回し方がちょっと見えてきたかな。
藤本:街の人たちの中でも徐々に定着してきた。
長嶺:だからこそ、朝井さんとの一冊を作ってみることができたり、しばらく放置気味だった宿もちょっとずつ動かそうかなと。あの、宿としての営業許可はもう取れてるんですよ。だから、やればいいだけの話なんですけど、楽しくないとやりたくないんですよ。楽しんでやりたいんです。
藤本:そりゃあそうですよね。一人でやるわけだし。
長嶺:準備が大事というか。わたし、準備の人だと思ってて。
藤本:それはめちゃくちゃ感じます。
長嶺:編集者って多分準備しかできないじゃないですか。
藤本:特に長嶺さんが編集するレシピ本って、数多ある書籍のなかでも、もっとも準備命みたいな書籍ですもんね。

長嶺:こんなこと言っていいのかわからないんですけど、撮影のときって、わたしはほとんど何もしないんです。ただ食べて美味しいか美味しくないか、しょっぱいかしょっぱくないかとかを伝えるくらい。なんとなく本にするときにこの写真使おうかなとかは考えてるけど、実際は撮影が始まっちゃったら、わたしにやることはほぼなくて。
藤本:たしかに、そのタイミングで何かいろいろ言い出しても混乱しかなさそう。
長嶺:そうなんですよ。現場でわたしが急に、「さっきサーモンって言ってましたけど、サバに変えてもらっていいですか」みたいなことを言い出したら、もう最悪じゃないですか。この器でやろうと思ってたけど他にしようとか、そのレベルはもちろんありますけど。
やっぱり軸というかベースを準備する編集者が急にブレ出したら、チームのメンバーもどうしていいかわからなくなって走れなくなるので。だからずっと準備してきたと思います。今でも。

藤本:あ〜そこだ。やっぱり長嶺さんがレシピ本を作る人だからだ。ちなみにぼくも親父が料理人だったこともあって、料理と編集って似てると思ってるんですけど、やっぱりつながってますよね。料理って段取りじゃないですか。
長嶺:そうだと思います。
積読とは未来の自分のための準備であり、段取りである
長嶺:ちなみに、藤本さんは料理しますか?
藤本:たまにします。得意とは言えないけど、好きではある。長嶺さんは?
長嶺:わたしはもともとパティシエだったんですよ。
藤本:そうなの!? 全部つながった。そういうことかー。
長嶺:フリーの編集者になる前に出版社に3年いて、その前は4、5年ほど音楽業界でコピーを書いたりしてたんですけど、その前はパティシエで。
藤本:十和田を出たのはいくつですか?
長嶺:高校を卒業したタイミングだから18歳ですね。わたし、ケーキ屋さんになりたくて東京へ行ったんですよ。
藤本:そういえばこの街、ケーキ屋さんが多いですよね。

長嶺:そうなんです。わたし、この地域では進学校と言われる高校に行ってて、バイトとかダメなのに、好きだからどうしてもやりたくてケーキ屋さんでバイトしてて。受験生なのにクリスマスケーキとか作ってたら、まあ普通に落ちますよね。志望校は、東京都立短大っていう今はない学校だったんですけど、とにかく東京に行きたい一心でした。
藤本:なのに落ちちゃった。
長嶺:だけどわたしはもう行くことを決めてたから、親にもちゃんと言っていて。だから別にへこむとかじゃなくて、東京に行くにはどうしたらいいんだろうみたいに考えて。
調べた結果、共立女子短期大学の夜学部を見つけて、「ここに行って昼間ケーキ屋さんでバイトする!」って言って東京に行きました。だから当時は17時までずっとカフェでケーキ作って働いて、18時から授業を受けるサイクル。
藤本:そうだったんですね。
長嶺:2年目になると、大学って週3日ぐらいしか行かなくていいから、わたしはそれをぎゅっとまとめて、そしたら4日空くじゃないですか。で、1日くらいは休んだほうがいいなと思ったから、残りの3日をちっちゃい個人のケーキ屋さんにバイトで忍び込んだんですよ。
藤本:その頃からもう半々にしてる(笑)。
長嶺:そのケーキ屋で朝から夜までずっと働いてたら、お店のマダムにも可愛がっていただいて。1年終わる頃にはシェフに「お前は本当にケーキを作りたいのか」って言われて、「やりたいです」って言ったら、「じゃあ俺の元部下が始める新規オープンの店があるから、未経験だけど入れてやる」って言われて、入り込んだんですよ。
藤本:おお〜。
長嶺:それでケーキ屋に入るんですけど、朝5時30分から夜の12時まで働くので、いつも駅までの道はダッシュして。特に下っ端なので、シェフの隣で、手術の「メス!」「はい!」みたいなことやるんですけど、あれって一番難しくて。だって、それこそ先が見えてないと準備もできないし、何も出せないんです。

長嶺:だけど一生懸命くらいついて、店の冷凍庫も整理しなきゃだし、2時間ずっと冷凍庫に入ってたりしたら、生理が止まったりして。もうこれはやばいなと思って半年ぐらいでやめたんです。
藤本:パティシエはキツいって聞くけど、壮絶ですね。
長嶺:当時の先輩に、次の会社に引っ張られて入るんですけど、その会社がまたとんでもなくて、給料がもらえなくて裁判になったんです。最初は楽しくやってたんですけど、年末の11月ぐらいからお金が振り込まれなくて。
一人暮らしだったし、働いたお金で家賃を払っているのに、お金が振り込まれないからどうしようと思ってたら、「12月のクリスマス商戦に向けてケーキを作ったらお金が入るから」って当時の社長に言われたんですけど、結局入らなくて。
藤本:うわ〜、つらい。
長嶺:裁判のときに当時の社長が「そんなことは言ってない」って言ってるのを見たときに、22歳のわたしの何かが弾けて、こんな真面目にやっても理不尽な世の中なんだったら、もう好きに生きさせてもらう! って、本当に思ったんですよ。
それで、そういえば雑誌とかの仕事もしたかったなっていうのを思い出して、編集の世界に舵を切ったんです。20代はマジできつかった。

藤本:パティシエはもうやめた、って感じだったんですか?
長嶺:その後、裁判になったことをかわいそうだと思って責任を感じた先輩が、銀座・和光のレストランに入れてくれたんですよ。そこはすごく待遇が良くて。1日7時間しか働かなくていいし、シフト制だし。
それで先輩に、実は編集の仕事もしてみたいから学びに行きたいって言ったら「いいんじゃないか」って言ってくれて。和光で働いていた2、3年の間に、編集の学校も並行して通って卒業しました。
それから、いよいよ編集の道に行ってみたいって言って、みんなに頑張れって言われながら、和光を円満退社させてもらって。とはいえ、そこから出版社に入るまでいろいろあったんですけど。
藤本:やっぱり長嶺さんは、何かをやるときに、常にもう一個何かを走らせる人なんですね。
長嶺:そうかも。うん、そうですね。ビビりなんじゃないですか。
藤本:そうだと思う。よい意味で慎重というか、不安なんだと思う。

長嶺:本当に藤本さんはズバッとそう言ってくれるけど、わたし、自信がありそうに見えるらしいんですよ。だけどそれは逆だよって思うんです。
いろいろやらないと、どこに芽が出るかわからないから、それぞれいっぱい走らせているだけで、本屋と編集と宿もそう。どこがうまくいくかなんてやってみないとわからない。1個だけやるのはわたしにとってはやっぱり不安。それがダメだったらどうしようっていうことは常に頭にあります。
藤本:きっとそれはみんなそうですよね。
長嶺:そうだと思います。
藤本:実家が太いとか、そんな人は一握りもいないですもんね。大抵の人たちがどこか不安定なままに生きてる。
あらためて長嶺さんの人生を聞かせてもらって、ずっと半々で走ってるのがわかってとてもおもしろかったです。夜間の学校に行きながらパティシエの修行をするのも、パティシエしながら編集の勉強をするのも、TSUNDOKUの月の半分営業も、全部がつながってる。
長嶺:たしかにそうですね。しかもわたしは多分、半歩ずつしかずらしてきてないんですよ。やっぱり仕事において次に行けるって、ある程度その人の得意なところに仕事が来るわけじゃないですか。
わたしが出版社に入れたのも、実はわたしがパティシエだったからなんですよ。それで、料理編集部に入れてくれたんです。
いわばわたしはパティシエをやってたから編集者になれた。その後、フリーになったときも、当然出版社にいたからフリーになれるわけじゃないですか。出版社時代は料理編集しかしてないけど、料理編集という名の編集をやってきたから、違う編集が今度はその半歩ずらしでやれるっていうか。
藤本:半歩ずらしなら前に進めるって、すごくいい。

長嶺:あともう一つ、意識的にやってることがあって。それは調子がいいときに次の一手を絶対考えるっていうことなんですよ。わりとすぐ調子に乗るっていうか、ちょっと今いい感じだなみたいに思うことがあるから、そこで調子に乗ってはいけない。
いいことばかりは続かないし、調子が落ちてるときにどうしようって考えたら、つらすぎるじゃないですか。
藤本:どうしようもないですよね。一層つらい。
長嶺:だから、上がってるときに、次に調子がわるくなったときに何をするかを考える。わたしは自信があるわけではなく、できるだけ不安をなくしたいし、楽しくやりたいから、すごい考えちゃう。
藤本:それはもう、原点がパティシエだからですね。パティシエがやる本屋さんだって思ったら、いろいろ理解できる。営業日も営業時間も、宿の話も全部。すべては並行作業。段取りの編集。
長嶺:本当にそうかもしれないですね。
藤本:半々っていうのが、不安の解消という話でもあったけど、それはイコール希望ですよね。ゴールとしての料理の完成イメージとか、それを食べてもらっている風景とか、そういったワクワクのための、段取り。そう考えたら、積読こそが、いつかの自分のための半分っていうか。未来の自分の段取りや準備かもしれないですね。
長嶺:わ〜、そこに終着しますか。
藤本:TSUNDOKU BOOKSは、パティシエの長嶺さんだからこそ生み出せたお店だし、発明なんだってことがあらためてよくわかりました。
長嶺:そうか。ありがとうございます。積読全肯定です。
藤本:ですね。みんな堂々と本積んでこ!

あわせて読みたい
この記事を書いたライター
有限会社りす代表。1974年生まれ。兵庫県在住。編集者。雑誌『Re:S』、フリーマガジン『のんびり』編集長を経て、WEBマガジン『なんも大学』でようやくネットメディア編集長デビュー。けどネットリテラシーなさすぎて、新人の顔でジモコロ潜入中。