
2018年ももうすぐ終わり。1年を振り返れば、年を重ねるごとに「あっという間だったし、よく覚えてない」なんて思いがち。しかしまあ、ぱらぱらと予定表をめくり、ツイートを読み返すと、「ああしんどかったな」「この仕事つらかったな」と、ぞわぞわ蘇ってきます。きっと皆さん、今年もよく悩み、よく働きました。
こんなシーズンにぜひ推したいのが、「疲れがとれやすい」温泉へ行くこと。大人の事情で「体が軽くなる」「体力が回復する」「ストレス解消になる」などと言い切ることはできないのですが、疲れを癒やすちょっとしたコツであれば、ご紹介できるかなと思います。
本記事の筆者は、皆さんと同じように今年も悩み、働いた、温泉オタクOLのながちです。全国400超の温泉を訪れ、数年前まで旅行雑誌の編集者をしていました。ときどきこうやって記事を書いたりしています。
今回は、疲れた方におすすめしたい、温泉の楽しみ方&スポットを紹介したいと思います。
リラックス効果が見込める「ぬる湯」のすすめ
熱いお湯に浸かると「交感神経」が高まり興奮状態に、ぬるいお湯に浸かると「副交感神経」が優位になりリラックス状態に……というのは、みなさんも聞いたことがあるかもしれません。
私としては、お疲れの方にはぜひ、「ぬる湯の温泉」を目指してもらいたいなあと思います。
ほとんどの旅館・施設で温度調節が行われている中で、ぬるい源泉をそのまま湯船に流し込んでいるところは、とても貴重です。「ぬるくて入った気がしない」といった声もある中で、ぬる湯ファンの思いをくんでくれているのですから。
副交感神経を優位にするのは、37~39℃の「微温浴」ができる、体温よりちょっと高いぐらいがちょうどよいといわれています。暖かい季節であれば34~37℃の「不感温浴*2」もぜひ試してみてください。
ぬる湯は全国各地に湧いています。有名どころでいえば、大分・長湯温泉をはじめ、山梨・下部温泉、新潟・栃尾又温泉、徳島・祖谷温泉など。夏に訪れたら涼やかで永遠に浸かっていられるほど居心地がよく、冬に訪れたらだんだん体がぬくまる感覚がたまらない……といった、癖になる浴感*3がファンをとりこにしています。
約39℃の新鮮なぬる湯で心身をほぐす「川古温泉 浜屋旅館」
今回ピックアップしたいのは、群馬県にある川古温泉 浜屋旅館。みなかみにある一軒宿で、マジで文庫本を持ち込んだら3時間浸かりっぱなしでした。約39℃の源泉がかけ流されているので、冬でもぬる湯がじんわり楽しめます。


湯場は男女別の内湯、混浴の内湯、混浴露天、女性専用露天の5種類。混浴露天の解放感はすばらしく、バスタオル巻・入浴着でも入れます。新鮮な温泉よろしく、肌にはプチプチとアワがつきます。芒硝(ぼうしょう)のにおいも心地よく、まさに天国でした。

宿の周辺は手つかずの森林。車で行かないとなかなかたどり着きにくいところにあり、非日常感はかなり高いかなあと思います。旅行のお供にはぜひお気に入りの一冊を。
連泊湯治プランやお料理控えめプラン、ひとり旅専用プランもあり、宿泊プランのバリエーションが豊富なのも◎。日帰り入浴も受け付けています。草津も伊香保もいいけれど、いつもとちょっと違う群馬の名湯を味わってみてください。
■川古温泉 浜屋旅館
http://www.kawafuru.com/index.html
あつ湯とぬる湯を行き来する「なんちゃって温冷交互浴」
熱いのと冷たいのを交互に入浴することで、自律神経の調整力を高めるといわれる「温冷交互浴」。湯船と水風呂、またはサウナと水風呂の往復も、温冷交互浴のひとつです。最近では、サウナー(注:サウナを愛する人たち)の「体と心が『ととのう』」といった表現も耳にするようになりました。手軽にできますし、体がスッと軽くなる気がして、私も大好きです。
しかし「やってみたいけど、どうしても水風呂が苦手」と尻込みする人もいるでしょう。
で、推したいのが私が勝手に名付けた、温泉でできる「なんちゃって温冷交互浴」です。温冷交互浴の温度差を「サウナ(お湯)と水風呂」と極端にせず「あつ湯とぬる湯」ぐらいにしてもだいぶ気持ちいいのでは……というのが持論です。
例えば約35℃の源泉湯船と、約42℃の加温湯船を行き来するだけでもよいと思います。先述した「ぬる湯」がウリな温泉宿で体験できるかもしれません(ぬる湯湯船だけのところもあるのでご注意を)。源泉を2本持っていて、あつ・ぬるどちらも源泉かけ流しの極上パターンもあります。
私が訪れたところでいえば、大分・ラムネ温泉館、鹿児島・霧島湯之谷山荘、山梨・岩下温泉旅館、青森・谷地温泉……などが挙げられます。それぞれ温度も状態も異なりますが、「あつ・ぬる」を行き来できるのは同じです。
ただし温冷交互浴は、体に負担がかかるのも事実。動脈硬化症や心臓病の人は避けた方がいいと言われていますので、十分注意してください。
2つの湯口から源泉が注がれる 「旅館 深雪温泉」
ピックアップしたいのが、山梨県・石和温泉郷にある旅館 深雪温泉。約36℃の源泉と、約50℃の源泉がそれぞれ2つの湯口から注がれている、変わった湯船が推しポイントです。

ぬるい湯口に近づけばぬるく、熱い湯口に近づけば熱く。ひとつの湯船でそんな楽しみ方ができるのは、まさに「なんちゃって温冷交互浴」。ものすごく気持ちいいです。

そして深雪温泉の魅力は何といっても湯量です。貸切風呂(内湯&露天)、男女別大浴場の内湯、露天がありますが、どれも全て源泉かけ流し。どこもかしこも新鮮。
温泉は少しだけ茶色~緑色がついていて、茶色い湯の花がふわふわ舞っています。肌触りはつるつるきゅっきゅ。硫黄のにおいもして、ぬる湯の近くにいけばアワもついちゃう。

ひとり旅はもちろん、カップル・夫婦、ファミリー、グループ旅にもおすすめできる万能な旅館です。東京から電車でサラッと行けちゃう距離感なのもすばらしい。
つま先から頭のてっぺんまで疲れているなら、リトリートできる宿へ
「今年の疲れは、今年のうちに」なんてのん気なことを言っていられないくらい疲労が溜まっている方には、チェックインからチェックアウトまで全力で癒やしてくれる宿がよいかな、と思います。
キーワードは“リトリート”。「日常生活から離れ、自分を取り戻す」といった意味合いで使われ、新鮮な地産野菜を中心にした食事や森林浴、ヨガといった心身ともにリフレッシュできるプランを提供するリトリート宿が注目され始めています。
リトリート宿は検索すればいくつか出てくるので、ぜひ見比べてみてください。ファミリー、グループ旅というよりかは、ひとりでしっぽり行くのがよさそう。リトリートとうたっていなくても、新しめの湯治宿だと、菜食玄米な料理を出すところが多々あります。
アクセスもしやすくふらり旅にも◎ 「養生館はるのひかり」
私が先日訪れてめちゃくちゃ良かったリトリート宿は、神奈川・箱根にある養生館はるのひかり。

その名の通り養生がコンセプトで、地産で100%無農薬の玄米や野菜を使った“養生食”が推しポイントです。夕食のカロリーは500kcal未満。噛めば噛むほど玄米は甘く、野菜はジューシー。自家製の果実酒も瑞々しく香り豊かで、どれもこれもごちそうでした。

温泉はといえば、つるつるの硫酸塩泉が源泉かけ流し。空気清浄機完備の客室には、だらだら文庫本を読みたくなるロッキングチェアも。食も湯も、大満足の滞在となりました。


箱根湯本駅から乗り合いバスで5分ほどで到着するアクセスの良さも◎。東京からふらっと行ける天国のような宿です。12歳未満のお子さまは宿泊できないので、ぜひ大人の自分をじっくり癒やすひとときにしてください。
■養生館はるのひかり
https://harunohikari.com/
おうちのお風呂じゃ味わえない、温泉ならではのこと

そもそも温泉って、どうして疲れがとれたような気がするのでしょう。さまざまな作用があるとされていますが、最後にちょっとだけ補足させてください。
温泉の効果は、大きく分けて「薬理効果(作用)」と「転地効果(作用)」の2つがあると考えています。薬理効果とは、温泉成分を皮ふから吸収することで得られる効果で、泉質によって異なります。
脱衣所で見かける表示に注目
脱衣所によく掲示されている以下のような文字列は「一般的適応症」と呼ばれるもの。泉質問わず共通して効果が期待できるものとして環境省が定めています。極端に言えば、これらは「おうちのお風呂でも得やすい効果」と考えてよいのだそう。
筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進
そして泉質ごとの適応症は「泉質別適応症」と呼ばれます。例えば、「不眠症」「きりきず」「皮ふ乾燥症」などは、指定された泉質特有の効果が期待できるもの。一般的適応症と同じく、環境省が科学的見地に基づいて定めています。脱衣所の掲示物では“健康増進”の後ろに書かれていることが多いので、チェックしてみてください*4。
温泉で過ごす体験自体が癒やしになる
転地効果は、「日常から離れて遠い場所に身を置くことで、心身が刺激されてリラックスできる」と言われているもの。
温泉に行ったときのことを、思い返してみてください。
家を空け、日常から離れ山奥や海辺の温泉地へ行き、鼻を硫黄や芒硝のにおいでくすぐられながら、夕方前にはチェックイン、地元の茶菓子で一息ついて、大きな湯船にざぶんと体をうずめ、肌をすべる温泉に包まれ、温泉成分で変色した床や湯船を眺め、たっぷり体を温めたら浴衣に着替え、温泉のにおいがうつった襟や衣紋を心地よく思いつつ、ふかふかお布団にダイブ……!

控えめに言って、最ッッ高じゃないですか。温泉は、湯に浸かる前の体験も、浴衣に着替えて客室に戻った後の体験も、全てが疲れを忘れさせてくれます。
薬理効果は温泉オタク的に見逃せないポイントではありますが、転地効果で"旅そのもの"を楽しんでもらえたら、それだけで十分では……と思うのです。
今年の疲れは、今年のうちに。今回紹介したポイントを参考に、温泉を選んでみてはいかがでしょうか。心地よい温泉旅行になりますように。
※記事内の情報は執筆時点(2018年12月)のものです
著者:ながち(id:takachilog)
 全国各地の温泉を取材した経験を持つ、IT企業の会社員。旅行情報誌「関東・東北じゃらん」の元編集。現在25歳、これまでに入った温泉は約400。好きな言葉は「足元湧出」。女性誌「GINZA」で温泉コラムを連載中。
全国各地の温泉を取材した経験を持つ、IT企業の会社員。旅行情報誌「関東・東北じゃらん」の元編集。現在25歳、これまでに入った温泉は約400。好きな言葉は「足元湧出」。女性誌「GINZA」で温泉コラムを連載中。
Blog:いつか住みたい三軒茶屋
Twitter:@onsen_nagachi
Instagram:@onsen.ikitai



 趣味/仕事で文章を書いている20代。フリーランスのライター・編集者として、主にネットでしこしこと文章を書いたり削ったりしています。酒、亀、ポルノグラフィティ、現代文学・短歌などが好きです。
趣味/仕事で文章を書いている20代。フリーランスのライター・編集者として、主にネットでしこしこと文章を書いたり削ったりしています。酒、亀、ポルノグラフィティ、現代文学・短歌などが好きです。












 普段は会社員をしている漫画家。お菓子、コスメ、珍スポなどの気になるもののレビュー漫画を描いたり 包み隠さない感じのコミックエッセイを描いたりします。「コミックDAYS」にて『
普段は会社員をしている漫画家。お菓子、コスメ、珍スポなどの気になるもののレビュー漫画を描いたり 包み隠さない感じのコミックエッセイを描いたりします。「コミックDAYS」にて『





 女子マンガ研究家。1977年生まれ。「マツコの知らない世界」に出演するなど、テレビ、雑誌、ウェブなどで少女/女子マンガを紹介。自宅の6畳間にはIKEAで購入した本棚14棹が所狭しと並び、その8割が少女マンガで埋め尽くされている。
女子マンガ研究家。1977年生まれ。「マツコの知らない世界」に出演するなど、テレビ、雑誌、ウェブなどで少女/女子マンガを紹介。自宅の6畳間にはIKEAで購入した本棚14棹が所狭しと並び、その8割が少女マンガで埋め尽くされている。



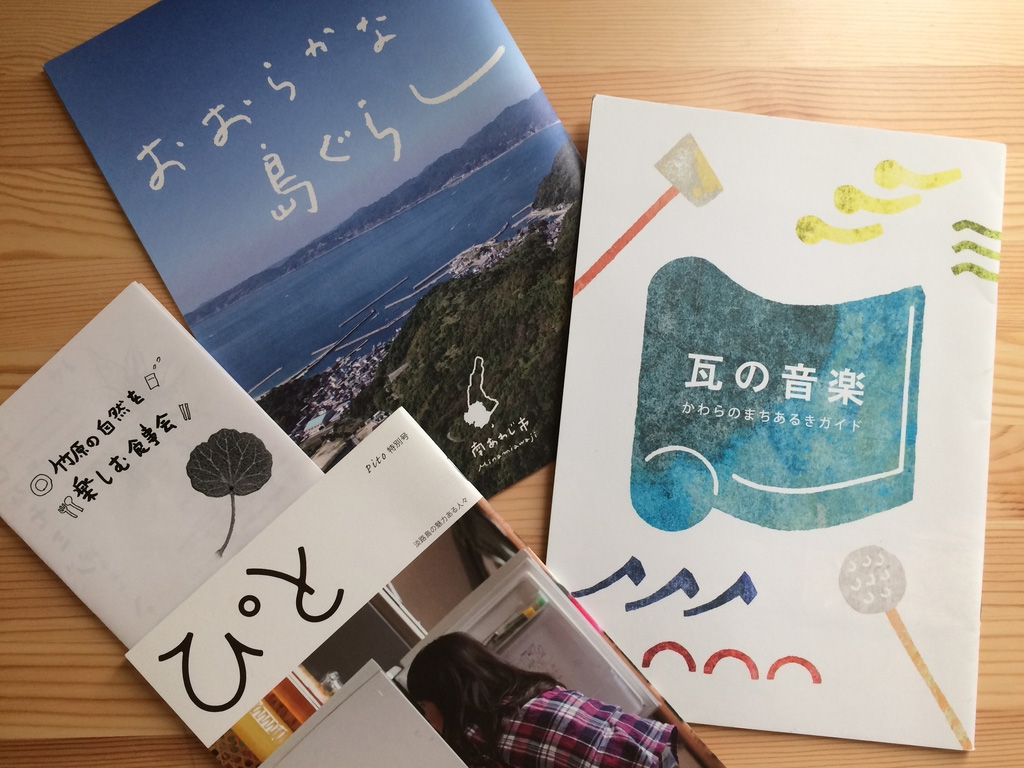

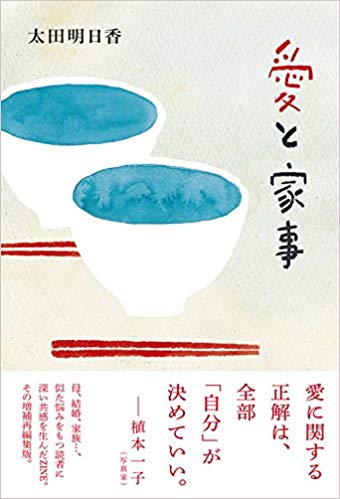 編集、校正、執筆。著書に『愛と家事』(創元社)、『福祉施設発! こんなにかわいい雑貨本』(西日本出版社、伊藤幸子と共著)。連載に『仕事文脈』「35歳からのハローワーク」(タバブックス)。
編集、校正、執筆。著書に『愛と家事』(創元社)、『福祉施設発! こんなにかわいい雑貨本』(西日本出版社、伊藤幸子と共著)。連載に『仕事文脈』「35歳からのハローワーク」(タバブックス)。











 お気持ちが高まった時に更新されるブログ『エモの名は』を書いている外資系激務OL。オシャレとズボラの狭間に生息し、ストレスを課金で潰すことに余念がない。趣味はNetflix、映画、ワイン、豚を塩漬けにすること。目標はゆとりのある生活(物理)
お気持ちが高まった時に更新されるブログ『エモの名は』を書いている外資系激務OL。オシャレとズボラの狭間に生息し、ストレスを課金で潰すことに余念がない。趣味はNetflix、映画、ワイン、豚を塩漬けにすること。目標はゆとりのある生活(物理)

 ライター/早稲田大学助教。書籍・マンガのレビューを中心としつつ、フードカルチャーやファッションなど、頼まれればなんでも書くライター。著書に『パンケーキ・ノート』(リトルモア)、『大学1年生の歩き方』(清田隆之との共著、左右社)、『40歳までにオシャレになりたい!』(扶桑社)などがある。大学では少女マンガ研究者としてサブカルチャー関連講義を担当。夫は「SCOOBIE DO」のドラマー、オカモト”MOBY”タクヤ。
ライター/早稲田大学助教。書籍・マンガのレビューを中心としつつ、フードカルチャーやファッションなど、頼まれればなんでも書くライター。著書に『パンケーキ・ノート』(リトルモア)、『大学1年生の歩き方』(清田隆之との共著、左右社)、『40歳までにオシャレになりたい!』(扶桑社)などがある。大学では少女マンガ研究者としてサブカルチャー関連講義を担当。夫は「SCOOBIE DO」のドラマー、オカモト”MOBY”タクヤ。

