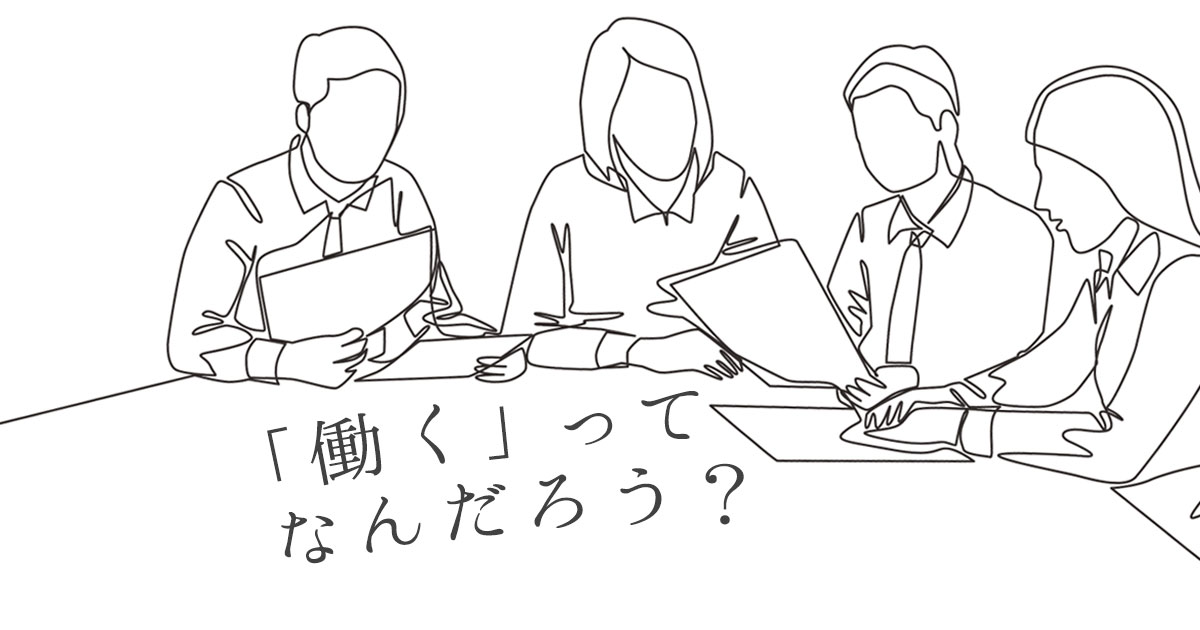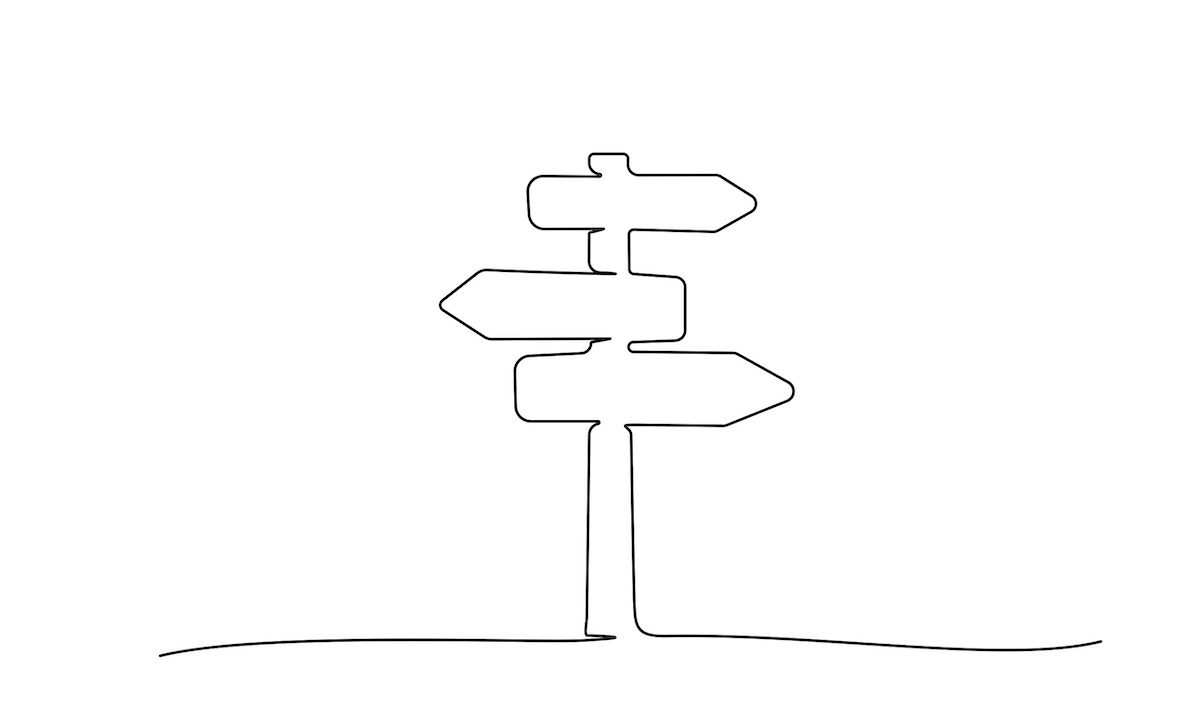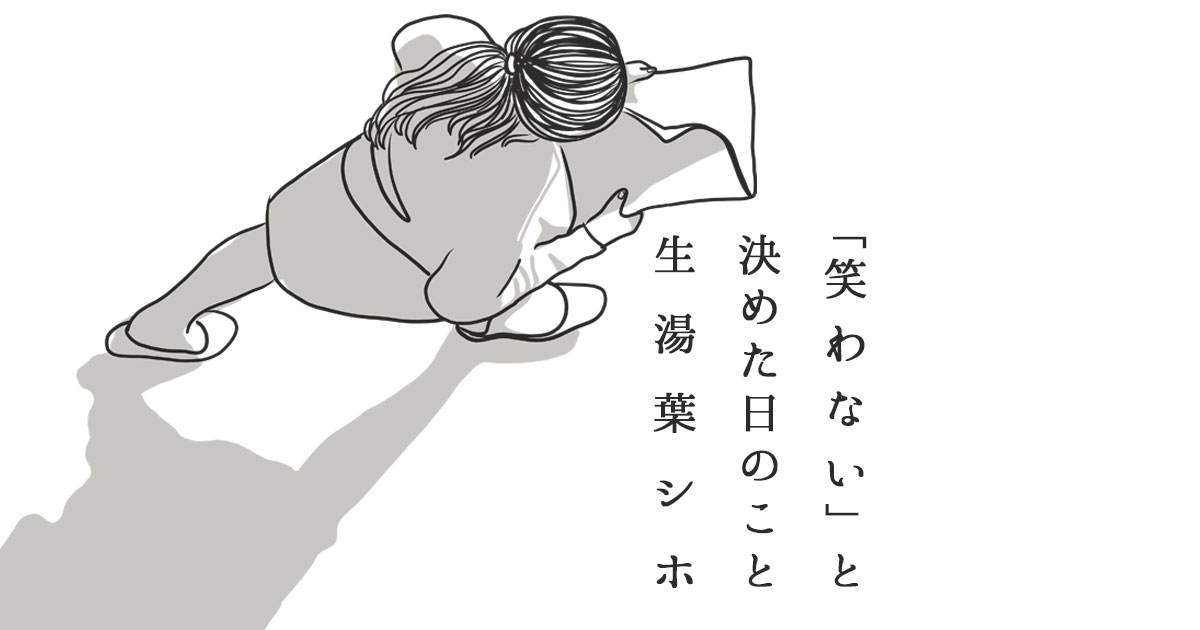忙しさに追われ毎日を過ごしていると、ふと「私はなんのために頑張っているんだろう?」と思ってしまうことがあります。「このままでいいのだろうか」という漠然とした焦りや不安は、多くの方に覚えがある感情なのではないでしょうか。
写真家・コラムニストの古性のちさんも、そんな苦しさを抱えてきたひとりです。幼い頃から集団生活になじめず、「組織に属さないで個として生きていく」を目指してさまざまな職を経験してきた古性さん。しかし、晴れて独立を果たしても言いようのない不安や焦りは消えず……。そんなときに出会ったあるワークショップが、働き方や生き方の道標になったといいます。
人生を見つめ直し、自分が何を欲しているのかに気付くきっかけとなった古性さんの体験を書いていただきました。
私は今、岡山の港町と東京の、それぞれの場所に拠点を構えながら生活している。
五感を思いきり開いて創作をしたくなったら海の側の岡山の家へ。
今はやりのものに触れたり、誰かと会いたくなったら東京へ。
滞在の割合基準は毎月なんとなく半分ずつを目安にしているけど、それも、自分の心が今どちらを心地良いと感じるかに合わせて変えている。
そんな私の生活を「なんだか漫画のようですね」と面白がってくれる人もいれば「それって将来家庭を持ちたくなったらどうするんですか?」と自分ごとのように心配そうにしてくれる人もいる。「今は良いけれど、老後のためにお金は貯めておいた方がいいですよ」と真剣にアドバイスをくださる方もいる。
私はそれらの言葉を真摯に受け止めつつも、心の真ん中とは違う場所にそっと置いておくようにしている。もちろんありがたいし、きっといつか、自然とぶつからなければいけなくなる問題もあるだろう。
でも今一番大事なのは、この瞬間「私が私の人生に納得感を持っていて、満足しているのか」なのだと思う。
今世は有限だ。私が私としてこの世界に存在できる時間は、自分が思っているよりもたぶんずっと短い。そう考えると、他人の物差しを自分の人生にあてがって、比べたり、悩んだりうらやましがっている暇は、正直ない。
「今の自分の働き方や人生に満足しているか」と聞かれたら、まだまだ控えめだけれど、YESと答えられると思う。
だけれどそんな私もほんの数年前まで、謎の焦りと、名前の付けられない不安の間で戦って、悩んで、揺らぎながら毎日を送っていた。
「何者かにならなければ、上手に呼吸できる日はこない」と思っていた幼少期

小さな頃から、それはそれは面倒くさい子どもだった、と思う。
私が私の親だったら、日々頭を抱えていただろう。
毎日過呼吸になるほど泣きわめきながら乗せられる幼稚園バスは、私にとって地獄行きの乗り物だった。到着してしまえば諦めがつくものの、みんなで歌を歌ったり折り紙を折ったりする時間は退屈で、何故こんな小さな所に閉じ込められ、自由に外にも行けず、決められた枠組みの中で過ごさなければいけないのかが分からなかった。
小学校に上がり、幼稚園時代から感じていた居心地の悪さはさらにエスカレートする。
理由がはっきりしない沢山のルールを押し付けられることが増え、なんのために覚えるのかも分からない授業にもひたすら気持ち悪さを感じて、「何でこれをやらなきゃいけないんですか?」と疑問を解決するべく先生に質問するたび、私に返ってくるのは欲しい答えではなく「困った問題児」や「先生に反抗ばかりする子」という名前のラベルばかりだった。
ひとつひとつ丁寧に理由を知り進んでいきたい私にとって、集団生活というシステムが根本的に肌に合わなかったのだと思う。学校が楽しい、と笑う友人たちはうらやましいほどにみんな眩しくて、いつもいつも泣きそうだった。
あの頃の記憶は、今も頭の隅っこの方で、ざらざらとした感触を残している。
早く大人になりたかった。
だけれど、年齢を重ねるにつれ理解したのは、結局大人になり多くの人が所属する「会社」という場所は学校生活の延長線上にある、ということ。この学校という場所は、他人と折り合いをつけながら一緒に生きていく、いわゆる社会性を身につける訓練をする場所だったことに気づいた時には絶望した。
ならば、そこからのはみ出し者はどうすれば良いのか。
単位ギリギリでなんとか卒業を迎えた高校生の私がたどり着いた答えは、「特別な何者かになって、会社ではなく個として生きていける力を持つこと」だった。
そこにしか自分の生きる道はないと思ったし、このシステムから外れることができれば、この気持ちの悪い生きづらさや不安からさよならできると思った。
そんな思いを持って私が卒業後に最初に選んだ職は美容師。「はさみ1本あれば世界中、好きなところで生きていけるに違いない」と思って選んだ職だ。
20代前半から中盤は、私はさらに「自分が心から好き、と感じる職で特別な何者かになれること」を求め転職を繰り返す。美容師から始まり、Webデザイナー・ライター・フォトグラファーと興味のありそうな職はがむしゃらに、片っぱしから試した。
その後、念願だった「組織に所属せず一人で生きていく状態」が叶ったのは20代半ば。「ライター兼デザイナー兼フォトグラファー」というまるでキメラのようになった肩書きで、フリーランスとして独立を果たした。
あの時の安堵感は忘れられない。幼少期から感じていた気持ち悪さとおさらばした後の自分の人生を考えると、興奮で眠れないほどだった。
ここまでくれば私は大丈夫。念願だった形で「何者か」になり、一番のネックだった組織からも開放され、もう何も怖くないと思った。

だからこそ、1年たっても言いようのない不安や焦りにいつも追いかけられていることを、初めは目をつぶって、見ないふりをしていた。
「何者かになる」という夢を叶えたのに、自分の人生に自信が持てない。 結婚をし子どもがいる同じ年の友人、ゆっくりと自分のキャリアを積み上げる人、新たな挑戦を胸に世界へ飛び出していく人、全ての他人が必要以上に眩しく見え、焦り、不安になる。うらやましくて、そわそわする。
もっとお金を稼がねば。もっと仕事をしなければ。良い恋愛をして、結婚しなければ。他人に素敵だと思われなければ。
じっとりした名前の付けられない感情は、ゆるやかに日々の私の精神を蝕んでいき、思い描いていた「何者かになった先の姿」とは程遠い精神状態で、だけれど涼しい顔を作りながら毎日暮らしていた。
自分の欲求を知るために「理想の一日」を書き出して気付いたこと
そんな日々を送りながら「まあでもみんな何かを抱えて、我慢しながら生きているんだから」と聞き分けの良い大人のふりをして生きていた頃、「朝起きてから夜寝るまでの理想の一日を考えてみよう」というワークショップと出会った。
内容は「ノートを開き、自分が思う理想の一日を朝から夜まで書いてみる」というとてもシンプルなもの。講師は心理学を専門に学んでいる女性で、「言葉にできない焦りや不安に、名前をつけるきっかけを作りましょう」と添えられていた募集文がその時の私の心にとても響いた。
対面式のワークショップで、当日集まったのは年齢も性別もバラバラの6人。
各々、黙々と自分の理想の一日を書き出していく。
形式はなんでも良かったので、パソコンを開き、物語調にカタカタと打ち込んでいく。自分はどんな朝を迎えたいのか、どんなふうに眠りたいのか。何をしている時が幸せなのか。「どんな状態が幸せだと感じるのか」を言語化する行為は、心がゆっくりと凪いでいくとても不思議な感覚だった。
静かになっていく心と一緒に、その時私の頭の中でコトンと、確かに何かの音がした気がした。
あの、じっとりした名前の付けられない感情は「自分の本当に欲している人生が分からないことへの不安や焦り」だったのだ。
頭の中で聴こえた音はたぶん、ずっと正体不明だった感情にやっと名前がついた音だった。
「何者か」になって組織から解放されることだけを目指し、そのあとはただ漠然と「幸せになりたい」と願いながら、先の見えない真っ暗な道を手探りで走っていたのだ。
どう考えたってそんなの、不安にしかならない。上手に走れないし、なんなら暗闇の中でぽっとたまたま現れた光に「これだ!」と思って無条件に飛びついてしまうかもしれない。
目指すものを見失わないために「最高の一日」を考える
家に帰り、ノートを開いて読み返しているうちに、もっと事細かに書いてみたら、具体的な理想の人生が見えてくるのでは、と思い立った。
そこで、この「理想の一日をノートに書く」に、自分ルールを加えてみることにした。
まずは、とにかく細部まで書くこと。
例えば「朝早く起きる」ではなく、どこで・どうやって・何時に起きるのか。家は海沿いなのか、山沿いなのか。はたまた持ち家なのか、賃貸なのか。隣にいるのは夫なのか、猫なのか、それとも一人なのか。それらを、頭をフル回転しながら書く。
書き終わったら、今度は現在の生活と理想の生活にそれぞれ分けて箇条書きにしていく。最後に、現在の生活を理想に近づけていくにはどうすれば良いかのアイディアを書き出していく。
机の上にはお気に入りの珈琲とお菓子と、耳にはお気に入りの音楽を引き連れて、疲れたら適度に休憩を挟みながら、黙々と書いていく。それらを書き終える頃には気づけば8時間以上経過していて、心も体も頭も、もうクタクタだった。
心の奥底から一生懸命絞り出した私の「理想の一日」は、笑ってしまうくらい現実とはかけ離れているのに、心はとても清々しかった。
初めて自分の「本当に欲しいもの」と向き合えたような気がした。
当時書いた私の「理想の一日」(状態も含む)の一部は以下。ここでは分かりやすく箇条書きにしているけれど、書き方は自分の肌に合うやり方を選んでもらえるとうれしい。ちなみに私は普段は「物語調」でまとめている。
・朝7時にお祈りの声と一緒に目を覚ます
・家はネパールの湖の側。1Kの賃貸に住んでいる
・窓際にはいつも切り花が飾ってある
・世界中で自由に写真を撮り、エッセイやコラムを書く仕事をしている
・自分のプロダクトを持っている。お茶や文房具に関するものだとなお良い
・一緒に五感を開いてくれるパートナーがいる
・自由な会社で、信頼できる仲間と働いている
・夜21時からは読書タイム。30分間はゆっくりと本を読む時間をとる
・23時にはふかふかの真っ白なベッドで眠る
このワークショップは、定期的に行う「最高の一日を考える」という個人ワークとして私の中の定番になった。今でも、半年に一度たっぷり一日休みを取り、ノートに書いたりやパソコンでカタカタと打ち込んだりしている。(以下の記事などでは、具体的な私の「最高の一日」の書き方と、現在の生活を理想に近づけていくにはどうすれば良いかのアイディアを書き出していくまでのやり方をまとめているので、気になる方はぜひ)
「特別な何者かになる」ではなく「自分の特別を知っている」ことの大切さ
理想の中には、既に叶っていることも、夢物語のように感じるほど遠くにあるものもある。初めてワークショップに参加した日からゆっくりと時間をかけて、生活の一部へと変わっていったものもある。
例えば毎日ふらりと何となく立ち寄るコンビニで、お菓子やら珈琲やらに使っていた500円を、部屋に飾る一輪の花に使うことを変えた。花が一輪あるだけで、部屋の中がぱっと明るくなる。毎日帰ってきた時に自然と目に入ると、心がふんわりと軽くなる。

何度「最高の一日を考える」を書いても登場する「朝早くに起きて本を読むこと」も少しずつだけれど、日常化している。慌ただしい毎日の中で、予定より30分だけ早く起きて、駅までの通り道にあるカフェでページをめくるようになった。本はいつも、毎日にちいさな発見をくれる。
今までは「何者かにならなければ」を原動力に、ただがむしゃらに仕事をしていた。だけれど最高の一日を考えるようになったことで、自然と「仕事」という言葉への価値や見え方が変わり、仕事で「自分がどんなことをしたいのか」が徐々に分かるようになってきた。細々とだけれど、苦手な部分は助けてもらいながら、自分のプロダクトも作り始めている。
結婚についても、「最高の一日」の中にパートナーの存在が出てくることはあったけれど、別に「絶対に結婚をしたい」というわけではないことに気付いた。それからは、周りの人をゆるやかに、心から祝福できるようになった気がする。
人生全体に、なんだかゆったりと余裕が生まれた。
もちろん焦りや不安がゼロになったわけではないけれど、私にとって、暗い道を照らしてくれたこのワークショップと出会えたことが人生の転機になった。
自分の理想的な状態、つまり自分の“特別”を知っている状態は、他人の人生を無駄にうらやんだり、選べずに迷い、疲弊してしまう時間から解放してくれる。同時に「このままで良いのか」と悩んで立ち止まってしまうことも、私は減った。
私の「最高の一日」は、年齢を重ねるたび少しずつ変化をしている。
だけれどその中で絶対的に変わらないものもある。
そういうものを手放さず、きちんとどれだけ未来に連れてゆくことができるかで、人生の豊かさは変わるのだと思う。

今私は、過去一度手放してしまった「組織の中で働く」にもう一度向き合うフェーズにいる。自分の理想の一日を考えてみたときに「信頼できる仲間と働く」というのを求めていることに気付いたからだ。
所属している会社は、出勤時間も勤務地も決まっていない。私自身は個人の仕事も並行していたり、岡山と東京の2拠点生活をしていたりする状態だが、それでも「仲間」と「組織」で働く自分もいる。最高の一日を考えなければ、こうした決断もできなかったように思う。
「なんだか感じている不安」には、ちゃんと名前がある。
「なんだか感じている焦り」にも、ちゃんと解決方法がある。
「人生、流れに身を任せて」も悪くはないけれど。
薄暗い道で立ち止まっている人にこそ、「理想の一日」を考える方法を試してみてほしい。私がそうだったように、きっと小さな光の道標となって、人生を照らしてくれるはずだ。
著者:古性のち
編集/はてな編集部