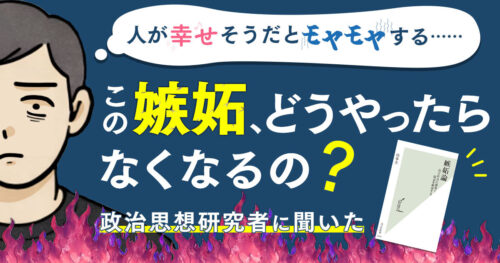ここ数年、ブームになっている「自費出版本」。文学作品や雑誌、ZINEなどの展示即売会「文学フリマ」は、北海道から九州まで全国の会場で年9回開催。ブックフェスなどの本の祭典も日本各地で実施されるようになり、自費出版の可能性が大きく広がっています。
私も友人とZINEを制作したことがあったのですが、私の生活環境の変化により2年続けた創作活動は現在休止中。
昇進、転職、結婚、出産などと、私たちの役割や責任は変化し続けます。変わりゆく日々の中で「好きなことを継続する」って本当に難しい。
そんな私の住む街である岩手・盛岡には、人生のフェーズが変わっても、約20年間、自費出版でミニコミ誌を作り続ける先輩方がいます。その雑誌の名前は『てくり』。

誌面の中に広告が一切ないのが特徴で、キャッチコピーは「伝えたい、残したい、盛岡のふだんを綴る本」。誌面に登場するのは、この盛岡に住まう「市井の方々」や「盛岡の日常」です。


そんな『てくり』は、地元在住のデザイナーやライターの方々が有志で集まり、「まちの編集室」という市民団体を立ち上げてスタートしました(※)。創刊当初から現在まで、女性メンバーだけで編成されています。
※現在はLLP(有限責任事業組合)として運営
また、出版社や印刷会社が版元ではなく、「まちの編集室」が自費出版で制作しているのも特徴の1つ。前号の売り上げを次号の制作費用にあてるというミニマムなサイクルを、スタート以来ずっと継続しています。
盛岡の街をテーマにした雑誌ながら、号を重ねるごとに取扱い店は全国に広がり、現在は東北6県、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方の約80店舗。

『てくり』を制作している「まちの編集室」の木村敦子さんは、デザイナーや編集者だけでなく、ブックイベントやクラフト市などの運営、伝統工芸品の伝承活動など、地域プロデューサーとしても活躍されています。
仕事、出産、育児も経験しながら、チームの方々とともに約20年間『てくり』を作り続けている木村さん。その裏側には、きっと「続けること」のヒントが隠されているはず。
私自身、友人と手塩にかけて作り上げたZINEが誰かの手元に渡ったときは、形容できないほどの心地よさを感じました。あの喜びをまた味わうには、どうすればいいんだろう?
環境の変化の中で、ものづくりを続けていくヒントを知りたくて、ジモコロ編集長の友光だんごさんと一緒に、木村さんにお話しを伺いました。
『てくり』が誕生したきっかけ

松浦「早速ですが、てくりがスタートしたきっかけは何だったんですか?」
木村さん「あるとき盛岡のフリーランスが集まる会があって、そこでライターの滝沢さんという方に『木村さん、デザインできるんだったら何か一緒にやらない?』と言っていただいたんです。私は盛岡に戻ってきたばかりだったし、人脈もないし、時間の余裕もあるしで『やろうやろう!』となったのが始まりでした」
松浦「始まった当時、他にはどんな方々が?」
木村さん「創刊時のメンバーは6名でした。滝沢さんと『まちの編集室』のメンバーであるライターの水野と赤坂のほかに、盛岡のラジオ局でパーソナリティを務めていたフリーアナウンサー兼ライターの方、現在は仕事や家族の事情で他県へ引っ越したフリーライターの方がいました」
だんご「そこで盛岡のことを取り上げる冊子を作っていこうとなったんですね 」

木村さん「私以外のみんなは、行政やクライアントの案件を日々バリバリこなしているわけです。充実はしているけれど、仕事と自分のやりたいことって、ずれるじゃないですか」
松浦「わかります……」
木村さん「あとはライターだけが集まっても、本はできないとみんなが言っていて。文章は書けるし、書きたいことがいっぱいあるけど、まとめられない。でもデザイナーがいると形になるって」
松浦「木村さんの存在が、みなさんの願いへのさらにひと押しになったんですね」
木村さん「みんな、仕事でメディアに関わっているからこそ、『広告とか全く考えなくていいようなメディアをやりたいね』というのが、創刊理由のひとつです」
松浦「『てくり』は前の号の売り上げを、次号の制作費に充てるというサイクルで制作されていますよね。自分たちで冊子を作る分、様々なコストがかかると思うのですが、一番初めの資金繰りってどうされたんですか?」
木村さん「やりたいことが決まっている一方で、お金はないわけです。どうしようと悩んでいたときに、当時、盛岡地方振興局にいらした女性係長が『あなたたちは団体になりなさい』とアドバイスしてくださったんです」

木村さん「それで『まちの編集室』という団体を作りました。ライターとデザイナーの集まりなので、編集のお仕事を受けられますよね。最初に行政のセミナー冊子を作るお仕事を頂いて、その30万円の売り上げを元手に『てくり』の創刊号を作ったんです」
だんご「なるほど、個人よりも団体のほうが受けられる仕事も増えますよね。その係長さんも、みなさんを応援したい気持ちがあってアドバイスしてくださったんだろうなあ」
木村さん「あの係長さんの助言がなければ、『てくり』はなかったと思います。行政とのお仕事の流れとかもよく分からず、ぼやぼやしていたにも関わらず、本当にありがたかったです。取材やデザイン、執筆は手弁当だったので、30万円の元手で印刷費などをまかなうことができました」
昔から、編集することが好きだった

だんご「木村さんは『てくり』で編集とデザインを担当されていらっしゃいますが、取材は同行されるんですか?」
木村さん「全部行きます。 現場に行かないと、デザインが浮かばないんです。私にとって、机上で考えているだけでは意味がないので」
松浦「そうなんですね! 私は元々、広告業界で営業をやっていたのですが、現場に同行してくださるデザイナーさんってそんなに多くないイメージでした」
木村さん「ほかの案件や納期の制限もありますしね。でも、取材の醍醐味って『裏側を見せてもらえること』だと思うんです。取材先のお店のことも知りたいけど、それを始めた人のことを知りたいという思いも強くて、取材のときは人にぎゅっと寄ってお話を伺う感じかな」
松浦「『てくり』では盛岡の街に生きる人たちの心模様や、今までの歩みが丁寧に優しく描かれているところに毎回強く惹きつけられていたんですが、木村さんのその想いがあったからこそなのだと思いました」
木村さん「私はデザインがものすごくうまいわけじゃなくて、並べたり繋げたり、編集することが好きなんです。言うなれば、デザインができる編集者、みたいな感じかな」
だんご「デザインできる編集者は最強ですね!」
木村さん「取材に同行していると、誌面の構成をイメージしながらカメラマンさんと撮る写真も相談できますしね。ラフは事前に細かく作り込まずに、『メインはこのカットにしましょう 』とかは現場で話しながら決めます。やっぱり、現場に行かないとわからないので」
だんご「現場主義が『てくり』をつくっていた……。木村さんが執筆されることもあるんでしょうか?」

木村さん「だいたいのタイトルや巻頭の言葉は私が書いています。ライターにはそれぞれが担当した記事をまとめてもらって、原稿が上がってきて内容を読んでから、じゃあ今回はメインキャッチは『写真と街」か、みたいなことをしています」
だんご「まさに編集してますね」
木村さん「実は中学生のときに、趣味が合う友達たちと一緒に漫画の同人誌を作っていたこともあって。ホチキス止めの本だったんですけど、誌面の構成も考えていました」
松浦「10代前半から雑誌づくりをされてたんですね」
木村さん「より内容を引き立てるために、どんなふうに友達の漫画を並べたり、繋げたりしたらいいかな、目次はどうしようかな、とか。それを考えるのが楽しかったんです。だから編集が好きなんですね、昔から」
木村さんの生い立ち。始まりは漫画家だった

松浦「14歳の頃に同人誌を作り始めていたとのことでしたが、木村さんの今までの歩みをお聞きしたいです」
木村さん「私は盛岡出身で、普通の県立高校を卒業しました。特に美術の勉強とかはしていないんですけど、17歳の時に漫画家としてデビューして。少女漫画を描いてたんですよ」
松浦「ま、漫画家……! しかも17歳ですか……!」
木村さん「集英社から出ていた『ぶ〜け』って漫画雑誌で賞をもらったんです。『よし行ける』と思って勉強しないで、漫画で生きていこうと思ったんですが、編集者さんとソリが合わなくて(笑)」

木村さん「大学も行かなくていいやと思ってたんですけど、ある種の現実逃避ですよね。漫画を描く大変さも知ったので、そこで漫画家の道は諦めました」
松浦「それからどうされたんですか?」
木村さん「絵が描けたので、経験は全然ないけれどデザインの仕事をやろうと思ったんです。そのとき私は仙台にいたんですが、地元の印刷屋さんが経験者のデザイナーを募集していて。そこに『経験はないですが、イラストは描けます!』って売り込みに行ったんです。そうしたら採用してくれて、デザイン人生がはじまりました」
松浦「行動力がすごい!」

木村さん「でも、会社でデザイナーとして働いたのは2年くらいなんですよね。その後は家庭の都合で転勤が多くて、まず秋田へ、それから青森、宮城、山形と引っ越しました。青森では印刷会社で働きながら、フリーのデザイナーとしての仕事もはじめました。福島以外、東北5県に住んだので、今思えば東北のいろんな街を見た経験が、今の仕事にも繋がっていると思います」
だんご「盛岡にはいつ戻って来られたんですか?」
木村さん「30歳のときに戻ってきました。まだ、子どもが幼かったのですが、それを機にフリーランスとして独立しました」
松浦「そこから、冒頭の『てくり』立ち上げの話につながるんですね」
楽しめる速度で、ルールを決めすぎず、無理をしないことが継続のカギ

松浦「『てくり』ではチームの方々が同時期に妊娠されて、お子さんを抱えながら編集会議をしていたという話を聞いたことがあります。子育てをしながら、お仕事もされながら20年も続けられるの、本当に尊敬します」
木村さん「本当に保育園にはお世話になりました。かえって、小学校に入ってからの方が大変でしたよ」
松浦「というのは……?」
木村さん「うちの子が通っていた保育園は、20時まで預かってくれたんです。でも小学校に上がると、学童はもっと早くまでしか預けられなくて。そして中学校になると部活動の送り迎えが早朝や土日に入ってきて。子どもが中学生のときが、私たちは一番大変だったかもしれないですね」
松浦「生活スタイルがお子さん中心にシフトしていく……」
木村さん「子どもが野球をやっていたメンバーが、付き添いで土日のイベントに参加できない、みたいなときも『しょうがないよね』『OK! 行ってらっしゃい! 』って送り出してました」
だんご「そこはお互い様というか。特に子どもが生まれると、仕事以外の活動を続けられなくなるケースも多いと思うんです」
木村さん「『てくり』はあまり細かく決めすぎず、集まれるときに集まっているという感じですね。『今年は1回しか発行できなかった』みたいなこともありました。子どもが小さいときは、編集会議に子どもを連れてくるときもありましたね。子守りしながら話し合うみたいな」

『てくり』9号の表紙に写っている赤Tシャツの女の子は、木村さんのお子さん
松浦「ライフステージが変わっても、その変化を受け入れてくれる居場所があるのは大きいですね。だから20年も続いたのかなと」
木村さん「無理せず、続けられるスピード感で進める。やりたいことをやっているわけだから、やめる理由がなかったんです。20年続いたのは、やめなかっただけじゃないですかね」
だんご「やめなかっただけ。すごく重みを感じる言葉です」
好きなことを続けていくコツと、型にとらわれない編集

だんご「長く続ける中で、メンバー間で意見が割れたりすることはなかったですか?」
木村さん「今の編集部は奇数なので、2人が賛成すると多数決で通るんですよ(笑)。メンバーが奇数なのが、続けられてきた理由のひとつかもしれませんね」
だんご「なるほど。偶数だと対立してそのままケンカに……みたいなこともありそう」
木村さん「それで終わっちゃうかもしれないですから。編集方針として『こうでないといけない』というのは少ないかな。企画がディープなものに寄りすぎても、読者との距離が生まれてしまう。いつも3人で話をしながら、バランスを調整しています」

だんご「雑誌って、時代の流れを意識する作り方もあると思うんです。『てくり』の特集では、時流って意識するんですか?」
木村さん「うーん。今、目の前にあるものを記録するような作り方だから、50年後にそういう時流が見えてくるのかな、みたいな気持ちでいますね。目の前の風景を残していって、それが将来的に時流の1つになっていくんだと思います」
松浦「本当に、長期的な視点で雑誌を作られているんですね。『てくり』の創刊当時は全国的に見ても、似たような雑誌も少なかったと思うんです。取材先にはどんなふうに企画趣旨をお伝えしていたんですか?」

木村さん「最初は取材相手に説明するのも大変だったので、『まちの編集室』メンバーの人脈を辿って取材していました。メンバーの出身校の後輩筋とか。でも、まず最初の号ができれば、それをサンプルとして先方に見せられるじゃないですか」
松浦「まずは作ってみるのが大事なんですね」

木村さん「まず1つ形にしてみるっていうのは、すごく大きいです。しかも続けようと最初に思ってたのもよかったんじゃないかな。『2号があるんです、続くんです。だから取材させてください! 』と言えたので」
だんご「1号で終わっちゃう自主制作誌も多いですからね……。『てくり』は販売されていますが、なぜ無料配布にしなかったんですか?」
木村さん「最初はフリーペーパーにして配っちゃおうかという話も出たんです。まずは自分たちのやりたいことができればいいよねって。でも、配ったらそれで終わっちゃうかもしれないよねと。売れたらその収入を次の号に充てられるから、試しに売ってみることにしたんです」
松浦「そんなエピソードがあったんですね。今は全国各地に『てくり』の取り扱い店がありますが、初めの頃の営業活動ってどうされていたんですか?」
木村さん「地元の本屋さんに『こういう本を出すんです』と『てくり』をもっていって、1軒ずつ営業しました。当時は『ku:nel (クウネル)』などのいわゆる『暮らし系』の雑誌が世の中に出始めた頃で、本屋さんの反応も良かったですね。1,000部刷ったのが、結構早い段階で完売しました」
松浦「自費出版本で1,000部即売はすごいです!」

木村さん「忘れもしないですよ。本屋さんの前でメンバーに電話をかけて『どうする? もう在庫ないよ、刷っちゃう?』って話をしたこと。もう1回1,000部刷ってまた売れて、結果3,000部刷ったんです。最初から3,000部刷れば良かった、なんて言ったりしてね」
だんご「発行元が出版社ではない、『てくり』のような自費出版の雑誌って当時はあったんですか?」
木村さん「 石川県金沢市の『そらあるき』や愛知県名古屋市の『なごやに暮らす』など、地域系のものが何冊かありました。あとは『Arne (アルネ)』というイラストレーターの大橋歩さんが自主制作したミニコミ誌があって、『自分たちで好きなことやっていいんだ、雑誌として売っていいんだ』と学びましたね」
松浦「自分たちで好きなことをやっていい……」
木村さん「それまで、街の本屋さんのシステムとして『取次会社』を通すというのが一般的なので、ミニコミの扱いはそう多くなかったんですよね。やっぱり本や雑誌は出版社がやるものだと思っていて、自分たちでやっていいのかな、みたいな戸惑いがあったので」
松浦「自主制作した本が書店に並ぶの、憧れです。『てくり』は直販で書店に?」
木村さん「そうです。自分たちで全部、納品書も書くし、封入作業もするので、いまだに大忙しです(笑)」

おわりに
取材の最後に、活動を続けるなかで嬉しかったというエピソードを、木村さんが教えてくれました。
「創刊当初は取材許可をいただけなかったお店を、5年越しに取材できたときは本当に嬉しかったです。一度断られていたけど、どうしても取材したい場所だったので諦められなくて、改めて伺ったら『あのときはすみませんでした』とまで言っていただけて。『てくり』が認知された、って思いました」
20年の年月を通じ、盛岡の皆さんから愛される雑誌となった『てくり』。木村さん自身も「てくりの木村さん」というイメージが広がり、個人の仕事にもつながっていったといいます。
現在の木村さんは、グラフィックとエディトリアルのデザイン事務所「kids」を主宰、盛岡の中心地にオープンした複合商業施設「monaka」のサインデザインをはじめとする県内企業のロゴマークやパッケージデザインなどを手掛けています。
さらには、盛岡に息づく伝統工芸品である毛織物『ホームスパン』を広めるために、イベントの提案や企画運営をしたり、日本各地から集まったクラフト作家が岩手公園(盛岡城跡公園)で出店をする大型イベント『北のクラフトフェア』の実行委員も務められています。

好きなことを持続できるスピード感で続けたその先に、いろんな出会いが繋がっていく。
まずは形にしてみること。前例ができることは、未来の自分自身をひと押しするお守りになるということ。好きなことを続ける速度は、無理なく自分のペースでいいということ。変わっていくことに、寛容でいること。
友人と始めた創作活動。ライフステージの変化により、以前のようなスピード感で創作ができず、断片的にしか続けられなくなっていることに負い目を感じることもありました。
だからこそ、取材中に木村さんから「無理せず、続けられるスピード感で進める」という言葉を伺ったときは、目頭がぐっと熱くなりました。そして、好きなものに対してどこまでもストレートに挑戦し続けられる木村さんの姿には、学ばせていただくことが数えきれないほどありました。
私だけでなく、木村さんの言葉に救われる方がきっといると思います。好きなことを続けていくコツ。少しでも多くの方々に、この記事が届きますように。
<お知らせ>
木村さんが実行委員をつとめる「北のクラフトフェア」が今年も開催します!
開催日:2024年10月12日(土)〜14日(月・祝)
時間:クラフトDAY 12日 10:00〜16:00 13日 9:00〜15:00 トークDAY 14日
会場:クラフトDAY/岩手公園(盛岡城跡公園)芝生広場 トークDAY/盛岡劇場メインホール
※詳細は北のクラフトフェア公式サイトをご確認ください
あわせて読みたい東北の記事
この記事を書いたライター
盛岡市在住。青森県八戸市出身。 広告業界の営業を7年したのち、フリーランスのライターへ転身。 青森や岩手など自分の住む街を中心に、撮ったり書いたりしながら活動中。 趣味はフィルムカメラで写真を撮ること。 人のお話を聴くのが好きで、人オタクだと自負している。