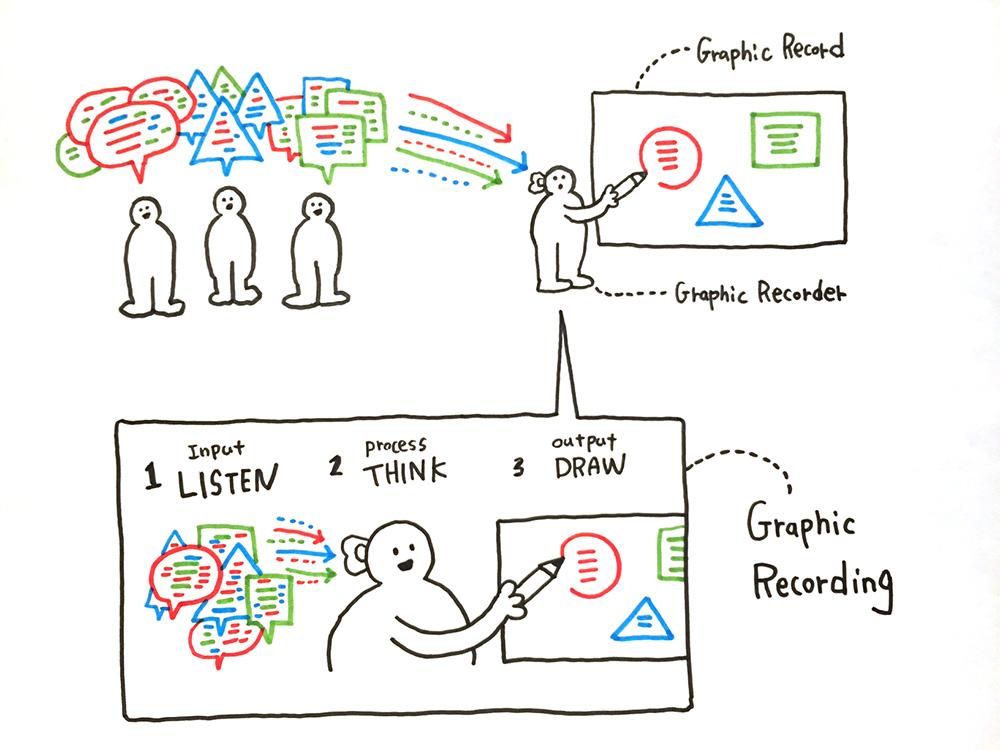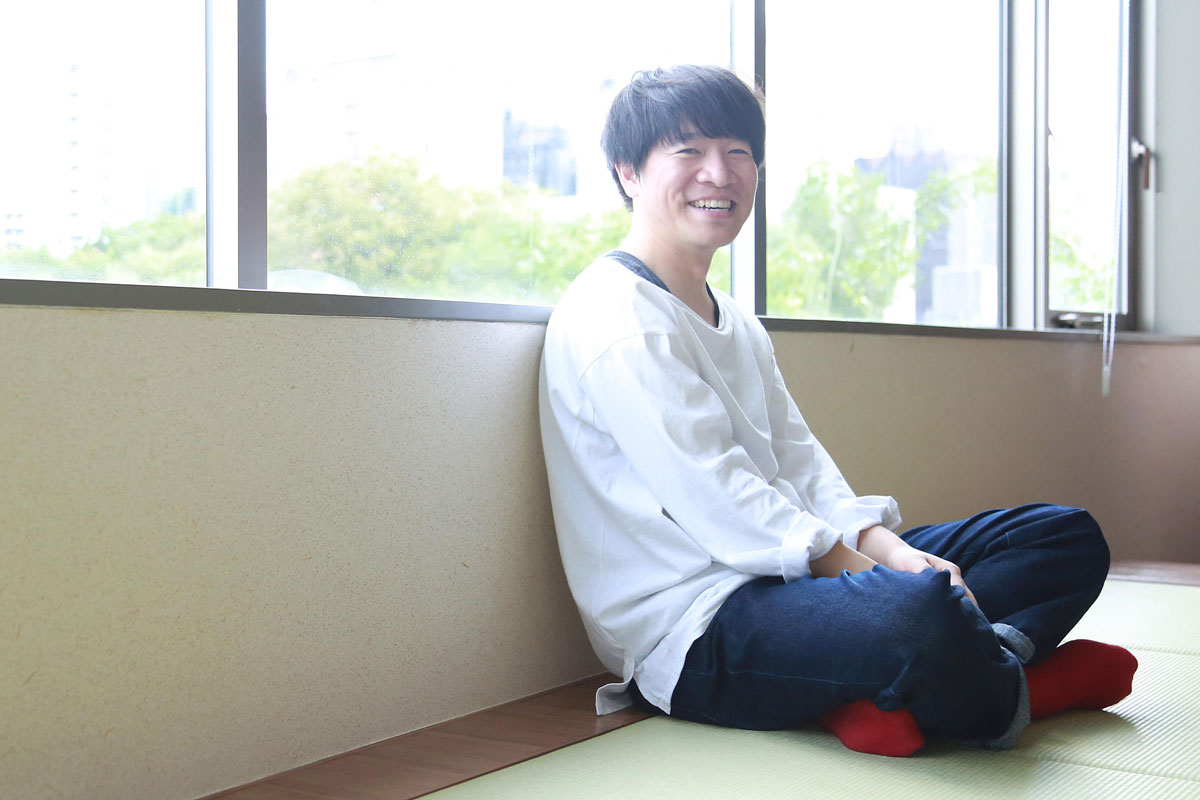2018年に出版され、大きな話題を呼んだ実録小説『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』(通称:『であすす』)。本書の著者である書店員・花田菜々子さんは、2013年からの1年間、実際に出会い系サイトを利用して出会った70名の人たちに「本をすすめまくる」活動をされていた異色の経歴の持ち主です。
「本をすすめまくった1年間の前と後では、自分の人生がはっきり分かれている気がする」と語る花田さんに、本をすすめる活動を経て感じられたことやその際に意識されていたこと、理想とする生き方や働き方などについて伺いました。
「アホだなあ私」と思うような行動をすることが必要だった
花田菜々子さん(以下、花田) そうですね。SNSにはずっと苦手意識がありました。
花田 いえ、いま振り返ると、自分でもずいぶん荒療治だったなと思いますよ(笑)。本に書いたとおり当時(※2013年)は仕事に行き詰まっていて、夫とも半別居のような状態だったので、とにかくなにか環境を変えてみたかったんです。
そういうときに習い事をしてみたり趣味のサークルに入ってみたり、という選択をする方は多いと思うんですが、そんな生ぬるい……というか無難な体験では、自分の負った傷は癒えないんじゃないかと思ったんですよね。
花田 そうですね。一度ガツンと殴られるような思いをしないとなにも変わらないような気がしていたので、自分から見ても「アホだなあ私」と思うような行動をとることが当時は必要だったというか……。やっぱりその頃は元気もなかったので、「こんなヘンなことをしている自分ってちょっと面白いよね」みたいなイメージを持つことで、自分のことをどうにか支えていたというのはあるのかなと思います。
それと、私が使っていた出会い系サイトは出会いの目的を恋愛に限定しておらず、あくまで「知らない人と30分だけ会って話してみる」という場を提供するサービスだったんですよ。そのアイデア自体も面白いなと思いましたし、「ここでなにかをしてみたら世界が広がるかもしれない」という直感があって。実際に、サイトで本をすすめまくった1年間より以前とそれ以後では、自分の人生がはっきり分かれているような気はします。

花田 確かに、同性の読者からは「自分だったら最初の何人かで心が折れてたと思います」というご感想を頂くこともあります。
熱心に本をすすめた相手が実は自分に性的な関心しか抱いていなかった、というときはもちろん私もがっかりはしたんですが、それ以上に「そうか、出会い系にはこういうこともあるのか」と世界のしくみをひとつ知れたみたいな気持ちでいたので、わりと平気でしたね(笑)。もちろん困った人もときどきはいたんですが、サイトで出会った70人の中にはいい人や面白い人の方が圧倒的に多くて。
基本的にはとても出会いに恵まれていたなと思いますし、その時期は友人が急にブワッと増えたので、休日のスケジュールを調整するのが大変なくらいでした。
花田 お会いした人の中には「いま仕事してないんだよね」という人や「これから起業しようと思ってる」みたいな人も結構いて、「あ、意外とみんな自由なんだな」と思えたのも経験として大きかったです。
会社がつまらなかったり家庭がうまくいかなかったりして、仮にその場所を失ったとしても、面白い場所って他にもいくらでもあるのかもしれないなと思えたというか。頭では分かっていたつもりだったんですが、実際に人と会いまくったことでそれを本当に信じられるようになった、という気がします。
出会い系での1年を経て「無理だ」とすぐに思わなくなった
花田 いま言ったことにも近いんですが、場数を踏むことって大事だなとあらためて思うようになりました。人に本をすすめるという行為って、当たり前ですがとにかく実際に人に本をすすめてみることでしかうまくならないんです。実際に70人に会ったことで、どういうふうに本を紹介すれば人が興味を持ってくれるのか、という実験をたくさんさせてもらったような気がしますし、活動を始めたときよりもはるかに短い時間で相手の方がどんな本を求めているかが分かるようになりましたね。

花田 なにか行動を起こす前に「無理だな」とは思わなくなったような気がします。昔はすごくやってみたいこと、憧れていることがあっても「そんなことできるわけない」って思うことが多かったんですが、「いや、やってみたら意外とできるかも」と思えるようになったというか。
花田 そうですね。もちろんそれまでも、自分から連絡をすれば会っていただけるかもしれないとは分かっていたんですが、「自分なんて……」みたいな遠慮の気持ちがあって。でもその1年間を経てタガが外れたというか、「絶対に無理」と思う前に「会っていただくにはどうしたらいいんだろう?」と考えられるようになったんだと思います。
……あっ、それで言うと、本を出すという目標も同じだったのかもしれないです。『であすす』を出す前に、実は友人と企画して『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』(朝日出版社)という本を出版しているんですが。
花田 昔だったらそうだったと思います。その本は出会い系での1年を経て転職したあとに出したんですが、一緒に本をつくった友人には散々「出版なんか無茶だよ」と言われ続けていました。で、私はずっと「いや分かんないよ、出せるかもしれないじゃん」と言い続けていて(笑)。
あるとき友人をうまく乗せて、「じゃあもしも仮にこの本が出せるとしたら、どこの出版社から出したい?」と希望の出版社をランキングにして5つ挙げてもらったんです。それを聞き出したところで、「じゃあこの1位の出版社から順番に乗り込んでみようか」と。友人は引いてたんですけど、結局、第一希望だった出版社から本当に出版していただくことができたんですよ。
花田 だからそういう図々しさというか、調子に乗ることも意外と大事だと気づいたんだと思いますね。もしもそれで出版社5社に断られていたとしても、こっちに失うものもないですし。出会い系での1年が、自分を必要以上に抑える、みたいなストッパーを外してくれたんだと思います。

作家の星座別で分けた「星座文庫」のコーナー。同じ誕生日の作家が書いた本に出会えることも
人に本をすすめるときにいちばん意識していること
花田 いちばん意識しているのは相手が話すことを否定したり自分の意見を押しつけたりは絶対にしないということですね。
花田 そうかもしれませんね。「本をすすめる」場合の話をすると、例えば「失恋してしまって恋人のことが忘れられない。なにかいまの自分に合う本を教えてください」というお客様がいらしたとして、「だったら早く忘れたいですよね」とか「新しい恋人を探した方がいいですよね」ということを私が言うのは違うと思っています。
その方が「新しい恋愛をしたいと思っています」と言うのであればそれに合う本を探すようにしますし、「忘れられなくて苦しいです」と言うのであればその苦しみに対しての本を探す、というイメージです。
花田 確かに、『であすす』を出したこともあって、自分でもなにが読みたいのか分からないけれどなにかすすめてほしい、という方もときどきお店に来てくださいます。お店だとどうしてもお話できる時間が短いので、そういうときにはこちらもなるべく早めに的確な回答を引き出せるよう、その方が出されたキーワードからひとつひとつお話を聞いていっていまのお気持ちを知ろうとしていますね。
もしも悩んでいらっしゃることがあるようだったら、「いまどういうお気持ちですか」と聞くよりは、「それはうれしい気持ちと不安な気持ちであればどちらに近いですか?」という形で聞くようにしています。
花田 極端な話、本を紹介するという最終目的がなければ「そうなんですね」「大変ですね」とずっとお話を聞くだけでいいと思うんですが、やっぱり相手の方にすすめるための1冊を決めるとなると、質問がどうしても具体的にならざるを得ないんです。「それって旦那さんに対する怒りですか、それともお子さんに対する怒りですか?」みたいに2択で聞いていかないと本が選べないので。
花田 やっぱり「本を探す」というひとつの目的があると、ただ漫然とお話を聞くよりも芯を食ったやりとりになりやすいのか、悩みや考え事がひとつ前に進んだ、と言っていただくことも多いです。


「自分には本しかない」とは決めつけない
花田 ああ、そうだと思います。「〇〇歳までに家を建てたい」とか「5年後までに年収を〇〇円にしたい」みたいなものが、たぶん私にはあまりピンとこなくて……。
花田 数年後を見据えるのって正直難しいですよね。私の場合は、どこかに旗を立ててその場所をひたすら目指すというよりは、たまたまそのときに流れてきたものに飛び乗ってみる、みたいな生き方の方がもともと好きなんだろうなと思います。自分がそう思っているからなのかたまたまなのかは分からないんですが、実際にここ数年は転職が続いていて。
ひとつ前の職場もこのお店(HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE)への転職もそうなんですが、「やってみませんか」というお話をいただいた形だったんです。そう言っていただいたからにはめちゃくちゃ頑張ってみようかな、というスタンスでこれまでやってきているので、私は流されるままの方が結果的に面白い仕事に出会えるのかな、と思ったりもします。もちろん、どこに流れ着いてもいい、というわけではないんですけど。

花田 多分、野心が強いタイプなんです。このお店も前職も新しい店舗を一からつくるというタイミングでの転職だったんですが、そういうふうに、できるなら新しいことをやりたい、新しい場所でチャレンジしてみたいという気持ちがあって。流れ着いた先で自分の持っているものを精一杯ぶつける、というのが合っているのかなと感じます。
花田 本屋以外の仕事ですか? やってみたい!(笑)書店員をやり始めてもう 20年くらいになるので、極端に言えば「書店で初めて自分の棚を持っておすすめ本を並べた瞬間」のようなフレッシュな感動は、もう二度と味わえないと思うんですよ。
もちろんこれまでの20年の蓄積があるからこそやれることもあると思いますし、実際にまだまだやりたいこともあるんですけど、一方で書店員以外の人生も味わってみたいな、と思ったりもします。
やっぱり対面でお客様とお話して本をすすめていくときのライブ感は大好きなんですが、その仕事しかできない、というのは思い込みかもしれないですもんね。……私、大学生のときにパンを製造するアルバイトをしていたことがあるんですけど、実はいまだにあれに勝る楽しい仕事はないって思っていて。
花田 クリームパンにクリームを入れたりする仕事だったんですけど、焼き上がったパンがラックにどんどんたまっていくので、ラックいっぱいになる前に仕上げて店頭に出さないといけなくて、テトリスみたいな感じだったんですよね。「○時までにここのパンは全部出そう!」ってバイトのみんなで頑張るのが最高に楽しかった記憶があって(笑)。
花田 だから多分、自分にはこれしかないはずだって決めつけない方がいいですよね。私には本しかないって思ったら選択肢が狭まってしまうだろうし、いつまで(本の仕事を)やるか分からないという気持ちがあるからこそ、やれるうちに全力を尽くしておこう、という気持ちがあります。
いつかまたパン屋さんがやりたくなるかもしれないですし、もしかしたら10年後、20年後には掃除のプロフェッショナルとかになっているかもしれないですから(笑)。そういう人生の可能性もあるのかな、と思うと、これから先がちょっと楽しみになったりはしますね。

撮影:関口佳代
編集:はてな編集部
『であすす』文庫版発売!
夫に別れを告げ家を飛び出し、宿無し生活。どん底人生まっしぐらの書店員・花田菜々子。そんな彼女がふと思い立って登録したのが、出会い系サイト「X」。プロフィール欄に個性を出すため、悩みに悩んで書いた一言は、「今のあなたにぴったりな本を一冊選んでおすすめさせていただきます」ーー。
悩みまくる書店員・花田菜々子が初めて書いた、大人のための青春実録私小説『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』待望の文庫版が発売!
お話を伺った方:花田菜々子さん