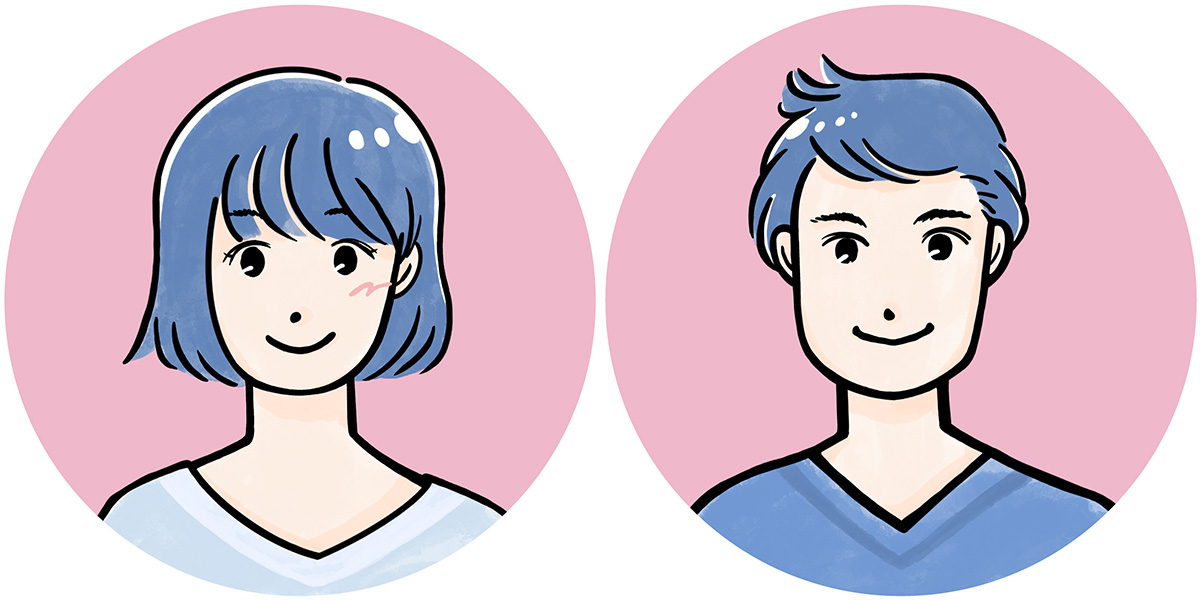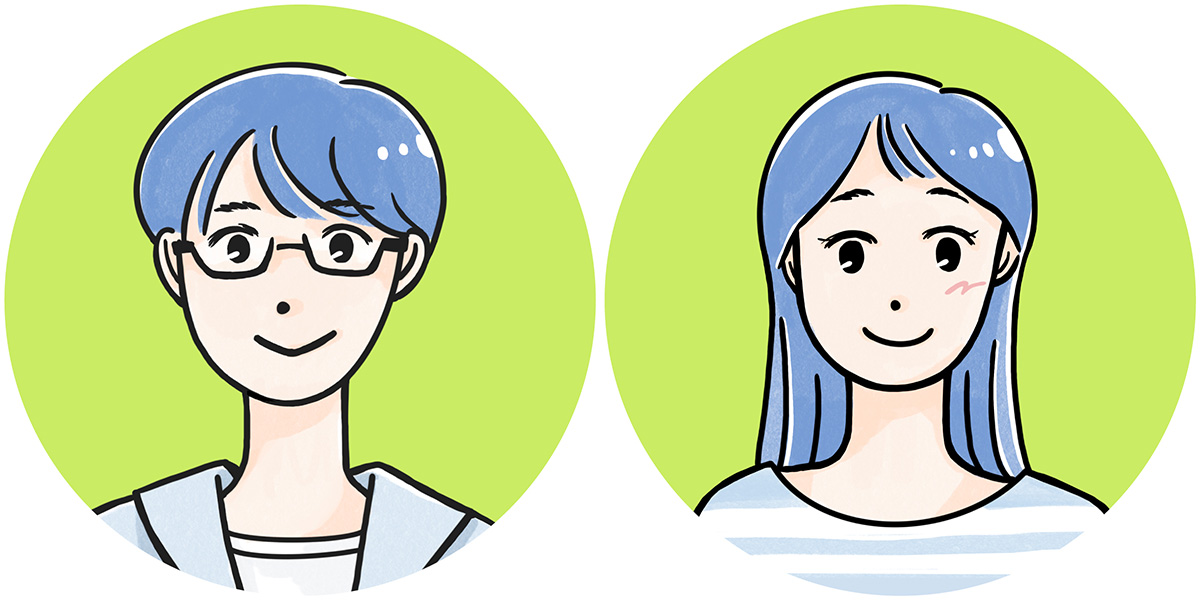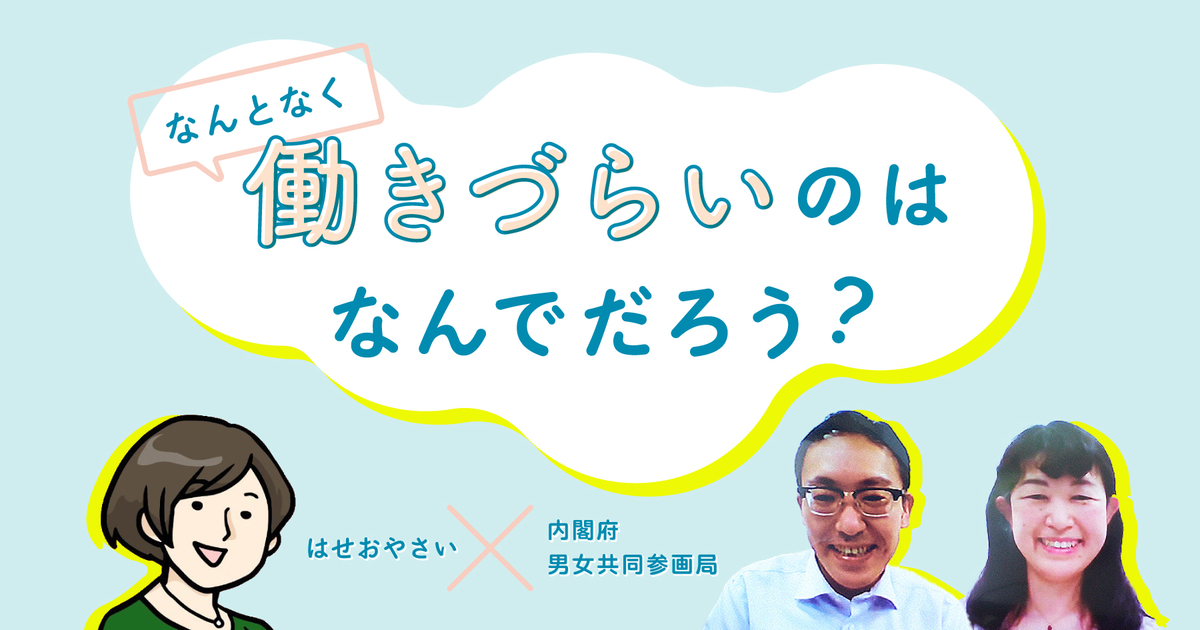不妊などの理由により「特別養子縁組(※1)」が選択肢に浮かんでいるけれど、夫婦共働きだと難しいかも……と考えていませんか。
今回は、特別養子縁組で子どもを迎えた二組の共働き夫婦による座談会を開催。養子を迎えることをどのように決めたのか、職場への相談方法、育休取得期間や復帰後のことなどについて、語っていただきました。
(※1)特別養子縁組……さまざまな事情により実親による養育が難しい子どもの福祉を目的として、養親との間に実の親子と同じ関係を結ぶ制度。児童相談所もしくは民営のあっせん団体を通じて、登録・研修・手続きなどを行う。
2017年1月の法改正により、特別養子縁組の場合も実子と同様に育休取得が可能になったが、職場における事例の少なさ、周囲の無理解、一般的な育休とは異なる手続きやフローなど、利用にあたっての課題はまだまだ多い。
夫婦二人か、養子縁組か。目指したい“家族”の形について考えた日々

りねんさん(以下、りねん) 不妊が分かってからお互いの意見や気持ちを受け止め合い、情報収集する時間なども作りながら、無理に結論を出そうとはせず、1年半ほどかけて少しずつ話しました。最初のうちはショックが大きく、夫婦間の温度差もあってなかなかちゃんとした話し合いにはなっていなかったですし、タイミングによって気持ちが変わることもありました。

寄り道さん(以下、寄り道) 当初は僕の方が“血のつながり”にこだわっていたんです。わが家の場合、主な原因は男性不妊だったので「僕は無理でも、妻と血のつながった子は得られるかもしれない」という思いで、ドナーから精子提供を受ける選択肢も考えました。
一方で特別養子縁組や里親に関する書籍を読んで知識を得たり、里親(※2)や養子縁組の社会的な意義について知ったりするうちに「血のつながりにこだわらず、二人で子どもを育てたい」と感じるようになりました。
(※2)里親制度……さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを、実親に代わって一時的に里親が預かって養育する制度。特別養子縁組とは異なり、親権は実親にある。参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/syakaiteki_yougo/02.html

瑛子えびすこさん(以下、瑛子) 私は38歳で結婚し、40歳までと期限を決めて不妊治療に取り組みました。治療中から授からなかったときのことも考えて特別養子縁組の情報収集をし、治療終了後すぐに説明会への参加や児童相談所での里親登録に進みました。
ただ、夫との間には温度差がありましたね。実際に動きながら夫婦で話し合いを続け、夫の気持ちが固まるのを待ちました。

山田太郎さん(以下、太郎) 僕はもともと「絶対に子どもがほしい」という強い思いがなかったんです。養子を迎えてまで子どもを持つべきだろうか、自分がそれに値する人間なのか……と悩み、少し腰が引けていたと思います。とはいえ、養親になるには年齢制限もあるため、研修などは気持ちが固まりきらないまま受けていました。
気持ちが変わったきっかけは、研修で養子への「真実告知(※3)」のロールプレイをした時です。講師に「本当に養親になりたいと思っているのか」と強く言われた時に反発的な気持ちがわいたことで「自分は子どもを持つことに対して真剣なんだ」とあらためて気付きました。
また、真実告知の本質は「血のつながりの有無は関係なく、子どもを大切に思っていることを伝える」ものだと教わったことで「社会的な意義や責任以上に、自分たちの気持ちが大切なんだ」という気持ちになり、どんどん前向きになったのを覚えています。
(※3)真実告知……血のつながりのないことや、生みの親が別にいるが事情があって育てられないことなど、養親が養子に生い立ちに関する真実を伝えること。参考:「子どものルーツと 実親との関係 - 厚生労働省」
突然始まる「育休」に備え、職場への相談と引き継ぎは念入りに

りねん 研修や説明会など、実際に養子を迎えた先輩養親さんのお話を聞ける場です。
私が気にしていた「働きながら養子を迎える」ことについて、職場への相談はどうするべきか、通常の妊娠・出産を経ての育休と異なるのはどんな点か、などをリアルな言葉で聞くことができ、大きな収穫がありました。自分にも置き換えてイメージしやすかったです。

瑛子 わが家も児童相談所や民間あっせん団体で話を聞きつつ、より多くの情報を得るためにネットで経験者のブログなどを探しました。
当時に比べると、今はブログやSNSで養子縁組について発信している人が増えましたし、情報も得やすくなっているように感じますね。それこそ、同じように悩んだり養子縁組に向けて動いたりしている人とつながれるようになったのも、いい変化だと思います。

※民間あっせん団体を介する場合、一部の流れが異なることもあるが、一般的には研修や面接などを経て親候補として待機登録され、委託後に養育を行い、家庭裁判所への申し立てを経て、審判が確定すれば縁組成立となる。

りねん 私は養親研修(※4)を受け始めたタイミングで、直属の上司に特別養子縁組を考えていることを伝え、子どもを迎えた場合の具体的な想定スケジュールを渡しました。
「研修が何カ月あって、このくらいの時期に待機家庭(※5)になる見通しで、そこからは養育の打診があれば翌日にでも育休に入る必要がある」といった見通しを示し、上司の判断で人事にも共有しました。そのおかげで、実際に娘を迎えた際には打診の翌々日からスムーズに育休に入れたんです。
業務についても上司と相談してチームメンバーに状況を伝え、自分が抜けることになる可能性を考えて、サブメンバーをつけてもらう、引き継ぎ書を作るなどして対応しました。それでも育休に入るまではバタバタしていたので、もし準備していなかったらと考えると怖いです(笑)。
(※4)養親研修……養子縁組で養親となるために必要な知識や技術の習得を学ぶための研修。
(※5)待機家庭……子どもを受け入れることができる状態。

瑛子 私も、特別養子縁組を希望していること、それに伴って育休を取得したいと事前に職場に相談していました。
ただ、育休の取得に必要な書類の中には家庭裁判所への養子縁組申立て後にしかもらえないものもあったりして、総務の方を悩ませることもありました。もっと事前に考えておけばよかったなと。

りねん 書類の入手問題、ありますよね……!

りねん 私が1年3カ月取得し、娘が1歳児クラスで保育園に入るタイミングで復職しました。本当は夫婦で取得したかったのですが、夫はタイミングや人員構成的に取得が難しくて。
利用したあっせん団体では「1年以上はどちらかの親がしっかりと養育にあたること」が定められていたのと、私も可能な限り娘と一緒に過ごしたかったので、個人的にはベストな期間だったと思います。

瑛子 私たち夫婦は同じ職場なのですが、私は娘を受け入れてから1歳までの約1年、夫は4カ月から1歳までの約8カ月取得しました。1歳の4月に娘を保育園に入れ、二人同時に復職しています。

太郎 特別養子縁組を検討していることについては妻側から事前に上司と共有していたので、ある程度の情報は職場側でも把握されていました。ただ、先ほど話した通り僕自身が「養親になる」という気持ちを固めるのに時間を要した結果、妻よりも育休取得の意志を伝えるタイミングが遅くなり、上司は「急に言われても困る」という反応でした。職場で男性の育休事例がなかったことも影響していたようです。
そこから相談・交渉を重ね、正式委託を受けてから3カ月後に育休をスタートしました。僕としてはもっと取りたかったなというのが本音なんですが、相談を重ねることで、双方で納得できる形にはなったかなと思っています。
今は当時よりも男性の育休取得が推奨されていますが、いずれにしても養子を検討しているのであれば早めに職場への共有をしておくのがいいと思います。
育休中、「翻意」の不安にどう向き合うか
(※6)監護期間……縁組成立のためには、養親となる人が養子となる子どもを6カ月以上監護する必要がある。そのため、縁組成立前に子どもと一緒に暮らし、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定する。参考:特別養子縁組制度について(厚生労働省)

寄り道 僕たちは不安に感じることがあったら、お互いにそれを吐き出して共有し合いました。

りねん 実親さんには、あっせん団体を経由して娘の成長を報告していました。実親さんも喜んでいると聞いてうれしく感じる一方で、「やっぱり自分で育てたい」と心変わりするかもしれないな、と感じることもありました。
でも私たちにできることは、目の前にいる娘にしっかりを愛情を注ぐことだけ。誰かに相談して助けてもらうよりも、自分たちの中にある娘への愛情を確かめながら過ごしました。

瑛子 私たちは実親さんとの交流はなかったのですが、翻意の不安はありました。でも、私がその不安を口にすると夫が「不安だけど、こちらにはどうしようもないことだから悩んでも仕方ないよ」と言ってくれて。それでも不安なときは、児童相談所の方や毎月訪問してくれる里親専門相談員さんに聞いてもらっていましたね。

太郎 そうですね。ただ「僕たちの環境でも育てられるはずだ」というのは伝えたいと考えていましたし、翻意があったとしても自分たちが納得できるような答えがほしいとは思っていました。
子どもの生活やスケジュールを考えて、復職後は働き方をシフトチェンジ

瑛子 共働きは続けるつもりでしたが、娘の生活リズムを最優先に考えた結果、「18時ごろまで働くフルタイム勤務は難しい」と感じたんです。また、一度時短にしても将来的にフルタイムに戻すことは可能だと考え、二人そろって時短での復職を選びました。

太郎 男性育休を取得したことで、時短での復職への理解は得やすかったように思います。育休中も職場に顔を見せに行き「家事や育児も妻と分担して取り組みたい」と伝えていたので、職場側も予想できていたのかもしれません。

りねん はい。復職に際しては「養子だから大変」ということはなく、おそらく実子を育てている親御さんと同じように「もっと一緒に過ごせる時間を作りたい」「仕事との両立は可能だろうか」という不安や葛藤を感じていました。
同時に「もう少しのびのびできる環境で娘を育てたい」という気持ちも抱いていたため、復職後まもなく、現在住んでいる長野へ移住し、夫は転職しました。私は退職し、働き方の柔軟性を重視してフリーランスを選びました。
「本当の親じゃないくせに」と言われても揺るがないような信頼関係を築きたい

りねん 日々、自然な会話の中で伝えています。娘を迎えた日と同じようなお天気の日に「あなたを迎えに行った日もこんなふうに晴れていたよ」とか。真実告知をテーマにした『ふたりのおかあさんからあなたへのおくりもの』という絵本を本棚に並べているのですが、娘が読み聞かせをリクエストしてくることもあります。

娘も少しずつですが「自分にはママが二人いるんだ」ということは理解しているようです。保育園の先生方にも養子であることは伝えているので、娘が実親さんについて口にすることがあっても、自然に受け止めてもらえるだろうと考えています。

瑛子 うちも同じように、何かタイミングがあれば、生んでくれたお母さんが別にいることを話しています。ただ、それがいわゆる「一般的な親子」とは異なるということまでは、まだ分かっていないように感じます。

寄り道 未来のことなので分からない部分もありますが、絶対にそばを離れず、子どもの思いに寄り添いたいなと思っています。そうすることしかできないし、それだけはしてあげたい。
そして、学校の側に明らかに配慮が足りないと感じることがあれば、そのときには親としてきちんと対話をしていきたいと考えています。

りねん 娘との関わりの中で意識していることがあるんです。私たち夫婦は実親さんに対して感謝の気持ちがありますが、この養子縁組に娘の意思は介在していないので、娘に「私も感謝しなくちゃ」と無理に思わせないようにしたいと思っています。
今後、自分の生い立ちに悩んだり、私たちや実親さんに対して嫌な感情を抱くこともあるかもしれません。それを娘のありのままの気持ちとしてしっかりと受け止め、一緒に悩んでいけるような親子になっていたいですね。

太郎 僕は養親研修で「真実告知をしていることで、家庭内での隠し事がなくなり、子どもが不安や疑問を感じたときすぐ親に尋ねることができる。それにより思春期以降の親子間の関係がよい方向に変わることが多い」と聞きました。それを聞いて、思春期になった娘が「本当の親じゃないくせに」と言ってくれたらいいなって。

太郎 そうですよね(笑)。でも僕は「これを口にしても受け止めてもらえる」と親を信頼しているからこそ、言える言葉かもしれないと思うんです。
血のつながった親子と変わりなく、本気でぶつかりあってケンカができるような信頼関係を築いておきたい。そのために真実告知を特別視せず、普段から「血がつながっているわけではない。でもあなたのことが大好き」と伝え続けています。


瑛子 私は、共働きで特別養子縁組をしてみて「ちょっと大変だけど、できる」ものだと感じました。
子どもを持つ選択肢としてもっと検討しやすくなってほしいし、一方で、そのためには社会や制度の変化がまだまだ必要だなとも感じます。
例えば特別養子縁組で迎える子どもの年齢は新生児に限らず、3歳やそれ以上ということもあります。しかし現在の法律では、育休を取得できる期間は出産した方と同じで原則1歳までです。共働きだと、1歳を過ぎた子どもを受け入れるハードルが高くなってしまいます。
経済的な余裕を維持しながら子どもを養育できる環境を整えるためにも、共働き家庭が養子を受け入れやすくなるような制度に変わっていけばいいなと。

太郎 自分たちにとっての「家族の形」について夫婦でよく考えて話し合うことが大切だと思いました。子どもにどう育ってほしいか、そのためにどんな環境が最適だと考えるか。それを突き詰めていった結果、僕たちが選んだのは共働きでしたが、どちらかが仕事、もう一方が育児に専念するという形ももちろんありだと思います。
ただ、どんな考え方や生き方、家族観でも、夫婦が「子どもを持つ」ことを望むのであれば、あきらめずにいられる社会であったらいいなと思います。

寄り道 多くの職場で特別養子縁組への理解がまだまだ浸透していなかったり、モデルケースが少なかったりして制度が整っておらず、大変な面もあると思います。
でも、自分がなぜ特別養子縁組を選んだのかをしっかり心の中に持ち、周囲に「養子を迎えて育休を取ること」への理解を求め、またお願いしたいことがあれば早めに情報共有や相談をするなど、ちょっとした工夫で乗りきれることもある。瑛子さんもおっしゃっていたように「ちょっと大変だけどできる、楽しい」とお伝えしたいです。

りねん 私は特別養子縁組を検討する中で、実は社会には「子どもを授からない」という悩みを持っている人が、思っていたより多いことに気付きました。
私が「もし養子を受け入れることになったら育休を取得したい」と周囲に伝えて以降、同じく養子を検討している人、“二人目不妊”に悩んでいる人、ステップファミリー(※7)で子どもについて考えている人などから、声をかけられることが増えました。
(※7)ステップファミリー……子どもを連れて結婚や同居をすることによってできる新しい家族
こういったさまざまな家族の形については、周囲へ理解を求める中で反発を受けたり、「家族はこうあるべき」というような個人的な家族観をぶつけられてしまうこともあると思います。ただ、私が発信をしたことによって「そういう家族の形もありなんだ」と思える後押しになればいいなと思いますし、私自身が今とても幸せだということを、もっと伝えていきたいなと感じています。
取材・文:藤堂真衣
イラスト:caco
編集:はてな編集部
共働きの育児、うまく両立するヒント
りっすん by イーアイデム
Xも更新中!
Follow @shinkokyulisten
<Facebookページも更新中> @shinkokyulisten