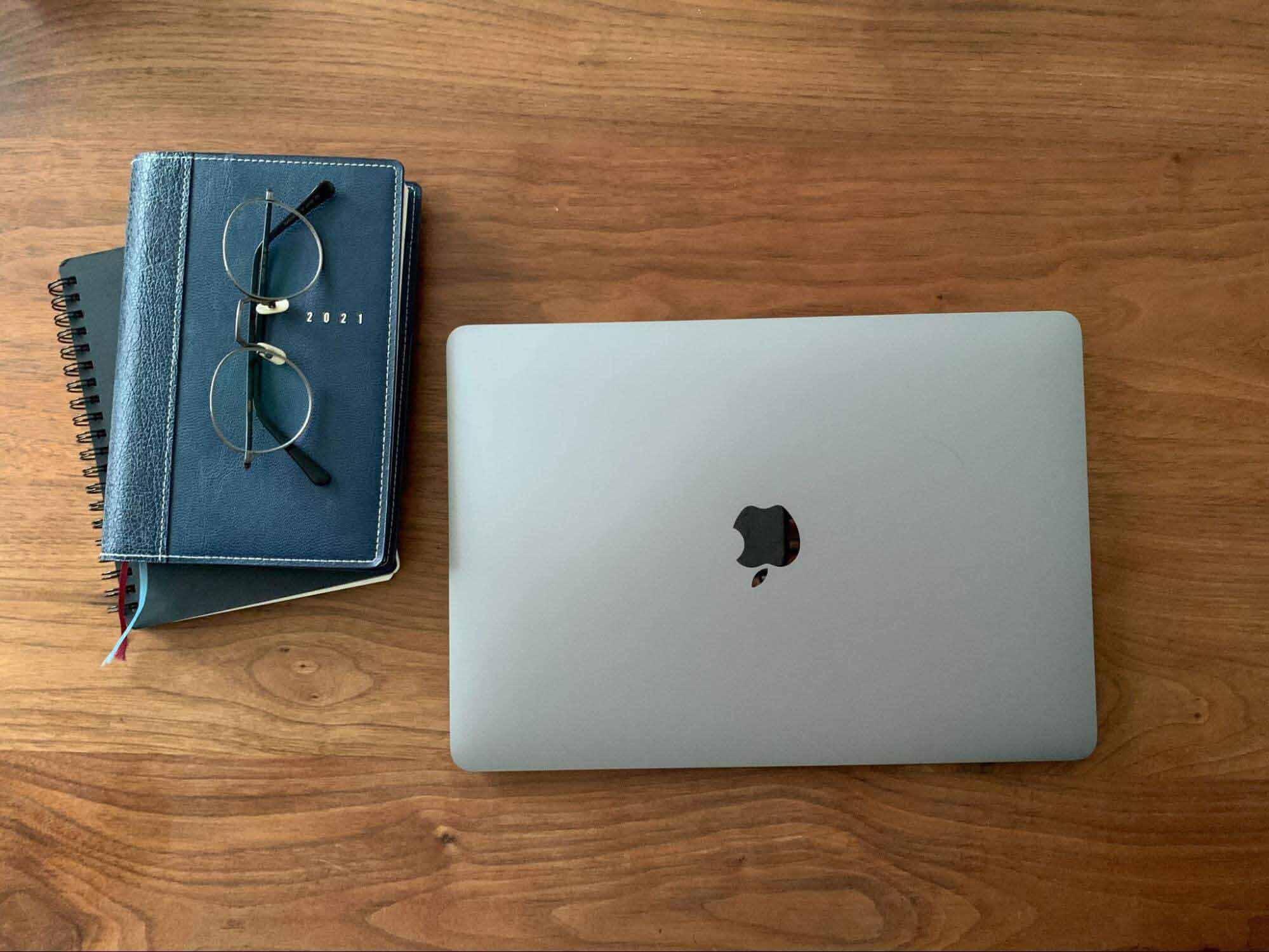予定していたタスクが終わらなかった……。一日を振り返るとき、そのように感じて気分が落ち込む人は少なくないのではないでしょうか。
副業や趣味を含む課外活動を行うことも珍しくなくなってきた昨今。どのように日々のスケジュールを管理し、マルチタスクをこなしていくかは重要性を増しているように思います。
学生時代から文筆家・書評家として活動している三宅香帆さんは、社会人3年目となる現在も、著書の出版や雑誌・Webメディアへの寄稿を多数行うなど、精力的に活動されています。
どのように日々のスケジュール・タスク管理を行っているのか。三宅さんに執筆いただきました。会社員兼作家業。二足の草鞋を履いてもう三年目になる。
本を読んだり書いたりするのが好きで、大学院生のときに一冊目の本を出版した。就活では副業可能な会社を探し、新卒でいまの会社に就職した。今年は六冊目の本が出るし、連載は毎月5本以上ある。「会社と執筆、どっちが本業なんだか分からない」と周囲に笑われながら、毎日働いている。
私自身、日々、時間の使い方やタスク管理について悩むことは多い。本業・副業ともに仕事をする時間はもちろん大切だけど、趣味に使う時間や人と過ごす時間も、同じくらい大切だ。やりたいこと、やるべきことは日々増える。でも、できるだけ楽しく明るく働きたい。
今回は、自分なりに気をつけている、タスクやスケジュールの管理方法について書いてみたい。もしかしたらこの記事を読んでいる人のなかに、私と同じように「本業とは別に副業をしている人」「趣味に使う時間も重視したい人」や、特に兼業はしてないけど「最近、だらだら仕事をしてしまっているな」という人もいるかもしれない。参考になったらとてもうれしい。
先に言っておくと、私が会社員と副業を両立する上で、一番気をつけているのは、自分にとってストレスのない方法を見つけることだ。
私の場合、社会人一年目の頃に(まだコロナのコの字もなかった頃だ)人生で一番ストレスフルな日々を送っていた。「せっかく就職で東京に来たし、誘われた飲み会はとりあえず行った方がいいかな」「原稿ができてないのに、趣味の本や漫画を読むなんてダメかな」などと思い込み、自分の好きなものを遠ざけ、とにかく「原稿」「会社」「人とのごはん」を優先した。結果、ぶっ倒れた。
そして悟った。「私は趣味より仕事を優先するなんて無理だ」と。
その後、「できるだけ好きなものに触れる時間は削らない」ことをモットーに、自分にとってとにかくストレスを溜めないスケジュール管理法を試行錯誤している。
ストレスはよくない。他人に合う方法と、自分に合う方法は違う。あくまで自分にとって、できるだけストレスのない方法を探すことが大切だと思う。なので、この記事で紹介しているものも「三宅にとってはこういうやり方がストレスがないんだな……」と思うくらいに留めてみてほしい。
方法1:月単位と週単位で手帳を使い分けたら作業効率が上がった
まず前提として、私は会社の予定は全て、会社で指定されたOutlookで管理している。多少の変動はあるにせよ、会社の勤務時間はある程度決まっているため、それ以外の空いた時間でいかにやりくりするかを考えた。
そこで私がたどり着いたのは、「スケジュール管理」のためのマンスリー手帳アプリと、「タスク管理」のための紙のウィークリー手帳を使い分ける方法だ。「スケジュール」と「タスク」はちょっと違う。前者は主に予定やタスクのダブルブッキングを避けるため……つまり月単位の稼働量を把握して、キャパオーバーにならないように予定の調整をする目的で使っている。一方、後者はやるべきタスクを処理していくために、週単位の動き方を決めるためにある。
スケジュールは、副業の締め切りもプライベートの予定も全て手帳アプリ「Life bear」に記入している。予定は、副業の原稿〆切はえんじ色、病院やお店の予約は赤色、友達との遊びの予定などはオレンジなどと、スケジュールの内容によって色を変える。
このアプリのいいところは、マンスリーの予定が見やすいところ。連載などは基本的に月単位で〆切があるので、私は月ごとの稼働量をすぐに確認できるようにしたいのだ。いろんなカレンダーアプリを試してみたが、月単位で予定を確認・編集できて、カテゴリごとに色を変えられるものが一番便利だなあと感じた。
一カ月ごとの予定を表示させることで、副業の執筆の締め切りなどが重なっている日が見やすくなる。あんまり重なっていて「これは間に合わないかも、やばいなあ」と思うときは、できるだけ各媒体の編集者さんに「この締め切りって、ずらしてもらえますか……」と事前に相談するようにしている(それでも間に合わない時も多々ありますが、ごめんなさい)。
また、できるだけ重い原稿の締め切りの前日あたりは予定を入れないようにするなど、余裕を持ったスケジュールになるように心がけている。

この月は26日の締め切りが、本の原稿の締め切りでかなり重かったので、それをできるだけ締め切りのない1、2週目にやっておこう……そのあたりにはごはんの予定を入れないようにしよう……などの調整を自分で考えたりしていた
ちなみに、多くの人が使っているであろうGoogleカレンダーアプリもインストールしたことがあるのだが……Googleカレンダーは週単位で使うことを前提としているように思える(私が確認した環境では)。
例えば、「Life bear」では、7月の予定を見ているとき、画面に表示されてしまう8月や9月の日付はマス目自体の色を変えてくれている。しかし、Googleカレンダーの場合はわずかに日付の数字だけがグレーになっているだけ。あるいはGoogleカレンダーでマンスリーページから日付をタップして予定を編集しようとすると、一回デイリーのページに飛ぶのも地味にいらっとする。それゆえ、私にとってはLife bearの方が圧倒的に使いやすい。Life bear推しである。
一方で、タスク管理に使っているのは紙の手帳。私は、まず月曜日にアプリで今後のスケジュールを把握し、締め切りごとにタスクに落とすようにしている。例えば、「本の書評の締め切り」が新たにスケジュールにあったら、「本を読む」「何を書くか決める」「実際に書く」などのタスクに落とす。そして、そのタスクをそれぞれウィークリーの手帳に書き、いつやるかを決める。タスクに落とし込むときは、できるだけ細かいタスクに落とし込むのが大切だなあ、とよく思う。
昔はこの「ウィークリー手帳にタスクを落とす」行為を省いて、Life bearのスケジュールしか見てなかった。しかし、実際にタスクに落とし込んでみないと、それがどれくらい重い締め切りなのか、自分でもよく分からないのだ。
例えば、スケジュール帳で見れば同じ「書評の締め切り」であっても、「今まで読んだことのある本の書評(1200字)」なのか、「よんだことのない本一冊の書評(3000字)」なのか、「その作家に対する論考(8000字)」なのかにより、かかる労力は全く違う。私の場合、ウィークリーの手帳にタスクを落とすときに、「ぎゃっ、この本読むのに時間がかかりそうだから、二日とっとかなきゃだめだぞ」とはじめて気づいたりする。
忙しくなると、ついスケジュールに予定を入れるだけになってしまいがちの人もいるかもしれないが、スケジュールとタスクの管理を別々にするようになってから私は効率が一気に上がったので、この方法を続けている。
方法2:リマインダーとメモでタスクに取り掛かる負荷が軽くなった
しかし、性格の問題だと思うのだが、手帳にタスクを記入しても、私は「タスクにとりかかるまで」が異常に遅い。
タスクの処理は、始めるときが一番つらい。取り掛かるまでとにかく時間がかかる。……基本的に怠け者なのである。
なので、とにかく自分に「まずはこれに取り掛かろう」と思わせる工夫をする必要がある。
そこで、自分があんまりやる気のないときは、スマホに入っているリマインダー機能にタスクを入れるようにしている。
リマインダー機能は、消すまで永遠にスマホの通知欄に存在する。するとスマホを見るたび「ああ、通知消したい……」と思うので、リマインダーを消すためにそのタスクにとりかかることができる。さすがにまだ取り掛かってないのに通知を消すのは罪悪感があるので、「まずは取り掛かる」という最初の一歩を踏み出すことができるのだ。
このとき、先ほどよりもさらに小さいタスクとしてメモすることを心掛けている。例えば「●●の原稿を書く」よりは、「●●の原稿の字数を確認」の方がいい。自分にとってできるだけ楽にできるタスクから始めることで、一番気が重い、最初の一歩をなんとか自分に始めさせるようにしている。
ちなみに私は買い物や録画、Twitterでの告知など、仕事には関係ないタスクも同じようにリマインダーに記入するようにしている。リマインダーにメモする癖を日頃から忘れないため、という理由もあるが、単純に忘れっぽいからメモしておきたい性分なのだ……。
ただ、ここまでやっても、大変な原稿に取り掛かるのはしんどい。
そこで、「次回の連載で書きたいこと」や「次の原稿の書き出し」、「修正したい点」など、実際に原稿に書く前に、日頃の生活のなかでぼやっと考えていることをスマホにとりあえずメモしておくようにしている。スマホだと、あとで検索できるので便利だし、何よりタスクに取り掛かるときの取っ掛かりになってくれるのだ。
SNSの更新なんかも、基本的に下書きでメモしておいて、時間のあるときにちゃんと書いて公開したりしている。例えば、私はTwitterで読んだ本や漫画の感想を書くことが多いのだが、とりあえず読んだ本だけ下書きに書いておいて、後でちゃんと感想を書くようにすることも多い。「これあとで書こう~」と気軽に下書きにほいほい入れるようにしているのだ(まあ、下書きに入れる間もなく、その場で書いて更新することも多々あるけれど!)。
方法3:「意識的」に落ち込むことをやめたら無駄がなくなった
最後に、実は私がいちばん心がけているのは、できるだけ落ち込まないことだ。
基本的に、仕事は最初に立てていたスケジュール通りにならない。でも予定通りできなかったとき、落ち込み過ぎたり焦ったりして、自己嫌悪している時間がいちばんもったいない。スケジュール通りにできないことも、いつかはできるようになるでしょう、どうにかなるでしょう、と私は「意識」して楽観的に受け止めるように心がけている。
昔は「なんでできないんだろ!?」とよく自問自答していたのだが……とくに答えはでなかった。今はもう、その時間が無駄だなあと感じるようになったので、スケジュール通りできないことを受け入れることも必要だと私は思う。というか過度に落ち込むときは、そもそも寝てなかったり水を飲んでなかったり、体が疲れていることが多い。落ち込む前に体を休めた方がはやいことに私は気づいた。落ち込むときは寝よう。それが無理なら好きなものに触れよう。
自分に甘いっちゃ甘いのだが、まあ、落ち込んでても何も変えられないし。普通の人間が楽しく兼業仕事を続けていくためには、時にサボることも必要だと思う。ただでさえ、兼業はスケジュールが逼迫しやすい。でも、休まないのはよくない。サボって休息を作ることも、ある意味、働き続ける上で大切なポイントではないだろうか……!
適度にサボって、こまめにストレス解消をして、できるだけ楽しく兼業生活を続けたい。というわけでスケジュール通りにいかなくても、私は落ち込まないようにしている。
仕事はいつだってそこにある。それらとどう向き合い、有効に時間を使うかは、自分の心持ちや工夫次第で変わってくるものだと私は思う。
私も試行錯誤している途中なので、明日にはやり方も変わっているかもしれない。たぶん大切なのは、冒頭にも書いたけれど、今の自分の性格や環境に合った方法を見つけることだ。
副業や趣味の活動などをしているみなさん、健康に気をつけて、自分を追い込み過ぎず、ストレスなく働けるように頑張りましょう。私も頑張ります!
編集/はてな編集部
仕事のやる気もアップするかも? な関連記事
著者:三宅香帆(みやけ・かほ)

1994(平成6)年生まれ。会社員の傍ら、文筆家・書評家として活動中。著書に『人生を狂わす名著50』(ライツ社)、『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)、『副作用あります!? 人生おたすけ処方本』(幻冬舎)などがある。
Twitter:@m3_myk