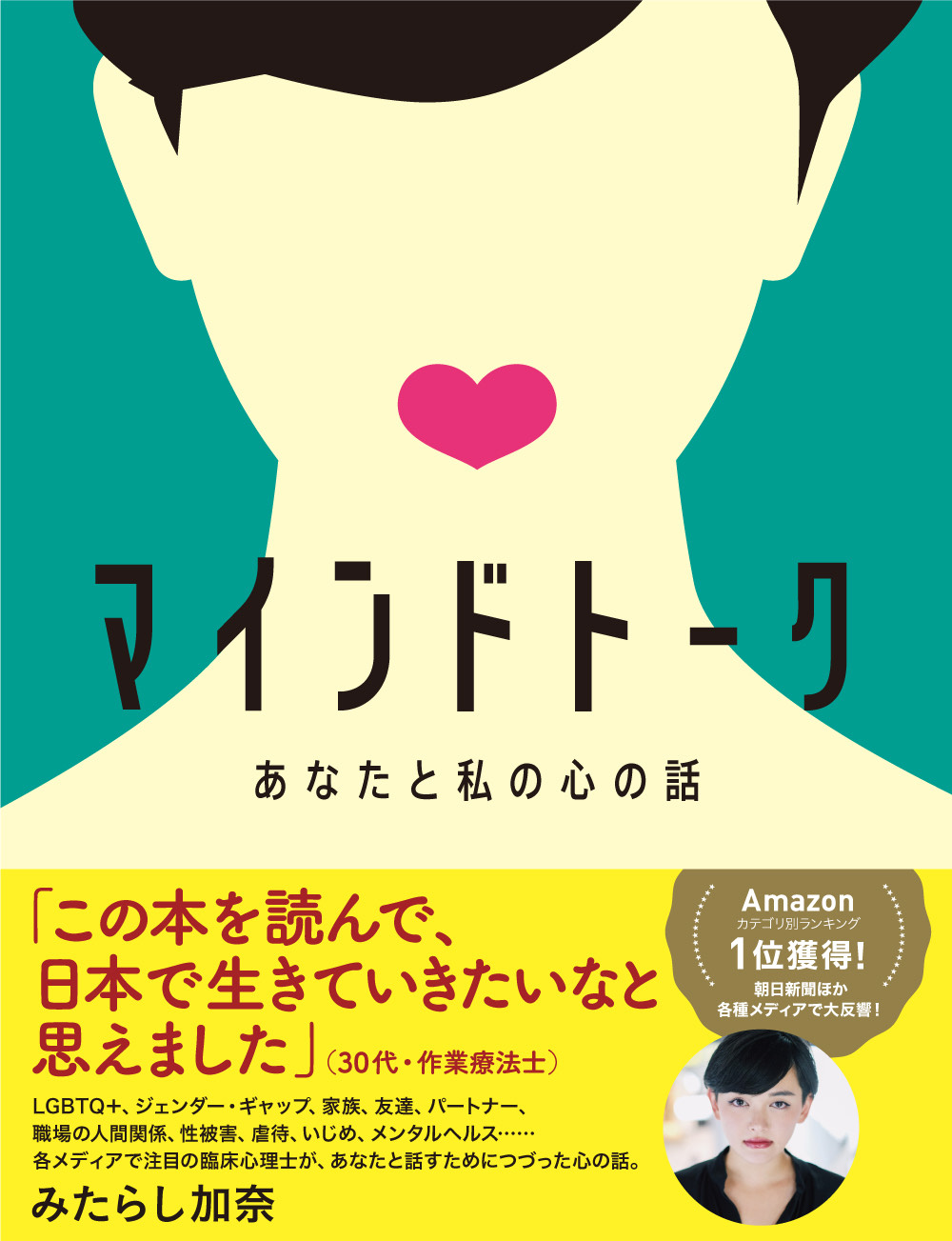日々の仕事を通じて感じた疲れやモヤモヤ、うまく解消できていますか? 中には、そういったマイナスの感情をどうやってリセットすればいいか分からず、毎日溜め込んでしまっている──という人もいるかもしれません。
『凪のお暇』や『珈琲いかがでしょう』などで知られる漫画家・コナリミサトさんの作品であり、2021年にドラマ化もされた『ひとりで飲めるもん!』は、「ひとり飲み」を通じて日々の仕事の疲れをリセットしたり、仕事の悩みや不安を整理したりする主人公・紅河メイの姿が描かれています。作者のコナミさん自身も、ひとりで「飲むこと・食べること」などを通じて日々のモヤモヤを解消しているそう。
今回は『ひとりで飲めるもん!』の制作背景とともに、コナリさん自身の「仕事で感じたモヤモヤ・イライラの解消法」について、オンラインでお話をお聞きしました。
作中の主人公のように、食を通じて仕事の疲れを癒やす
コナリミサトさん(以下、コナリ) チェーン店のような大衆的な場所でひとり飲みをする女の子の話が描きたい、というのがまずあったんです。私自身、もともとチェーン店でひとりでのんびり飲むのが好きで、こういうことをネタにできたら面白いかもしれないと思って。

「ひとりで飲めるもん!」1軒目より
(C)コナリミサト /芳文社
コナリ 例えば「すき家」とか「松屋」みたいな牛丼や定食のお店で飲むのも好きですね。すき家は、実はうなぎが毎年進化していてすごいんです。松屋は、以前話題になった「シュクメルリ」が本当に好きで……期間限定だったんですが、レギュラー化してほしいって思いました。
飲み屋さんでいうと、高円寺にある「大将」っていう焼き鳥居酒屋がすごく好きですね。
コナリ 大将はマカロニサラダが最高なんですよね……あと、個人的におすすめなのがフードコート飲みなんです。
コナリ フードコート飲みのよさ、あんまり知られていないと思うんですよ! いまはコロナの影響でちょっと難しいんですが、フードコートって本当に老若男女がおしゃべりをしている場なので、他人の存在を感じられるんですよね。近くのテーブルのお客さんたちの気配を感じながらごはんを食べたりするのが好きなんです。
コナリ 私、そういうスポットを探しながら常に街を歩いているというか、新しい飲みスポットを開拓するのがすごく好きで。風が気持ちよくて、そんなに混んでいない場所だと特にいいですね。デパートの屋上とかも好きですし。
コナリ そうですね。ただ、お酒は大好きなんですが「ネーム作業をしている期間は飲まない」って決めているんです。だから、ネームが上がったり原稿作業が一段落した日にする「雑な晩酌」がすごく幸せで……。もちろん外食も好きなんですけど、疲れている日の夜は、雑なごはんくらいがちょうどいいんですよね。
コナリ そうですそうです。お豆腐に塩をかけただけのものとか。最近はまってるのは、マキタスポーツさんがラジオで紹介されていた「10分どん兵衛」。それをさらにアレンジしたのが雑誌に載っていて。カップうどんのどん兵衛の縁ギリギリまでお湯を入れて、10分寝かせて麺をゆるゆるにしてから食べるっていう。小さいサイズのカップうどんって、おつまみにちょうどいいんですよ。
そういう、冷蔵庫と部屋を行ったり来たりするだけで済んで、お腹いっぱいになったらそのままお布団にダイブできるくらいの雑さがお気に入りなんです(笑)。その瞬間のお酒を目指して、毎日仕事を頑張ってます。

(写真左)最近は豆腐にごま油と味の素をかけたものにハマっているそう。
(写真右)10分どん兵衛には七味をどばっとかけて食べるとのこと
(画像提供:コナリミサトさん)
外ではバリバリ仕事をしつつ、飲むと「ほぐれる」人を描きたかった
コナリ メイは、いろいろな友人の合体系、という感じかもしれません。私の周囲には仕事をバリバリ頑張っている友人が多いのですが、外ではしっかりやっているんだろうけど、一緒にお酒を飲んだりごはんを食べているときは緊張がほぐれてフニャフニャな感じになってくれる子が結構いて、それがすごくいいなあと思うんです。みんな世代的にもどんどん出世したり責任のある立場になっていったりしているんですが、飲むと昔のままというか。
コナリ そうですね! 1990年代のアニメって、コミカルなシーンになったときに突然汗の粒が大きくなったり、走っているときに足がぐるぐると渦巻きになったりするじゃないですか。子どもの頃ああいった表現が好きだったので、自分の漫画のキャラクターにもさせたいなあと思って。メイの場合は食事とお酒で分かりやすく「ほぐれている」のが表現できそうだと思い、ここぞとばかりにああいう描き方にしてみました。

周囲が思わず見とれてしまうような雰囲気を持つメイが、チェーン店でのひとり飲みのときにだけ「ほぐれる」様子(「ひとりで飲めるもん!」5軒目より)
(C)コナリミサト /芳文社
コナリ 会社員あるあるみたいなエピソードの場合、友人の話を参考にさせてもらうことはわりとありますね。例えばメイの同期が転職してしまうエピソードなどは、同期の転職が決まって寂しいけれど引き止めるわけにはいかないし……という話を友人から聞いて、そこから着想しました。
自分の本心をさらけ出せる瞬間があることの大切さ
コナリ 会社を辞めようか悩んでいるメイが、劇場に映画を観に行くお話が気に入っています。女戦士が登場する映画を観て、「じゃあ、私はこれからどうしよう?」と自問自答するエピソードです。

高級寿司を食べた直後に入ったチェーン店での気軽さに癒やされながら、自分の今後について見つめ直すメイの様子(「ひとりで飲めるもん!」18軒目より)
(C)コナリミサト /芳文社
コナリ そうですね。メイは結局「このままこの会社に残って働くことがいまの私にとっての冒険だ」という結論にたどり着くんですが、あれ、我ながらいいせりふだったなと思っています。
「冒険」ってどうしても新しいところに飛び出していく際に使われがちだと思うんですが、必ずしもそれだけじゃないよなあという思いがあって。『凪のお暇』が会社を辞めるお話だったので、「でも、残るのも冒険だよな」と心のどこかでずっと思っていたのかもしれないです。

「ひとりで飲めるもん!」最終軒より
(C)コナリミサト /芳文社
コナリ 雑貨屋さんの店員をしていたことはあるんですけど、自分にはちょっと合わないなと感じて、わりとすぐに辞めてしまったんですよね。それ以降はいろんなバイトをかけもちしながら漫画を描いていたのですが、実は28歳くらいのときに漫画家を辞めようかすごく悩んだことがあって。つらい時期だったのでもはや記憶から抹消されかけているんですが……。
コナリ 私、デビューからずっと、全っ然売れてなかったんです。同じくらいの時期にデビューした周囲の漫画家さんたちがどんどん売れていっているのを目の当たりにして、もう私にはこのまま続けるのは無理かもしれないなと思ってしまって。
コナリ どうしてだろう……身もふたもないですが、他にできることがなさそうだったからというのが大きいかもしれないです。いろんなバイトを経験する中で、自分のミスが全員の連帯責任になってしまったりするような環境を経験して、これは自分には向かないなと。
漫画の仕事って、うまくいってもそうじゃなくても、全部自分のせいにできるのがいいところだと思っていて。だから、すごく迷ったけど結局描き続ける道を選んでしまいました。確か、その直後に描いた作品が『珈琲いかがでしょう』だったんじゃないかな。
モヤモヤは、作中の「面白いエピソード」にして消化する
コナリ 仕事でいま行き詰まっているなあと感じるときは、サウナとジョギングでリフレッシュするようにしています。サウナは、タナカカツキさんの漫画『サ道』を読んだのがきっかけではまりました。水風呂の存在を知れたのがデカイです。モヤモヤしているものを手放せる感じがするというか、スカッとできるので好きですね。
ジョギングは1年くらい前から運動不足が気になってやり始めたんですが、筋肉もつくし、半強制的に脳が休まるような感じがいいなって。ネームがどうしても思いつかないとき、なにか別のことを考えよう……と思って走ってみたら、たまにいいアイデアが浮かんだりもするので、最近はわりとよく走っています。もちろん、どうしても浮かばないときもあるんですけど……。
コナリ とにかく散歩をしますね。ただ、最近は暑くて外を歩くのもなかなかつらいので、家や仕事場の中を歩き回ったりしています。
コナリ 私はあまり編集さんとじっくり相談しつつ作っていくというタイプではないかもしれません。むしろさっきお話ししたように、お酒を飲みながら友人の話を聞いたりしているときに作品の原型ができていく方だと思います。
お酒の場で自分の悩みをようやく言語化できたり、「いまのせりふは〇〇のキャラに言わせよう」と考えたりしているので、コロナ禍になって気軽に飲みに行けない現状が本当につらいんですよ……。現実世界で言えなかったことやモヤモヤしていることをお酒の場を通してエピソードにし、それを漫画という形で消化しているようなイメージなんです。
コナリ そうですね……穏やかな言い方じゃないかもしれないですが、モヤモヤ・イライラしたことは漫画の中でできるだけ面白い話にすることで復讐している、というか(笑)。私は愚痴を人に聞いてもらうときは「面白おかしくすること」がせめてものエチケットだと思う方なので、漫画に描く際にもあまり生々しいエピソードにならないよう、一旦時間を置いて、激情に流されないようになった頃に少しつまんで出す、というのを心がけています。……あっ、それから、ひとりで飲みながら落書きする時間も日々の癒やしのひとつかもしれないですね。
コナリ ひとり晩酌しながら落書きするの、大好きなんです。さすがに仕事中は絶対にお酒は飲まないようにしてるんですが、そうじゃない時間はいくらでも飲みながら描けるので楽しいですよ! ほろ酔いで、自分の漫画のキャラのエロい絵とかを描くこともあります(笑)。本当にあっという間に時間が過ぎるので、やっぱり描くのが何より好きだなあと思いますね。
取材・文:生湯葉シホ 編集:はてな編集部
『ひとりで飲めるもん!』 発売中

芳文社刊
▶ひとりで飲めるもん!
お話を伺った方:コナリミサトさん