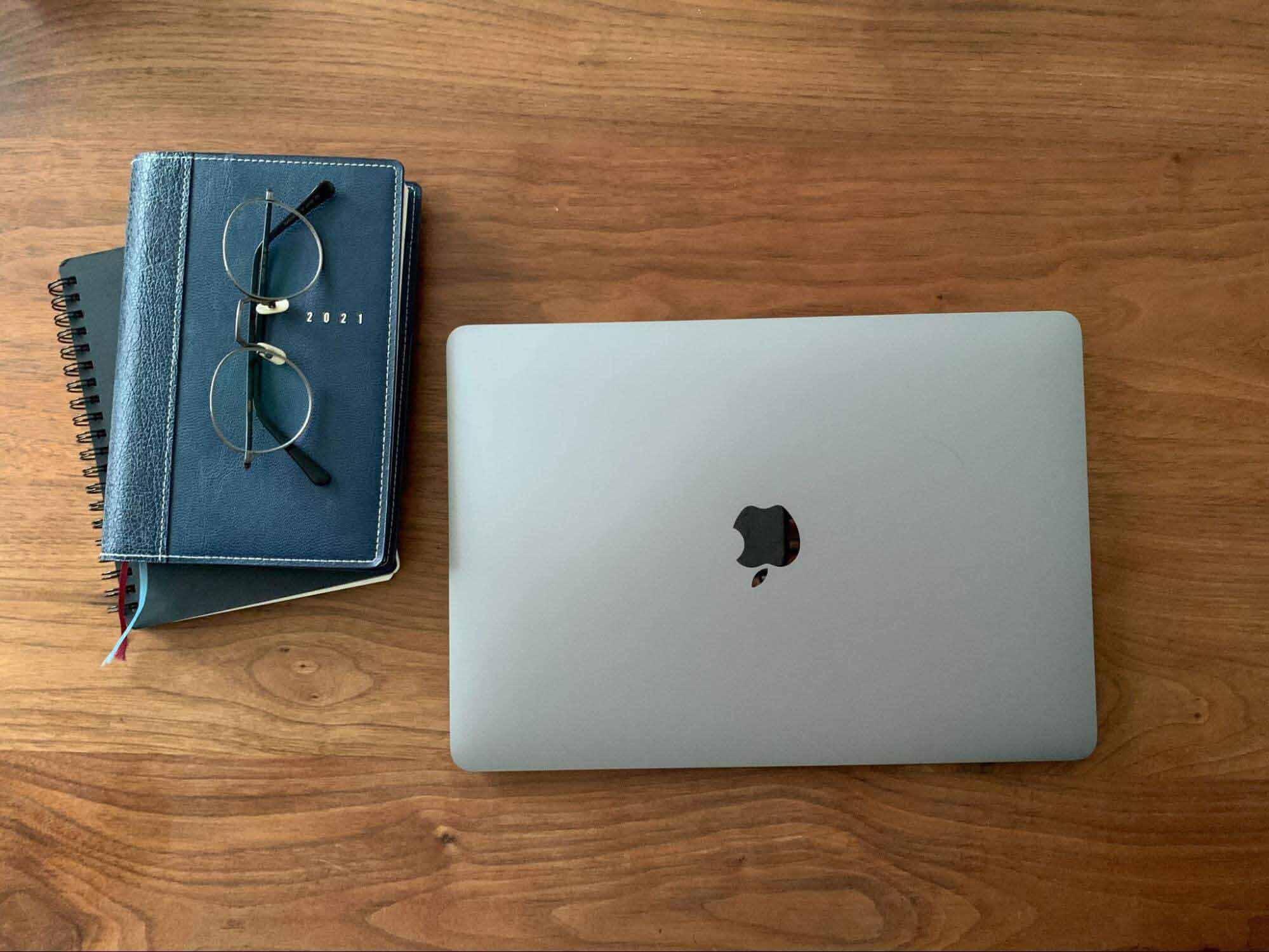フリーライターの宮崎智之さんは、数年前まで事あるごとにアルコールに頼り、不安を打ち消すようにテンション高く仕事に取り組んできたといいます。ただ、そんな生活を続けるうち、いつしか身体はボロボロに。以来、断酒を始め、息切れしない「平熱」の働き方を模索するようになったそうです。
今回は、作家・吉田健一の言葉をヒントに、断酒してからの5年間を振り返っていただきながら、息切れしないための働き方について執筆いただきました。
破綻を迎えたアルコールに頼った生活
息切れせずに働くのは難しい。特に根が真面目な人は、息切れするまで働かなければ、働いた気がしないのではないか。少なくとも僕はそうだった。
現在のように世の中が不安定だとなおさら、「一生懸命働いて他人と差をつけなければ」「休日も勉強をしてスキルアップを」と焦る気持ちを抱く人が周囲にも増えているように思う。だんだんと無理がたたって、最後は疲れ切ってしまいそうである。
ちょっと変な言い方になるが、ハードワークをしなくてもハードな仕事はできる。熱狂しなくても、「平熱」のまま創造的な仕事はできると、僕はこれまでの経験から思うようになった。
僕は離婚を経験し、30代前半でアルコール依存症となり、二度の急性膵炎で入院した。今は5年4か月、断酒を続けている。
振り返れば、新卒の会社を1年で辞め、夢だったメディア企業に転職して23歳で記者職についた。いずれはフリーランスの物書きになるという目標を持っていた。小さな会社だったけど硬派な編集方針のもと基本を叩き込まれ、追われるように20代を駆け抜けた。仕事は充実していた。しかし、全国区の雑誌や新聞に書くような物書きになって、自分の本を出版しながら暮らしていくという夢が諦めきれず、6年間勤めて転職した。
転職先である編集プロダクションの仕事も同じく充実していた。ただ、転職する少し前のあたりから、すでにお酒の飲み方は常軌を逸するようになった。勤務中に酒に手を出してしまう頻度も増えてきた。31歳のときにはフリーランスになり、傍から見れば順調なように思えるかもしれないが、その間もお酒の量はどんどん増えていった。
なぜ、当時の僕はそこまでお酒を欲していたのだろうか。
それは、不安だったからだと思う。いくら働いても働いた気がしない。もっとたくさん働き、もっとたくさん勉強している人はたくさんいる。自分のような凡人が、この程度しか努力しないで大丈夫なのだろうか。成長できない自分に焦燥感を覚えていた。
そんなとき、お酒を飲むと不安が忘れられた。気持ちが大きくなり、全能感に包まれた。
だから、その後も酒量は増え続け、次第にお酒を飲みながら原稿を書くようになった。お酒を飲んでいるといい原稿が書ける気がした。だいたいは酔いが覚めたら読み直して修正することになるのだが、とにもかくにもお酒を飲めばテンションが上がり、原稿は進んだ。仕事が終わったら酒をさらに飲んで、気絶するように眠った。枕元にあるお酒を一気飲みして、少し眠ってからシャワーで臭いを誤魔化し、取材に向かったこともある。
そしてあるとき、明確な破綻が訪れた。二度目の急性膵炎で入院した際に、「今後一切、お酒を飲まないでください」と宣告されたのだ。長く生きたければ、そうしなければいけない。離婚もして、心も身体もぼろぼろだった。そのとき、まだ34歳になったばかりだった。
平熱のまま生きるという挑戦
今思えば、「物書きは酒を飲んでなんぼ」という価値観が無意識にしみついていたようにも思う。確かに、そういう「熱狂型」の作家の人生から、たくさんの名作が生まれたのも事実である。しかし、僕にはそれを徹底することができなかった。徹底するには、心も身体も弱過ぎたのだ。
僕は働き方を変更しなければいけない必要性に迫られた。もしくは、物書きという仕事を辞めるかのどちらかだった。僕は前者を選んだ。
最初は、素面のまま面白い原稿が書けるのか不安だった。しかし、お酒を飲んでいたときに、「やめたら◯◯できなくなる」(例えば「やめたら華のない人生になってしまう」)と考えたことのほとんどは、思い込みにすぎなかった。ただかつてあったお酒のない人生に戻るだけだ。
お酒は、適度に嗜むことができれば「人間関係が円滑になる」などのメリットもあるので、その存在自体は悪ではない。僕に手に負える相手ではなかっただけである。一度目の急性膵炎で入院した後、「節酒」に挑戦したが、見事にリバウンドしてしまった。僕には、お酒をコントロールすることができない。しかし、正直、お酒にまったく未練がないかと言ったら嘘になろう。もう一度、あの全能感を味わいたい。フレンドリーになって、もっとたくさんの人と話したい。
でも、僕にはもう駄目なのである。再びお酒に手を出したら、元の酒飲みの生活に戻るに決まっている。そんな僕がお酒に再び手が出そうになったとき、寸前に止めてくれるのは「弱さ」である。どんなに節酒をしようとしてもコントロールできない。僕にはもう駄目なのだという「諦め」、「弱さ」を認める勇気、そういったものが、僕のストッパーになっている。
お酒をやめてから、少しずつ世の中の見え方が変わってきた。より詳細に見えるようになったと言った方がいいだろうか。考えてみればお酒を飲んでいるときは生活をしていなかった。少なくとも生活に向き合っていなかった。酔いに身を任せることで、自分の弱さを認めていなかった。
しかし、素面のまま、平熱のままで過ごしてみると、さまざまなものが目に入るようになってくる。文筆家の吉田健一は、「食べものの話、又」という随筆の中で、「何を食べても同じ味がする人間は、その人間の仕事に掛けても信用出来ない」*1と記している。「少なくとも、その人間がものを食べている時は頭が遊んでいることになり、そういうものが自分の仕事のことになると急に注意深くなるというのは、ありそうなことではあっても、俄かに信じ難い」*2とも。
これは本当にその通りだ。ほとんどの仕事は、生活に関わるなにかしらを提供している。生活をしていなければ、仕事ができないのは当たり前ではないか。日々の生活の中にも、じっと目を凝らせば未知のもの、不思議な現象がたくさんある。もちろん、生活は楽しいことばかりではない。試練も度々訪れる。しかし、それに向き合って生きていくこと自体が生活である。
そもそも人間は生活するために仕事をしているのだ。その生活が疎かになっていれば、いい原稿が書けるはずがない。試練や葛藤を乗り越えながら、または寄り添いながら生きていくこと。その態度こそが大切なのに、僕は階段の初めの一段で躓き、ずっと足踏みしていたのである。
まずは目の前にあるものをじっと見つめる。じっと見つめ続けて、小さな変化を感じとる。熱狂せず「平熱型」で生きることは退屈な行為でもなんでもない。むしろ挑戦的な生き方である。コロナ禍の今は、そうした「平熱」の息切れしない働き方に切り替えるチャンスでもある。
その証拠となるかわからないが、僕は昨年12月から、晶文社スクラップブックというサイトで「モヤモヤの日々」というコラム連載をしている。なんと平日毎日、17時公開だ。毎日ネタを探さなければいけない上に、書かなければいけない。毎日午前にその日の原稿を書いている。
コロナ禍で外出自粛をしているなか、ネタを探すのが難しいのではないかと思いきやそうでもない。じっくり生活に腰を据えてみると、いろいろなモヤモヤの種が次から次へと現れる。あと、この手の連載は「熱狂型」では続かない。熱狂するような刺激的なネタが毎日あるはずはないからだ。もしある人がいるのだとすればうらやましい限りだが、体を壊さず頑張ってほしい。
僕はそうでないので、周囲にあるものに執着する。外出自粛が続いたことにより気付くこともある。例えば、道端に咲く草花を綺麗だと思うようなった人は多いのではないか。実際に花の名前を画像で検索できるアプリがはやっているそうだ。コロナ禍になってから、草木が芽吹く日本の5月の美しさにあらためて気づいた。そんなことでも、コラムのネタになるのだ。
刺激的なことがなくても、日常生活に目を凝らせばクリエイティブの原資をたくさん見つけられると思っている。そもそも自分の親のことだって、大して知りはしないのだ。僕はその原資を、まだ3分の1も使いこなすことができていないような気がしている。
息切れしないために自らの欲望と向き合う
リモートワークが浸透し、一度起こった「オフィス離れ」は仮に新型コロナウイルスの感染拡大がおさまった後も、必ず出社や現場への移動が必要な仕事以外は、不可避に進むものと思われる。そんな状況では、各々が自らのモチベーションとうまく付き合い、意識的に生活と仕事(在宅ワーク)のバランスを整えることが、息切れせずに働き続けるために大切になる。
職場に行かなくなれば、対面での会議や朝礼などの集会、歓送迎会などが激減するだろう。そうなると、モチベーションの維持の仕方に変化が生じてくる。今までの企業はスタッフを一か所(職場)に集めて密をつくり、目標や課題を共有することで、社内の士気を保っていた部分がある。そこでは、情報だけではなく、熱が共有されていた。よくも悪くもそうした熱を共有することで一体感やモチベーションを高めることができた。
しかし、在宅勤務の流れが進めばそうはいかなくなる。当然、企業側は対策を迫られるが、スタッフ側も各々が各々でモチベーションを保たなければいけない時代になるのではないかと、僕は予想している。
ここで前述した吉田健一の文章を再び引用したい。「わが人生処方」という随筆のなかで吉田は、「どうも人間が生きて行く上では、各種の肉体的な欲望が強いことが大切だという気がしてならない。食う為に仕事をすると言うが、実際に食いたくて仕事をするのと、ただ食う為と思っているだけでは随分話が違う」*3と記述している。
つまりこういうことだ。人間は「食うため」に働くというが、「食うため」とはどういうことなのか。月給をもらうことなのか。原稿料をもらうことなのか。そうではなく、吉田は「どこそこの生牡蠣を五人前食ってやろうと思って仕事をしている」*4と言い切っている。
確かに「食う」とは抽象的なものではない。人間の具体的な欲望だ。「食う」というからには、なにかを「食う」のである。その「なにか」をまったく想像もせず「食うため」に働いているのだとしたら、それほど滑稽なことはない。吉田は「つまり、魂を失わずに生きて行く為に、肉体的な楽しみに執着することが必要なのであり、人間が出世するのは珍しいことではないのだから、そうなると益々食欲その他を旺盛にして、魂を繋ぎ留めて置くことが大切になる」*5と続けている。
吉田健一がふたつの「食べもの」のたとえで伝えたかったのは、抽象的、観念的な思考や生き方に陥り過ぎることの危険性であろう。先行きが見えない今だからこそ、目の前にすでにあるものをもう一度じっくり見つめ、点検し、そこから想像力を膨らませていくことが大切になる。
階段の初めの一段で躓き、足踏みしていないか。きちんと欲望を具体的なイメージで描けているか。そうした基本的なことを確認しながら前に進むのが、僕の思う息切れしない「平熱」の働き方だ。
編集/はてな編集部
ゆるやかに働くためのヒント
著者:宮崎智之