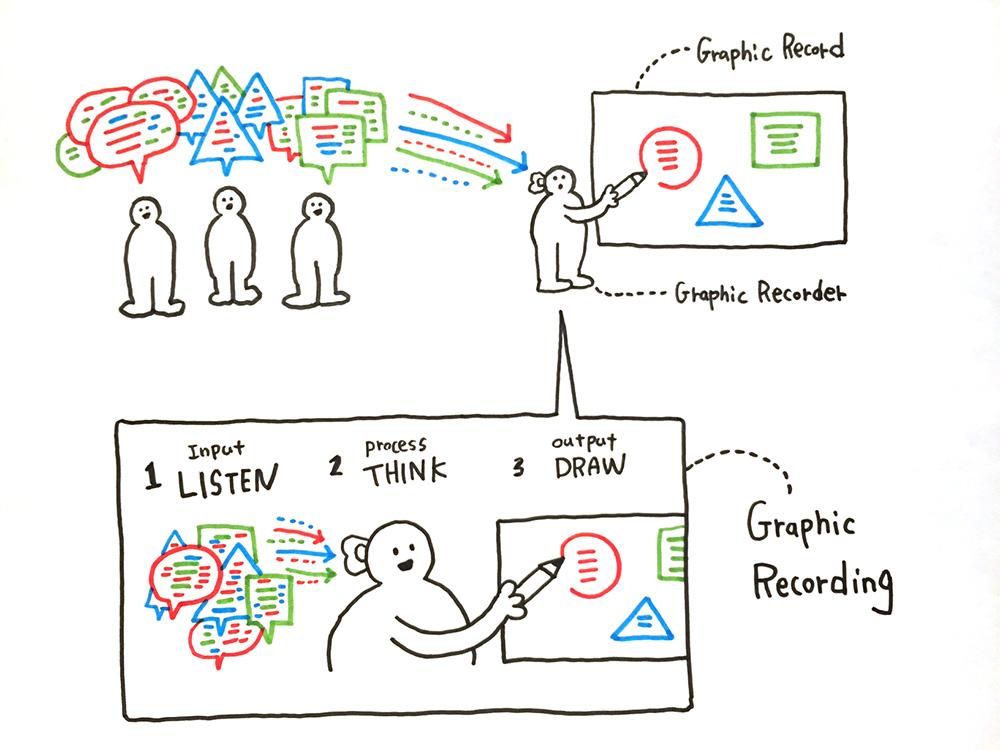キャリアを積んでいく過程で、「転職」を考えることもあるのではないでしょうか。ただ、子供に手がかかる育児中は、なかなか転職活動にかける時間を確保しづらいもの。また、子供がいると転職に不利になるのでは……と不安に思う人もいるかもしれません。
そこで、ママになってから転職を果たした3人の座談会を実施。転職のきっかけ、転職活動での苦労、成功するポイントなどについて、語っていただきました。
<<参加者プロフィール>>
「夢を叶えたい」「面白い仕事をしたい」そんな思いが転職のきっかけに
佐伯さん 私には子供の頃から「貧困問題の課題解決をしたい」という夢がありました。それを実現するために、必要なスキルや経験を身につけたいと思っていたので、ずっとひとつの会社にいるという発想はなかったんです。新卒入社以来、何社か転職して、昨年秋にソーシャルビジネス(社会問題の解決を目的としたビジネス)を扱う企業に入り、社内起業を目指していました。

佐伯さん その後、元同僚から教育事業の立ち上げに誘われて「このタイミングを逃してはいけない」と思い、今は退職して起業しています。
Tomoさん 私も子供の頃からの夢が、システム構築をすることでした。そういう意味では、新卒でSIer(システムインテグレータ)に入社して、希望だった職につけました。事業を拡大する途中の通信関連のシステムに関われたのもいい経験でした。
ただ、前の会社の仕事は、顧客のシステム構築を手伝うのがメインで、自分で何かを生み出す・作り出すというわけではありません。このまま同じことを続けていていいのかなと疑問を持ち始め……。ちょうどその頃、SEの情報交換コミュニティに参加するようになり、「自分が井の中の蛙だ」と思うようになって。同じ時期に、システムの構築から運用までトータルで手がけるSREという職が注目され始めたので、それができる会社に移りたいなと思いました。
はなさん 私は、何か明確な夢があったわけではなく、新卒で入った会社は「面白そうなベンチャー企業」という理由で選びました。そこから転職したきっかけは、地方に作った事業所への異動を求められたことです。次は、育児休業中に、自分が新規事業で手掛けた会社のM&A(会社の合併・買収)が決まったため、復職と同じタイミングで転職しました。自分のタイミングで転職しているんですが、基本的には「どこかに移ったら面白そう」「今転職すれば面白いんじゃないか」という気持ちを持っていました。

はなさんはリモートで座談会に参加
佐伯(敬称略、以下同) 私は主に、選択肢を増やす目的で転職エージェントを利用しました。人材サービスの会社にいた時は転職エージェントが顧客だったので、各社のメリットをよく知っていたんです(笑)。タイプの違うエージェントをいくつかピックアップしていました。最後の転職では5社くらい受けました。
はな 私は、転職エージェントを利用したり、知り合いのつてで会社を紹介してもらったり。ママになってからの転職は、カジュアルに会社訪問させていただいたところも含めると、10社くらい受けたと思います。
Tomo 私の場合は、SEの職歴が長かったこともあって社外の同業の知り合いが多く、その人たちから情報収集したり、実際に紹介してもらったりしました。同業であれば「あの会社は雰囲気が良さそう」「この会社はすごく厳しい」など、事前にある程度評判が分かるんです。そこから興味のあるところ、よさそうなところを絞り込んで、アプローチしました。最終的に5社くらい受けました。
働くママの転職は、時間との戦い!
佐伯 圧倒的に「時間がない」ことでしたね。昼間は仕事があるし、夜は保育園のお迎えや子供たちの世話があるので、面談に行く時間がない。ですから、エージェントとの面談は、可能な限りオンラインか電話にしてもらいました。
佐伯 はい。転職活動期間が長くなると、肉体的にも精神的にも負担が大きいと思ったので、候補の会社を絞り込んで短期集中でやりました。夜の面談が続く場合は、夫の出張中に自宅から2時間くらいの距離にある実家に居候し、父母に子供たちを見てもらったことも。やっぱり、独身だった時や子供がいない時とは違うと身にしみましたね。
Tomo ものすごく分かります! 夫婦ともに実家が遠いので頼れず、たくさんの会社を受けたいという気持ちはありましたけど、併行して活動できたのは2社くらいが限界でした。転職用のレジュメを作るのにも時間をとられるので、睡眠時間もかなり削られます。

Tomo 当時は、朝3時に起きてレジュメを作り、家事をして会社に行って、帰りに子供のお迎えに行って、夕食を食べてぱたっと寝る……という感じでした。夫は転職に対しては反対することはありませんでしたが、家事・育児を率先してやってくれるタイプじゃなかったので、「少し手伝ってほしかったかな」というのも本音です。
はな 私の場合は普段から夫が家事や育児に協力的で、転職活動中も、面談で家を開ける時は子供を見ていてくれたので助かりました。でも、当時は子供1人でしたからね。今のように子供2人になってから同じようにできるかというと、難しいでしょうね。
佐伯 勤務時間が条件と合わないことはしょっちゅうありました。子供がいない時なら「いくらでも働きます」とか「気合で頑張ります」とか言えるかもしれませんが、夜遅くまで仕事をすることが必須だと、諦めざるを得ません。
はな 私も転職活動の最初の頃、いいところまで行くのに最終的に断られることが続いてしまって、エージェントに理由を聞いたら「似たようなスペックで、子供がいなくて時間の制約もない人がいたら、そちらを選びますよね」ってダイレクトに言われて。その時はさすがに、「私はハンデを背負っているんだ」と凹みました。
でも、その後の面接からは気持ちを切り替えて、「二人目の子供を考えています」と積極的に言うようにしましたし、それを「いいことだよね」って言ってくれる会社を選びたいなと思うようになりました。そうでないと、実際に働いていけないですしね。
佐伯 子供がいる以上、柔軟な働き方をさせてもらえない会社は厳しいですね。転職活動を進めるにつれ、そういう融通がきく会社かどうかは、面接の時の話しぶりなどからだんだん分かってくるようになりました。
それぞれの事情に合わせられる「柔軟性のある職場」を選び取る
Tomo 転職の理由の一つに、前の会社で働き方への違和感が出てきたということがあります。妊娠中に夜中まで仕事することもありましたし、復職後も、制度はひと通り整っていたものの、実態に合ってない内容もありましたから。例えば「子の介護休暇」を取得するのに、事前に何枚も書類が必要になったり……。こういう働き方を続けるのは、自分にとっても子供にとってもよくないなと思っていました。
はな 私も最初の妊娠中は、新規事業の立ち上げの真っ最中で、仕事で終電を逃してタクシー帰りが何度もあったので、それはよく分かります。
佐伯 私が妊娠中に転職した会社は、ママでも働ける環境は整っていたんですが、フルタイムに近い形でだんだん時間に押し潰される感じになっていって、最後はしんどかったんです。平日に子供たちを病院に連れていくと、その分土曜日に補わなければいけないとか。もう少し余裕を持った働き方をしたいと考え、上司に相談し、融通を利かせてもらいました。また、その次の会社では思い切って、最初から9時〜16時の時短勤務で、必要ならリモートワークも可能という形で採用してもらいました。
Tomo 私も、いくつか会社を受けた中で、転職先が唯一「最初から時短勤務でいい」と言ってくれたんです。あとは社内に働くママがいらっしゃったのも決め手になりました。心強いし、自分が働くイメージも湧きやすい。面接では、エンジニアのトップの人が、実際に保育園の送迎の予定が入ったスケジュール帳を見せてくれて「自分もこうだし、あなたも子供のことを第一優先で考えていいですよ」と言ってくれたんです。そういう考え方の会社で仕事をしたいと思いました。
はな 私も、転職先の候補に残った会社には、実際の働き方を聞きたかったので「働くママがいれば話をさせてほしい」とお願いしていました。その希望に対応してくれるかどうかで、企業のマインドが分かりますよね。
結局、転職を決めた今の会社では、私が“働くママ第1号”になったのですが、フレキシブルかつ本質的なことを大切にする会社なので、非常に働きやすいです。面接の一環として会社のミーティングに呼んでもらった時に、「5~15分の遅刻の報告は、生産性がない会話だから勤怠報告を撤廃します」という宣言があったんです。そういう意識が共有されていると、朝に子供がぐずった時でも「始業時間に少し遅れそう!」とカリカリせずに済みますよね。働くパフォーマンスを上げるためなら、有給休暇も自由に取っていいと言われています。
佐伯 制度がキッチリ決まった大企業より、少人数の会社の方が融通がききやすいかもしれませんね。個人への信頼があって、アウトプットをきちんと出していれば、細かい報告はいらないというような。私は、妊娠中に転職した会社にいる時に、産休中・復職後と後に続く人のために、就業規則を自分で作りました(笑)。子供が小学校に上がるまではコアタイムなしのフレックスにする、リモートワークの時間や日数の制限はなしにするなど……。そういう働き方を認めてもらえる会社だったのは、ありがたかったです。

身近な家族からアドバイスのプロまで。周りへ話をしてみれば応援してくれる人はいる
Tomo 社外の同業者や、働く先輩ママ、以前一緒に仕事をした人ですね。特に一緒に仕事をしたことのある人からは、自分の強み、弱みを客観的に言ってもらえて、参考になりました。
佐伯 私は前回の転職ではコーチングのサービスを利用してみました。子供たちが1歳を過ぎ一息ついて、改めて自分と向き合って、今後のキャリアを考えようと思ったものの、ゆっくり時間はとれない。ならば、プロの力を借りれば短時間で考えがまとまるんじゃないかと思って。キャリアのことや家庭についてもやもやしていることを吐き出して、それをコーチングの人と一緒に整理したら、自分がやりたいことがクリアになりました。それで転職への一歩が踏み出せたので、よかったですね。
Tomo 確かに、誰かに客観的に整理してもらうことで、自分の心の中の本音も、ぽろっと出てきたりする気もしますね。自分の悩みに対して、「こういう考えもあるんじゃない?」って指摘してくれる人もありがたい。そういえば私も、年上の社外の同業者で、お子さんをお持ちの方に、よくアドバイスを受けていました。
はな 私は強いて言うなら、元同僚だった夫ですね。あとは、過去に書いたブログやメモを見て自分を振り返って、「今なぜ転職したいのか」について考えてみたり。でも自分だけで考え込むこともあったので、振り返ってみればコーチやメンターの人がいたらよかったなと思います。
佐伯 やはり夫の理解がないと、チャレンジは難しかったですね。支えられているなとは思います。
Tomo 私の夫は、先ほど言った通り家事や育児を手伝ってくれるタイプではなかったですが、ある会社に落ちて落ち込んでいる時に「就職は縁みたいなもの。縁がなかったと思えばいいんだよ」と言ってくれて。よくあるせりふだし、自分でも分かっていることですが、実際に言葉に出して励ましてくれると、救われるなと思いました。

はな 転職活動中、うまくいかなくて心が折れそうになることってありますよね。縁がなかったとはいえ、会社に不合格と言われると、自分が否定されているような気分になるし。でも、子供と接していると、気が晴れてきます。まあいいか、この子は私のことを「大好き」って言ってくれるし、って(笑)。
Tomo 自分を肯定してくれますからね。私も凹んだ時は子供にハグを要求していました(笑)。
途中でやめても、立ち止まってもいい。小さな1歩が今後の糧になる
佐伯 私もかつては「子供ができたらキャリアはどうなるのか」という漠然とした不安がありました。でも働くママになるのも、転職するのも、やってみないと分からない。やってみたら意外に何とかなるし、協力してくれる人も出てきます。だから、思い切ってチャレンジしてみては、と思います。もちろんパワーもいるし時間もかかりますが、先輩でも友達でもコーチングでも、間口を広げていろいろな人に相談してみれば、何か道は見えると思います。
Tomo 昔に比べたら、子供がいることが不利にされることは減ってきたと思うんです。それは先輩ママたちが苦労してくれたおかげですね。そこに甘えつつ、でも、さらに自由に働いていきたいです。「子供がいることが不利になる会社は、こちらからお断り」くらいの気持ちでいた方がいいと思うんです。今は育児の話ですが、そのうち介護も出てくるかもしれない。働く人それぞれの事情に対処できないような会社では、人が働き続けられないし、将来も危ういと思いますから。
はな 転職をしたいという気持ちがあれば、何か少しでも行動をしてみたらいいと思います。転職エージェントに問い合わせてみるだけでもいい。小さな1歩でも、前に進めば、何か今後の糧になります。また転職活動を始めてからでも、途中で家族が体調を崩したり、自分のメンタルがしんどくなったら、ストップしてもいいと思います。他の会社を見てみて「やっぱり今いる会社がいい」と思えば、前とは違うマインドで仕事に臨むこともできますし。あまり肩肘はらず、休憩もしながら、一歩一歩を積み重ねていければいいのかなと思いますね。
編集:はてな編集部
※座談会参加者のプロフィールは、取材時点(2020年2月)のものです