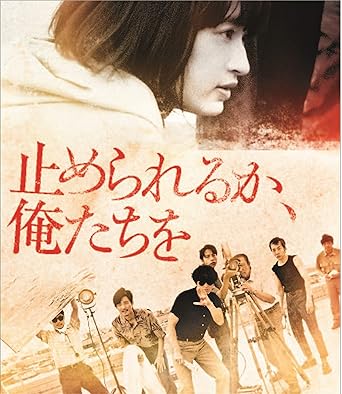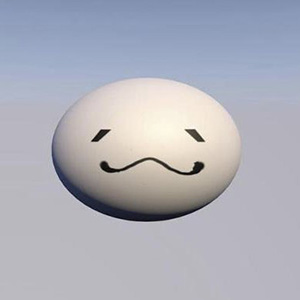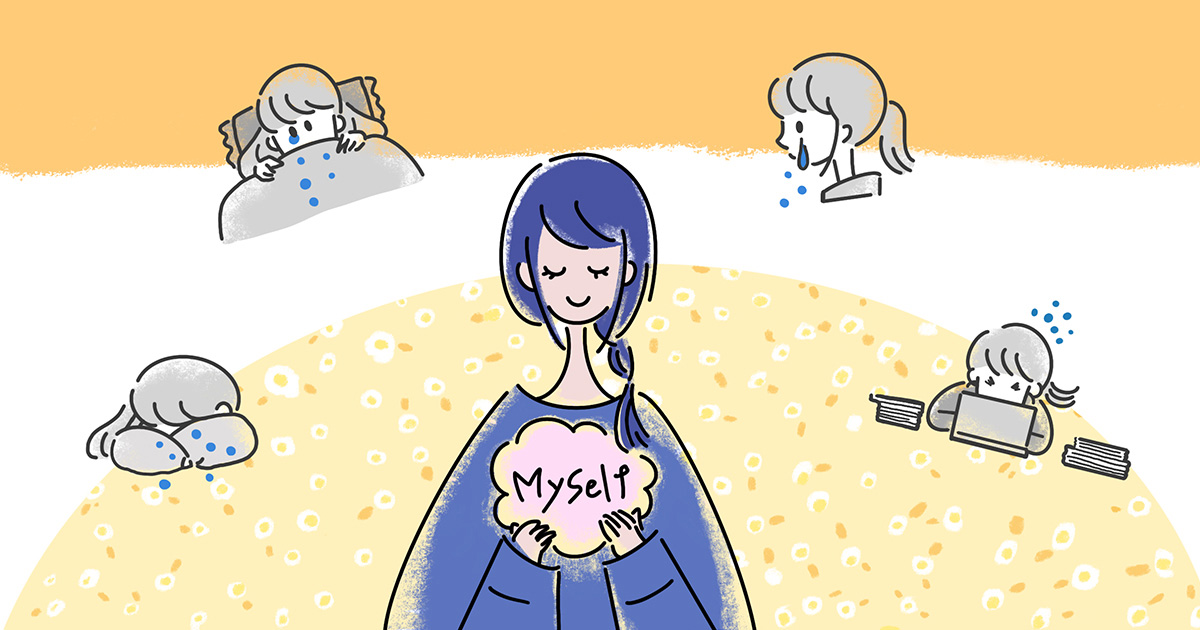武蔵大学准教授であり、さまざまな芸術作品をフェミニスト批評という観点から読み解いた『お砂糖とスパイスと爆発的な何か 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』の著者・北村紗衣さんに、1935年に公開されたフランス映画『女だけの都』を紹介いただきます。
作中で描かれる男女の関係性は、2020年時点の日本社会にも共通する点が多いのだそう。今を生きる私たちと85年前の作品との共通点や、そこから見えてくるものとは?
※ 編集部注:以下には、作品内容に触れる情報が含まれています
管理職に就く女性がまだまだ少ない日本の現状
女には何もできない、専門的な仕事や政治などは男のものだ、という考えは長きにわたり、男性のみならず女性を縛ってきた。現在の日本にもそうした風潮が強くあり、国会議員の女性比率は先進国で最低レベル*1、管理職に占める女性の割合もG7最下位*2だ。
これは日本の女性が努力していないとか、能力がないからそうなる、というわけではない。 政治家の性差別発言が後を絶たないことからも分かるように、社会システムが女性が議員になったり、管理職になったり、自由にやりたいことをすることに対して著しく消極的だからそうなる。
この記事では、そんな状況と、頭を使ってこれを切り抜ける女性たちを描いた映画『女だけの都』(La Kermesse héroïque)を紹介したい。1935年という昔に作られたフランスのモノクロ映画である。悲しいかな、日本に住む女性が置かれた状況は、この85年も前に作られた映画と比べられるところがたくさんある。
モノクロ映画の時代に描かれた「女性が働く」姿
ジャック・フェデー監督の『女だけの都』は、1616年のフランドルを舞台にした歴史ものだ。舞台は現在のベルギーにあたる地域の町、ボームである。スペイン軍がやってくるという知らせを聞いたボームの男たちは怖じ気づき、町長が急死して服喪中だというウソをでっち上げて雲隠れするが、一方で町長夫人コルネリア(フランソワーズ・ロゼー)率いる女たちはスペイン軍を迎えて立派に外交業務を果たすという物語である。
本作は、基本的に歴史をネタにした諷刺コメディだ。作中にも若き画家ジャン・ブリューゲルが町長夫妻の娘シスカの恋人として登場するが、映画全体がブリューゲルなどのフランドル絵画を思わせる魅力的なビジュアルコンセプトにそって作られている。この映画で描かれているスペイン軍のボーム来訪は史実に基づいて描かれているわけではなく、むしろ翌年からナチスドイツがヨーロッパの各地で進駐を開始することを考えると、過去を振り返るよりは近未来に起こりそうなきな臭いことがらを予想するような作品であったと言える*3。
この映画は、冒頭からボームの女たちが忙しく働くところを丁寧かつ生き生きと見せている。町長夫人をはじめとする女たちが家や店を切り盛りするため動き回る様子が、まるでブリューゲルの絵のように表現されている。一方、男たちは女たちに比べると動きが少なく、町のお偉方は集団肖像画を描いてもらうところだ。
記念の肖像画というのは権威を示し、虚栄心を満たすためのものであり、町の男たちは権力にこだわっていることが分かる。ここから読み取れるのは、どうやら男たちは自分の見栄のせいで気付いていないが、実際はボームの町は女たちの仕事のおかげで回っている、ということだ。男たちは女の力を認めておらず、町長は娘の結婚相手をどうするかについて町長夫人と言い合いになった時(町長はブリューゲルが気に入らず、助役を娘と結婚させたがっている)、女は口ばかり達者だとか、家に帰って大人しくしていろとか、バカにしたようなことばかり言っている。
しかしながら、女の力を軽く見ているボームの男たちは、実際はその働きなしにはやっていけないくらい、女たちに頼っているのである。女たちが働くのは当たり前だと思っているから、男たちは評価しないのだ。
「檻」に閉じ込められがちな現代社会を予期している?
これを見て「現代の日本と同じだ!」と思う方もいるだろう。日本の政府は女性活躍推進法*4などというものを出しているが、こんなものがなくても、日本の女性はすでに社会のいたるところで活躍している。子供を育て、家事をしながら外で働いたり、お店や農家などを切り盛りしているのだ。世間は無償かつ不可視化された女性の労働で回っているのに、男たちがそれに気付いていないだけだ。
映画は人の生活をのぞき見するようなメディアだと言われることもあり、ふつうなら見えなくなってしまっているような隠されたものを見せるのが得意だ。『女だけの都』は1935年の時点で、女の仕事がこなせて当然のものとして評価されなくなってしまうような状況を認識し、面白おかしく洒落た映像で描き出していた。ところがこの偉そうにしている男たちは、急場ではさっぱり頼りにならない。スペイン軍が町にやってくると聞いた時、町のリーダー格である男たちは町中で略奪や虐殺が行われ、女は全員強姦されるだろうと予想し、情景を思い浮かべて震え上がる。
この男たちがスペイン軍の乱暴狼藉を想像する場面はけっこう暴力的で生々しいタッチで描かれているのだが、男たちは女をこうした残虐な戦時性暴力から守るために立ち上がるどころか、町長が急死したという話をでっちあげて雲隠れすることにする。男は強くて女を守るものだというような建前は全部吹っ飛ぶ。町長夫人が忌々しげに言うように、「ひげもズボンも銃だって役に立ちゃしない!」のだ。
町長たちがニセの急死事件をでっちあげると決めたところから、女たちの逆襲が始まる。町長夫人は女にも政治をする力があると主張し、女たちの前で大演説をする。最初は不安になっていた女たちも町長夫人の演説に鼓舞され、スペイン軍との外交交渉に乗り出すことにする。ここで、何人かの女たちが最初、伝統的に男のものとされている仕事が自分たちにできるのだろうか……と心配そうな発言をする。
これは、あまり女性が進出していないような分野に興味を持った女性がよく陥る思考回路だ。女性がやりたいことをやろうとする時に邪魔になるのは外側からの抑圧だけではない。女性に限ったことではないが、人は社会の偏見や思い込みを吸い上げて育つので、知らず知らずのうちに見えない「檻」を自分で作って入り、自分の行動を制限してしまうことがある。
あんなことは女にはできないとみんな言っているから自分にもできないのじゃないか、こんなことをしたら世間から批判されるのじゃないか……というような不安がこういう「檻」を作る。この檻から出るのは一苦労だが、ボームの女たちにとっては町長夫人という人望あるリーダーの後押しや、他の女たちと協力してやるんだという絆の感覚が檻を破るきっかけになる。ひとりでは怖くてできないことも、志を同じくする者同士で集まって連帯してやれば楽しく実行できるかもしれないのだ。
『女だけの都』における恋愛の描き方

町長夫人は見事な采配で人員を配置し、スペイン軍の歓待準備を整える。幸運なことに、やってきたスペイン軍は噂ほど残虐ではなく、魅力的で礼儀正しいオリバレス公が率いていた。感じのいい女たちによる丁寧な歓待にいたく喜んだスペイン軍は、暴力的なことは一切せずに町で休むことにする。オリバレス公はどうも頭が良くて成熟した女性が好みらしく、夫を亡くしたばかりで寂しいというふれこみの町長夫人が醸し出す色香に夢中になってしまう。町長夫人もまんざらでもなさそうな様子だが、一方で政略は忘れておらず、オリバレス公に頼んでその権限でさっさとシスカをブリューゲルと結婚させてしまう。
他の女たちも男たちの監視の目がないのをいいことに、色男の兵士たちと宴席で盛り上がる。1935年の映画なのでそこまで露骨ではないが、それでも相当に艶っぽい描写がたくさんある。このあたりで女にも性欲があり、いい男がいれば惹かれるということを非難なしに面白おかしく描いているのがこの映画の楽しいところだ。
もうひとつ面白いのは、女たちと遊ぶのにあまり興味がなく、宴会そっちのけでスペインの軍人と町の男が手芸について語り合って盛り上がる場面があることだ。明示されてはいないが、この2人はゲイなのではないかと思わせる描き方になっている。少々コミカルではあるが、他の登場人物に比べてバカバカしいとか、ネガティヴだとかいう表現にはなっておらず、たくさん人がいれば同性愛者や宴会嫌いがいても当然で、そういう中でいい出会いがいろいろありますね、というような雰囲気で場面が進む。この映画は、恋愛についてかなりおおらかな描き方を貫いている。
摩擦を回避しつつ要望も通す町長夫人の姿に重なるもの
最後、オリバレス公の軍は女たちとの別れを惜しみつつ、出発する。ボームの町は女たちの働きのおかげで1年間の税金免除特権を獲得するが、町長夫人はこの功績について、全く役に立たなかった夫に花を持たせ、町民たちの前で夫を褒める。この場面は一見、町長夫人が従順な妻に戻って終わったようにも見えるのだが、夫が調子にのる様子を見せる一方で、カメラは町長夫人の微笑みとも寂しさともつかぬ微妙な表情にフォーカスする。
この場面が示しているのは、町長夫人は娘の結婚や自分とオリバレス公の間に起こったことについて夫にああだこうだと言わせないため、わざと夫を持ち上げているのだな……ということだ。税金免除が町長夫人の功績であることはおそらく町の人々はうすうす感づいていると思われるし、誰が見ても町長夫人の方が一枚上手なのだが、ここで夫をおだててやれば自分の地位は今後も安泰だ、ということだ。
正面から抵抗するのではなく、策略を使って自分のやりたいことを通す町長夫人のやり方は、すごく不満なことがあるけれどもなかなか声をあげられない……ということも多いであろう日本の女性にとってはとても共感できる終わり方かもしれない。
著者:北村紗衣
編集/はてな編集部
*1:参照:女性議員の割合 日本165位 先進国で最低水準 | 注目記事 | NHK政治マガジン ※2019年時点の情報。閲覧日:2020.01.17
*2:参照:世界の女性管理職比率は27%、ILO 日本はG7最低 :日本経済新聞 ※2019.03.07発表。閲覧日:2020.01.17
*3:BBC Gloucestershire Films - Carnival In Flanders (La Kermesse Héroique) Review
*4:参照:女性活躍推進法特集ページ








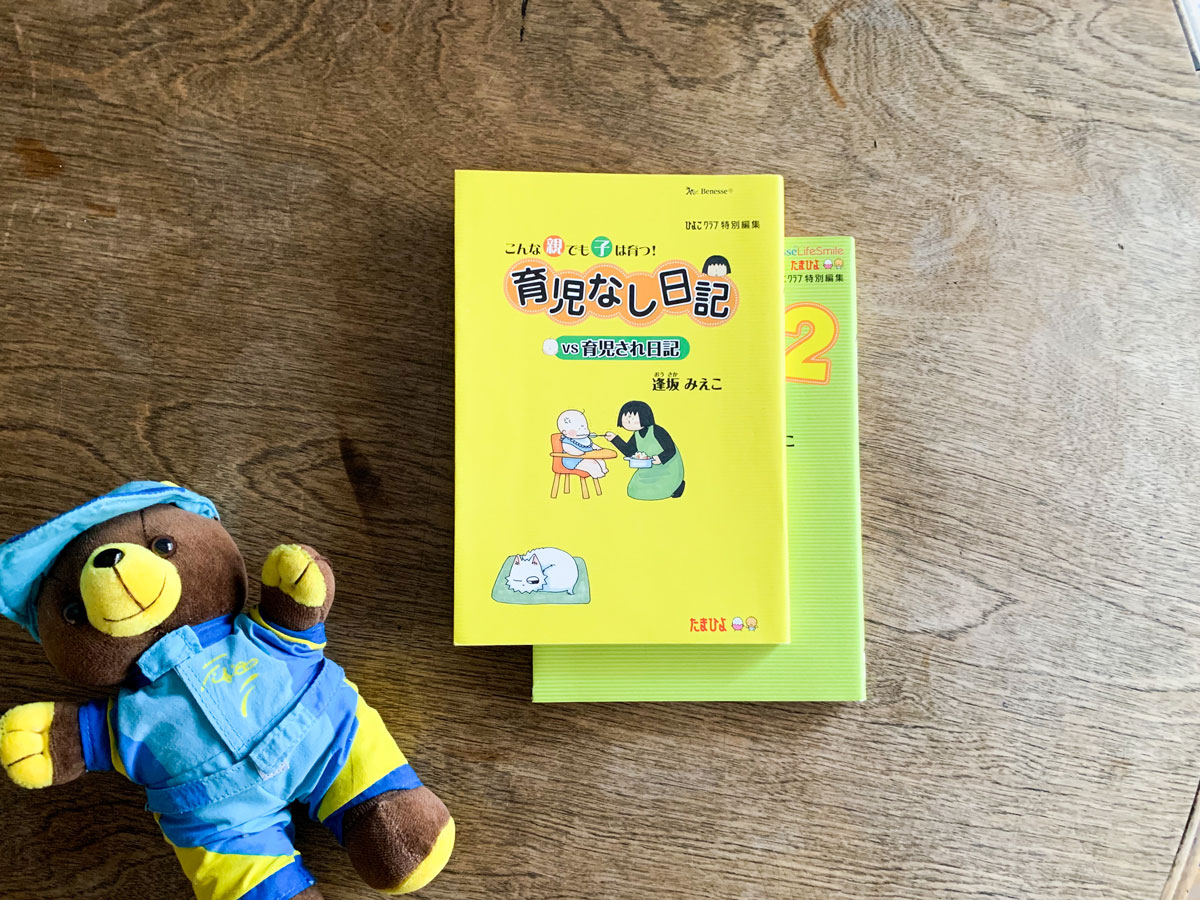
 女子マンガ研究家。1977年生まれ。「マツコの知らない世界」に出演するなど、テレビ、雑誌、ウェブなどで少女/女子マンガを紹介。自宅の6畳間にはIKEAで購入した本棚14棹が所狭しと並び、その8割が少女マンガで埋め尽くされている。
女子マンガ研究家。1977年生まれ。「マツコの知らない世界」に出演するなど、テレビ、雑誌、ウェブなどで少女/女子マンガを紹介。自宅の6畳間にはIKEAで購入した本棚14棹が所狭しと並び、その8割が少女マンガで埋め尽くされている。


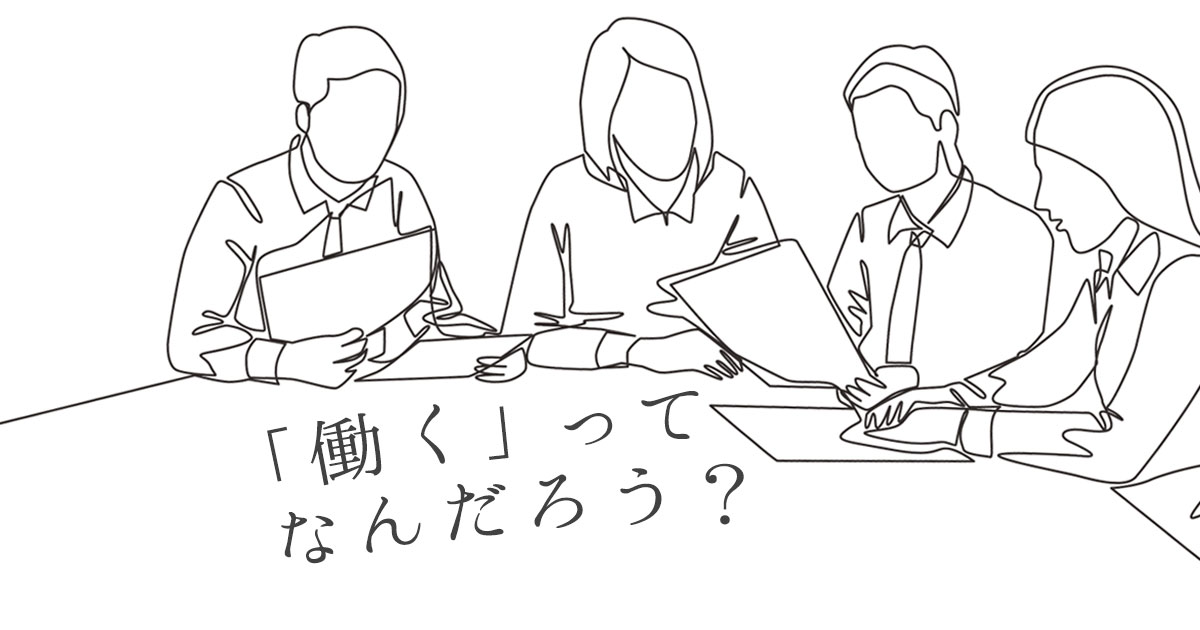
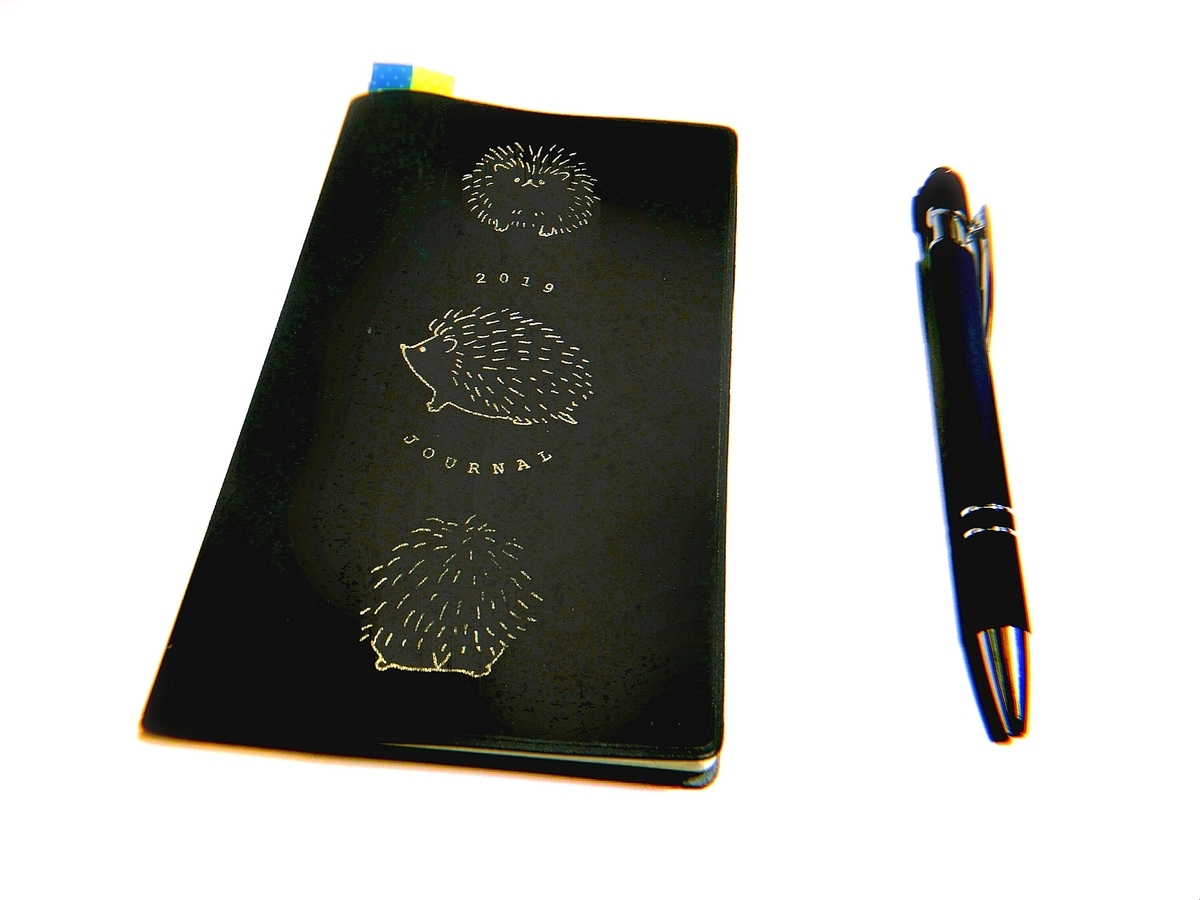
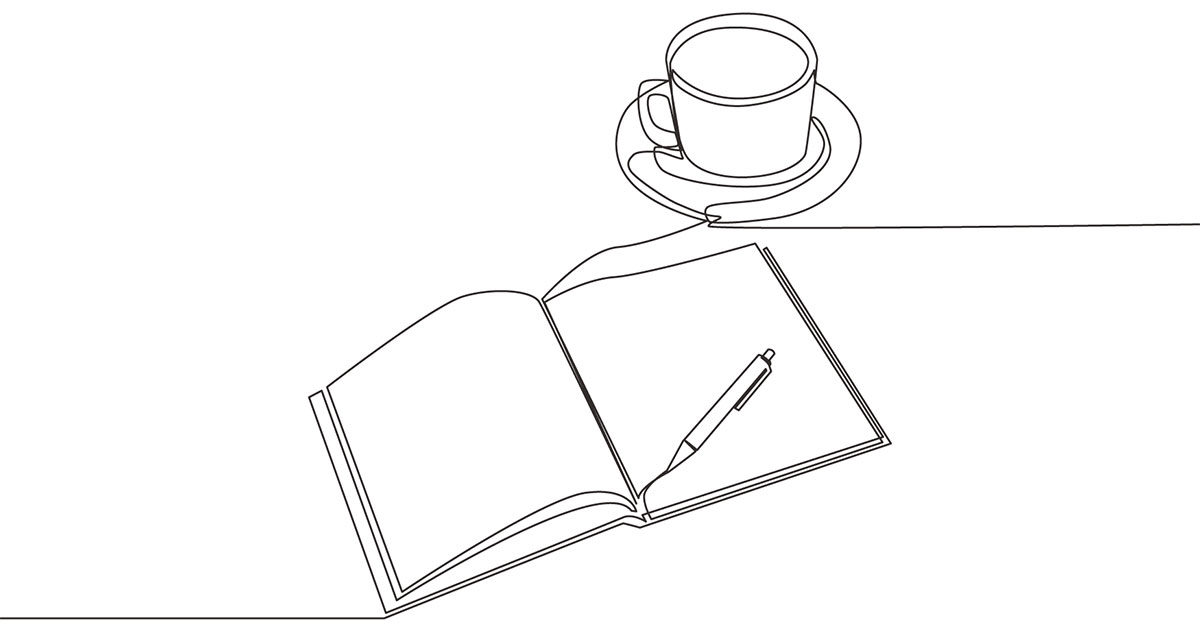











![コーヒーが冷めないうちに 通常版 [DVD]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91dmexxDkhL._SY445_.jpg)
![21世紀の女の子 [DVD]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Xgh79QPnL._SX569_.jpg)