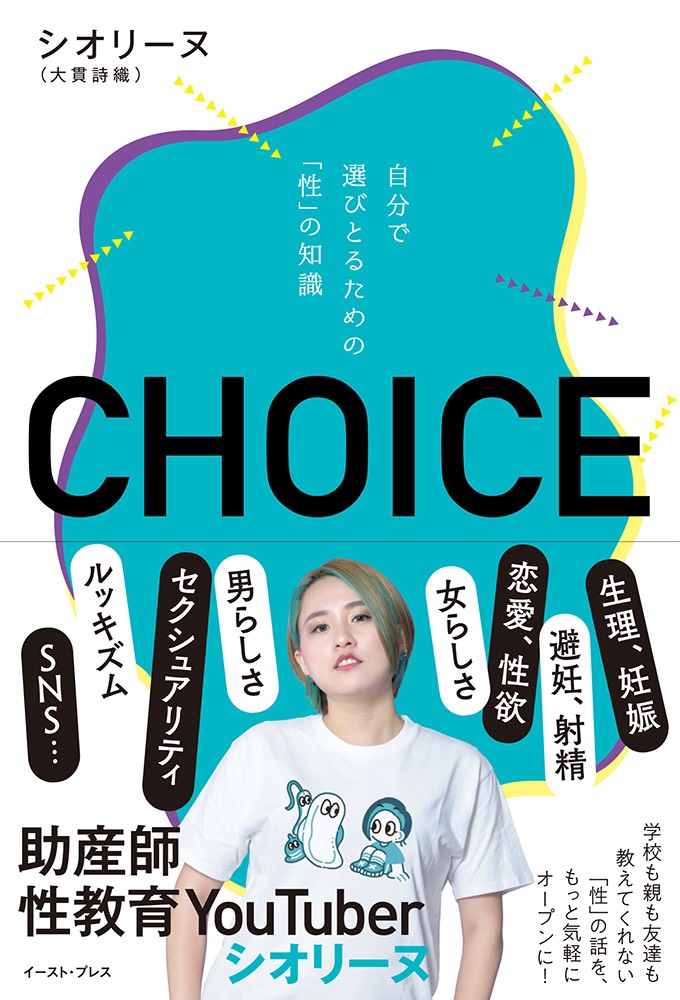小川さやかさんは、東アフリカのタンザニアを中心に商人たちの経済活動を研究する文化人類学者。著書の『「その日暮らし」の人類学~もう一つの資本主義経済~』などでは、未来に縛られず「今」を生きる商人たちの姿を報告しており、その日本とは対照的な彼らのあり方は、私たちが当たり前だと感じている「働き方」や「人間関係」を捉え直すヒントを提供してくれるかもしれません。
そこで今回は、日本の状況と照らし合わせながら、タンザニア商人たちの柔軟性あふれる仕事観や人間関係の捉え方についてお話を伺いました。
※取材はリモートで実施しました
仕事にこだわりは持たない。タンザニア商人の労働観
小川さやかさん(以下、小川) 「仕事は仕事」って言葉自体は日本でもよく使われると思うんですが、「仕事なんだから、つらくても割り切ってまじめに取り組もう」という文脈のことが多いですよね。でもタンザニア商人たちの場合はちょっと違って、「どんな仕事でもいいときと悪いときはあるんだし、いずれ飽きるからこだわりを持ち過ぎない方がいいよね」みたいなニュアンスなんです。
タンザニアの人たちって、お給料が高かったり安定した仕事に就いていたりする場合でも、突然に「飽きた」と言って仕事を辞めるんですよ(笑)。もちろん本当の理由は分からないですが。それで、そのあとに自分で新しいビジネスを始めたりする。
小川 私も最初はすごく驚いたんですが、いいお給料がもらえる仕事って当たり前ですけどそれなりに大変な仕事であることも多いですよね。また、安定している仕事かもしれないけど、そのためにはボスの顔色を常に窺わなければいけない、ということもある。
それに、彼らにとって雇用されるというのは、自分がなんらかのビジネスを始めるための貯金の期間という位置づけであることも多いです。いつかもっと儲かることに挑戦したいから、いまの仕事にはこだわり過ぎないでいつでも機敏に動けるようにしておこう、という。
スペシャリストを目指し、一貫性を持つことがよいことだとされる日本の価値観からすると妙かもしれませんが、社会環境が急変しやすいタンザニアではそれよりも柔軟性が求められるんだと思います。もちろんタンザニアにも職人のような人はいますが、私が調査対象にしている商人たちの多くはそういった価値観です。

小川 おそらく、日本でもずっと昔からいまのような状況だったわけではなく、高度経済成長期のあとに若者が一斉に就職した時代を経て、ひとたび終身雇用が価値観として定着したことは大きいと思います。終身雇用自体は変容しつつありますが。
もちろん長期的な視点で考えて、数十年後にもなくならないような仕事を選んでなるべく長く続けるというのはとても合理的な判断だと私も思います。しかし日本ではなぜこんなに起業や転職のハードルが高く見積もられるようになってしまったんだろう? という疑問もあります。
小川 そうですね。いま、新型コロナの影響でこれまでの仕事を維持できなくなってきている人が世界的に増加していると思うのですが、タンザニアの人たちは本当にあっという間に仕事を変えるので、近くで見ていても驚かされます。
例えば、日本ではお店が潰れそうになってしまったらクラウドファンディングをしたり、その事業をなんとか維持させることに心血を注ぐ方が多いと思うんですが、タンザニアの商人たちは、自分のお店を売ってまったく違う仕事を始めたりするんです。
小川 実際に貿易関連の仕事をしているタンザニアの知人のなかには、新型コロナの影響で中国との取引ができなくなり、即座に自分のお店の在庫をぜんぶ処分し、それまでに儲けたお金を全投資して養鶏場を始めた人がいます。私から見ても「取引が再開されるときまでせめて店は残しといたらええやん、なんで急に養鶏場?」って感じなんですが、彼は「また中国でビジネスができるようになったら、そのときは養鶏場を売ればいいんだよ」と(笑)。
小川 アフリカはこれまでにもコレラがはやって全ての飲食店が閉まったり、エボラがはやって物流が止まったりといったことを何度も経験しているので、日本や先進諸国とは新型コロナのとらえ方にも違いがあるかもしれません。
それに、私が過去に調査をしていたアフリカの商店街では、行政がもっと商店を増やすと一方的に決め、古い商店を全て壊すと急に言い出したことがありました。だから感染症に限らず、“不条理さ”を織り込んで生計を考えている側面もあります。すぐに割り切れるわけではないですが、コロナに対しても、数ある不条理な出来事の一つ、という態度の人が多いのを感じます。
もはや会社も不要? 彼らが次々と新たな仕事を始められる理由
小川 以前、古着の路上商人に仕事を始めたいきさつを聞いたら、「市街地でひとつ50シリングで売っていたオレンジを買って、それを自分の居住区で100シリングで売ったのが最初だった」と話してくれたことがあります。
彼は日雇いの仕事をクビになってしまい、手持ちのお金が底をつきそうで悩んでいたときに、ふと目についたそのオレンジで商売をすることを思いついたそうです。その街と自分の居住区を1日何往復かしているうちに無事にごはんを食べられるようになり、オレンジの行商人になったと。そうしているうちに小銭が貯まったので、じゃあ次は服を売ってみようか……という感じでやっていったそうなんです。
小川 その理由は、営業許可の申請などをせずにしているインフォーマル経済だからというのも大きいですが、彼らの多くは生計多様化をしていて、そもそも一つの仕事に専念しておらず、その仕事以外にも不動産経営や配達といった仕事をいくつかしているケースが多いんです。だから、仮にうまくいかなかったらそのビジネスだけ畳んでほかの仕事に回そうという発想がありますし、だからこそ新しい仕事にスピーディーに取り組むんだと思います。
小川 いえ、タンザニアの行商人たちもいまはみんな、スマホで商売をしています。これまではどこかで仕入れた服や雑貨を持っていってオフィス街や住宅街で買い手を探すという形でしたが、いまはもうコミュニケーションアプリやSNS上で注文を受け、必要な商品だけを市場や商店街に探しに行き、必要な人のところに最短ルートで届けるというUber Eatsのようなスタイルも増えていますよ。だから商店に行くと、みんなスマホで商品を撮影して「どれがほしい?」と画面の向こうのお客さんに言ってます。
小川 先にも述べたように、彼らのような零細で不安定な自営業者たちはインフォーマルセクター*1と呼ばれていて、かつては偽装失業層などと呼ばれ、フォーマルな会社組織を立ち上げる前の段階として理解されていたところがあります。近年、そうした単線的な発展図式は研究者の間で再考されてきましたが、研究の理論動向に関係なく、インターネットが発達した今や、彼ら自身の間で「会社なんて作る必要ってある?」という考え方がより現実的になり、どんどん仕事の幅を広げているようにみえます。
例えば、タンザニアにはネイルアートの行商人というビジネスがあるんですね。10年ほど前までは、ネイルアートのサンプルをいくつも持ち歩いて行商するというスタイルだったんですが、いまはお客さんがネット上で「いますぐネイルしてほしいです」と連絡すると、いちばん近くにいるネイルアート商人がやってきてネイルしてくれる……というような感じなんですよ。
小川 だから、インフォーマル経済が次第にフォーマル経済になっていく、すなわち企業や組織へ発展していくという状態へと全てが向かうのではなく、インターネットを介した新たなインフォーマル経済へと発展していくものも多いのではないか、という予想をしています。逆に、日本や先進諸国のように、企業やシステムがある程度完成されている国で新たなプラットフォームをどう使いこなしていくか、というのはとても難しい問題だと感じています。
小川 いま、アフリカでは「リープフロッグ現象」が起きていると言われています。日本語に訳すと「蛙跳び」なんですが、固定電話が普及していなかった国で携帯電話が普及するとか、教科書が足りていなかった学校にシリアスゲーム(教育目的で使われるゲームアプリ)が導入されるとか、先進国が持っていた既存の社会インフラや制度などを飛び越えて新技術が入ってくるという現象です。アフリカではそういった新技術と自律分散型の社会のあり方が偶然にもマッチして、社会が急速に変化しつつあるんですよ。
でも逆に、日本のように既存のインフラがきちんと整備された社会だと、新技術や新しいインフラを導入しようとしたときに「安心安全に使える制度や法定通貨がこれだけ普及しているのに、どうして電子マネーや仮想通貨を使わなければいけないんだ」「これだけ既存の資本主義経済が国を発展させたのに、どうして自律分散型のプラットフォーム資本主義のような不安定なものに乗らなければいけないんだ」と考える人もいます。
小川 もちろん、アフリカにはそもそも企業の社会保障の恩恵を受けられない人が多いという別の問題はあるんですけどね。そういった現象が、新興国と先進諸国とのあいだでいま起きているのは事実です。
一貫性の背後には「説明責任」を求める監査社会がある
小川 そもそも日本の人たちはあまり態度が豹変しない、というのもあるかもしれないですね。例えば、タンザニアだと、ついこの前まではすごく羽振りがよくて「お金なんてぜんぶ俺が出すよ!」と言っていた人が、きょうは虎視眈々と私の財布を狙っているみたいなことがあります(笑)。でも、彼も羽振りがいいときにはすごくいい人だったのを周りも知っているので、「また状況がよくなってきたら付き合えばいいや」と思うこともあります。
小川 そうですね……。日本では、本当に追い詰められたときにおろおろと泣き出したり、逆ギレしたりといった態度をすると、普段は立派な人格としてコントロールしている“彼/彼女”は見せかけで、本性が出た、みたいな理解をしますよね。
タンザニアの人って、しんどい状況にある人を見ておおらかに笑うことがあるんですよ。それを最初に見たときはひどいと思ったんですが、よくよく話を聞いていると、笑われている側もそれほど気にしていないんです。彼らは常にピンチと隣合わせで生きているので、窮地においていかに変身、つまり豹変してそれを乗り切るかが大事だと了解もしています。だからピンチのときに豹変する人を見て、もしかしたら「これはこの人が生き抜くための知恵かもしれない」と考えるのです。したたかな逞しさ、生命力かもしれないと。
むしろ、そのときの状況によって態度が変わるのは当たり前と考えているところがあります。だから、ペルソナ(仮面)と本性というような二元化された人格観ではないんです。

『チョンキンマンションのボスは知っている アングラ経済の人類学』
香港の地でビジネスを行うアフリカ系商人たちの営みを記録している。本書でも彼らの裏切りが描かれている
小川 それって、ごく近代的な“監査文化”が生み出した価値観だと思うんです。いまやもう私たち誰もが、他者を評価して説明責任を求めるということを身体化してしまっているんですよ。春日直樹氏が書かれた『遅れの思想』に分かりやすく書かれています。
小川 例えば、報告書や成績表といったなんらかの指標を用いて自分のパフォーマンスを管理者に説明するというのが分かりやすい“監査”ですが、それだけではなく、芸能人が浮気したときに謝罪会見を開くといった慣習も監査文化が生み出したものだと思います。テレビの視聴者やTwitterの投稿者として、みんなでみんなを評価して監査し合うというのがふつうになっている。
小川 説明責任を常に求められる社会になると、あとから説明できるような行動を常にし続けていないのはおかしい、という考え方になりがちです。しかも、他者が他者を評価するという土壌の上に資本主義経済がうまく乗って、さまざまな“憧れの私キット”みたいなものを提供しようとしてくる。
コスメや洋服、あるいは職業や資格といった「こんな自分になれますよ」というバラエティ豊かなキットが売られていて、私たちはついその先に見えている“望ましい私”になるためにキットを買い、がんばってそれに追いつこうとするわけです。けれど、“望ましい私”は未来からの逆算でしか成り立たないので、常に先にいて永遠に追いつけない。
小川 いま、それがもう限界値に達しかけていて、みんなしんどくなっているんだと思います。けれどそれは全世界的に起きているのではなく、資本主義経済と結託した社会特有のできごとなんですよね。資本主義経済は“私キット”を売れば売るほど儲かるから。
小川 そうですね。もちろん私のタンザニアの友人たちも、努力するのはいいことだと言います。ただ、努力した結果としてなにか失敗をしたり人に迷惑をかけたりしても、関係のない人にまで説明責任を果たす必要はない、と語ることが多いです。迷惑をかけた人には当然謝るけれど、そうじゃない人に「あいつはだめなやつだ」と言われる筋合いはないと。
それに、そもそも一貫した自己というものが極端に規範化していないので、自分の意見や主義主張も違うと思ったら柔軟に変更する人も多いですね。相手の意見が真っ当だと思ったら「そうかも。ごめん、俺もきょうからそうするわ」と。
小川 コロコロと意見が変わるとちょっと疲れますけどね(笑)。タンザニアの人間観は最高だから日本も見習うべきだ、というふうには決して思わないです。
ただ、日本で監査文化が浸透し過ぎてしまって、自分の権内と権外の区別がつかなくなっている人が多いのは怖いことだと思います。監査社会のなかでは、人は常に自分自身をコントロールすることを求められる。だから他者に対しても同じようにそのコントロール権が及ぶと思ってしまって、ネットメディアで見ず知らずの他者を過剰に叩いたりすることにもつながるように思います。
小川 コントロールしきれたらいいけど、本当は自分自身ってままならないものじゃないですか。私も「きょうはがんばろう!」と思っても寝てしまったりするし、急に風邪をひいたり急な相談をもちかけられたり、自分がコントロールしきれないことってたくさんありますよね。それを乗り切ったときに褒めてもらえるのではなく、「乗り切れるのが当然だ」と人に言われるのはしんどい……って私は思っちゃいますけどね。
小川 本当にね(笑)。だから日本の人はすごいなあ、とは思うんですが……。「自分だってこんなにままならないんだから、ほかの人もたぶんそうだろう」と思えれば、誰かが大きな失敗をしたり信頼を失ったりすることがあっても、いずれまた付き合えるだろうとおおらかに受け止められるような気はするんですけどね。
変化を受け入れ、貸し借りのスパンを延ばしてみる
小川 確かに、日本の人は貸し借りのスパンをすごく短くとらえがちかもしれないですね。タンザニアの人たちにも決して借りの感情がないわけではないんですが、将来の見通しが不確定なので、そのスパンがもうすこし長いんです。
「仕事を病気で◯日休んでしまったから、復帰したらすぐに◯日分は挽回する」という考え方って、借りを返すまでのスパンがすごく短いじゃないですか。でも、病み上がりでいきなり挽回するのって実際はすごく大変だと思うんです。タンザニアの商人たちの場合は「自分にもうすこし余裕ができたら周りを助けよう」という感じで、周りもすぐに借りをとりたてようとしないんですよね。
小川 そうですね。その人が返せるときに返してくれればいいよ、という。日本にもそういった文化はあると思いますが、いまの私たちは“贈与”がとてもしにくい社会を生きていると感じます。つまり、親切心から人になにかをしてあげたりしてもらったりしたときに、本来はそれが返ってくるとは限らないのに「早く返してほしい」「早く返さなきゃいけない」と思ってしまう。
それは、もうただの交換なんですよね。常に未来を先取りしてプランを立てていくことに慣れていくと、贈与に対するお返しまでもがプランに組み込まれてしまうんです。そのスパンをすこしだけ伸ばして考えられたら、もうちょっと気楽になれる気がするんですが。
小川 人生の保険として人間関係の貸しをたくさん残しておくと、自分がいずれなにかで困ったときに周りを頼ることができますしね。日本の人たちはみんなまじめだっていうのは世界的な評判なんですが、「それが苦しいんだよ」って言うと「え~」って言われます(笑)。もうすこし気長に長期的なスパンから人間関係をとらえることができたら、それがいちばんよさそうですよね。
取材・文:生湯葉シホ (@chiffon_06)
編集:はてな編集部
お話を伺った方:小川さやかさん
*1:統一的な見解はないが、一般に政府の雇用統計に載らない零細な自営業や日雇い労働を意味する