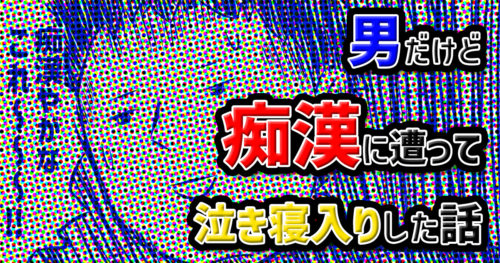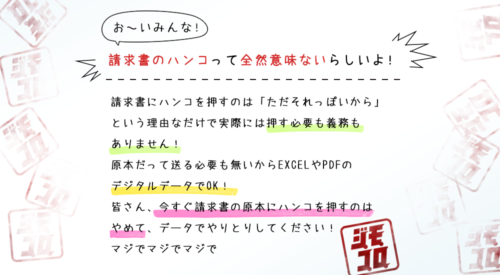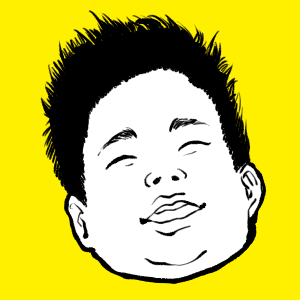こんにちは、上田啓太です。
「京都ひきこもり大演説」の第二回です。本日は、ひきこもり生活で起こることについて書きたいと思います。
「ひきこもっていると、自分に肉体があるという当り前のことが不思議になる」
これが本日の話の要約です。しかし、すこし分かりにくい話になりそうですし、なにより観念的な言葉遊びに聞こえてしまう可能性もありますので、まずは私の子供のころの話をきいてください。
呼吸を意識しすぎて病院に行った話
小学校低学年のころ、自分が呼吸をしているということが気になって仕方ありませんでした。きっかけは単純でした。
「人間は呼吸というものをしている」
親か、教師か、とにかく誰かにそんなことを言われたんです。それで意識してみると、たしかに自分は呼吸というものをしている。つまり、鼻から空気を出し入れしている。口でも空気を出し入れしている。なるほど、これが呼吸か、と思いました。
「ちなみに、呼吸しないと人は死ぬ」
誰かの話はそんなふうに続きました。それで驚いたわけです。これをしてないと、僕は死んでしまうのか!
当然、心配になりました。
「ちゃんと呼吸しないとな。呼吸を忘れるのヤバいな。死ぬもんな」
ほとんど戸締りやガスの元栓でも気にするかのように、呼吸のことが気になりはじめたんです。もちろん呼吸というのは無意識になされるものですが、子供の自分にはそれが分からないから、「僕が見張っていなくちゃ」と思ったんです。
そして、ノイローゼのようになりました。
何をしていても、自分が呼吸できているか確認しないと気がすまない。しかし、そんなことを常に意識していると、当然、他のことに集中できない。何をしていても半分くらいは呼吸に意識が向いてしまう。ウンザリしました。
そして母親に言いました。
「最近、ずっと呼吸が気になる」
母親は「は?」と言いました。これはまあ今なら分かります。たしかに「は?」となるだろう。しかし私は必死でした。
「なんとかして!」
で、病院に行ったんですよ。
といっても、近所の内科です。風邪なんかひいたときに行っていたところ。母親といっしょに病院の先生に相談しました。今でも覚えてますが、先生も困惑していました。
「まあ、しばらく様子をみてください」
それだけ言われて、帰されました。
「サジ投げてんじゃねーよ!」と今なら思いますが、当時はそれでいよいよ「どうしよう…」と思いました。これから僕は、ずっと呼吸のことを気にする人生なのか……ぜんぜん楽しくない……でも呼吸を忘れたら死ぬし……。
それからも呼吸が気になって仕方ない状態は続きました。ちゃんと呼吸できているかを確認しながら、毎日を過ごしてました。鼻中心の生活です。勉強でも遊びでもなく、鼻が生活の中心にある。最悪の日々です。
ところが、この日々はいつのまにか終わってました。
正確な時期はわかりません。小学校高学年のころには、自然消滅していました。だから医者の言ったことは一応正しかったのかもしれない。いつのまにか気になって仕方ない状態じゃなくなっていました。
おそらく、徐々に学校が忙しくなり、ゲームやテレビやマンガも覚え、異性にも関心を持ちはじめたからだと思います。あとで詳しく説明しますが、自分の中の「社会」が強くなった結果です。
呼吸の話の余談
この話には余談があります。
二十年くらい過ぎて、私は京都でひきこもり生活をはじめました。そこで衝撃的なことを発見しました。ちょうど仏教への興味が出てきたころで、いろいろと本を読んで調べていたんですが、そしたら仏教における瞑想法のひとつに、
自分の呼吸を見守る
というものがあったんです。
このときはもう笑った笑った。いや、笑うというリアクションが正しいのかは分かりませんが、私は笑いました。二十年ごしの伏線が回収された感覚がありました。
だから、あのときの私に必要だったのは、医者じゃなくて釈迦だったんです。近所に釈迦がいればよかった。かかりつけの釈迦がいればよかったんです。そしたら「は?」とか「様子をみてください」とは言われなかった。
「あなたのそれは瞑想です、続けなさい」
そう言われたことでしょう(たぶん)。
脈拍や心拍をはかると吐き気がした話
もうひとつ、似た話があります。
子供の頃、「脈をはかる」という行為が気持ち悪くて仕方ありませんでした。学校で「自分で脈をはかってみよう」という授業があって、手首に指をあてて回数を数えるんですが、あれをやると吐き気がしてできませんでした。
同じく、「心拍数をはかりましょう」というものもありました。こちらは自分の胸に手をあてて、心臓が鼓動を打つ回数を数えるわけですが、やはりダメでした。
脈にしろ、心臓にしろ、手をあてて、ドク・ドク・ドク……という動きを観察しているうちに、ものすごく気持ち悪くなってくるんです。自分の体内に臓器があって、血液が流れていて、心臓が動いていることを強制的に意識させられる。すると落ち着かなくなって、吐き気がしてくる。
だから、脈拍も心拍も数えるふりだけして、実際はちょっと手を浮かせてました。数字はまわりの子の紙を見ながら適当に書いていました。学校というのはなんでこんなひどいことをやらせるんだろうと思ってました。
夏目漱石とブラマヨ吉田のエピソード
さて、ここから本題です。
呼吸、脈拍、心臓、これは要するに、肉体が勝手に動いているのが気持ち悪いということです。ひとことで言うならば「肉体があることへの違和感」です。もちろん当時はそんなこと考えてません。この六年のひきこもり生活で考察した結果です。
自分の肉体とされているものへの違和感。自分の肉体と言われてるものが、実際は自分とは何の関係もなく勝手に動いていることが気持ち悪い。
これは、誰でも共感できるほどメジャーな感覚ではないようですが、そこまで珍しいものでもないようです。
たとえば、夏目漱石の『それから』という小説の冒頭では、主人公が自分の心臓が動いていることを不思議がっている描写があります。ちなみに、この主人公は現代でいうところの「ニート」です。
もうひとつ、ブラマヨの吉田さんがテレビで言っていたんですが、まだ全然売れていないころ、「心臓がどうして動いているのか不思議でしゃあない」と言って、相方の小杉さんを困らせたことがあるそうです。
ポイントは、漱石の小説の主人公は「働いていない」こと、当時のブラマヨ吉田さんは「全然売れていない=時間があり余っている」ことです。
そして私の場合、小学校低学年のころ(当然、ヒマです)に呼吸や心拍が気になり、成長するにつれて自然と忘れ、ひきこもり生活をはじめたことで、ふたたび「思い出した」んです。
社会の退場と肉体の登場
「肉体への違和感」が出てくるには、一時的に「社会」が退場する必要があるんです。
社会というのは、人間関係のあれこれのことです。会社での仕事、恋人とのデートや友人との飲み会、それに家族や親戚などなど。
そういったものが後景に退いていき、ぽつんと「一人」になった時、自分の肉体が意識の対象にあがってくるんです。自分が呼吸している。自分の心臓が動いている。その当り前が気になりはじめるんです。
なぜ肉体を意識すると、「吐き気」や「落ち着かない感じ」が生まれるのか?
肉体が自分とは無関係なものに感じられるからです。
心臓や脈というのは血液の流れです。呼吸というのは空気の流れです。どちらも自分の肉体とされているものなのに、ありあまる時間のなかで観察していると、自分とは無関係に、勝手に流れているものに思えてくる。
川が流れ、風が吹くように、体内を血液が流れ、顔にあいた穴から空気が流れている。髪の毛だって草のように伸びている。胃袋のあたりでは食物の消化が勝手に進んでいる。肛門からプスーと空気が出ていった。
そこに自分の意志はない。
じゃあ「自分」って何なんだよ、という話になります。
ここに違和感の原因、吐き気の原因があるんです。
そろそろ長くなってますが、もうすこしだけ踏み込ませてください。
ひきこもり状態で観察を進めていくと、肉体だけじゃなく、「思考」というのも、川の水のように頭のなかを勝手に流れているように感じられます。「感情」というのも、勝手にパッと生まれては消えていく花火のように感じられます。このあたりは素直には飲み込めないかもしれません。別の回で詳しく書いたほうがいいかもしれません。
人は普通に過ごしていると、私の体、私の気持ち、私の考え、というふうに、さまざまなものに「私の」をつけています。しかし一人で静かに観察したとき、どれも勝手に生まれ、勝手に消えているなら、本当にそれに「私の」なんて付けてしまっていいのか?
ひきこもり生活においては、そんなふうに、肉体とも、感情とも、思考とも、距離が生まれはじめるんです。「自分」から切り離されていくんです。「自分」というものがどんどん貧しくなっていくんです。これは自分じゃない、これも自分じゃない、呼吸も、心臓の鼓動も、思考も、感情も、自分じゃない。
じゃあ「自分」って何なのか?
この問題に集約されていくんですが、いいかげん字数の限界がきました。
本日はここまでです。
※前回のコラム