履歴書作成術から面接失敗談など、
これからお仕事をはじめる人に役立つ情報を
まとめました!
アルバイト・バイト・
パート・派遣のお仕事探しは
イーアイデムで!
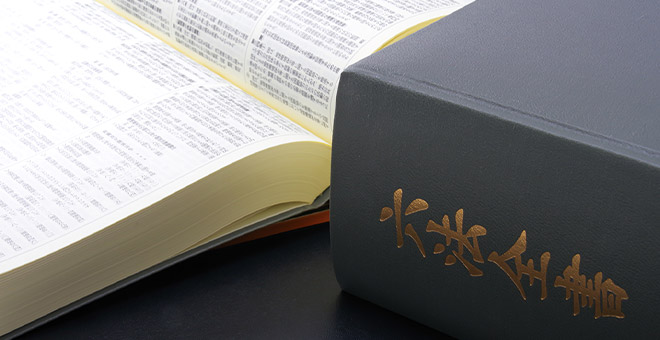
アルバイトも労働者として認められており、労働時間や休憩などが定められています。
本記事では、アルバイトに役立つ法律についてご紹介します。
アルバイトといえども、法的にはれっきとした労働者です。正社員とアルバイトではかなり異なる印象を受けますが、「労働基準法」の下ではアルバイトやパートも賃金や時間、社会保険、休暇などさまざまな面で、労働者として同等の権利が与えられています。
アルバイトの場合は、短期雇用が前提となっているため、事業者によっては正社員と比べると労働条件を細かく取り決めていないケースもあります。働き始めてから後々「こんなはずではなかった」と困らないためにも、アルバイトとして働く上で役立つ法律を知っておくとよいでしょう。
アルバイトやパートタイマー、嘱託社員、契約社員など、労働者にはさまざまな呼び名がありますが、正社員よりも所定の労働時間が短い労働者は、法律では「パートタイム労働者」と定められています。
これはパートタイム労働者が正社員に比べて不利益を被らないように制定された法律で、労働者としての権利はアルバイトも正社員とほぼ同等です。
例えば、アルバイトでも半年以上(全労働日の8割以上を継続して働いた場合)は、10日間の有給休暇を取ることができます。
そして雇用主は雇用時に、使用者に対して「労働条件通知書」や「雇用契約書」などの書面で、労働基準法で定められた労働条件を知らせることになっています。
アルバイトの採用面接の際には、以下のような労働条件が示されているかをチェックしましょう。雇用主から具体的な提示がなかったり、労働条件について分からないことがある場合は、質問して確認するとよいでしょう。
労働者には、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険という保険制度があり、加入資格が法律で定められています。これらの社会保険は、会社や勤務条件によって、アルバイトでも加入することができる場合があるので、事前に確かめておくとよいでしょう。
労災保険については、一般社員だけでなく、アルバイトやパートなど労働者全員の加入が義務付けられています。例えば、業務上の事由や通勤による災害については、アルバイトでも労災保険による災害補償が行われることになっています。
一方で、アルバイトで所得を得た場合、法律では労働者として税金を納めることを義務付けています。賃金にかかる税金は、大きく分けて所得税と住民税の2つがあります。
ただし、所得税は、年収103万円まで(学生の場合は、勤労学生控除によって27万円分がプラスされ130万円まで)は所得税がかかりません。また住民税については、年収100万円以下は非課税です。
税金については、賃金を受け取る際の給与明細や年末の源泉徴収票で確認しましょう。
アルバイトをする際に知っておくとよい法律は、「労働基準法」と「パートタイム労働法」。
労働条件で分からないことがある場合は、雇用主に確認しよう。