編集者・ライターとして働く太田明日香さん。仕事を介して家族や故郷と関わることで「遅れて来た反抗期」が終わったようだと語る太田さんに、「嫌いだった」と語る地元や家族のこと、今思うことについて寄稿いただきました。
反抗期はいつですか?
反抗期というと小学校高学年から高校生くらいまでに来るというイメージがあるが、皆さんはどうだろうか。
わたしにはちゃんとした反抗期がなくて、その代わりに、いきなり30歳を過ぎた頃に反抗期がやって来た。
2018年1月に出した『愛と家事』という本の「遅れて来た反抗期」という文章でも詳しく書いたが、私は小学6年生のとき、入院したことがある。この時期反抗期の入り口にさしかかっていたのが、心配し、看病する親や家族の姿を見て、「こんなにしてもらってどうやって恩を返したらいいのか分からない」というような気持ちの方が先に立った。本当だったら思春期という自分を確立する時期に反抗できなかったせいか、わたしはいつまでも親の顔色を見て行動するくせが抜けなかった。
その後、29歳のときに離婚したことがきっかけで、精神的に親離れしようとする「遅れて来た反抗期」が30歳を過ぎた頃いきなりやって来た。最近、その「遅れて来た反抗期」は終わった気がする。どうしてこんな気持ちになったのか、そのいきさつを書いてみたいと思う。
帰って来い! VS 帰りたくない!
わたしの故郷は淡路島で、地元の集落には家が6軒しかない。いわゆる限界集落というやつだ。今は3世帯しか住んでいなくてほとんど60歳以上の人ばかりだ。あと15年もてばいい方だろう。

わたしは子どもの頃から自分の地元が嫌いでしょうがなかった。山と川と田んぼと畑しかない上、近所には友達も住んでいない。どこへ行くにも親の手を借りなくてはいけなくて、必然とテレビと読書が友達という感じになった。子どもの頃はテレビで見る世界にあこがれて、早く大人になって、都会に出たくてしょうがなかった。
島の中には大学がなかったから、高校を出て進学する場合はたいてい島を出ることになる。わたしもその例にもれず、島外の大学に進学して、一人暮らしを始めた。
家族の期待は、大学卒業後地元に戻って公務員や教員になってほしいということだった。わたしもそれを疑いもせず、ぼんやりとそうするものだと思っていた。
けど、大学に行って島では出会わないような仕事や生き方を知って、「自分は今までなんて狭い価値観の中で生きてきたんだろう」「もっと自分の可能性があるんじゃないか」と思い始めた。
母はわたしに「好きな事をしろ」と言うけど、電話をすれば「教員免許を取れ」とか「公務員試験を受けろ」とか「帰って来い」ばかりで、ほんとうは自分と同じように地元に帰って、家族の近くに住んでほしいんだろうなと感じさせるような発言が多かった。今思えば、母はわたしをいつまでも自分の一部みたいにとらえていたようなところがあって、「心配だから」と言いながら、必要以上にわたしに干渉してきたんだと思う。
わたしは母の意見を取り入れなければという気持ちと、でも自分の本当にしたいことをしたいという気持ちをうまく言葉にできなくて、母と話すといつもイライラした。
やりたい仕事は地元じゃできない!
結局、大学を出ても地元には帰らなかった。
わたしは大学生の頃からずっと出版業界にあこがれがあって、ライターや編集者をやるには都会じゃないとだめだと思っていた。堅い仕事でもないし、地元でできる仕事でもない。教員や公務員になってほしいという母の気持ちを裏切っているような気持ちはあったけど、やっぱり本心では家族とか故郷とか関係なしに、もっと好きなことだけして自由に生きたかった。結局わたしは、無理矢理自分の意思を押し通した。
表面上は親に反抗できているように見えるかもしれないが、うまくいかないと親のせいにするような甘えや依存心、精神的に弱いところが残っていた。
東京の大手の会社でばりばり正社員で働けるような気概も実力もなくて、どうにかアルバイトで京都の大学受験問題集を作る会社に入ることができた。
それからも、正社員になる機会や希望する媒体に関わるチャンスを求めて、非正規雇用で中小の出版社を転々とした。両親はいつまでも正社員にならないで転職を繰り返すわたしにだんだん失望しているようだった。
実家に帰れば「資格を取れ」とか「結婚しろ」とか、思いつきで見当違いのアドバイスばかりしてくる両親にはイライラが募った。どうせ何か相談しても「やめとき」と言われるに決まっている。それなら、事後報告で進めた方がいいと、だんだん何も言わないようになった。
3社目に勤めた会社を辞めたとき、このまま出版業界で正社員になることを目指して仕事を探し続けても同じことの繰り返しだと気付いて、フリーランスになった。わたしは29歳になっていた。
いつの間にやら地方移住ブームが
淡路島や地元の集落への目が変わったのはその頃だった。
2011年に原発事故が起こってから、地方移住する人が増えた。コミュニティデザインという言葉ができたり、地域おこし協力隊の制度が始まったりして、地方に注目が集まり始めていた。
いつのまにか、地方は遅れて寂れたイケてない場所ではなく、何か変わったことやおもしろいことがしたいという若者が集まるフロンティアになっていた。

移住希望者向け空き家ツアーの様子
淡路島でもその動きは同様だった。たまに島へ帰ると、都会にはない暮らしを求めて淡路島にやって来た同世代に会うことが増えた。自分があれほど嫌っていたものに、そんなに魅力があるのかと、とても不思議だった。
そうやって移住者やUターンする同世代と接するうちに、わたしもだんだん淡路島の魅力を外から来た人の目で知るようになった。
この頃影響を受けたのが『フルサトをつくる』という本だ。
京大卒のニートで有名になったブロガー・作家のphaさんと『ナリワイをつくる』を書いた伊藤洋志さんが書いた本で、田舎と都会のいいところ取りをして、二拠点居住をしようという提案をしている。これを読んで目からうろこが落ちた。
今でこそ地方や多拠点を移動しながらライターや編集の仕事をする人は多い。けど、当時はまだノマドやリモートワークという言葉がはやり始めた頃で、いろんな場所を移動しながら仕事をするスタイルはあまり知られていなかった。
わたしも編集やライターは都会でするものというイメージにしばられて、好きな仕事をするために故郷を捨てるか、地元に帰って農業や家事を手伝うかみたいな二者択一でしかものを考えられなかった。
けど、この本を読んだおかげで、「編集やライターをするからといって、都会に住まなくてもいいんだ。都会と地方を行ったり来たりしながら、いろんな場所で編集とかライターの仕事をすればいいんだ!」と考えられるようになった。
自分の中にあった固定観念から解放されたのだ。
さらに、淡路島の地域おこしイベントや地元のアートイベントに行くうちに、広報物や報告書を作る際に編集者やライターという仕事が必要とされていることを知った。これまでそういった仕事は都会にしかないと思っていたけど、淡路島でも仕事があると知って、「そうだ、地元でこの力を生かそう!」と思った。そこから淡路島の仕事に関わるようになった。
それに、わたしはずっと都会のメディアが地方のことを取り上げて、地方がそれに後追いしていく風潮に違和感があった。どうせだったら、地元の出身者や住民の人たちの手でメディアを作った方がおもしろそうだ。せっかく淡路島に編集やライターの仕事があるのなら、わたしも携わってみたいと思った。

いままで淡路島で関わったパンフレット類。これ以外にもイベント運営なども手伝った。左下のNPO淡路島アートセンターによる、食品ロスを減らすためのパンフレットが初めて携わったもの
距離やカベを作るための反抗期
地元の集落でも変化が起こっていた。
父や集落に残る若い世代(といっても60代)の人たちが、集落にあるあじさい園でイベントをやったり、地域おこし協力隊の人たちや市役所と連携して大学生の実習プログラムをしたり、集落を生かす道を探り始めていた。
だんだんと淡路島の仕事をするようになったことで、地域おこし協力隊の方や、他の淡路島の仕事で知り合った方が集落で何かするときに、わたしにも声をかけてくださるようになった。最初は参加者として軽く様子見するだけだったのが、だんだんイベントのチラシや冊子を作る手伝いにも加わるようになっていった。
そんなに地元の集落や家族と距離を取ろうとしていたのにどうして? と思った人もいるかもしれない。
わたしはずっと、出て行きたいという気持ちとは裏腹に、心のどこかで自分が故郷を捨てたような罪悪感を持っていた。
帰るたびに地元の集落が獣害や水害で荒れ、住民がだんだん年老いていくのを見るも心が痛んでいた。
人間とは都合のいいもので、引き止められたら重くて出て行きたくてたまらないのに、なくなるかもしれないと思うと、自分が根無し草になる不安でたまらなくなった。だから、自分の得意なことで地元に関われるなら少しでも役に立ちたいと思ったのだ。

集落の人が集落に人を呼ぶために、自分のうちの田んぼを使って始めたあじさい園
そういうふうに仕事を介してみると、少し親との関係も変わってきた。
話し合いをしているときに、親の「あ、嫌だな〜」と思う面を間近に見ることがある。前は、自分にもそういう部分があるのが嫌で、親のことが恥ずかしくてしょうがなかった。
逆に、関わってくれる人たちが両親について褒めてくれることもある。前は、そういうときも照れてしまって身内をくさしていた。
でも、仕事として関わってみると、親という感じは少し小さくなって、「仕事相手として」見えてくる。時々変なことを言っても、全部真に受けないで適当に聞き流す。すると、親のことを少し困ったところもあるけどまあそこそこ愛嬌のあるおじさんとかおばさんくらいに思えなくもない。
反抗期というのは、それまで一体だった親との間に、反抗することで距離やカベを作ることで、違う意志を持った生き物だと知らしめるためにあるのだと思う。
わたしにとっては、「仕事として親と関わる」ことがいい感じに距離やカベを作れることに作用したんだと思う。それに気付いて、わたしの反抗期ももう終わりだなと思った。
ほんとうの自立
日本には「水入らず」とか「水臭い」なんて言葉がある。家族の間に遠慮がないこと、距離がないことが美徳だという風潮がある。
だから、生計は別でも家族というだけで、家族と自分が一体という感覚を持ちがちなような気がする。家族に対して育ててもらってありがたいという気持ちも、逆に何か根に持つ気持ちがあって許せないという気持ちをもつ人もいるだろう。なかなかそう簡単に割り切れるものではないが、それをいつまでも気にしていると、ずっと家族にとらわれ続けるのではないだろうか。
だから、無理矢理カベや距離を作って、親離れや子離れする選択があってもいいと思う。18歳くらいまで一緒にいて、たくさん影響を受けていたって、そのあとは別々の人生なのだ。親の代わりに生きることも、子どもの代わりに生きることもできない。
いいところも悪いところも飲み込んだ上で、家族と自分を切り離して、適度に付き合うことができるようになるといい。家族みんなが「家族のため」でも「家族の犠牲になった」でもなく、「自分の人生を生きている!」と心の底から思えることこそが、ほんとうの自立なのだと思う。
著者:太田明日香(id:kokeshiwabuki)
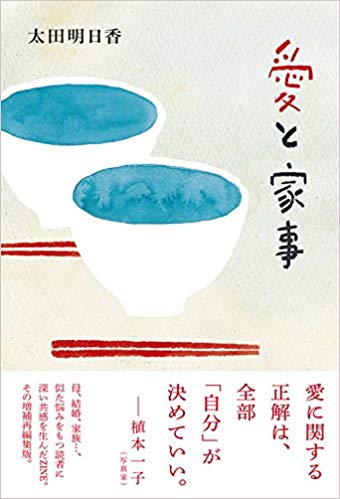 編集、校正、執筆。著書に『愛と家事』(創元社)、『福祉施設発! こんなにかわいい雑貨本』(西日本出版社、伊藤幸子と共著)。連載に『仕事文脈』「35歳からのハローワーク」(タバブックス)。
編集、校正、執筆。著書に『愛と家事』(創元社)、『福祉施設発! こんなにかわいい雑貨本』(西日本出版社、伊藤幸子と共著)。連載に『仕事文脈』「35歳からのハローワーク」(タバブックス)。
Blog:夜学舎
お知らせ:共働きをテーマにしたイベント「りっすんお茶会」を開催します
「りっすん」では、2018年11月25日(日)にイベント「りっすんお茶会」を開催します(※11月15日(木)11:00申込締切)。詳細は下記のリンクをご参照ください。
www.e-aidem.com
編集/はてな編集部



