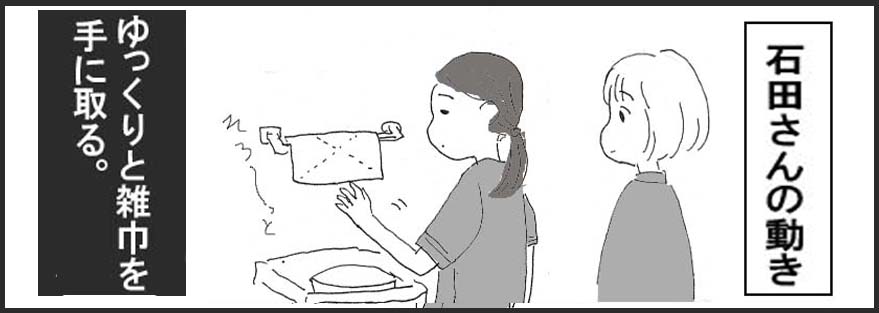あるNPOがつくり出そうとしている、子どもとの関係性
はじめまして。望月です。スマートニュースで子どもや家族といった領域を中心に非営利団体の支援プログラム(SmartNews ATLAS Program)を運営しています。これからの家族や社会のあり方を考えるにあたって、このプログラムで支援している「PIECES」(ピーシーズ)というNPO団体の話から始められたらと思います。
PIECESは児童精神科医の小澤いぶきさんが代表を務めるNPOで、虐待や貧困といった問題を抱える子どもたちに寄り添い、そうした子どもたちが普段の生活ではなかなか得ることができない「大人との信頼感を伴った継続的な関係性」を一つずつ構築しようとしています。

PIECESのメンバーに聞くと、その関係性は「家族」でも「友だち」でもなく、そして「先生」でも「アドバイザー」でもない。いま存在する言葉ではなかなか表現しづらい関係性だけれど、この関係性こそが、子どもたちが自分の困難とうまく付き合って生きていくために必要であるような、そういう関係性。いまはうんうん唸りながらも「伴走者」という言葉をひねり出して使ったりしているようです。
この「伴走者」が子どもと一緒に何をするかといえば、日常のたわいもない話をすること、スポーツや料理をしたり遊びに行ったりすること、勉強や恋愛の相談に乗ること、そして、こうした積み重ねを通じて困ったときに相談してもらえる関係性をつくること。困ったことというのは、勉強や恋愛のことかもしれないし、いじめのことかもしれない。妊娠のこと、親からの虐待のことなのかもしれない。自傷のこと、学校に行けないこと、家に居場所がないことかもしれません。
こうした困難に直面したとき、心を許して相談できる関係性がどんな子どもにもあるわけではありません。そして、たくさんの子どもがそうした関係性を持てないことによって、袋小路(と感じられる状況)から抜け出すことが難しくなっています。親との関係、先生との関係、友だちとの関係、それらがうまくいっていなくても、「伴走者」がいればなんとかなるという関係性をつくれるかどうかが大事なのだと思います。
さて、一人の子ども、そして一人の人間が生きていくうえで必要な関係性を適切に表現する「言葉」がない、このことを知って私はとても面白いと思いました。PIECESがつくろうとしている関係性のことは直感的に理解できるし、その重要性もよくわかる。だけれど、確かにそれを表すうまい言葉が思いつかないのです。
近代社会と親密性の領域――家族が直面する二重の要請
ハンナ・アーレントという20世紀の思想家による「親密性の領域(the sphere of intimacy)」という言葉があります。「親密圏」とも訳されるこの言葉は、アーレントが『人間の条件』(1958年)という本で展開したものです。それは、近代社会がもたらす画一主義に対する抵抗の拠点として、近代人が発見したものであるとアーレントは言います。

- 作者: ハンナアレント,Hannah Arendt,志水速雄
- 出版社/メーカー: 筑摩書房
- 発売日: 1994/10/01
- メディア: 文庫
- 購入: 10人 クリック: 105回
- この商品を含むブログ (158件) を見る
親密さの最初の明晰な探究者であり、ある程度までその理論家でさえあったのは、ジャン=ジャック・ルソーである。(中略)彼が自分の発見に到達したのは、国家の抑圧にたいする反抗を通してではない。むしろ、人間の魂をねじまげる社会の耐え難い力にたいする反抗や、それまで特別の保護を必要としなかった人間の内奥の地帯にたいする社会の侵入にたいする反抗を通してであった。(ちくま学芸文庫『人間の条件』61頁 「第二章 公的領域と私的領域」より)
近代になって発生した人間と社会の関係はとても複雑なものです。近代社会にはいくつかの特徴があります。身分制度が解体し、人々が同じ公教育を受ける機会を持つようになります。資本主義的に組織された市場社会で賃金労働者として働く人たちが増え、それに伴って自分が生まれた土地を離れる人が急増します。
こうした近代社会のあり方が人々に大きな恩恵をもたらしたのは事実です。社会的流動性が増し、生まれた環境がその後の人生をすべて決めてしまうわけではなくなりました。全体的な生活水準も向上し、その積み重ねのうえにいまの私たちの暮らしぶりがあります。
しかし、同時に忘れてはならないのは、多様な背景を持った人々を一つの大きな社会のなかに取り込んでいく近代化の運動によって、アーレントが言う「画一主義」と、私たちは付き合っていかなくてはならなくなったということです。
この大きな影響を受けたのが「家族のあり方」だと私は思います。家族における画一主義、それは社会が求める「理想的な家族のあり方」を忠実に実行しようとする家族の姿です。「家族」が「学校における良い子」や「社会における良き働き手」を育成するための機関とみなされ、その成功や失敗が語られるようになりました。
それは親にとって潜在的に大きなプレッシャーとなって現れます。もし子育てに「失敗」すれば、子どもの人生にとってのリスクを抱えるだけではなく、社会的に失敗の烙印を押されてしまう。親たちは常にその恐怖と戦わなくてはならなくなりました。もちろん教育や子育てには一定の費用もかかりますから、経済的に「失敗」できないというプレッシャーもかかってきます。
こうした家族のあり方に対する社会的プレッシャーの存在が、具体的な親子関係を通じて、子どもたちに困難を与えてしまうということが多いのではないかと私は思います。受験や就職の問題、セクシュアリティの問題、そしてもちろん虐待の問題。子どもを取り巻くさまざまな社会問題を知ると、その核心に家族の問題があるケースが非常に多いことがわかってきます。
アーレントの問題意識に即せば、個人にとって社会からの画一主義に抗するための足場が必要になったちょうどそのときに、家族が画一主義の出先機関のような形で編成されてしまったといえると思います。そこでは親密性の足場は誰にとっても自明なもの、安定的に供給されて当たり前のものではないのです。
近代社会においては、社会のあり方そのものからある種の画一主義が要請され、同時にその画一主義に対抗して自分らしい生き方を選び取るために親密圏の構築が要請されます。そして、家族はその両方の要請を真正面から受け止める存在となり、その2つの折り合いをつけることの難しさに常に直面しているのです。画一主義と親密性という二重の要請が家族を押しつぶしているケースがあると私は思います。
「家族」と「親密圏」はずれることがあるし、ずれていてもいい
こうした二重の要請の間で折り合いをつけることが難しいからこそ、「家族」と「親密圏」の間にはずれが生じることがあるし、そしてそれは仕方のないこと、ずれが生じて当然のことだと考える必要があると思います。その時々の状況によって、「家族関係が親密性の領域ではない」という状況はあり得ます。私たちはまずこのことが現実にあり得るということを深く理解するところからスタートすべきだと思うのです。
理解して何になるか。一つには、家族以外の「誰か」が「親密圏」の担い手として存在している必要があるということを私たちが理解することにつながります。冒頭に紹介したPIECESが追求していることが、まさにこの担い手の育成、彼らの言葉では「コミュニティユースワーカー」の育成、ということになるのではないかと私は思っています。
そして、もう一つには、家族が家族の外に助けを求めてよいという理解が広がることにつながってほしいと私は願っています。家族の問題は家族が解決しなければならないという思い込みから親を解放することで、子どもが親密圏を新たに回復するチャンスにつながる場合も多くあると思うからです。
大阪の釜ヶ崎に「こどもの里」というNPO法人の施設があります。地域の子どもたちを無料で24時間預かってくれる施設で、大阪市からの補助金やバザーの売上、そして賛助会費や寄付金などさまざまな支援によって成り立っているそうです。私は先日、“さと”と呼ばれるこの施設を舞台にした『さとにきたらええやん』というドキュメンタリー映画の上映会を開きました。
映画には小さな子どもから18歳の子どもまで、さまざまな子どもたちが登場します。そして、子どもたちの親も登場します。あるシーンでは、5歳の男の子の母親が子どもを叩いてしまいそうになって“さと”に電話をかけ、結果として夜遅くに子どもを“さと”に預けに来る様子が映されていました。このシーンを観て私が考えたのは、もし“さと”がなかったらこの親子はどうなっていたのだろうということです。
“さと”以外に電話をかける先があれば大丈夫だったかもしれません。でも、もしそうした先がなかったら叩いていたのかもしれません。それは、誰にもわかりません。ただ、家族に対する「画一主義と親密性」の二重の要請から解放される必要があるのは子どもだけではなく、親もまたその重圧からの逃げ場を必要としているということを、このシーンであらためて考えさせられました。これまでの社会のなかで当たり前とされてきた「家族に対する期待」のあり方を、私たち自身がこれから見つめ直していく必要があると思っています。
この名もなき関係性を私たちはつくっていく、さまざまな形で
もう1本だけ映画の話を。昨年公開された西川美和監督の『永い言い訳』という映画についてです。
こちらの予告篇にも登場しますが、中学受験を間近に控えた小学校6年生の男子の葛藤を描く場面があります。筋書きはこうです。主人公である作家の男がバスの事故で妻を失います。妻と一緒にいた妻の友人も同時に亡くなります。そして、その妻の友人には2人の子どもがいて、長男は小6で中学受験を控えている。妹はまだ保育園に通っています。父親は長距離トラックの運転手だからなかなか帰ってこないし、あまり頭が良いほうでもない。
妻の死をきっかけに、主人公はこの父親と再会します。そして、これまで母親が担ってきた家事の負担を長男がせざるを得ず、中学受験をあきらめようとしていることを知ります。そして、介入する。定期的にこの家に通って妹の世話をし、それによって彼が塾に行くための時間を確保しようとします。
映画で描かれる家庭への介入の具体的なあり方が「正しい」かどうかということをここで言いたいわけではありません。この映画自体もそういうことを言おうとしているわけではないと思います。ただ、「家族」ではなくても、「他人」であっても、脆弱な状況にいる子どもや人間に対してできることがあるということをこの映画はとても美しく描いていると思いました。
「他人」であっても、と言いましたが、「他人」が「家族」になるケースもあります。そして、その関係性のうちに親密圏が形成されることもあると思います。
アメリカの歌手Alicia Keysが昨年発表した曲「Blended Family」で、客演したA$AP Rockyというラッパーが「9歳の頃4人も継母がいた」という自分の少年時代について歌っています。この曲ではAlicia Keysが夫のSwizz Beatzの子どもたちに向けたメッセージを歌っていて(Swizz Beatzには、Alicia Keysと結婚する前にすでに3人の子どもがいました)、「I remember having...」から始まるA$AP Rockyの歌詞もその文脈に沿ったものになっています。
(歌詞はこちら ▶ Google Play Music

そもそも「9歳の頃4人も継母がいた」ということ自体に驚きますが、彼がそのことを肯定的に歌い上げているということにもまた大きな衝撃を受けました。もちろん実際にはこの歌に歌われていないいろいろな出来事があったでしょう。でも、いま28歳の彼が当時のことをこうした形で歌詞に昇華できているということに感動を覚えましたし、昇華できるだけの関係性が実際にそこにはあったのではないかと思います。
私たち人間には多様な家族のあり方があり得るし、家族以外の人々ができることもたくさんある、このことをむしろ困難ではなく可能性だと捉えることができるのではないかと私は思います。その可能性の受け皿は必ずしも血のつながった家族に限られる必要はないし、家族である必要もない。A$AP Rockyが歌うように、振り返って大事だったと肯定できる他人との関係性を私たちはいろいろなやり方でつくっていく必要があるし、つくっていくことができるはずだと私は考えています。
これまでPIECESがつくろうとしている「しっくり来る名前がまだ存在しない関係性」について考えてきました。アーレントの「親密圏」という概念を補助線に引きましたが、まだその関係性に名前をつけることまではできていません。「家族」でもなく、「友だち」でもなく、単なる「他人」でもなく、「先生」でもない、この関係性。私たちがこの関係性の大切さをもっとよく理解して、その多様なあり方をさまざまな工夫を通じてつくりだしたとき、もしかしたら新しい言葉が、そこに生まれているかもしれません。
著者:望月優大(id:hirokim21)

経済産業省やGoogleを経て現在スマートニュースでNPO支援などを担当(SmartNews ATLAS Program)。個人としても様々な非営利団体の広報支援に携わりつつ、国内外の社会的テーマに関する文章を書いています。特に貧困・社会保障、移民・難民、ナショナリズム・国家論など。東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了(後期フーコーの統治性論/新自由主義論)。1985年生まれ。
ブログ:HIROKIM BLOG / 望月優大の日記
Twitter:@hirokim21
Facebook:hiroki.mochizuki