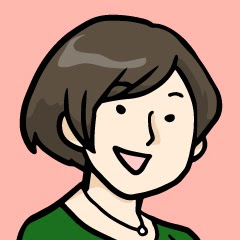Twitterには、「趣味で見たもののログ」を書き残している
1989年(平成元年)生まれで今20代後半です。Webメディアに所属して、記者をやっています。新卒入社した会社に4年ほどいて、2年目から記者職になり、今年転職をしました。
もぐもぐ💸✨ (@mgmgnet) | Twitter
インターネットもぐもぐ
インターネットは小学校高学年からがんがん使い始めました。本格的にブログを使い始めたのは大学に入ってからです。私はブログよりもTwitterを先に使っていて、自分の書いたものがたくさんRT(リツイート)されるのを見ていてすごく面白かった。Twitterの140字では書き切れないことを書こうと思ったのが、ブログを始めたきっかけです。
それまでもネットはずっと好きだったけど、「先生むかつく」みたいな友達同士の話題や日記っぽいことばかりで、何かを書いて残そうとは思っていませんでした。ブログで最初にバズった記事が、3記事目だったんです。
今思えば結構辛辣な反応が多かったんですが、特になんとも思わず、へこみもしませんでした。当時の仲間内で言い合っていたことを外向けに書いたら、他の人にとってはこんなに面白いんだって、文化の断絶、落差を感じました。同じものを見ているのに違うふうに感じる人がいるんだ、というのが面白かった。
過去の自分がふわふわと書いたもの、世代のリアリティがあるものが残っているほうが、自分が後から読んでも面白い。そう思うようになりました。
そんなに変わっていないかもしれません。Twitterは別人格のひとつみたいな感じで使っていて、意識して人格を分けているわけではありません。仕事の自分とネットの自分はよく見ていれば同じ人だとわかるようになっていて、仕事の相手から「もぐもぐさんですよね」なんて言われることはありました。Twitterで炎上するという経験もないんですが、たぶん私は自分のことしか書いていないから、「女性はこう」「日本はこう」というように主語が大きくならない。私生活のことは書いていないから、どこで何をしているかもわからない。Twitterに書くことは生活のログではなくて「趣味で見たもののログ」という感じですね。
好きなジャンルがたくさんある人の情報収集方法は?
そうですね……最近だとなんだろう。ちょっとログをさかのぼってみます。
- ジャニーズ(Sexy Zone)
- 宝塚(月組中心)
- 女子アイドル(今はNMB48、欅坂46を最近勉強し始めた)
- 将棋(完全に観るだけ)
- 歌舞伎(この1年くらい)
- 2.5次元系のミュージカル(直近では黒執事を観ました)
- その他のお芝居やミュージカル(誘われて行くことも多い)
- 音楽(スピッツがずっと好き)
- 映画(話題になったものだけですが)
- 漫画(そこそこ読んでいる程度)
- ドラマ(今期は今のところ4つ、「黒い十人の女」が最高)
- アニメ(今期は今のところ7つ、楽しみにしているのは「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」)
私はどんどん興味の対象が変わるんです。しかもそれに罪悪感がないですね。だから、何かにはまりすぎて困るということはないです。むしろ、それを防ぐためにいろいろ見ているんだと思う。例えば、何かのジャンルでトラブルがあって、ファンがちょっとぴりぴりしたり落ち込んだりしているときに、他のジャンルの話題を見ているとメンタルが安定するんですね。自分のテンションを上げるための道具をたくさん持っていた方がいいな、と考えています。
私の場合はTwitterがハブの役割になっています。どのジャンルでも私よりきちんと追っている人がいるので、ハブになる人を探してフォローしておけば、今何が熱いか、何を見ておかなければならないか教えてもらえます。例えば将棋の場合、毎日何かしら並行してあるので、さすがに全部は追いかけられていないです。「映画『聖の青春』の打ち上げ生中継に羽生先生(羽生善治三冠)が出演している、これは熱い!」といわれているのを見つけて、別のことをしながらラジオみたいにニコニコ生放送を聞いておく、というような感じで。
あとは、通勤時間には意識的に本を読むようにしています。仕事関連の本から小説まで……自分で時間を作らないと全然読まないので。
趣味と同じように、インターネットへの愛情もつづられているブログ
体調面でいえば元気です! でも、好きなものから“元気をもらう”というわけではなくて、やっぱり「書きたい」んです。耽溺している感じではないですね。モチベーションとして、面白かったものをTwitterやブログに書こう、というのがあります。書き物の対象として面白いものが欲しいから、疲れないのかもしれない。面白くなかったら、本の場合は途中で読むのをやめることもあります。舞台を観に行っても面白くなかったら何も書かない。
仕事にだけ集中するのを避けようと、意識的に趣味を増やした
どちらも「頑張ってやっている」というわけではないです。記者という仕事が割と好きなんですよね。情報収集していることが直接的にではなくても何かにつながるので、そういう意味では仕事と趣味に連続性はあるかもしれません。なんとなく流行っていることや自分が面白いと思ったものが、世の中の大きな流れにどうつながるか、アンテナを立てておくのは、仕事と近い性質があると感じます。
自ら志望したのではなく異動で記者になったのですが、いざやってみたら、これならいける、向いてると思いました。でも、それって比較しなければわからなかったことでした。1年目にやっていた仕事は、やりがいがなかったわけではないし、つらいとも思っていなかったんですが、今思えば向き不向きでいうと向いていたわけではないな……。「新卒だから頑張って働いていた」という感じでした。
そのときに仕事にだけ集中していても疲れちゃいそうだなと思って、意図的に趣味を増やしたのが、今こうやってミーハーな日々を過ごしているきっかけですね。ちょうどAKB48では前田敦子さんの卒業があった時期で、ジャニーズや宝塚も追い始めて、それまでは全然見ていなかったのに突然アニメを見始めたり。ぼんやりしていても時間はたってしまうから、自分のテンションが絶対に上がるものの手札を増やそうとしていました。
スケジュール管理はGoogleカレンダーでやっています。やりくりで苦労しているという感じではないですね。大きい公演の場合はだいたい半年先、3ヶ月先が埋まっていくので、当日券で行く以外は「今週末どうしても行かないと!」という予定はあまりないです。一度めちゃくちゃハイペースで予定を入れて、お金を使い過ぎるし疲れてしまった、ということがあったから、だいぶペースがつかめてきましたよ。
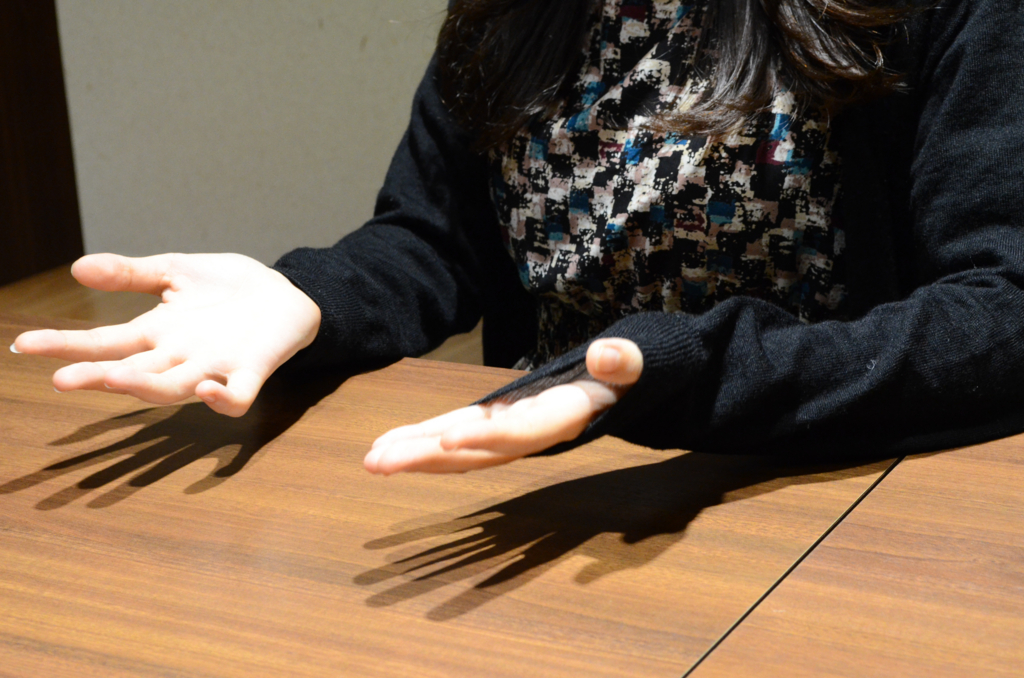
その時期に、意識的に好きになろうと思えば何でも好きになれるってわかりました。私が「好きになりやすい人間」なのかもしれないけど、好きなものが雪だるま式に増えていく。私、何かに誘われたときにあんまり断らないんです。信用している人から「これ面白いから行きましょうよ」って言われたら「行く行く」っていう感じで。
歌舞伎がそんな感じでした。「ワンピース歌舞伎」がすごく面白くて、そのことをブログに書いたら「それが面白いなら、こういう演目のここが面白いと思うよ」とか「市川海老蔵めっちゃかっこいいから一緒に行こう!」なんて教えてもらって。義経千本桜や、コメディチックな八月納涼歌舞伎など、今年に入ってから4~5回は行っていますね。だいたい面白かったものを言ったり書いたりすると、誰かが関連するものを勧めてくれるので、いろいろなことを知りたい私にとって、精神衛生にいいということがわかりました。
年間150回くらいは何かしら観に行っているけれど、そんなにお金はかかっていない……かも
2014年くらいから「エンタメ記録」を付けていて、何かしら遊んだ回数を旅行も映画も全部含めてカウントしてるんですが、だいたい150くらいはいきますね。そう思うとちょっとやばいですね。
目が泳いでしまいますね……働いてないなこの人、って感じだな、本当に。よく働いているな……。
ちょっと考えたくないですね。収支管理、怖くてしてないです。クレジットカードの明細は薄目で見て、そっと閉じます。意外になんとか大丈夫です。家賃も光熱費も払えてますよ! 結構「えっ、お金大丈夫なの?」なんて言われるんですけど。毎月末に死にそう……って感じではないです。
同世代に比べてどうかは不明ですが、貯金はそこそこしてます。月何万かは、よけてちゃんと積立はしているんですよ。そもそも実はそんなにお金がかかってないと思うんですよね。舞台や旅行にはかかりますけど、テレビやネットで見られるコンテンツが結構あるし……。あとはやっぱり、はまりすぎていないから無理はしていない、というのは大きいです。どうしてもこれに行きたいから悪魔に魂を売ってでもどうにかする!ではなくて、じゃあその日は違うことしよ、ってなります。
そうですね。そう考えると、多趣味の方がもしかしたら収支が抑えられるかもしれない! 逆転の発想になってきました。パラダイムシフトが今起こりましたね!
興味を持つジャンルのひとつとして「結婚」「子育て」がある
記者の仕事はやはり割と向いている気がするので、しばらくはこれをやっていきたいです。働き方というよりも、取材して書くことが楽しいから。ブログはブログで好きですが、自分の中では結構分けていられています。「書くことが楽しい」ということをどこで実現するか、ですね。
何ででしょうね……天啓?(笑) 辞めよう、と思った日のことは結構覚えてます。何か嫌なことがあったとか我慢できなくなったとかではなくて、ある記事を書きながら、あ、そろそろ違う場所で何かをしよう、と思ったんですよね。
それまで転職したいって全然思ったことなくて、仕事は好きで楽しかったし、取材もたくさんさせてもらってハッピーだったけど、そのときほとんど初めてその選択肢を意識したんですよね。だから逆に「あ、これは今なんだ」と思って。

年齢的なことは特に関係ありませんでした。年齢というよりは、4年間続けてきたしそろそろ次かな、と。幅を広げるためには環境を変えるのが一番いいかなという気持ちが単純にありました。
そうだな~、次は結婚したいですね。人生ゲームのコマを埋めたい、みたいな。趣味に生きてはいても、このままでいいというわけではなくて、普通に結婚してみたいと思っています。興味の範疇のひとつとして、「結婚」「子育て」があります。次にはまりたいジャンル……?
「今すぐ結婚したい、20代後半だから」というよりは、これまでいろいろやってきて、まだまだ知らないことをもっとしたい。となると、次は結婚が自然と視野に入ってきます。
そういう場合は「したいっすよ! いい人紹介してよ!」って逆ギレしますね(笑)。よく「結婚願望ってあるの?」とは聞かれます。その理由はよくわかっていて、たぶん「結婚しろ」っていうけしかけをしたいんじゃなくて、「一人でも人生が楽しそうだけど、どうなの?」という感じなんだと思います。聞かれること自体はあんまり嫌な感じはしないですね。一人でも楽しいけど、二人が嫌っていうわけじゃないし。子育てハック、してみたいじゃないですか。
そう言われてみるとあんまりいないですね。もう少し長く働いていたいとは思いますが……私が今問題に直面していないからかもしれないけど、ロールモデルを意識したことはないです。書くことを仕事にするという点では、やり方の幅は広いんじゃないかとは思います。自宅でできる可能性もありますし、フリーで活動している先輩もいるし。
「ネットのお兄さんお姉さんたち」に話を聞いてもらうことは結構ありますね。ずっとネットをしてきて、いろいろな人に会ったりかわいがってもらったりしたのがすごく大きいな、と思います。
「これから転職しようと思ってるんですよねー」くらいの温度感で少し相談事ができる、ちょっと先輩の、しかも利害関係がない人って、リアルではどうしても作りにくいですよね。そういう人たちにネットで出会えたのは本当によかったなと思います。それこそ趣味の世界でつながった人が似たような業界にいたり、業界は全然違っても会っているときに「今度何かやりましょうよ」という話になったこともありました。ずっとインターネットをしていてよかったなって思います。
お話を伺った人:もぐもぐ (id:haruna26)

平成元年生まれ、インターネット育ち。ふみコミュニティとロリポップとヤプログ!に生息していた日々よ……。紆余曲折を経て、大人になってからの方が絶対に人生楽しくなった。だいたい毎日幸せです。
ブログ:インターネットもぐもぐ Twitter:@mgmgnet