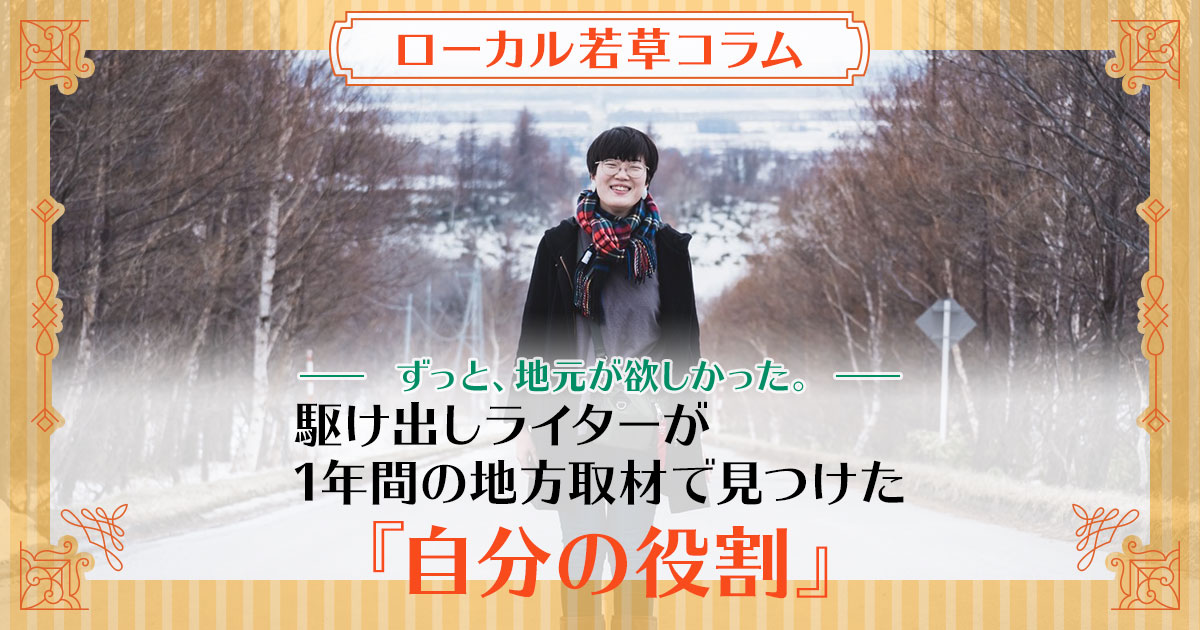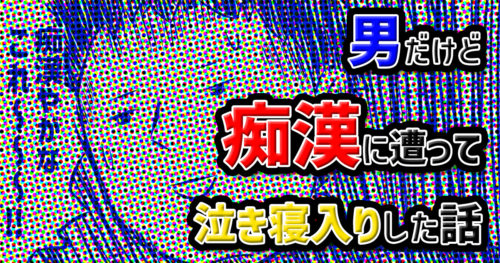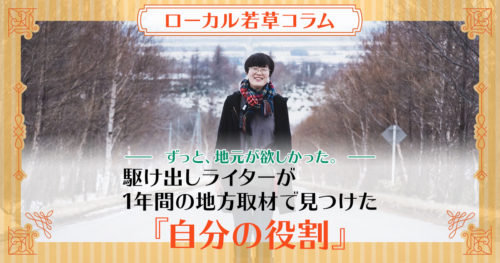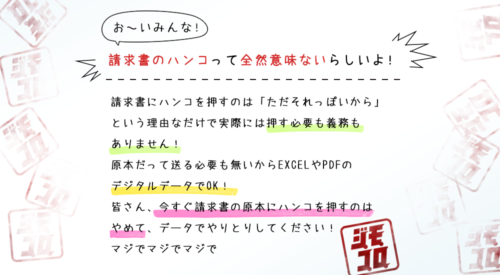ジモコロをご覧のみなさん、はじめまして。ライターの菊池百合子です。すきなものは地方取材です。

(photo by 小松﨑拓郎)
私は神奈川で生まれ育ち、中学から大学まで東京の学校に通ってきました。いわば、首都圏で完結する人生。
一方で小学生の頃から、「地方で暮らしてみたい」と思っていた記憶があります。
祖父母も家の近くに住んでいたので、「離れて暮らす祖父母に会うために帰省する」イベントが憧れでした。
田んぼが広がる「田舎」に帰ると、畑で収穫した野菜をいっぱい使ったごはんを、親戚みんなでずらっと並んで一緒に食べて。
そんな『サマーウォーズ』のような夏休みが、うらやましかった。その理由は景色でも食べ物でもなく、「地元」という帰れる場所の存在でした。
やりたいことがなくて、どう生きたいかわからない。そんな自分であっても、いつでも帰っていい「地元」がほしかった。
勝手な空想ながら、地方には帰れる場所がある気がしていたんだと思います。

地方への憧れを持ったまま東京の会社に就職。新卒研修では、希望して北海道の牧場へ
とはいえ大学進学や就職で首都圏を離れる勇気もなく、憧れのままだった地方暮らし。
2018年にフリーランスになってからさまざまなタイミングが重なり、今なら東京を離れられると気づいたとき、ふと「いつまでも地方暮らしに憧れたままなんだろうか?」と思ったんです。
結局それだけの理由で、2018年9月、縁もゆかりもなかった滋賀県長浜市に引っ越しました。
長浜に行ったことのある人たちから背中を押してもらい、「合わなかったら東京に戻ればいい」と自分に言い聞かせて。

そうして初めての地方暮らしをスタートし、まもなく二年が経とうとしています。
「憧れ」だった地方暮らしが日常になり、一年前から雑誌やウェブメディアで他県に取材に行かせていただく機会も増えました。
ローカルを舞台に活動する各地の先輩たちに出会い、「人生で何をしたいのか」「誰の何の役に立ちたいのか」と問いをもらう日々。
二年前はその問いかけに答えられなかった私も、少しずつ変化してきたように思います。
そのなかでも一番大きな変化は、「自分の役割」を見つけたこと。
人生を賭けて担いたい役割を、どう決めるのか。
先輩たちの背中を追いかけながら「何に人生を賭けたいか」を決めるまでの道のりを、ここに書いてみます。
原動力は「地域のため」じゃなくていい

引っ越して半年後に手伝った、長浜の若者が主催するイベント。右端の自分に、当時の絶妙な距離を感じる
憧れの地方暮らしをはじめてから半年。当たり前かもしれないが、「ただ住んでいるだけでは、その場所は地元にならない」と知った。
地域のイベントに参加するようになり、誰も知っている人がいない街から、顔の思い浮かぶ人たちが暮らす街になった。でも引っ越して半年では、「この地域のために、これをしたい」と思える役割を、見つけられなかった。
むしろ地域で暮らす当事者になったことで、メディアで取り上げられる「ローカルヒーロー」たちが、遠く感じるようになった。
画面越しに「人のため、地域のため」を掲げる彼らの活躍を見るたびに、地域で生きる覚悟を決めきれない自分が浮き彫りになる気がして。
だから滋賀に引っ越してから初めての地方取材で一番聞きたかったのも、「なんでそこまで、誰かのために頑張れるんですか」だった。

和歌山県海南市のカフェ「Kamogo」。農業の魅力を伝える発信拠点であり、地域の外から人が集まる交流の場でもある(photo by 寺内尉士)
この問いを持って雑誌『TURNS』の取材で向かった先は、和歌山県海南市下津町。
地元の農家と連携してオリジナル商品を手がける「FROMFARM」を立ち上げた、大谷幸司(おおたに・こうじ)さんをたずねた。
大谷さんは家業である花の農業を継いだものの、35歳のときに農業以外の事業に注力する決意をする。これまでにない視点で地域の農産物を広める商品開発に、自分の役割を見出したからだ。
その後もカフェをオープンしたり、若者と農家の接点をつくる取り組み「みかん援農」をスタートしたりと、地元の可能性に光を当てるために率先して動いてきた。

当時Kamogoはまだオープンしたばかり。果汁100%の搾りたてジュースをいただきながらインタビューした(photo by 矢野航)
どうしてそこまで、人のために動けるんだろう。地域の課題を簡単に解決できるわけではないと知りながら、それでも動き続ける原動力は、どこにあるのだろう?
人生を賭けてでも、地域のために動く。その理由を知りたかったのだ。
大谷さんは私の問いかけに対して、しずかにこう答えてくれた。
家族の病気をきっかけにUターンしてからずっと、心のどこかで「なんで僕が家業をしなくちゃいけないんだろう」と思っていたんですよ。
僕が家業の花農家をやりたいわけじゃないのに、仕方なくやっている。
そして何かうまくいかないと、心のなかで家族の病気や状況のせいにする。そういう自分が嫌でした。
だから、自分で選んだ道を生きようと思ったんです。
自分の言葉で聞かせてくれた大谷さんの原動力は、人のため、地域のため、ではなかった。
決断の主語は、「自分」だ。
自分が地元をおもしろがりたくて、地元で見出したチャンスをつかみ、ずっと挑戦してきたのだ。

下津町から四国方面を望む。山と海の近さが新鮮に感じられた。山の斜面には、みかんの木が植えられている(photo by 寺内尉士)
地元にいようと家業を継ごうと、人生も役割も、自分が選べる。
そう証明するかのように動き続ける大谷さんの背中から、自分で決めた人生を歩む覚悟を感じた。
人生の軸とは、自分を立たせてくれるもの
役割は、自分が決めるもの。そう学んだものの、じゃあ何を担いたいのか、まだ見えてこなかった。
やりたいことって、どう決めているのだろう。
そんな疑問を持ちながら『TURNS』で取材したのが、京都府京都市で140年以上続いてきたお茶筒の専門工房「開化堂」の6代目・八木隆裕(やぎ・たかひろ)さんだ。

開化堂本店で、若手職人たちと。右端が八木さん。手前の机に並んでいるのがお茶筒(photo by 山崎純敬)
このときのテーマは、「伝統工芸」。
正直に言えば、私は伝統工芸にさっぱり縁がなかった。それでも八木さんが工芸を広めるために挑戦していることは強く伝わってきた。
かつて、ほとんど国内でしかお茶筒を販売していなかった開化堂。八木さんはそのお茶筒を世界中に届ける目標を掲げ、売り上げの減少ゆえに工房を畳もうとしていた先代の反対を押し切って、自ら開化堂に入った。
それから20年以上にわたって、八木さんがお茶筒の魅力を発信し続けた結果、今では世界中で開化堂の商品が販売されている。
さらにものづくりにとどまらず、「工芸を体験する空間をつくりたい」とカフェをオープンした。

2016年に京都にオープンした「Kaikado Cafe」。暮らしの道具として伝統工芸を体験できる空間でコーヒーをいただいた(photo by 山崎純敬)
八木さんが目指すのは、開化堂のお茶筒だけでなく、工芸について広く伝えること。そのために自ら国内外を飛び回って工芸の魅力を語り、伝え方を常に模索している。
どうして、誰も経験していないことに次々と挑戦できるのだろう。伝統や家業の重荷を背負いながら、自分がやりたいことをどう決めているのだろう。
八木さんは工芸を伝えたい理由として、「お茶筒を世界中の人と楽しみたいから」と話していた。
「楽しさ」を軸にやりたいことを決めている八木さんは、どうして人生を賭けてまで、楽しさを追い求めるのだろう。

開化堂本店前を流れる高瀬川。幼い頃の八木さんにとって遊び場だった(photo by 山崎純敬)
「話していて、今思い出したんですけど」
取材中、八木さんがそう切り出した。
小学生の頃から、ずっと楽しさを探していたかもしれなくて。
今日は学校が6時間授業で、体育がない、図工もないな。学校が終わったら家庭教師の先生が来る、あの先生厳しいんだよな。それでもう一日終わりやん、て。
そういう毎日のなかで、ちょっとした楽しみを見つけようと必死でした。
家に転がっている、こんなちっちゃいゴジラの消しゴムが大好きで。筆箱に入れて学校に持って行くだけで、しんどいことを乗り切れたり。「友だちとこんなふうに遊んだら楽しいかも」と新しい遊び方を考えたり。
毎朝目が覚めるたびに暗い気持ちになるけれど、なんとか一つ楽しいことを見つけてから起き上がるようにしていたんです。
だって、人生しんどいじゃないですか。だから乗り切るための何かを、ポケットに入れておく。そういう心の拠り所が「楽しさ」でした。その楽しいこと探しを、今も続けているのかもしれない。
そうじゃないと、立てなかったから。
しんどいよりは、楽しく生きていたい。そうやって必死に見つけた楽しさが、同じようにしんどいと感じる誰かの支えになるかもしれない。
それは八木さんが見出した希望であり、やりたいことを決める軸になっていった。
その軸が、今では開化堂の、そして伝統工芸に携わる後進たちの希望になっている。
この投稿をInstagramで見る
(取材後にInstagramにアップされていた、ゴジラの消しゴム。次にお会いしたら見せてくださるとのこと)
「やりたいことが見つからなくても、誰もが自分の軸になるものを持っている。
小さい頃の記憶をひもときながら、何を大切にして生きたいのかを考えてみたら、きっと軸を見出せると思う」
そう語りかけてくれた八木さんの記事は、同世代の友人たちが読んでくれた。送ってもらった感想を八木さんに届けたときのお返事を、ずっと覚えている。
「僕だけでは伝えきれない人に、工芸の魅力を伝えていってほしい」
私が人生を賭けて大切にしたいのは、こういうものだと思った。
取材で出会った方に託してもらったバトンを、未来につないでいく。その役割は、一本のインタビュー記事だけでは終わらない。
だってこれは、取材させてくれた方と私との約束なのだ。
人生をどう過ごしたいか。何に希望を見出すのか。
八木さんの記事が、その答えに気づくきっかけをくれた。
ぼくたちが引き継ぐと決めたものが、未来をつくる
八木さんとの出会いを通じて人生を賭けて大切にしたいものを見出したものの、もう一つわからなかったことがある。
役割を担う場所は、はたして「どこ」なのか。
これまで出会ってきたのは、地元もしくは自分で決めた場所で、役割を見出している人ばかりだ。
また、立ち止まってしまった。
私はその「土地」を決められない。

460年以上続いてきた、ご近所の酒造「冨田酒造」にて(photo by 矢島絢子)
今では滋賀に大切な人がたくさんいるし、受け継がれてきたお祭りや街並みを次の世代につなぐために、私ができることをしたいと心から思う。
一方で、八木さんのように取材で出会ってきた方々との約束も、私にとってすごく大切なものだ。その約束は、全国各地に散らばっている。
だから「ずっと滋賀にいるの?」と聞かれると、滋賀だけにひもづいた役割を見出せない私には、その選択がしっくりこなかったのだ。

北海道斜里郡にある「天に続く道」から、初めてオホーツク海を眺めた(photo by 原田啓介)
そんな悩みを抱えて『TURNS』の取材で向かったのは、北海道の北東部に広がるオホーツク地域。このエリアで活動する、さのかずやさんに会いに行った。
さのさんは大阪や東京、岐阜で暮らしながら、地元であるオホーツクとの関わりを模索してきた。地元と関わるためなら、月に何度も北海道に通う労力も惜しまなかった。
さのさんも、「土地」にひもづいた役割を見出したのだろうか。
そう見えたけれど、少し違っていた。

(photo by 原田啓介)
祖先や先輩から引き継がれて、子孫や後輩に引き継いでいく。自分もその「ストリーム」のなかにいる当事者なんだよね。
その役割は、必ずしも土地にひもづくものでなくていいと思っていて。
だって引き継がれたものをぜんぶ引き継げるわけではないし、引き継がなくていいものもある。ぼくは小学生の頃に地元で感じた絶望を、次の世代に引き継ぎたくないと思って動いているから。
逆に引き継ぎたいものがあるなら、新しいことを始めるのもいい。
自分が引き継ぐ者であることを自覚した上で、誰に何を引き継ぎたいのかを考えていきたいね。
さのさんは大学生の頃に書いたブログをきっかけに、各地で活動する大人たちに会いに行った。
結果的にさのさんが役割を見出したのは「地元」だけれど、彼が未来の地元に引き継ごうとしているのは、全国で出会った大人たちから引き継いだものも含まれるのだろう。
滋賀でも取材先でもたくさん引き継いでもらっている私は、それらをどうすればいいのか分からなくて、少し苦しくなっていた。
でもさのさんに「引き継ぐものは、自分で選べばいい」と言ってもらい、すごくほっとしたのを覚えている。

さのさんが運営する宿泊施設「オホーツクハウスきよさと」にて。取材に合わせて、北海道の各地からさのさんの友人が集まってくれた(photo by 原田啓介)
取材を終えてお礼の連絡をしたら、さのさんがこう返してくれた。
「引き継ぐことに気負わずに、助け合っていきましょう」
ぜんぶ一人で引き継ごうとしなくていい。誰かと一緒に引き継げる部分があるなら、手を取り合えばいい。そう教えてもらった。
先輩たちの問いかけから、自分の役割を決めた
やりたいことがない。
そんな悩みから始まった地方取材を通じて、おぼろげながら「どう生きたいのか」が見えてきた。
自分も次の世代に何かを引き継ぐ当事者であり、そのために人生を賭けて担う役割がある、と自覚したからだ。
これまでは、未来にバトンをつなぐのは地元や継ぐ家を持つ人の仕事であり、自分にはバトンを渡す相手などいないと思っていた。
でも地元で暮らしていようとそうでなかろうと、どんな仕事をしていようと、自分の役割があると考えるようになった。
自分が、何に希望を見出し、誰に何を引き継ぎたいか。
そう考えてみると、全く分からなかった役割がおのずと見えてきたのだ。

オホーツク取材では、流氷の向こうに沈む夕陽を見届けた(photo by 原田啓介)
私は一ヶ所の「土地」にひもづくものだけでなく、地方取材で出会った各地の先輩たちに託されたバトンも、未来に引き継ぎたい。
だからこれからもまだ知らない土地に足を運び、自分の感性で受け取れたものを持ち帰り、引き継ぎたいものを伝えていこう。
記事を書いて終わりにせず、記事以外にも引き継ぐ方法を考えて、行動につなげよう。
これが、初めての地方暮らしを体験しながら地方取材を一年間続けてきた私が見出した、「自分の役割」です。
これからもご縁のあった出会いにまっすぐ向き合い、変化も楽しみながら、泥臭く前に進んでいこうと思います。
ローカルで活動されている全国のみなさん、あなたが役割を見出した場所でお会いできる日を、心から楽しみにしています!

(photo by 原田啓介)
■ このコラムに登場した『TURNS』記事の詳細はこちら↓
FROMFARM 大谷幸司さん https://turns.jp/29774
開化堂 八木隆裕さん https://turns.jp/36867
さのかずやさん https://turns.jp/37931